-
現代につなぐ歴史授業デザイン
- 刊行:
- 2025年8月22日
- ジャンル:
- 社会
- 対象:
- 中・他
- 歴史という教科において、このように机上の空論にも寄らず、実践に伴いながら理論的でフラットな視点に立たれている硬派な内容の本が出されるのは大変嬉しいです。「現代につなぐ」という共通姿勢を持っているため、生徒に興味を持たせるのが難しいような内容でも、ある程度近くまで歩み寄れるような設計に工夫されているように感じられます。重厚な内容のため、今後もじっくり読んで参考にさせていただきます。2025/10/11プーちゃんの肉球
-
中学校社会サポートBOOKS考えと対話を引き出す 「ジレンマ発問」でつくる中学校社会科授業
- 刊行:
- 2023年1月20日
- ジャンル:
- 社会
- 対象:
- 中学校
- 「ジレンマ」に陥る発問を通じて考えさせるという切り口で授業設計がされています。地理、歴史、公民と分野は分けられているものの、それぞれの発問を通して社会科の教科全般を横断する形で学ぶ機会が持てそうなことや、悩ましい発問を通じて自分との関わりを深めるような体験ができるように感じられるのではないかという印象を受けました。まだ熟読には至っていませんが、ワクワクするような発問が多く大変勉強になります。授業づくりの参考にさせていただきます。2025/10/11プーちゃんの肉球
-
通常の学級でやさしい学び支援3読み書きが苦手な子どもへの<漢字>支援ワーク 1〜3年編
- 刊行:
- 2011年8月3日
- ジャンル:
- 特別支援教育
- 対象:
- 小学校
- 子どもに合っているのでよかった。書店でたまたま見つけたが、もっと早くにこういったものが販売されていつことを知ることができればよかったと思う。2025/10/1140代・女性
-
SCHOOL SHIFT 2あなたが未来の「学び」を創出する
- 刊行:
- 2024年7月26日
- ジャンル:
- 教育学一般
- 対象:
- 小・中・高
- よかった2025/10/1130代・小学校教員
-
楽しい体育の授業 2025年9月号陸上運動は運動神経では決まらない!記録を伸ばす指導法
- 刊行:
- 2025年8月4日
- ジャンル:
- 保健・体育
- 対象:
- 小学校
- 運動会の短距離走から,現在のハードル走まで指導のポイントわかりやすくて助かりました。2025/10/1150代・小学校教員
-
社会科「自己調整学習」学び方を生かした単元デザイン
- 刊行:
- 2025年6月20日
- ジャンル:
- 社会
- 対象:
- 小学校
- 単元全体で考えることの大切さがよく分かった。2025/10/1150代・小学校教員
-
道徳科授業サポートBOOKS続 「ザワつく」道徳授業のすすめ「問題の本質」レベルを捉えるとうまくいく!
- 刊行:
- 2025年6月20日
- ジャンル:
- 道徳
- 対象:
- 小・中
- 前回に続いて,教材の捉え方の視点を得ることができた。2025/10/1150代・小学校教員
-
「非常識」な授業づくり 悩んだ時に立ち返りたい40の疑問
- 刊行:
- 2025年3月14日
- ジャンル:
- 授業全般
- 対象:
- 小・中
- 日頃のふり返りに役立った。2025/10/1150代・小学校教員
-
子どもが動くのは、ルールより関係だったオルタナティブスクールから学ぶ「つながる」教室づくり
- 刊行:
- 2025年8月28日
- ジャンル:
- 学級経営
- 対象:
- 小・中・高
- これもひとつのあり方であり、これをすごいとか、いいとか評価するような見方ではなく、とらえたいと思いました。
と同時に、自分としては好きな考え方でありとりくみだと感じています。植物に、その植物にあう光と水を見極めて、ただただ元気でいるよう願い愛でる、そんな環境と付き合い方だ、と感じました。
人にとっても、人がそだつ過程において自然な状況というか、必然な環境であるかのように思えた点が、好きだなぁ、と思った次第です。
そして、気づきももちました。
自分自身の話です。乳幼児期の子どもとのつきあいは、今のその子を見て、やっていることそのものをみて驚き喜ぶ。致命的な怪我をしないように家の中の環境をととのえる。それくらいで、はやく寝返りうて、とか、話せ!とかそんなことも思わずもちろん指示せず、まだやらないまだできないと嘆くことも、他の子はできてるのにと思うこともなくつきあっていたように思います。
それがいつの頃からか、あれやれこれやれ、あれできてないこれできてない、普通にみながやっているように学校にいってくれ、などと思いそれを伝えている。これでは育つものもそだたない、むしろつぶすだけだと、この本をよんで気がつきました。
子どもたちにとって、その子の基本の場所は、それぞれが、その人にあう基本のものを選択できる状況になったらよい、と考えます。いちかゼロではなく、基本部分をその人にあうものに、と。時間の使い方や開始終了の時間とか、環境のルールとか。それを選択してよいといえる大人でいようと。
そして、どれをえらんでも、「(そこでも)大丈夫だよ。今は自由だから」と、言われない社会がいい。大多数のメジャーな選択肢が“いいもの‘’で、それ以外でも大丈夫、という大人たちの思考にさらされない環境で、子の成長を待てたら、と、この本をよんであらためて思いました。
発刊に感謝します。
ありがとうございます。2025/10/940代・会社員



















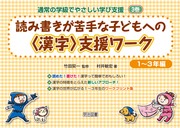







コメント一覧へ