-
子どもの世界をよみとく音楽療法特別支援教育の発達的視点を踏まえて
- 刊行:
- 2007年3月1日
- ジャンル:
- 特別支援教育
- 対象:
- 小・中
- 徳島の養護学校の先生がブログに書評を書かれているのをみて購入しました。
<http://ameblo.jp/creative−conduct/entry−10032570870.html>
1.発達の視点に基づいて、それぞれのレベルでの効果的な音楽の用い方が書かれている。
2.アセスメント票、評価表がついている。
3.特別支援教育の現場に即している。
4.CDがついている。
5.音楽活動が、身体や脳の発達にいかに必要なものであるかが、よく書かれている。
と紹介されていました。
すごく読みやすく使いやすいです。2007/5/30青レンジャー
-
子どもの世界をよみとく音楽療法特別支援教育の発達的視点を踏まえて
- 刊行:
- 2007年3月1日
- ジャンル:
- 特別支援教育
- 対象:
- 小・中
- 『子どもの豊かな世界と音楽療法』とあわせて購入しました。近作では音楽療法の解説の合間からにじみ出る著者の子どもへの温かな視点(厳しくもあり)がよりリアルに伝わってきました。
CDにある指導場面の動画はセッションの雰囲気を実際に感じることができてオススメ。2007/5/20ト音記号
-
社会科教育 別冊 2004年6月号新版!社会科学習用語まとめくん
- 刊行:
- 2004年5月19日
- ジャンル:
- 社会
- 対象:
- 小学校
- 今、5年生で使っています。その単元で大事なことがスッキリまとめられており、本当に使いやすいです。
「実験楽しかった」「グループ活動楽しかった」…でも、テストで点が取れなかった、わかってなかった…じゃ、ダメですよね。まとめ・定着という点で、この本、おすすめです。
基礎編は、選択肢から答える形も多く、どの子にも解きやすいので、授業中にこまめに活用できます。単元終わりにテスト直前復習問題として基礎編と発展編を一緒におさらいとして解かせるのも有効です。
6年生のページを見ると、「こっちのページも早くつかいたい」とウズウズです。このまま学級持ち上がりで6年担任になってもたくさん活用します!
合わせて買った「5年理科用語まとめくん」も、同様に使いやすいです。理科も社会もどっちも「まとめくん」で、バッチリですね。
たくさんの先生方に、両方を使ってほしいです。2007/2/24青森りんご娘
-
向山型で算数授業の腕を上げるシリーズ5向山型授業のシステムづくりの法則
- 刊行:
- 2001年7月
- ジャンル:
- 算数・数学
- 対象:
- 小学校
- 算数授業の進め方がよく分かる一冊です。
ノートの使い方、練習問題の答え合わせの方法やテンポよく授業を進める方法など、新卒教員にはとても参考になる本だと思います。
くどくど説明をしないなど今までの常識が覆ります。2007/2/11kyuちゃん
-
イラスト漫画で早わかり プロ教師が拓いた教育技術の基礎基本
- 刊行:
- 2006年11月21日
- ジャンル:
- 授業全般
- 対象:
- 小学校
- 教育現場・教育現実の何処に問題が潜んでいるのか、そのことをじつにシンプルな仕方(見開き2ページにまとめられている)で示している。そこがいい。『教師の仕事365日の法則』とあわせて、(とくに、教育学部の学生にとって)学校教育学の入門書として、じつによくできているのではないかと思う。
向山氏は、同書の109ページでいっている。
<……、子どもの可能性を伸ばすのは「支援」というような口当りのいいことではなくて、何もないところからでも「ひっぱり出す」激しさが必要だからだ。
ここまで書いて、これと同じように言った人がいたはずだと思い出している。多分、斎藤喜博だ。彼なら、そのように書いているはずだ。>
斎藤喜博は『授業入門』(国土社)の56ページでつぎのようにいう。たぶん、ここのことをいっているのではないかと思う。
<……、教育とは、子どもたちに教えるとか、助成するとかいうなまやさしいものではなく、子どものなかにあるものを、つかみとり、引っぱり出してやる激しい作業だと思っている。地下に眠っている石炭を地上に掘り出し、火をつけてもやすような作業だと思っている。また、子どものなかにないものまでも創り出してやる作業だと思っている。>2007/2/8後藤隆一
-
基幹学力の授業 国語&算数 2006年12月号4号 国語&算数授業=どこで「か(書)く・か(描)く」?
- 刊行:
- 2006年11月28日
- ジャンル:
- 授業全般
- 対象:
- 小学校
- 先日,筑波大学付属小学校での研究会に参加した際に購入しました。筑波大付属の先生方の理論や実践が詳しく紹介されているだけでなく,全国の先生方の貴重な実践が多く紹介され,大変刺激を受けました。まだ4冊しか発行されていないのが残念ですが,今後は月間として定期的に発行していただければ,大変ありがたいです。2007/1/14こだまっち
-
AさせたいならBと言え心を動かす言葉の原則
- 刊行:
- 1988年
- ジャンル:
- 授業全般
- 対象:
- 小・中
- 指示・発問作りには最高級の本です。
生徒が動かない、反応がないのは生徒の責任ではありません。
すべて、先生の発問・指示が悪いのです。これを気づかせて
くれた本。具体的な指示・発問の作り方まで書かれてある。
この本では、ただ単に、生徒を動かすための指示・発問とは
考えていません。生徒を知的な動きにさせる指示・発問作りです。
この本を読んでいるだけで、知的な活動に参加してしまう。
岩下先生の莫大な事例を集め、原則を導き出した多大な努力に
脱帽します。また、まねすべき姿勢です。2007/1/1T
-
小学校英語活動 365日の授業細案すぐ使えるゲーム&イラスト集
- 刊行:
- 2005年2月7日
- ジャンル:
- 総合的な学習
- 対象:
- 小学校
- 小学校の英語必修化について多く議論されている今日、「どんな英語活動を組めばよいのか?」「6年間を通したカリキュラムをどう作るのか?」「手軽に英語活動をするには?」などの”英語”にまつわる悩みが多い時代となりました。
その時、その本はとても役立つ。カリキュラムの編成、ゲームのアイディア、そして授業で活用しやすいカード類が充実でいている。また活動の様子をCD−ROMで見られるのもとてもためになります。
「英語どうしよう?」と思っている人には是非お勧めです。また、たくさん英語活動の書籍が発売されていますが、その中の一冊に加えて頂く価値のあるものだと思います。
まずは授業細案のままやってみてください。年間数時間の英語活動への消極的な気持ちがやわらぎ、楽しく簡単な英語活動を行えます。英語活動の敷居を下げてくれる内容となっています。2006/12/26stargazer
-
調べる力・考える力を鍛えるワーク社会科の基礎基本学力をつける
- 刊行:
- 2002年8月
- ジャンル:
- 社会
- 対象:
- 小学校
- 教科書や資料集では小さくしか載っていなくて使いにくかった資料がこのワークには詳しく大きく載っていて授業で使いやすいものになっています。
イラスト形式は子どもの関心を高め、用意されている質問・発問も詳しく書かれ、解説も十分にあって授業でとても使いやすいです。また、自分なりに加工して使える発問もたくさんあります。
歴史嫌いの子どもでもイラストには興味を持たせてくれ、このワークを使った授業では通常の調べ学習よりも意欲的になりました。
イラスト資料も貴重な資料財産となる優れものでした。有田先生の教材研究のおいしいところを手軽に味わえるものとなっています。
授業でぜひ、活用してみてください。特に導入や資料活用の授業で役出てます。2006/11/25スターゲイザー

















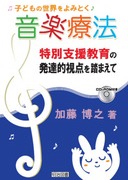
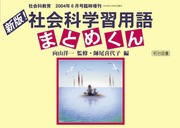
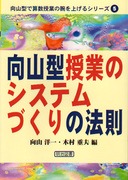
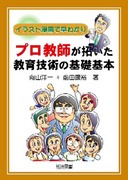
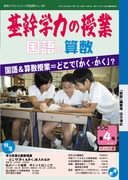

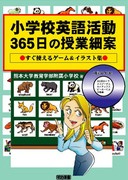
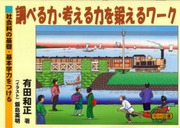

一例を挙げる。昼休みにドッジ・ボールをやっている。で、リーダー格の子供が「最後にボールをさわった人がボールを片づけることにしよう!」と提案し、ほかの子供も同意する。で、最初の二、三日はわりあいうまくいくのだが、あるときから、特定の子供(Aとしよう)をターゲットに、集中的にボールをぶつける。つまり、Aにボールを片づけさせるのである。
で、Aはふてくされて、校庭にボールをおきっぱなしにしたり、リーダー格の子供と喧嘩になったりする。で、担任の先生が「子供の声に耳をかたむける」と、いったいどうなるかというと、Aが、みんなできめたルールを守らなかったということが分る。で、Aは怒られてしまうわけだ。「みんなできめたルールなんだから、きちんと守らなくちゃダメよ!」と。
ちなみにこれをふせぐためには、ふだんから「ボールにせよなんにせよ、物は、それをだしてきた人が片づける」というルールを徹底させなければならない。で、こんなのは教育現場の常識中の常識と思っていたのだが、あんがいそうでもないというか、上の「最後」のルールについて、うまくいっているんだったらそれでいいじゃないかといわれたことがあるのである。
教師の善意が、正しい方向で使われるために!
コメント一覧へ