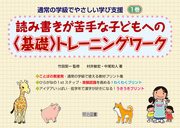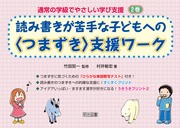- �x���̂���N���X�Â���
- ���ʎx������
�@����͗��N�x�́u�x���̂���N���X�Â���v�ɂ��Ă��搶�����k�ɂ�������Ⴂ�܂����B
���搶
�@���N�x�A���ʎx������Ɋւ��邢�낢��ȑΉ��������Ă��������܂����B�S������܂��V�����N���X�̒S�C�ɂȂ�܂��̂ŁA�����ł�����x�A���ʎx������̎��_���������w���o�c��q�ǂ��̑Ή��̃|�C���g�������Ă��������B
�T�q�搶����̃A�h�o�C�X
�@�S���̎������k���́A�S�̂Ƃ��Ė��N�������Ă��܂����A���ʎx�������v����q�̐��́A���ɑ������Ă��܂��B���ɒʋ��ɂ��w������]���鎙�����k���͉E���オ��ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���݂͐��I�Ȏx���͎Ă��Ȃ����A���炩�̎x�����K�v�Ǝv����P�[�X�����ɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�@�܂�A���ꂩ��́A�ǂ̋���̏�ɂ����Ă����ʎx������̎��_���������w�����K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�u���ʎx������v�Ƃ����ƁA�������ʂȒm����Z�p���K�v���Ǝv���܂����A����Ȃɍ\���邱�Ƃ͂���܂���B�V�����N�x�̃X�^�[�g��O�ɂ��āA������ƈӎ����Ă���������A�����̎q�ǂ����������S���ăX�^�[�g���邱�Ƃ��ł��܂��B
�N���X�S�̂̂��Ƃ��l���܂��傤
�@�w���o�c�̊�{�������Ă݂܂��B
�E��l��l���ɂ����w���o�c
�@����͓��ʎx����K�v�Ƃ���q�ǂ��������ɂ���w���o�c�̂��Ƃł͂���܂���B�����Ђ����͂ǂ̎q�ɂƂ��Ă���Ό��Ȃ��Ƃł��B
�E�������[���A�w�K���[���m�ɁA���[���ɉ������w���o�c
�@���ɂ���āA�l�ɂ���ă��[�����ς�邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
�E�ǂ����Ƃ͂ǂ̎q���ق߁A���߂Ȃ��Ƃ�������ǂ̎q������
�@�قߕ��A������ɂ́A�����ŁA�킩��₷�����t�̑ԓx���K�v�ł��B
�E�킩��₷���A�y��������
�@�q�ǂ������ƂɏW���ł���悤�ɁA���ƌ`�Ԃ���e�ɕω����������Ă����Ƃ悢�ł��傤�B
�E���o�x�����̍H�v
�@�q�ǂ��̋����E�S����������悤�r�W���A���Ȓ��@���̍H�v�ɓw�߂܂��傤�B
�E�͂�����ƒZ���w���E����
�@�w��������́A�͂�����ƒZ�������q�ǂ��ɂ͂킩��₷�����̂ł��B
�@�ǂ���w���o�c�̊�{�ł���A������O�̂��Ƃł����A���̓�����O�̂��Ƃ��S���A�T���ł������艟�����Ă������Ƃ���ł��B�S�C�����[�_�[�V�b�v�����āA�i�߂邱�Ƃ��ł���ƁA�ǂ̎q�����S���ĉ߂����A�����������N���X�ɂȂ�܂��B
�@�����������̂킩��₷�����[�������闎���������N���X�́A���ʎx����K�v�Ƃ���q�ǂ������ɂ��߂����₷�����ƂȂ�܂��B
�ʂ̎x�����K�v�Ȏq�ǂ��ւ̑Ή��ɂ��čl���܂��傤
�@�N���X�o�c�̑�O��Ƃ��āA
����͂��ׂĂ̎q�ǂ��ɕ����ɗ^���������
�x���͈�l��l�̃j�[�Y�ɉ����ė^�������
���Ƃ������Ƃ��o���Ă��������B�܂�A��l��l�ւ̋�̓I�Ȏx���̓��e��ʂ͈قȂ�̂ł��B
�E��l��l�̂��ɂ����ɖڂ������悤
�E��l��l�̍D���Ȃ��Ƃ⓾�ӂȂ��Ƃɂ��ڂ������悤
�E�ʂ̎w���v���ʂ̎x���v��A�A�w�x���V�[�g��L���Ɋ��p���悤
�@�N�x�̏��߂ɂ͕K���ڂ�ʂ��āA��l��l�̔z��������w�����e�ɓ���Ă������Ƃ���ł��B
�E���ӂ���Ƃ��ɂ́A�Â��Ȓ��J�Ȍ��t��
�@�������ӂ́u�{��ꂽ�v�Ƃ����C�����������c��A�ǂ����Ă�����ꂽ�̂��͗����ł��Ȃ��܂܂ɂȂ�܂��B
�@�����ŗ��������A�吺���o���A�F�B�ɗ��\�ɂȂ�Ȃǂ̖��s���ɂ́A�K������������͂��ł��B�������s���Ƃ��ĔY�ނ̂͂Ȃ��A���̎q�͉����������Ă���ȍs�����Ƃ��Ă���̂��낤�ƍl���Ă݂Ă��������B�����̓��������Ă��܂��B
�@�������q�ł͂Ȃ��A�����Ă���q�Ƃ��čl���Ă�����ƁA�����v�����͂��ł��B
���搶
�@�䂤���搶�A�w���o�c�̃q���g�����肪�Ƃ��������܂����B�S���E�T���������ł��ˁB������Ă݂܂��B
�V�w���E�ǂ̎q���y�����x���̂���N���X�Â���̃|�C���g
- �����Ă���͎̂q�ǂ��̎��_��Y��Ȃ�
- �q�ǂ��̎��_�ɗ����āA�������w���̍H�v���l����
- �搶���g���y�������S�n�̗ǂ��N���X���Ǝv���邱�Ƃ����
-
�ǂ߂��I�������I�P�N���́����ȏ��̊������w�юx���I
-
�u�킭�킭�v�u���������v���u�ł����I�v�ɂȂ���v�����g�W
-
�ǂ̎q���ł����I�ɂȂ��鋳�ނ̃��j�o�[�T���f�U�C���I