
- ����I�s�j�I��
- ���ƑS��
�@�E���������Ă݂�ƁA�����Ԃ�ƎႢ�搶���������Ȃ��Ɗ����܂��B��X����́A���݃~�h�����[�_�[�Ƃ��Ċe�Z�̒��j��S���|�W�V�����ɂȂ��Ă��܂����B�܂��A����܂Ō�������������Ă��Ă����������A������x�e�����ƌ�����搶���̐����ǂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B����Ԍ𗬁A�����āA�����p�����}���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�S���I�Ȋw�Z�ł̉ۑ�ƂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���N�x�A�V�̗p�̐搶����̐搶�Ɗw�N��g�݁A�q�ǂ������Ɛ������A�w���o�c���Ă���搶���͏��Ȃ��Ȃ��͂��ł��B����Ȓ��ŁA�f�ތ�������n�܂�A���ތ������s���A���ƌ������d�ˁA���X���H���Ă��܂��B�������A�������Ƃ��āA�Z��������̎d���ŏo���ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ�������A�w�����ł̃g���u���̑Ή��ɒǂ�ꂽ��ƁA�Ȃ��Ȃ����Ƃ̏��������鎞�Ԃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����A����2�`3�N�ōl���邱�Ƃ́A�u�x�e�����̕��X���Ζ�����Ă���ԂɁA�����鋳��Z�p��w���o�c�̕��j��l�����A�q�ǂ������ւ̎w�����@�A�ی�҂Ƃ̘A�g�E�Ή��p�Ȃǂ�����ɋz������ƂƂ��ɁA���ւƂȂ��ł����Ȃ�������Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�c���ꂽ���Ԃ͂��Ƃ킸�����Ƃ�����@���̂��ƁA���X���߂����Ă��܂��B�܂��A�E�����ł̐搶���̎d���ʂ���A�����Ɍ����悭�A�q�ǂ������̊w�K���ʂ��グ�Ă����悢�̂����l���܂��B
�@�����ō���́A��L�̂��Ƃ���A���ƂŎg����t���b�V���J�[�h�ɓ������āA��l�ł������̐搶���̂����ɗ��Ă�Ɗ肢�A���p�p�������Ă����܂��B
1�@������O�Ǝv���Ă����X�L����������ւƂȂ��ł���
�@���ƒ��ɏo�Ă���w�K�L�[���[�h�⋳�ȏ��{�����ɏo�Ă���p��A�l�����ȂǁA��b�I�E��{�I�Ȓm���ƂȂ錾�t���t���b�V���J�[�h�ɂ��āA�J��Ԃ������Ă����A�m���̒蒅��}���Ă����܂��B���̍ۂɁA������O�Ǝv���Ă����t���b�V���J�[�h�̈��������ǂ���������O�ł͂Ȃ��Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B�����ŁA�ǂ̂悤�Ɏq�ǂ������փt���b�V���J�[�h�����悢�̂��B���t�̗����ʒu�A�����A�p���A���t�̎����A�J�[�h�̂߂�����A�J�[�h�̎������Ȃǂ��k�t���b�V���J�[�h�̎g�p��̗��ӓ_�l�Ƃ����`�Őْ��i���L�̎Q�l���Ёj�ɏڂ����f�ڂ��Ă���܂��̂ŁA���Q�Ƃ��������B
2�@���t�̋���Z�p��������ƍl���钆�ł̋Z��1�Ƃ��Ă̂Ƃ炦
�@�t���b�V���J�[�h�����ƒ��ɂ���悢�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��w�K�X�L����1�Ƃ��ĂƂ炦�āA���p���Ă����Ƃ悢�ł��傤�B���Ԃ̎��Ԃ���Ƃ̍ŏ��A�I���Ə�ɌJ��Ԃ��Ă������ƂŁA�������K�ƂȂ�A�q�ǂ������ɂƂ��Ă̒m���̒蒅��}��܂��B�����鋳��Z�p�̒��ł�1�̕��@�Ƃ��Ēm���Ă����đ��͂���܂���B�K���A����ɖ𗧂��܂��B�܂��A�q�ǂ������ւ̋�����ʂ������ł��邱�Ƃł��傤�B
3�@�e���Ȃ̎��Ƃɂ�����g�p���@
(1)�w�K���ʂ̌���
�@����ȂŌ����A�����⌾��A�S�l���A�Љ�ȂŌ����A���j�l������p��A�Z���ȂŌ����A������L���ȂǁA���X�̎��Ƃ̒��ŕK�v�ƂȂ��Ă����{�I�E��b�I�Ȓm����蒅�����邽�߂ɁA���ď����Ă��J��Ԃ��܂��B�������邱�Ƃɂ���āA�w�т̗���ƂȂ�A�₪�Ē蒅���Ă����܂��B
(2)�w�K�����̌���
�@�u����H�@�Ȃ��������H�v�Ǝv���o���̂Ɏ��Ԃ�����������A�J��Ԃ��ď����Ă��邱�ƂŁA�u���Ɏv���o�����Ƃ��ł��܂��B���ȏ���m�[�g���ēx���Ԃ��Ă��悢�̂ł��傤���A�L���Ƃ��Ďc���Ă������ƂŁA�w�K�������オ���Ă����ł��傤�B���x�����x���A�J��Ԃ��J��Ԃ��A���ꂪ��{�ł��B
(3)����y�����\
�@����A�ْ��ɂ�CD-ROM��t���Ă���A������v�����g�A�E�g������悵�B�p�\�R���Ŏ�������ăv�����g�A�E�g������悵�B���~�l�[�g������ƁA���x�ł��g���܂��B�܂��A�q�ǂ��������m�ł��g�����Ƃ��ł��܂��̂ŁA�J�̓��ɂ͋����ŐÂ��ɉ߂������߂̃A�C�e���Ƃ��Ĉꋳ����1�Z�b�g�A�������ł��傤���B�q�ǂ��������m�Ŋw�э����Ă���p��������̂��A�Ȃ��Ȃ��������낢�G�ɂȂ�܂��B
(4)�I���W�i���e�B
�@CD-ROM�Ɏ��^����Ă�����̂��g���̂��悢�̂ł����A���������ł�����A���̓y�n�A���̊w�Z�A���̊w���A�搶�����g���₷���t���b�V���J�[�h�Ɏd�グ�Ă��������A�q�ǂ������̊w�K�Ɏg���Ă���������K���ł��B�܂��A�q�ǂ������́A�I���W�i������D���ł��B���蕨��A�����ɂ����Ȃ����̂ɁA���̃t���b�V���J�[�h���d�グ�āA�Ί炠�ӂ��y�������Ƃɂ��Ă����Ă���������ƍK���ł��B
4�@�J�[�h��
�����@�w��(�Ȃ�)���̌��t�x�@
�@�������@�A�������@�B�����@�C���������@�D�������@�E�˂����@�F�������
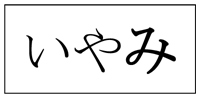
���Q�l����
![�����@���L(��)�w���Ƃ�w���o�c�Ɋ�������t���b�V���J�[�h�̍����E�g�����\CD�]ROM�t���x�i�t�����[�C2016�j](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/P/4654019278.01.MZZZZZZZ.jpg)
���Ƃ�w���o�c�Ɋ�������t���b�V���J�[�h�̍����E�g�����\CD�]ROM�t�������@���L(��)�t�����[�C2016
