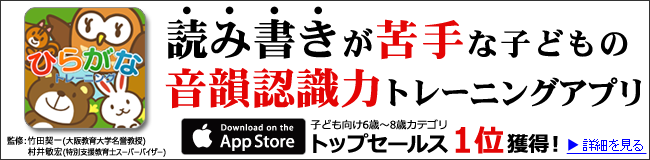- ���W�@100�ς��琶��AI�܂Ő������Ă�����Ƌ���
- ���W�ɂ���
- �q���Ɍ��ʓI�ȋ��ނ̂�����E�p����
- �^
- �g�������낢��I�@100�σO�b�Y�̊��p�p
- �^
- ���ނÂ���ɖ𗧂I�@�ŐV�A�v���̊��p�p
- �^
- ����AI�����p�����ł̒��ӓ_
- �^
- ���Ƃ������Ɗy�������鋳�ށ����p�A�C�f�A
- ��������ۑ�
- �i�P�j���ʎx���w�Z�@����^�~���[�W�b�N�p�l���V�A�^�[�Łu�E���灛�ԖځI�v
- �^
- �i�Q�j���ʎx���w�Z�@����^100�σO�b�Y�ŕ������ǂ݂�i�K�w���I
- �^
- �i�R�j���ʎx���w�Z�@�Z���E���w�^���ٓ��Â���Ő��̗���
- �^
- �i�S�j���ʎx���w���@�Z���E���w�^��������i�����E�ׂ��j���Ȃ��߁i�㉺���E�E���̈ʒu�j
- �^
- �i�T�j���ʎx���w�Z�@���������^�������ނ��g���C�X�̂킩�����m��
- �^
- �G�J�[�h����
- �i�P�j���ʎx���w�Z�@�Z���E���w�^�G�Ŋw�ԁg���h�̐��E
- �^
- �i�Q�j�ʋ��w�������@���������^�������u����v���X�b�Ɛg�ɂ��I�����Ŋw�ׂ�X���J�[�h�Q�[��
- �^
- �v�����g����
- �i�P�j���ʎx���w���@�Z���E���w�^100�܂ł̂�����1000�܂ł̂����w�K�v�����g
- �^
- �i�Q�j�ʋ��w�������@���������^�u�v���������[�N�v���g���������w�K�̎x��
- �^
- �i�R�j�ʋ��w�������@���������^�������ɂ���������悤
- �^
- �f�W�^������
- �i�P�j���ʎx���w�Z�@����^�ǂ��Ԃp�[�e�B�[
- �^
- �i�Q�j���ʎx���w�Z�@�Z���E���w�^�X���C�h�̍쐬
- �^
- �i�R�j���ʎx���w���@�����P���w�K�^�y���݂Ȃ���m���̒蒅��}��uKahoot!�v�̊��p�@
- �^
- �i�S�j���ʎx���w���@���������^����AI�ŌʍœK�Ȏ�������
- �^
- �i�T�j�ʋ��w�������@���������^�A�v���ʼn��ǂ̎x��
- �^
- �A�C�f�A�����ς��E�N�ɂł��ł���w���@
- �s����̖��Ƀ`�[���Ō��ʓI�Ɏx����������@
- �^
- �`PTR�iPrevent-Teach-Reinforce�j���f�������p������̓I�Ȏx���̎��H��`
- ���Ƃ�ʔ����������O�b�Y
- �G���Ď����I�@���Ď����I�@�҂�����10�J�[�h
- �^
- �y�����w�ԁ@�������K�̎w���A�C�f�A����
- �^
- �q���C�L�C�L�E�w�K����
- �y���������z�F�B�Ɋւ�낤�Ƃ���q�������������
- �^
- �`�݂�Ȃʼn^��ŃI�j��|�����I�`
- �g�s�b�N�X (��113��)
- �u��������R�c����������番�ȉ��ے�����@����ے������ʕ���v
- �^
- �q���Ƃ̂�������ς��錾�t�I�т̃R���Z�v�g�E���C�L���O (��5��)
- �U��̐����̌��������炷�C���V���i���r���[�t
- �^
- �z���C�g�{�[�h�E�~�[�e�B���O(R)�ł���u�ʂ̎w���v��v (��5��)
- �q���ƐU��Ԃ�\���i����c
- �^�E
- �S���w�I�e�N�j�b�N�����p�����q���̉ۑ�����A�v���[�` (��5��)
- �䖝��������q��
- �^
- �`�y�������߂̐S���w�I�Z�@�z����\�o�g���[�j���O�`
- �u���Ƃ̋����v�̒S���ɂȂ�����u���Ƃ̒x��v�̎w���@��b��{ (��5��)
- �w����g����
- �^
- �m�I��Q�җp���ȏ��\���{�\�����p�������Ǝ��H (��5��)
- �y���������z�킽�������̂܂��ipp.78�`81�j
- �^
- �ʏ�̊w���̋��Ȏw���@�ɉ������z�� (��5��)
- �Љ�Ȃɂ����鍢��ւ̎x��
- �^
- �w�т̓y�����މ^�������� (��5��)
- �w���������ł���悤�ɂȂ�^��������
- �^
- �q������ށu��Â��苳�ށv�A�C�f�A (��11��)
- �m���ƂE�R�~���j�P�\�V�����n������Ƃ��ƂΗV�с^�m���ƂE�R�~���j�P�[�V�����n�\��E���Ƃ}�b�`���O
- �^
- ���ʎx���w���̋����Â��聕�A�C�e�� (��11��)
- ���������̊w�т�����������
- �^
- �ʐ^�Ō���@�H�v���L�������������Â���E�Z�����Â��� (��44��)
- ���k�����t��ICT�����p���ċ����Ōf������n��
- �^
- �`�f�U�C���c�[��Canva�����p�������k�Q���̍Z�����Â���`
- �ҏW��L
- �^�E
�ҏW��L
�@���ʂȋ���I�x����K�v�Ƃ��Ă��鎙�����k��l��l�̏�Q����Ԃɑ������w�������ʓI�ɓW�J����ɂ́A���ނ̍H�v���������܂���B���ނ��H�v���邱�ƂŌɉ������w���̏[�����}���܂��B���̂��Ƃɂ��A�������k�̋����S�����܂�A�w�тɌ������ӗ~�����サ�܂��B����ɁA�������[�܂邱�Ƃ����҂ł��܂��B�������A�ʍœK�Ȋw�т̏[���ɂȂ���ɂ́A�e���ȓ��Ŏ������k���A�����ǂ̂悤�Ɋw�Ԃ̂��A���̂��߂ɁA�ǂ��������_�ŋ��ނ����̂��B���ꂪ�������k�̊w�т���ɂǂ��Ȃ���̂�����������ӎ����邱�Ƃ��d�v�ł��B
�@���݁AGIGA�[����P�l�P��[���̓����ɂ��A�^�u���b�g�[���Ȃǂ�ICT�����p���A�A�v���Ȃǂ����ނƂ��邱�Ƃ��i��ł��܂��B
�@�܂��A���߂ł͐���AI�̋}���Ȑi���Ɨ����p�̍L�܂�ɂ��A����AI���w�Z����ŗ����p���邱�Ƃ��b��ɂȂ��Ă��܂��B�ߘa�U�N12���Ɏ����ꂽ�u������������i�K�ɂ����鐶��AI�̗����p�Ɋւ���K�C�h���C���v�ɂ́A����AI�ɂ��āA�������k�̊w�K��ʂɂ����Ă��A��l��l�̃j�[�Y������ɍ������w�т�����������A�V���Ȏ��_����[�����_�̏o�͂���w�т�����w�[�߂��肷��Ȃǂ̗����p���i�ނ��Ƃ��\�z�����Ƃ���܂��B
�@�����Ŗ{���ł́A�u100�ς��琶��AI�܂Ő������Ă�����Ƌ��ށv�Ƒ肵�ē��W���܂����B���ނ́A���Ƃ̗v�̈�ł��B���Ƃł̎w����ʂ́A�W�c�w���y�ьʎw��������܂��B�{���W���Q�l�ɂ��āA�w����ʂɑ��������ށA�֘A�t�������ނ��H�v�����Ƃ̏[����}���Ă��������B
�@����ɁA�������k�̎��Ԕc���Ɋ�Â��A�g�ɕt�������͂ɂ��Ă̂R�ϓ_����������ӎ��������ނ����p���Ăق����ł��B
�@���悢���ލ쐬�͋��t�̏d�v�Ȑ�含�ł��B�������k���y������̓I�Ɋw�K�ł���悤�ɂ��Ă��������B�����āA�p�ӂ������ނŊw�ԁA�������k���v�������ׂď������邱�Ƃ���ł��B
�@�ċG�x�ƒ��͋��ލ쐬���邽�߂̎��Ԃ����ɂ́A�悢�^�C�~���O�ł��B�������k���킭�킭����悤�ȋ��ނ̍쐬������Ă��܂��B
�@�@�@�^�O�Y�@���L�E�����@����
�{���ł��Љ�Ă��鎑���͈ȉ�����_�E�����[�h�ł��܂��B
�����\�� ���N���b�N����ƃ_�E�����[�h���n�܂�܂��B
���N���b�N����ƃ_�E�����[�h���n�܂�܂��B
�{���Ɍf�ڂ���Ă��郆�[�U�[���ƃp�X���[�h����͂��ă_�E�����[�h���Ă��������B
�����̃_�E�����[�h
| ���e | �t�@�C���� | �T�C�Y | �@ |
|---|---|---|---|
| ���[�N�V�[�g | 26229.zip | 169KB |  |
��PDF�t�@�C���̉{���ɂ� Adobe Reader�����K�v�ƂȂ�܂��B
-
 �����}��
�����}��















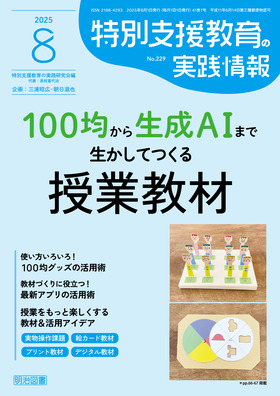
 PDF
PDF