- 特集 「ごんぎつね」の授業 THE BEST
- [巻頭提言]「ごんぎつね」はなぜ私たちを惹きつけてやまないのか
- 消失した語り手が見せてくれたもの
- /
- 「ごんぎつね」の授業 THE BESTセレクション
- 物語全文を俯瞰する読みから,ごんの変容に迫る読み
- /
- 「つぐないの数」から作品を解釈する
- /
- 二つのごんぎつねで劇的な探究活動
- /
- 「ごんぎつね」は連続ドラマで
- /
- 草稿「権狐」との比べ読みの授業
- /
- 自分だけの「ごんぎつねの世界」を表現する
- /
- 構造をとらえ、問いを深める
- /
- 自由進度学習を通して、自分の考えをアップデートする
- /
- どこで子どもは“誤読”するのか―「ごんぎつね」の難しさ
- /
- すぐに使える!「ごんぎつね」全板書 光村図書
- 1
- /
- 2
- /
- 第2特集 令和7年度 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方
- 小学校 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方
- 調査問題の出題の趣旨と活用のポイント
- /
- 中学校 全国学力・学習状況調査の見方・活かし方
- 学習指導を改善するための視点
- /
- おもしろすぎて誰かに話したくなる教室から広がるオノマトペ (第6回)
- 宮沢賢治のオノマトペ
- /
- 言葉による見方・考え方を働かせる学習課題 (第6回)
- 理論/「言葉による見方・考え方」と個別最適な学び,および,協働的な学び
- /
- 小1/やくそく(光村図書)
- /
- 小2/ニャーゴ(東京書籍)
- /
- 小3/グループの合い言葉を決めよう(東京書籍)
- /
- 小4/クラスで話し合って決めよう(東京書籍)
- /
- 小5/心の動きを短歌で表そう(東京書籍)
- /
- 小6/模型のまち(東京書籍)
- /
- 中1/星の花が降るころに(光村図書)
- /
- 中2/ヒューマノイド(光村図書)
- /
- 中3/故郷(光村図書ほか)
- /
- 学びが見える!今月の国語板書録 (第6回)
- サーカスのライオン(東京書籍3年)
- /
- ごんぎつね(東京書籍・教育出版・光村図書4年)
- /
- 日本語学が拓く国語科教材分析 (第6回)
- 文法的観点から分析する
- /
- 生成AI vs. 作文教育 (第6回)
- リクエストリーディングの紹介
- /
- 国語教育の実践情報 (第114回)
- 小学校/令和7年度全国学力・学習状況調査問題について〜大問3〜
- /
- 中学校/学習指導要領を踏まえた授業づくり
- /
- わが県の国語ソムリエ (第160回)
- 三重県
- /
- 編集後記
- /
- 今月号 掲載教材一覧
編集後記
小誌ではここ数年、「徹底研究「ごんぎつね」「故郷」の授業」(2022年9月号)、「徹底研究「大造じいさんとガン」「走れメロス」の授業」(2023年11月号)、「徹底研究「海の命」「少年の日の思い出」の授業」(2025年1月号)と三回にわたって特定の教材に特化した特集を組んできました。
当初は、あまりに間口が狭いのではないか…という懸念もありましたが、蓋を開けてみればかつてないほどの反響・ご好評をいただき、連続企画となりました。定番教材で研究しつくされている…と思いきや、いただいた原稿からは、読めば読むほど新しい発見があり、その魅力に虜になるという、教材の底力を感じるとともに、ご執筆いただいた先生はもちろん、ご感想をお寄せくださった先生みなさまの、教材への熱い思いも感じられました。
――といった経緯もありまして、今号でも、「ごんぎつね」を再び取り上げてみようと思いました。「ごんぎつね」は、書籍・論文といった先行研究はもちろんですが、SNSで検索しても、板書例からちょっとしたつぶやきまで、山のようにヒットします。私も含め、ですが、多くの先生方が「ごんぎつね」が大好きなんだなとあらためて思いました。ゆえに、今回は既刊号とはちょっと趣を変えて、それぞれの先生の「ごんぎつね、大好き!」が感じられる項目立てにしてみました。バックナンバーとも見比べながら、ぜひ「ごんぎつね」の魅力を再発見いただき、授業づくりに役立てていただきたいと思っています。
/林 知里
-
 明治図書
明治図書- 英語科の教員をしていますが、国語教育から学ばせていただいていることが非常に多いです。今後も購読を楽しみにしています。2025/10/2240代 研修主任
- ごんぎつねの研究授業をしたかったのですが、一度にこれだけの先生方の考えを拝見できて、とても便利だし、勉強になりました。2025/9/2220代・小学校教員















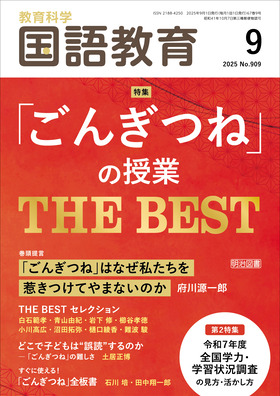
 PDF
PDF

