- 特集 総力大特集 令和時代の新教養!国語教師のための重要用語事典
- 教育・授業のキーワード
- 教育施策
- 1 OECD2030
- /
- 2 GIGAスクール構想
- /
- 3 個別最適な学び
- /
- 4 プログラミング教育
- /
- 授業デザイン
- 5 インストラクショナルデザイン
- /
- 6 インタラクティブ・ティーチング
- /
- 学力・学び
- 7 PISA型読解力
- /
- 8 深い学びと思考ツール
- /
- 9 マジックワード
- /
- 関連科学
- 10 メタ認知
- /
- 11 非認知能力
- /
- 12 メタ言語能力
- /
- 国語教育・授業のキーワード
- 学習指導要領
- 13 言葉による見方・考え方
- /
- 14 考えの形成
- /
- 15 3観点の学習評価
- /
- 16 「論理」教育
- /
- 新しい教育
- 17 国際バカロレア
- /
- 18 インクルーシブ教育
- /
- 指導方法
- 19 読書メソッド
- /
- 20 ドルトンプラン
- /
- AIに負けない「読解力」を考える (第11回)
- 授業において「読解力」をどのように指導していくか(1)
- /
- 〜国語科の場合〜
- 問い×交流が生み出す読みの学習デザイン (第11回)
- 問いの要件から見た二つの授業実践
- /
- 論理的に「考える国語」の授業づくり (第11回)
- 「考える国語」で習得・活用する思考活動の技 その2
- /
- 〜「方法」の習得・活用〜
- 小学1年/二匹の赤ちゃんの何を比べているの?
- /
- 〜[教材]説明文/「どうぶつの赤ちゃん」(光村図書)〜
- 小学2年/中心人物のこだわりに着目して読む
- /
- 〜[教材]文学/「スーホの白い馬」(光村図書)〜
- 小学3年/物語の伏線に着目する
- /
- 〜[教材]文学/「ゆうすげ村の小さな旅館」(東京書籍)〜
- 小学4年/読み手が感じる「こわさ」から,作品の論理を読む
- /
- 〜[教材]文学/「初雪のふる日」(光村図書)〜
- 小学5年/具体と抽象に着目して要旨を捉える
- /
- 〜[教材]説明文/「想像力のスイッチを入れよう」(光村図書)〜
- 小学6年/意味段落のつながりから【根拠】【理由】【主張】の関係を捉えて要約しよう
- /
- 〜[教材]説明文/「今,あなたに考えてほしいこと」(光村図書)〜
- 主体的・対話的で深い学びを実現する学習課題&発問モデル (第11回)
- 描写を実感的に捉え,語りの必然性を問う「トロッコ」(三省堂,東京書籍・1年)
- /
- 中学1年/筆者は何をねらったのか? 序論部の「役割」や「効果」について検討しよう
- /
- 〜2月/読むこと 【教材】「ニュースの見方を考えよう」(東京書籍)〜
- 中学2年/比べ読みをして自分の考えを築こう
- /
- 〜2月/読むこと,書く事 【教材】「達人のことば 宮大工 西岡常一・彫刻家 外尾悦郎」(三省堂)〜
- 中学3年/登場人物同士の関係に注目して読む
- /
- 〜2月/読むこと,書く事 【教材】「坊っちゃん」(三省堂)〜
- クラス全員が達成感を味わう! DOI流 国語教室づくり (第11回)
- 子どもが夢中で取り組む国語科短時間学習
- /
- 野口芳宏の国語授業四方山ばなし (第11回)
- 教育技術の法則化運動・零れ話(下)
- /
- 〜講座,合宿,論文審査〜
- 国語教育の実践情報 (第59回)
- 小学校/「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料の事例4
- /
- 中学校/「調査問題活用の参考資料」の作成について
- /
- わが県の国語ソムリエ (第106回)
- 和歌山県
- /
- 編集後記
- /
- 今月号 掲載教材一覧
編集後記
新型コロナウィルスの感染拡大による臨時休校要請から1年近くになりますが,最近では,第3波の到来などが日々報じられ,学校でも新しい生活様式を常に意識した環境づくりや授業の工夫がなされていることと思います。そのような中で,2月末以降は中止の多かった研究会も,オンライン開催などに切り替えるケースが増えてきており,また個々の学校での研究授業なども参観者を制限したり,授業を動画配信したりする工夫をしながら実施されるなど,教師の学びを止めない新たな動きが出ているのを感じます。
9月には,文部科学省の「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」で,「誰一人取り残すことのない『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜多様な子供たちの資質・能力を育成するための,個別最適な学びと,社会とつながる協働的な学びの実現〜(中間まとめ)」が公表されました。ここでは,ポストコロナのニューノーマルな世界における学校教育の在り方を考えるための多くの視点が示されており,今後の動きにも注目したいと思っています。
この中間まとめを拝見していますと,「AI」,「ビッグデータ」,「IoT」,「Society 5.0」,「デジタルトランスフォーメーション」「GIGAスクール構想」,「タスクフォース」,「個別最適な学び」,「STEM教育」,「SDGs」などの用語が出てきており,令和になってからのこの数年で,さまざまな新しい用語が出てきたことを実感します。
この号が刊行される2021年(令和3年)には,大学入試が大学入学共通テストに変わり,中学校では新学習指導要領による教育課程がスタートするなど,また教育界での新しい動きがある年です。このような時期であることも踏まえて,今号では,「令和時代の新教養」として,教師が押さえておきたい20の重要用語を解説していただく特集を企画いたしました。
本誌で用語の特集をするのは,2017年6月号「総力大特集 国語科授業に活かす新学習指導要領キーワード事典」以来なのですが,今回の重要用語は,教育施策,授業デザイン,学力・学び,関連科学などの教育全般に関するものと,学習指導要領,新しい教育,指導方法などの国語教育に関連するものの大きく2つに分類し,20語に絞って取り上げました。用語の解説は,関連の書籍をご執筆されていたり,その内容でご講演などをされたりしている先生方にお願いいたしました。
この号が,読者の先生方一人一人の,2021年からのニューノーマルな教育や授業を再構築する一助となればと思います。
/木山 麻衣子















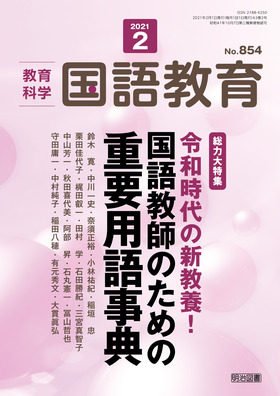
 PDF
PDF


コメント一覧へ