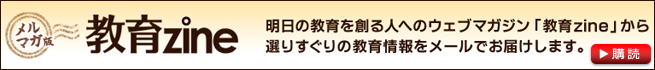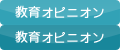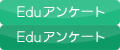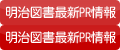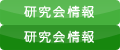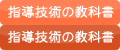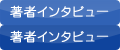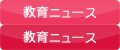- 著者インタビュー
- 授業全般
過去15年間の高校教師生活、同じく15年間の大学教員生活の中で経験的に醸し出された、よい授業を実現するための心構えのことです。
私は、自分自身が小学校から高校、大学院、老人大学まで、すべての校種でのべ1万回に及ぶ授業実践を経験しています。また、日本のみならずアメリカ・オーストラリア・フランス・イギリスを舞台に、小学校から大学までさまざまな「現場」をこの目で見てきました。そうした数多くの実践はすべて異なる出来事でありながら、どんな現場にも不易と言うべき学びの真実があるという実感が、降り積もる雪のように重なったのです。その中で、夏の日差しでも決して溶けることのないかたまりが、いつしかことばとなって自分の口から出るようになりました。それを最も簡潔なことばでまとめたものが、「授業づくりの知恵」です。
「うるさい教室ではささやき声で。」
世界のどこに行っても騒然とした学級に出会うことがあります。その教室で奮闘する先生の様子を見ていると、頻繁に「シー」と口にしたり、ご本人が「静かにしなさい」と叫んだりしておられます。
一方、同じ学校でも、子どもたちが実に穏やかに大人びた顔で授業に参加している学級を見かけます。その学級を担当するほぼすべての先生に共通してみられる特徴は、先生の話し言葉が滑舌よく、しかもささやくような音量なのです。
はじめ、私は、静かな教室だからこういう声でも通用すると思い込んでいました。しかし、そうではなかったのです。今は静かな学級でも、かつては崩壊直前の混沌に陥っていたと耳にすることが少なくありませんでした。なぜささやくように話すと教室は穏やかになるのか。ここに授業づくりの知恵が隠されています。
「『どうすれば』の前に『どうしてか』と考える。」
「言語活動の充実」と耳にすると、子どもたちが盛んに発言したり夢中で作文を書いたりする姿を思い浮かべることでしょう。そして、そういうカタチを実現するにはどうすればよいかを考える。でも、なかなか目の覚めるようなアイデアは思い浮かばず、指導書を参考にどうにか切り抜ける。これが多くの先生の日常ではないですか。それでかまいません。
充実した言語活動の究極は、子どもの自己内対話活動の充実にありますので、外面でどんなに稚拙な言語活動が展開されてもどうってことないのです。問題は、見た目によい活動を披露することが言語活動の充実だと思い込んでしまうことです。力のある先生ほどこの錯覚に陥ります。言語活動の充実として大切なのは、活動の見た目でなく、その意味です。何のためにこういう活動をし、何がどうなることが充実なのか、それを常に考えて授業づくりを目指してください。
「答えはいくつあってもよいが、無限ではない。」
国語の授業では、しばしば答えが一つにならないからもどかしいという声を耳にします。もとより、問いの答えというのはどの教科でも必ずしも一つに限りません。
たとえば数学でも、解が1<χ<5であれば、この枠の中に収まる答えとしての数値は一つではありません。だからといって1や6は正解ではありません。答えが一つに定まらないような活動の評価には、(1)それがわかっているか、できるかどうかという二者択一的な次元と、(2)どのようにわかっているか、どの程度までできるかという質的な次元との、二つの次元があります。
まずは(1)がどういうことかをしっかりとことばにしてください。先ほどの数学でいえば、子どもの答えが1<χ<5の中に収まるかどうかということです。その上で、(2)に臨んでください。1<χ<5に含まれる変数を最低1つ指摘できるというレベルから、問いの答えは1より大きく5より小さい数であるという枠組みを発見するレベルまで、子どもの知識・理解には差があります。それは実際に子どもたちと学びを共有する中で実感することになります。
答えが限りなくあるようにみえる問いでも、二者択一的判断の次元では正誤が指摘できることを先生が自覚しておいてください。答えはいくつあってもよいですが、問いに対応する以上、どこかで閉じていなければなりません。
あとがきに書きましたが、授業というのは教師の設計通りに動く機械ではありません。教師の存在が決定的に大きいことは事実ですが、授業づくりの主体は教師と子どもたちです。授業に参加するすべての人によって協働的に生成される予測不可能な出来事こそが、現実の授業なのです。
ですから、若い先生方は、まずは子どもとともにあるという感覚を経験してください。彼らは授業を受けるプロです。どういう授業が快適で、どういう授業がダメか、体でわかっています。そういう現場に身を置いてたくさんの失敗をし、省察し、そうして長い時間が過ぎ、教師としての力量が熟成するのです。誠実に授業に向かっていれば、こういうときにはこうするというノウハウではなく、こういう心構えで子どもたちに向かえばよいのだという身体感覚が身につきます。
本書は、その身体感覚を引き起こす引き金だと思ってください。授業は、本質的に教師の思い通りになりません。それが本書に一貫した姿勢です。本書の知恵は読者のみなさんの授業スタイルを縛りません。だからこそ、さまざまな現場で使えるはずです。
我ながら、こういう本を上梓できて、本当によかったと思っています。