- 特集 小集団学習に入れる“共同と競争”の条件
- 授業に小集団学習は必要か?―と問われたら
- 自律性と創造性が授業づくりの命
- /
- 学び合うために
- /
- 最大効用は「気晴らし」
- /
- 〈QAで解明〉授業に小集団学習=入れ方の基礎知識
- 小集団学習の規模・人数
- /
- 小集団学習と机の配置
- /
- 小集団学習の時間数
- /
- 小集団学習と教師の出番
- /
- 小集団学習の評価
- /
- 小集団学習の定番を活性化する“共同と競争”の条件
- 観察活動
- 細部のズレを修正し、正しい観察ができるようになる集団活動
- /
- 調査活動
- 「共同、競争」せざるを得ない状況に教師が追い込め
- /
- 話合い・発表活動
- 心地よさが生まれるか
- /
- 作業活動
- 作業の「目的」をはっきりさせよう
- /
- 板書活動
- 「競争を意識した板書」で理解を深める
- /
- 小集団学習で陥りがちな問題点と対応策
- リーダーが固定化しやすい
- リーダーの固定化を防ぐ三つの方策
- /
- メンバーチェンジ
- 日常的な学級経営・授業づくりにこそメンバーチェンジの対策はある
- /
- 小集団間の関係づくり
- 子どもの力関係に左右されない小集団を教師が保障する
- /
- 小集団と全体の関係づくり
- 「習得の場面」か「活用の場面」かを意識する
- /
- “共同と競争”が効果をあげる小集団活動の場づくり
- 小学校国語
- 「討論の授業」という場は集団の思考を高める
- /
- 小学校社会
- 集団知の授業=河田流共同・競争の場づくり
- /
- 小学校算数
- 具体的な手順や役割を教えない小集団活動は「放置」である
- /
- 小学校理科
- 脳内神経伝達物質に着目せよ
- /
- 小学校体育
- 変身ロープリレーで、共同と競争の場づくりをする
- /
- 小学校英語
- ペアがつくれると四人組がつくれる
- /
- 中学校国語
- 小集団を活用する三つの場
- /
- 中学校社会
- 「わかる! できる! 笑いがある!」協同学習を目指して!
- /
- 中学校数学
- 生徒の出力場面を増やす効果的な小集団の場づくり
- /
- 中学校理科
- 理科室の実験班を活かした共同と競争
- /
- “協同と競争”が効果をあげる小集団活動の場づくり
- 中学校英語
- /
- 教育研究スクランブル
- デューイ&“学びの共同体”の教育論
- /
- ヴィゴツキー&“学びの共同体”の教育論
- /
- フレネ&“学びの共同体”の教育論
- /
- “この教育用語”のルーツ&活用凡例
- 教え合い・学び合い
- /
- 対話と話合い
- /
- 基礎学力と発展的学力
- /
- 自立と助け合い
- /
- 集団とリーダーの必要性
- /
- 発信型学力と受信型学力
- /
- 競争と切磋琢磨
- /
- 学びの共同体
- /
- いま流行“学びの共同体”の小集団学習に思うこと
- 公開研修会=参観記
- 小集団による学習は、学力を保障できるのか―中学校数学の授業―
- /
- 「アジアで一斉授業は北朝鮮と日本だけ」は本当なのか?―高校国語授業―
- /
- 見せかけの学びあいで、学力保証がどこにあるのか―中学二年・英語―
- /
- 「聴き合う」姿勢は、すばらしいが……―小学三年・国語の授業―
- /
- 「公開研修会=参観記」を読んで
- 「学び合い」についてのディスカッションを
- /
- さらなる「教育の公共性」の広がりを
- /
- 万能薬はない
- /
- 教員が創る「教えの共同体」
- /
- 小特集 教師は“笑顔が勝負”=私のトレーニング法
- 鏡を見て毎日笑いの練習をする
- /
- 圧倒的笑顔のためのトレーニング、5つの秘訣
- /
- 幸福感をもてる授業をつくっていくことこそが笑顔の秘訣
- /
- 毎日の「鏡」との対面が勝負
- /
- 子どもをほめて、笑顔になる
- /
- 頭を通さないで出てくるのが一番美しい
- /
- 幼児の済んだ瞳が、「笑顔」を鍛える
- /
- どんな気分のときも笑顔でいる、と心に決める
- /
- 崇高な心は無くても笑顔は出来る!
- /
- 私の教室環境づくり―ポイントはここだ (第7回)
- 教室環境と「授業の学び」をつなぎ、授業を活性化する
- /
- 私のクラスの“学級通信”or“学級新聞” (第7回)
- 学級通信、学級新聞はホントに必要!?
- /
- 表紙の絵・目次の作品 (第7回)
- 読書感想画への道7/【就学旅行絵巻】
- /
- 授業と学級づくりのインターフェース=今月の先回り布石 (第7回)
- 〈1・2年〉思いやりのある子どもを育てよう
- /
- 〈3・4年〉授業で「譲る」経験をさせる
- /
- 〈5・6年〉校外学習・宿泊学習グループ決めは教師が仕切る
- /
- 谷和樹プロデュース ビギナーズ・泣き笑い道場 (第7回)
- この指導案=ここを赤ペン添削すると大成功!
- /
- ~学習活動のねらいをどのように評価するのかがわかる指導案~
- この学級経営案=ここを赤ペン添削すると大変身!
- /
- ~いじめに対する対応を校内の危機管理委員会と連動させて示した学級経営案~
- 「係・当番・日直にリズムとテンポ」 (第7回)
- 10月の重点:日直も、『ほめる』『評定する』で動かす
- /
- 今月の学校イベント=企画~本番の準備・組み立てシナリオ (第7回)
- [文化祭]「生徒主体の文化祭」の歴史を刻むために
- /
- 実物紹介=今月の生活目標 (第7回)
- 忘れ物への対応も大切な教育の場である
- /
- 今月のしつけ・重点目標はここだ! (第7回)
- 「活用力」を育てるシステムへの変換を
- /
- 師尾喜代子プロデュース“ルールとモラル”を樹立する教室づくり (第7回)
- 【今月のルールづくり】雨の日のルール
- /
- 【今月のモラルづくり】高学年女子の心とうまく付き合う技術6
- /
- ~難しい時期だからこそ、上手く付き合う技術が必要!~
- 生徒指導主任日誌=教師の本気度こそが試されているのだ! (第7回)
- 本物の小中連携を目指す
- /
- 特別支援教育に正対する=教師の剣が峰はここだ! (第7回)
- やめさせるより満足させる
- /
- 編集後記
- /
- スキマ時間に使えるトレンド情報 (第7回)
- どの子も熱中!で図工大好き!“動物の絵”
- /
編集後記
半年ほど前、ある附属の先生から、「今、流行している“学びの共同体”に関わる実践で出版したい」というメールをいただきました。“学びの共同体”とは、東大の佐籐学先生が推進されていることは承知していたのですが、附属の先生からもこういうお話があるとは…とびっくりすると同時に「学校とはそもそも、本来、“学びの共同体”じゃないですか。言葉のトートロジーでは…」とエラソーにご返事したことがありました。
で、今回この問題を取り上げるにあたり、
・そもそも学級に小集団が必要なのか?
・必要だとすれば、どういうことを土台にして実践する必要があるのか?
・ 今、全国の中学校、一〇〇〇校に及ぶという“学びの共同体”の実践の広がりには、どういう教育的・時代的背景があるのか?
・ そもそも、“学びの共同体”の源流は、デューイやヴィゴツキーの影響があるといわれますが、今から一六年前の一九九六年には、『フレネの教室“学びの共同体”』という書籍も出版されているのに?、何でここにきて大流行しているのか?
などに迫ってみたいと願いました。
それにしても、最近、ベテランの先生方からの、「一斉授業が出来ない人が小集団学習だと言って逃げ込んでいる」というキツイ意見もあります。そういうことも背景にあるのかなと思う一方、「学力向上の方策の一環として取り入れることが半ば強制された“習熟度別指導”の、いわば後遺症?として、学級の中に“共同体意識”を醸成したいという願望が広がったのではないか」という気もします。
ところで、どんなに?一斉指導が上手い教師でも、学習活動のねらいによっては、小集団活動を導入することは普通に行われていると思います。
ま、それだけ多くの授業で活用されているのは、導入に効能があるからなことは当然ですが、その効果を一層高めるには、“小集団内の共同と競争”また“小集団間の共同と競争”という教育的作用を意識し、双方のバランスをどう押さえるかが成否を握る大きなカギとなるのではないか?と思い、あえて特集タイトルに“共同と競争”と掲げました。
(樋口 雅子)
-
 明治図書
明治図書















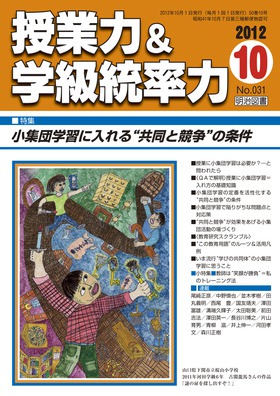
 PDF
PDF

