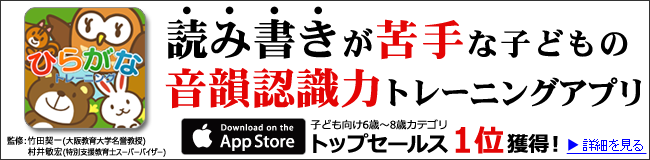- 特集 子どもが生きる,伸びる学級経営の工夫
- 特集について
- /
- 提言・子どもが生きる,伸びる学級経営とは
- まず教師の側が変わる
- /
- 子どもが生きる,伸びる学級経営の実際
- 小学校低学年の学級経営
- 基本的な行動を最優先する〜スムーズな移動に向けて〜
- /
- 子どもと一緒にクラスを作ろう
- /
- 決まり事や約束事のある生活の基盤をつくる
- /
- 小学校中学年の学級経営
- 絵や場面の変化に目を輝かせる敦史〜子どもの「この子らしいところ」に注目して〜
- /
- 児童が生き生きと主体的に活動できるようになるための学級経営
- /
- 小学校高学年の学級経営
- A児に対して行った学級経営と「音楽(好きなこと)」が有効な支援となった実践について
- /
- 子どもの「こだわり」の活用
- /
- 個々の児童の実態に応じた学習環境の整備と学習支援
- /
- 中学校の学級経営
- 一人の世界から友達を意識して関わるクラスへ
- /
- 楽しみながら,友達とつながる
- /
- 個別の学習から小集団での活動につなげて〜生き生きと活動できる学習場面の創造〜
- /
- 高等学校の学級経営
- 「自分だけの世界じゃない」〜コミュニケーション能力の向上を目指す〜
- /
- 就労体験から企業への就職へ〜就労体験に必要な力を身に付けるために〜
- /
- 特別支援学校における自閉症学級と学校経営
- /
- 子どもの作品
- /
- 構造化のアイデア (第10回)
- トイレットペーパーを補充するお手伝いの構造化
- /
- 自閉症の子どもに効果的な教材・教具
- 「図工大好き!」〜子どもが一人で活動し,満足感を味わうことができる授業の教材・教具〜
- /
- 自閉症の子どもに効果的な授業の工夫
- Mさんが主体的に取り組む姿を引き出すための支援
- /
- 学校と家庭の効果的な連携の実際
- 校外学習を通しての連携の例
- /
- こんな余暇の利用の仕方がある
- 一人でも,みんなと一緒でも,楽しく
- /
- こんなパソコンの利用の仕方がある
- 教科書・スキャナー・プロジェクターを活用した授業展開の工夫
- /
- こうすれば不適切行動は改善できる
- 攻撃的な行動が改善したA君の事例
- /
- 実践研究
- 自閉症の子ども達に英語活動を!
- /
- 何でも教育相談室
- 重度自閉症児の,自立に向けての相談
- /
- わが校の自閉症教育
- 「わかりやすい」「すごしやすい」環境を整えることへの取り組み
- /
- 本の紹介
- 「図解・よくわかる自閉症」
- /
- コミュニケーション能力を高める支援・対応 (第3回)
- 絵・写真・身振りを用いたコミュニケーションの形成
- /
- 子どもを生かすアセスメントと授業改善 (第3回)
- 把握した実態の解釈と授業づくり
- /
- 指導者に求められる実践力とは (第3回)
- 援助する力と最適な補助・修正の方法
- /
- 企業で働く人たち (第11回)
- ひと・もの・雰囲気に支えられて生き生きと
- /
- 自閉症の子どもを育てて (第11回)
- 英を育てた人たち
- /
- 就労を実現する自閉症教育 (第11回)
- 日常生活の指導の再検討を
- /
- 編集後記
- /
特集について
子どもが生きる,伸びる学級経営の工夫
今回の特集では,どのような学級経営をすれば,自閉症の子どもが生き生きと活動し,伸びるのか,どういう学級経営方針を立てればより効果的か,学級担任は何に留意し,指導,支援をすべきか,について考えてみたいと思います。
学級経営とは,学級の全教育活動の計画,展開,運営を言います。具体的には教育課程,授業,家庭との連携,学級事務,健康・安全に関することなど,子ども達に学校で行わなければならないすべての活動を指します。子どもに焦点を当てれば,「子どもが学校生活で自主的,主体的に活動できるようにするためにはどうすればよいかを考える」ことが学級担任が行うべき,最優先の学級経営ということになります。学級経営は学級担任にとっては,まさに命とも言えるものであり,学級経営の仕方,方針,工夫により子どもの伸びがまったく違ってくることは言うまでもありません。
学校現場を訪問すると,子ども一人ひとりが生き生きと主体的に活動し,活気あふれ,集団としてのまとまりのある学級に出会うことがあります。こうした学級の担任から学級経営方針について話を聞くと,子ども達の実態を的確に把握した上で,1年後を見通した計画を立て,個々の子どもを伸ばす方策と,学級集団をどのように育てていくかという目標が明確に打ち出されていることに気づきます。
また,その一方では,子どもが落ち着きがなく,情緒不安定で,集団学習であるにもかかわらず,集団としてのまとまりがあまり見られない学級に出会うこともあります。こうした学級の担任からは「子どもの障害が重く,多様化しているため,学級経営がむずかしい。日々対応に苦慮している」という声を多く聞きます。果たしてそうでしょうか。どんなに障害が重く,多様な障害を持つ集団であっても,個々を伸ばすことを主眼におき,学級集団としてまとめていく方策を考えていくのが,担任が目指さなければならない学級経営です。
本号では,自閉症の子どもがいる学級の学級経営で成果を上げておられる先生方にお願いして,自閉症の子どもを生かし,伸ばすためにはどのような学級経営方針を立て,どのような工夫をし,教育活動を行うべきかを,まとめてもらいました。当然ながら,年齢や学年によって学級経営は違ってきますので,小学校低学年,小学校中学年,小学校高学年,中学校,高等学校の5つの年齢段階に分けて,それぞれの時期の特徴を生かした学級経営の実際を提供してみました。学校教育12年間というサイクルを通して,効果的な学級経営のあり方を検討する機会になればと願っております。
(上岡 一世)
-
 明治図書
明治図書















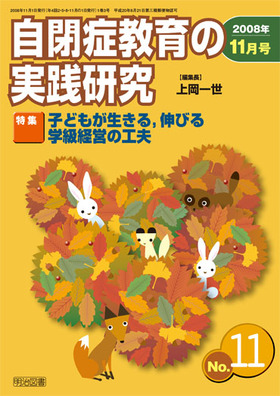
 PDF
PDF