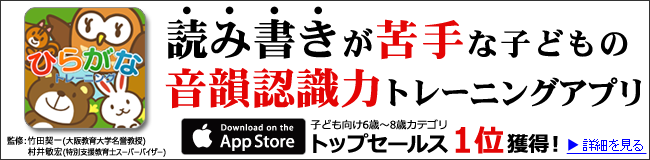- ���W�@ICT���p�E�w�K�x���E���ȕ\�o�̍��𖢗��ց`�uS.E.N.S�N����� in ���v���`
- ���W�ɂ���
- �^
- ICT��p�����w�K�x��
- �q�r�����x����ICT�C�Ȃ��K�v��
- �^
- �ǂݏ����ɍ���������������k�ɑ���ICT
- �^
- MIM��p�����w�K�x��
- �q�r���w�w�����f��MIM�@����܂ł̒m�����m���ɐ�����
- �^
- ���w�w�����f��MIM�@�ǂނ��Ƃ������ɂȂ邽�߂̎w��
- �^
- ���w�w�����f��MIM�@�ǂ݂̃A�Z�X�����g�E�w���p�b�P�[�W�̎��H����`�q�ǂ������Ɗy���ޓǂ݂̎w���`
- �^
- �q�܂Ƃ߁rMIM���ނ̂���Ȃ銈�p�ɂ���
- �^
- ���ȕ\�o
- �q�r�����I�z���̐\���ɕK�v�ȁu�����ɂ��ĕ\�o����́v�Ƃ�
- �^
- ���Z�E���w�Z�E���w�Z�̊e����i�K�ɂ�����u�����ɂ��ĕ\�o����́v����ގ��H
- �^
- �q�܂Ƃ߁r�w�Z����̂Ȃ��ň�܂��u�����ɂ��ĕ\�o����́v
- �^
- S.E.N.S�N�����@�����̗l�q
- �^
- ESSAY
- �e�N�m���W�[�̑P���g�������Ă邽�߂�
- �^
- �ʐ^�Ō���^�����B�x���Ƌ��� (��10��)
- �w�Z�����ւ̎Q�����y�ɂ���A�C�f�B�A�A�@�����ړ�
- �^
- ���B��Q�̎q�ǂ��ɖ𗧂I���傱���Ǝx���̋��ށE���� (��46��)
- To Do �����ł��傱���Ǝx��
- �^
- <���ʊ�e>�ǍD�Ȋw�K���Â���ƎЉ�⊴��ʂ̔��B���x�����鋳��
- �^
- ���B��Q�̂���q�ǂ��ւ̃L�����A���� (��2��)
- �Θb���Ƃ����Ċw�т��Ӗ��t���C���l�t����L�����A�E�p�X�|�[�g�̊��p
- �^
- ���B��Q�ƈ�Â̍ŐV��� (��2��)
- �Q�[�����������k�ɂ����炷���Ɖe
- �^
- �����ōs���@�݂�Ȃ̔F�m�s���Ö@ (��2��)
- ���Ƃ����{����\Do�i���s�j�\
- �^
- �`��L�ƘA�g�c�[���Ƃ��ā`
- ���ʎx������R�[�f�B�l�[�^�[�̎d���p (��2��)
- �ʂ̋���x���v��E�ʂ̎w���v��̍쐬�Ɗ��p
- �^
- �ʋ��w�������@���̋����Љ� (��2��)
- �q�ǂ��́g���킢�炵���h�������o���ʋ��w�������ł��邱��
- �^
- ���B��Q�ƕs�o�Z (��2��)
- �s�o�Z�ɑ��鍑�̕��j
- �^
- ��x�͎�ɂ������{
- �m���w�Z�n�ʋ��w�������S���̎d���X�L���i�R�����i���j�^�ʋ��w�������̎��H�@�A�Z�X�����g����w���܂Łi�R�c�[�Ғ��j
- �^
- ���ʎx������X�e�b�v�A�b�v�u�� (��23��)
- ���ȗ����ƃZ���t�A�h�{�J�V�[
- �^
- S.E.N.S���H�̏��� (��7��)
- �u�ЂÂ�����v����̕ω�
- �^
- �`����܂������˂ł��������I�ł����I��������ƁC���������Ď��g�߂�悤�ɂȂ��Ă����I�`
- SENS for S.E.N.S (��41��)
- S.E.N.S�ɂȂ���
- �A�Z�X�����g�Ɣ���
- �^
- �K�v�Ȏ��ɕK�v�Ȏx����
- �^
- ���ʎx������m���i�F�苦���̂��m�点
- �ҏW��L
- �^
�ҏW��L
�@�{���́C2024�N�W���Ɋ�茧�����s�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ��U��S.E.N.S�N�����in���ɂ����鋳��u����V���|�W�E���̓��e����W�L���Ƃ��ĕ��܂����B�����O����̑����̎Q��������C���O��ɂ͊��x����Ǝ��̌��C����J�Â��C�����̉�����т�S.E.N.S�ɊS���Ă��鑽���̋���W�҂ɂ��Q�����������܂����B�W�̊F�l�ɉ��߂܂��Č���\���グ�܂��B
�@���āC����x�C���W�L������Ă݂܂��B�����ł́C����S���w�҂ł���Shulman, L. S.�i1986�j������Pedagogical Content Knowledge�iPCK�j�Ƃ���ɂ�����苓�����Ă���uKnowledge of Learners and Their Characteristics�i�w�K�҂ɂ��Ă̒m���j�v�̂R�̒m�����ϓ_�Ƃ��܂��B�܂��CICT���p�ɂ��čl���܂��B����́C�V�����e�N�m���W�[��p�����uPedagogical Knowledge�i������@�ɂ��Ă̒m���j�v�Ƃ��āC��������܂��B�����āC�����������������ɗp����ۂɂ́C������@�Ƃ��Ă̊��p�����ł͂Ȃ��C������e�Ƃ��Ă̑��ʂ�����܂��B�܂�C�w�K�҂��w�ѕ����w�ԍۂ̓��e�Ƃ������Ƃł��B����͂܂��ɁuContent Knowledge�i������e�ɂ��Ă̒m���j�v�Ƃ������ʂł��B����ɁCICT�̊��p�͂��������w�K�҂̎x���j�[�Y�ɉ����Ē����ƍl�����܂��B�w�K�҂̎x���j�[�Y��c�����邱�Ƃ́C�uKnowledge of Learners and Their Characteristics�i�w�K�҂ɂ��Ă̒m���j�v�Ɋ�Â����̂ł��B
�@���ɁCMIM�ł��B���ꎩ�̂��R�̒m���������H������D�ꂽ�p�b�P�[�W�ł���悤�Ɍ����܂��B�������́CMIM��ʂ��Ă����ɓ�������Ă���R�̒m����ǎ�����Ƃ����w�т��ł��܂��B�܂�CMIM�ɂ�����uKnowledge of Learners and Their Characteristics�i�w�K�҂ɂ��Ă̒m���j�v�͂����Ȃ���̂��C���邢�͂ǂ̂悤�ȕ��@�ł��̒m���悤�Ƃ���̂��BMIM���W�I�Ƃ��Ă���uContent Knowledge�i������e�ɂ��Ă̒m���j�v�͉����B���̏�ŁC������e��w�K�҂̎x���j�[�Y���ƂɓK�p�����w�����@������MIM�ɂ�����uPedagogical Knowledge�i������@�ɂ��Ă̒m���j�v�ł���Ƃ����܂��B
�@�����āC���ȕ\�o�i�����I�z���̐\�����ɕK�v�ȁu�����ɂ��ĕ\�o����́v�j�ł��B����́C���猻��ɂ�����w�K�҂̎p��[���Ƃ��܂����B�܂�C���H���Ɋ܂܂��uKnowledge of Learners and Their Characteristics�i�w�K�҂ɂ��Ă̒m���j�v���E���グ�C�w�K�҂̐S���I���B��Љ�I���B�������Ȃ���uContent Knowledge�i������e�ɂ��Ă̒m���j�v���������C�uPedagogical Knowledge�i������@�ɂ��Ă̒m���j�v��n�o���悤�Ƃ��鎎�݂ł����B
�@�ȏ�C����قǂɁC�������̊w�тƂ��������p����`�������W�̓��X�ɏI���͂Ȃ����ƂɋC�����܂��B�����āC���̂悤�ȓ��I�ȓ��X�����C�������̎g���ł���C��肪���ł��邱�Ƃɂ��C�Â��܂��B�R�̒m���������C�����C�����ɕ\���Ȃ�C�������g�̒m���ʂƂ��Ă̒����̂��`���܂��B�ǎ҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮC���̒����̂̑̐ς��g�債�Ă������Ƃ��߂����Ȃ���C�e�n�̊e����ł�����邱�Ƃ�����Ă���܂��B
�@�@�@�^���X�@�S
�y�Q�l�����z Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15, pp.4-14.
-
 �����}��
�����}��















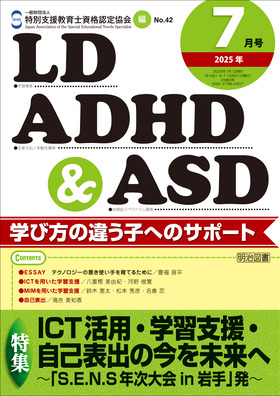
 PDF
PDF