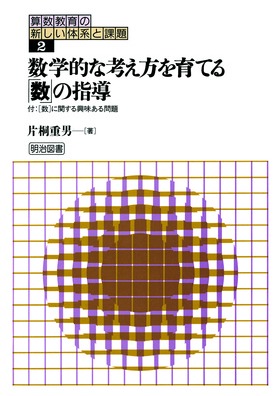- はじめに
- 第1章 「数」の指導
- §1 指導内容と指導段階
- 1 昭和23年の学習指導要領
- 2 昭和26年の学習指導要領
- 3 昭和33年の学習指導要領
- 4 昭和43年の学習指導要領
- 5 昭和52年の学習指導要領
- 6 平成元年の学習指導要領
- §2 「数」の指導内容
- 第2章 数えることと整数の意味
- §1 数えること
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 4 指導の留意点
- 1) 数える対象を明確にとらえることの指導
- 2) 一対一対応の数量の保存性を考えさせる指導
- §2 数の用いられる場合
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- §3 数え方の工夫
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 4 指導の留意点
- 第3章 記数法・命数法
- §1 十進位取り記数法
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 十進位取り記数法について
- 2) 命数法について
- 4 指導の留意点
- 1) 既習内容を生かすこと
- 2) 記数法と命数法の指導の順序
- 3) 1年で100以上を教えることについて
- 5 発展的考察
- 1) 漢数字による数の表し方
- 2) ローマ数字による記数法とその他の記数法
- 3) n進位取り記数法について
- §2 十進位取り記数法のよさと単位の考え
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 4 指導の留意点
- §3 0の意味とよさ
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 第4章 小数・分数の意味
- § 小数・分数の意味
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 4 指導の留意点
- 1) 分数や小数の導入について
- 2) 分数が2つの量の割合を表す場面の取り上げ方
- 3) 分数がわり算の商を表す場面の取り上げ方
- 4) 分数と小数,整数との関係
- 5 発展的な考察
- 1) n進記数法による小数表示
- 2) 数の関係
- 第5章 数の表現と数のモデル
- §1 数の表現と数の名と数字
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 数の抽象と数概念
- 2) 数の表現
- 3) 数のモデル
- 4 指導の留意点
- 1) 数の抽象の指導
- 2) 数直線の指導の系統
- 3) 数図などの教具の活用と誤用
- §2 小数・分数の表し方とモデル
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 小数のモデルとしての数直線
- 2) 分数のモデルとしての数直線
- 3) 関数尺としての数直線
- 4) 線分図,面積図
- 第6章 数の性質
- §1 整数と小数の大小順序と記数法(数直線)
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察と指導の留意点
- 1) 整数の大小順序の基礎的な経験
- 2) 整数・小数の大小順序と数直線
- 3) 整数・小数の大小順序と位取り記数法
- §2 数の合成・分解
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 数の合成・分解(1)
- 2) 合成・分解の教育的価値
- 3) 数の合成・分解(2)
- 4 指導の留意点
- 1) 1つの数が種々の2数に分解されることの指導
- 2) 1つの数を他の数の積で表す指導
- §3 約数・倍数
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 1) 約数・倍数
- 2) 偶数・奇数
- 3 詳しい考察
- 1) 約数・倍数・公約数・公倍数の求め方
- 2) 偶数・奇数
- 3) 剰余類
- 4 発展的考察
- 1) 約数の求め方
- 2) 約数の個数
- 3) 最大公約数の求め方
- 4) 最大公約数・公約数・最小公倍数・公倍数の性質
- §4 分数の大小・順序
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 第7章 概 数
- §1 概数とこれを用いる必要
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 4 指導の留意点
- 1) 「概数」を指導するとき
- 2) 概数を求める問題設定について
- 3) 小数の概数も
- §2 四捨五入,切り上げ,切り捨て
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 四捨五入
- 2) 切り捨て,切り上げ
- 4 指導の留意点
- 1) 概数をとる3つの方法のうち,適切な処理方法を判断すること
- 2) 意味の指導をしっかり行うこと
- §3 概数と近似値
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 「概数」と「近似値」
- 2) 近似値と誤差
- 4 発展的考察
- 1) 近似値の和・差
- 2) 近似値の積・商
- §4 数感覚
- 1 問題の所在
- 2 解説
- 3 詳しい考察
- 1) 数感覚の意味
- 2) 数感覚の内容と指導法
- 4 指導の留意点
- 第8章 数概念を深める興味ある問題
- §1 問題1:数カードで神経衰弱
- ・1年(目標・準備・展開)
- §2 問題2:双六ゲーム
- ・1年(目標・準備・ゲームの仕方・展開)
- §3 10,1のカードで58を作ろう
- ・2,3,4年(問題の趣旨・目標・準備・展開)
- §4 分数の3目並べ
- ・5,6年(目標・準備・展開)
- §5 カップを下に向けよう
- ・5年(目標・準備・展開)
- §6 数表の倍数のパターン
- ・5,6年(目標・準備・展開)
はじめに
算数教育に限らず,きちんと筋道立てて数学教育の研究をしようという者から,「どの本をまず読んだらよいか」ということをきかれたとき,すすめられるものが全くありません。また,算数教育を研究している人や,ベテランの教師から,これまでの自分の研究を振り返り,自分の算数教育,数学教育に対する考えを整理し,より確実なものにしていきたいが,どの書物を頼りにしたらよいだろうときかれても,紹介できる適当なものがありません。
指導事例集とか,算数教育のあるテーマについて深い研究を著した書物,啓蒙的な書物はいろいろでています。しかし,これらはいずれも算数教育の一部を取り上げたものであって,算数教育全体の中での位置づけが明確なものではありません。算数教育の講座もありますが,これとても,内容を詳しく体系的に説いてはいません。これが算数教育界で現在最も欠けている点であります。
算数教育で,確実な足場の上に立って学問的な研究をしていきたいというときには,この分野全体について,体系的にしかも詳しく示した書物が必要なのです。
さらに,系統的に各内容を深く掘り下げた研究をしていきたいというときには,確実な体系の上に立った,各内容やその扱い方の深め方を示した書物が頼りになるはずなのです。
そこで,算数教育の目標,内容,指導と評価の留意点,数学的な考え方・態度をのばす興味ある問題について体系的に詳細に考察した,この
『算数教育の新しい体系と課題 全10巻』
を著すことにしたのです。
算数教育の全内容を覆う,体系的なものにし,これからの人にとっても,ベテランの人にとっても,研究者にとっても,必ずこれを通らなくてはならないというものを著そうと努めました。
しかしこれまでに,このような書物は全く著されていないために,参考にするものがありませんでした。だからこの講座は,もっぱら,何十年かにわたって著者の頭の中に蓄えてきたものを,文字に著すということで書き上げたものです。
したがって,著者の考え,主張が強く現れているところもあります。
この講座の各巻を書き上げるに当たって,長谷川雅枝さんに大変協力していただきました。長谷川さんは,はじめは算数教育を勉強し直したいという動機から,この原稿を見始めたのですが,結局,この各巻をすべて読み,長年の算数指導の経験をふまえて,実際的なものにするための改善の意見を詳しく寄せて下さいました。これによって,一層指導の実際に応えるものになったと思います。ご自分のための時間のほとんどをこれに使われたのではないかと思います。改めてお礼を申し上げます。
最後になりましたが,この講座を出版するに当たって,明治図書の間瀬季夫氏・石塚嘉典氏をはじめ,編集部の方には,算数教育のためということで無理なお願いを受け入れてもらい,この企画から編集まで非常な苦労をかけてしまいました。ご苦労に対して,心から感謝いたします。
1995年3月 /片桐 重男
-
 明治図書
明治図書