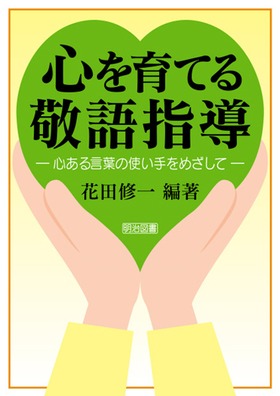- まえがき
- Ⅰ これからの敬語指導のあり方を考える
- 一 心ある言葉の使い手を育てよう
- 二 敬語の知識と運用の指導法を考える
- 三 「敬語の指針」をどう読むか
- 四 「敬語・敬語指導」に関する意見や批判をどう読むか
- 1 新聞報道の記事などに見る意見や批判
- 2 文化審議会国語分科会委員などに見る意見や批判
- 3 教育雑誌や学会誌などに見る意見や批判
- Ⅱ 敬語知識を中心とした指導の実際
- 一 丁寧語と普通語の違いに気づかせる指導(小学校・低学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 二 敬体と常体の違いに注意させる指導(小学校・中学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全三時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 三 日常敬語の使い方に慣れさせる指導(小学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全四時間)
- 3 本時の内容
- 4 本時の評価と考察
- 四 敬語の基礎知識を理解させる指導(中学校・低学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全三時間)
- 3 本時の内容(第一時)
- 4 評価と考察
- 五 敬語について理解を深めさせる指導(中学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の効果と考察
- 六 小学生が間違いやすい敬語知識を正す指導
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 七 中学生が間違いやすい敬語知識を正す指導
- ~待遇表現としての敬語~
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全四時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 八 高校生が間違いやすい敬語知識を正す指導
- ~平家物語「忠度の都落ち」から深める敬語表現への試み~
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全六時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- Ⅲ 敬語運用を中心とした指導の実際
- 一 自己紹介で敬語運用を身につけさせる指導(小学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全四時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 二 自己紹介で敬語運用を身につけさせる指導(中学校・低学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全四時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 三 インタビューで敬語運用を身につけさせる指導(小学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全三時間)
- 3 本時の内容(第一時)
- 4 学習の評価と考察
- 四 インタビューで敬語運用を身につけさせる指導(中学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全五時間)
- 3 本時の内容(第三時)
- 4 評価と考察
- 五 電話で敬語運用を身につけさせる指導(小学校・中学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 六 電話で敬語運用を身につけさせる指導(中学校・低学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 七 話し合いで敬語運用を身につけさせる指導(小学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 八 話し合いで敬語運用を身につけさせる指導(中学校・低学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全五時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 九 手紙で敬語運用を身につけさせる指導(中学校・高学年)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全三時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 一〇 小学生が間違いやすい敬語運用を正す指導(1)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 一一 小学生が間違いやすい敬語運用を正す指導(2)
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 一二 中学生が間違いやすい敬語運用を正す指導
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全六時間)
- 3 本時の内容
- 4 学習の評価と考察
- 一三 高校生が間違いやすい敬語運用を正す指導
- 1 単元設定の趣旨とねらい
- 2 単元の計画(全二時間)
- 3 本時の内容(第二時)
- 4 学習の評価と考察
- Ⅳ 敬語指導の実践に寄せる今後への期待
- 一 児童・生徒の敬語生活の実態を的確に把握する
- 二 基礎的な敬語知識や技能を実践的に活用する
- 三 国語科を中心としながら全教育活動で取り組む
- 四 心ある言葉の使い手を育てる基盤を創る
- 主な参考文献
- あとがき
まえがき
二〇〇七年二月二日、文化審議会国語分科会が、「敬語の指針」について、文部科学大臣に答申した。その中で、これまでの「敬語の種類」を三分類から五分類にしたことが大きな反響を呼んだことは承知の通りである。特に、「謙譲語」を「謙譲語Ⅰ」(「伺う・申し上げる」型)と「謙譲語Ⅱ」(丁重語「参る・申す」型)の二種類に分類したことに対して、様々な立場から賛否両論の声が上がった。
また、中央教育審議会の初等中等教育分科会は、「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」(二〇〇七年一一月一七日)を発表した。その中で、「敬語」に関しては次のような「改善の基本方針」を報告している。
敬語の指導については、人間関係を円滑にし、日常の言語生活を豊かにするため、相手や場に応じた言葉遣いが適切にできるようにすることを重視する。
さらに、「改善の具体的事項」について、「小学校」と「中学校」の項で次のように述べている。
敬語の指導については、基本的な知識を理解し、実際の場面において使い慣れるようにすることを重視する。(小学校)
敬語の指導については、社会生活において使用されている敬語の役割を知り、体系的な知識を得ながら、適切に使えるようにすることを引き続き重視する。(中学校)
なお、高等学校では、直接「敬語の指導」には触れていないが、これは中学校までの「敬語」の指導をふまえてさらに充実させることが強調されている。たとえば、次のような文言である。
中学校までに培われた国語の能力を更に伸ばし、社会人として必要とされる国語の能力の基礎を身に付けることができるようにする……(「改善の基本方針」)
実生活で活用できる国語の能力を身に付けるため……(「国語総合」)
実生活で活用することのできる表現の能力を確実に育成する……(「国語表現」)
言語生活の在り方、言語の役割、国語の特質等についても指導し……(「現代文A」)
言語の役割、国語の成り立ちや特質についても指導し……(「古典A」)
以上は、「改善のまとめ」から「敬語指導」に関わる部分を一部引用した。これらは、前出の「敬語の指針」などをふまえて発表されたものである。
このような時代の要請の中、一般社会に限らず、教育・国語教育界においても、各種の月刊雑誌や学会誌などでも、「敬語指導」に関する提言や論文や実践などが報告されるようになった。これについては、Ⅰで紹介したい。
ところで、「敬語は心ある言葉の使い手を育てることをめざして指導したい」というのが私の願いである。「心ある言葉の使い手」とは、「ものごとの本質をとらえ、目的や相手や状況などに応じて適切に言葉が使える人」という意味である。「敬語」もまた、広くとらえれば「言葉の使い方」「言葉遣い」の問題にほかならない。これについても、Ⅰで詳しく述べたい。
このような考えで「敬語」や「敬語指導」についてとらえていることを雑誌などで発表したり、国語教師の研究仲間達と語り合ったりしてきた。そんな折に、明治図書の江部満編集長から「現場の先生方に役立つような『敬語指導』のあり方について編んでください」というご依頼があった。これまで、まとまった具体的な「敬語指導」に関する本がないというお話もあり、「お引き受けします」と快諾し、本書を刊行することに到ったのである。
Ⅰでは、「これからの敬語指導のあり方を考える」という題目で、「敬語」「敬語指導」に関する様々な意見や批判などを紹介しつつ、私自身の「敬語指導」に対する基本的な考え方を中心に述べた。
Ⅱでは、「敬語知識を中心とした指導の実際」という題目で、小学校・中学校・高等学校の現場の八名の先生方に執筆をお願いした。
Ⅲでは、「敬語運用を中心とした指導の実際」という題目で、小学校・中学校・高等学校の現場の一三名の先生方に執筆をお願いした。
Ⅳでは、「敬語指導の実践に寄せる今後への期待」という題目で、現場の先生方二一名の実践報告を読んで、私が学んだことやこれからの課題だと思うことを総括編としてまとめた。
本書が、「これからの敬語指導」の方向に少しでもお役に立ち、一人ひとりの児童・生徒が「心ある言葉の使い手」として、生涯にわたって成長してくれることを願ってやまない。
二〇〇八年一月二日 書き初めの朝に 編著者 /花田 修一
-
 明治図書
明治図書