- はじめに
- 一章 子どもがぐんぐん育つ! 学級づくりの基礎を培う キラー視点
- 仕掛け場面1 始業式に「誕生日色紙」を渡す
- 仕掛け場面2 初日の姿勢に「加点法」
- 仕掛け場面3 だまって後ろに行かせてみる
- 仕掛け場面4 連絡帳を出すということ一つを大切にする
- 仕掛け場面5 よく見て描くそっくりの絵
- 仕掛け場面6 もっとやりたいプラス1の心を育てる
- 仕掛け場面7 「花心」が子ども達の中に広がる
- 仕掛け場面8 「根心」も子ども達の中に広がる
- 仕掛け場面9 二日目から図書室に行く
- 仕掛け場面10 観音タイムの実施
- 仕掛け場面11 並ぶのを待たない
- 仕掛け場面12 音がしない返却
- 仕掛け場面13 「草心」「素心」を知る
- 仕掛け場面14 人とちがうことを一つしてください
- 仕掛け場面15 【5分もある】時間心をもつ
- 仕掛け場面16 二日目に【図工】を入れて心力チェック
- 仕掛け場面17 1・2・3・4で心が揃う
- 仕掛け場面18 スケジュール速い組は「先見の明」がある
- 仕掛け場面19 「共育カード」がもどってくる
- 仕掛け場面20 廊下は玄関発想
- 仕掛け場面21 「ことわざカルタ」で心をつなぐ
- 仕掛け場面22 4月のビッグキラー視点は「揃う」
- 仕掛け場面23 1週間以内に「ザ・チャイルド」を書く
- 仕掛け場面24 子ども版「ザ・チャイルド」続々
- 仕掛け場面25 カラーバス効果の利用
- 仕掛け場面26 5月からのビッグキラー視点
- 仕掛け場面27 係システムからリーダーシステムへ
- 仕掛け場面28 よいこと10運動
- 仕掛け場面29 ラダー効果を常に意識する
- 仕掛け場面30 左利き用の定規があるか
- 仕掛け場面31 率先垂範の姿
- 二章 授業場面で鍛える! 学級づくりに生きる キラー視点
- 仕掛け場面1 体育の授業に行く時の一瞬
- 仕掛け場面2 理科室でモノの用意に工夫あり
- 仕掛け場面3 うまい字・へたな字の授業で心を育てる
- 仕掛け場面4 視点を変えることで見えるもの
- 仕掛け場面5 差と差別の授業で「差」を意識する
- 仕掛け場面6 折り紙・あやとりコンテストで教え愛
- 仕掛け場面7 知的学級掲示自学で学び心が広がる
- 仕掛け場面8 心を伝える手紙の学習
- 仕掛け場面9 学級通信で授業記録を公開し続ける
- 仕掛け場面10 集め学びで「みんな力」を高める
- 仕掛け場面11 飛び込み授業「式と計算」にみる心力アップ
- 仕掛け場面12 質問「5のトビラ」でミスに感謝
- 仕掛け場面13 ふしぎ発見虫メガネ漢字とプラス1の心
- 仕掛け場面14 すぐに作れる「マネッコ漢字問題」
- 仕掛け場面15 主役・脇役法で「宝物」をうみ出す図工指導
- 仕掛け場面16 面白ドリルワークで親子学び
- 仕掛け場面17 2mの山になる自楽ノート群
- おわりに
はじめに
教師になって,31年が過ぎました。
31年間,1年から6年までの全ての学年を担任し,特別支援学級も持たせていただきました。
いつの年も,新しい学級づくりを進めて行く過程で,この視点だけは常に意識していたというものがあります。それを「キラー視点」と呼んでいます。ちなみに,学級づくりは,子ども達の心田を耕し続けることだと思っています。
31年間,日々の一瞬一瞬の出来事にキラー視点を絡ませて,子ども達の心田を耕し,心の芽を成長させていく試みを行ってきたと言っていいです。
今回,この本を書くにあたって,31年間の学級通信・授業記録を読み直しました。すると,全ての実践の裏に,キラー視点が隠れているのを感じることができました。
この本に紹介したキラー視点は,これらです。
○必ずありがとう ○花心 ○根心 ○さり気ない手本 ○しつこい確認 ○うそも方便 ○用意,ドン発想 ○かくし指示 ○挑戦心 ○季節感 ○主役・わき役 ○特別な日視点 ○加点法 ○強く端的に褒め言葉 ○おしい ○変化・進化のあるしつこいくり返し ○待たない ○時間を守る ○見える化 ○プラス1 ○一石二鳥学び ○いいものマネ ○全員経験の原則 ○二度確認 ○ミス蜂発想 ○教え合い(教え愛) ○共育 ○相談力 ○細心 ○揃う ○他者褒め ○礼儀 ○返事力 ○Must-Can-Willの原則 ○ルールを守る ○褒め点 ○もう一歩前 ○共創 ○深化・芯化 ○自然体 ○視点の移動 ○差と差別 ○学びのおすそ分け ○親子学び ○親子対話 ○学びの動作化 ○切り替え力 ○つながり学び ○続き学び
もちろん,ここでは紹介していないのですが,キラー視点以外の「微細視点」「瞬間視点」というのもあります。
細部にわたる仕掛けです。これについては,『授業づくり編』を読んでいただけると,見えてくるのではないかと思います。
いかに細かな部分にまで,キラー視点・微細視点・瞬間視点を生かし,仕掛けを仕組んでいるか。これを感じることができるはずです。
ただ,これらのキラー視点を知ったから,学級づくりがすべてうまくいくとは限りません。
これらのキラー視点は,子ども研究と連動しているからです。
大切なのは,目の前の子ども達。キラー視点が一番ではないのです。
目の前の子ども達の「今」をしっかりとらえた上で,キラー視点を使って,どのような「仕掛け」を作っていくかを考え続けることで,学級の土壌が耕されていくのだと思うのです。
可能なら,拙著『一人ひとりを見つめる子ども研究法の開発』(明治図書)を手にしていただけるとありがたいです。
ここには,子ども達の「かすかな動き」を感じるまでに,教師自身が心を磨き,感性も磨く過程を紹介しています。
この本でキラー視点を学び,子ども研究の扉を開く。そして,授業づくり編で,授業づくりの仕掛け作りを日々楽しみ,子ども達の学び心を膨らませていく。
教師自身が大きく変わる一歩として,キラー視点があるのではないかと強く思うこの頃です。
2014年2月 /福山 憲市














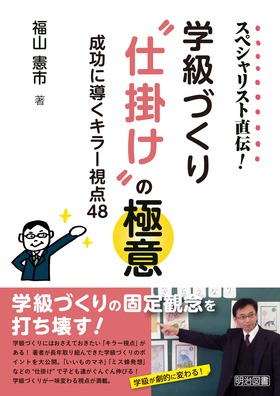
 PDF
PDF EPUB
EPUB

コメント一覧へ