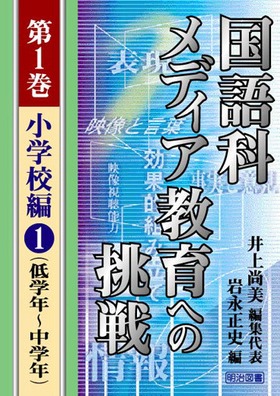- まえがき
- 国語科メディア教育とは
- Ⅰ 実践編
- 一 なつさがしをして、おてがみをかこう
- ――デジタルカメラを使って、書きたいことを集める(小一)――
- 1 お手紙を書いてみませんか?
- 2 どんなことを書こうかな
- 3 デジタルカメラを持って夏をさがしに行こう
- 4 どんな夏を見つけてきたのか教えてほしいな
- 5 楽しいお手紙を書こう
- 6 達成基準を踏まえた学習の評価
- 7 今後の課題
- 二 おしえてあげよう わたしのおきに入り
- ――写真をもとに、聞いたり思い出したりしたことを文章に書く(小一)――
- 1 わたしにもあるよ、お気に入りの写真!
- 2 さあ書こう! でも、どうやって…
- 3 おうちの人にインタビューしよう!
- 4 書く材料はそろったよ。さあ書き始めよう!
- 5 友だちの作文のいいところをさぐろう
- 6 達成基準を踏まえた学習の評価
- 7 今後の課題
- 三 鳥の絵カードで読み札作り
- ――分析的な比較検討力をつける(小低学年)――
- 1 わかりにくいヒントもあるね
- 2 どのヒントから書いたらいいの?
- 3 どの読み札がわかりやすいかな?
- 4 達成基準を踏まえた学習の評価
- 四 絵本の絵を読み解こう
- ――写真や映像を読み解く基礎は、絵の読解(小四、五)――
- 1 どこに、何が描かれているかな?
- 2 どうしてそう言えるの?
- 3 見つけたことは、どうつながっているの?
- 4 達成基準を踏まえた学習の評価
- 5 今後の課題
- 五 「読みたいな」って、開いてもらえるメールのタイトルをつけよう
- ――中身が見える素敵なタイトルを!(小四)――
- 1 電子広告を出そう!
- 2 クイズ「伝わった? わかった? 読みたい?」
- 3 タイトルのつけ方ガイドを作ろう
- 4 送ったよ 読んで感想を聞かせてね
- 5 メディアレポートを書こう
- 6 達成基準を踏まえた学習の評価
- 7 今後の課題
- 六 新聞記者に変身だ!
- ――メディアの比較を通して書く力を育てる(小四)――
- 1 取材ウオーミングアップ大作戦!
- 2 ワクワク・ドキドキ取材デビュー
- 3 知ってるつもり? 新聞のこと
- 4 違いのわかる子どもになろう!
- 5 めざせ! トップ記事の書けるトップ記者
- 6 達成基準を踏まえた学習の評価
- 7 今後の課題
- 七 二分の一成人式で自分の成長を語るデジカメスピーチ
- ――画像を言語化して表現する(小四)――
- 1 デジカメスピーチって何?
- 2 プロカメラマンの写真集から撮り方を学ぶ
- 3 デジカメスピーチのネタ探し
- 4 スピーチを分析する
- 5 スピーチの話題や撮る場面に関する思いや考えをまとめる
- 6 デジカメスピーチ発表メモ作り
- 7 自分のスピーチに合う写真をデジタルカメラで熱写
- 8 デジカメスピーチ個人練習
- 9 グループ発表会で個人のデジカメスピーチを批評し合う
- 10 二分の一成人式でデジカメスピーチを実施
- 11 達成基準を踏まえた学習の評価
- 12 今後の課題
- 八 「お客さんが喜んでくれるスーパーマーケット」の宣伝をしよう!
- ――お客さんの立場を考えたチラシ・CM作り(小三)――
- 1 こんなのうそだよ
- 2 車の広告は何曜日に多い?
- 3 チラシやテレビCMを作る作戦を練ろう
- 4 スーパーのチラシやCMを作ろう
- 5 どこのスーパーに行きたい?
- 6 達成基準を踏まえた学習の評価
- 7 今後の課題
- 国語科メディア教育の授業
- ――実践の解説
- 1 デジタルカメラで映像取材を体験する
- ――なつさがしをして、おてがみをかこう――
- 2 インタビューで映像に隠された情報に気づく
- ――おしえてあげよう わたしのおきに入り――
- 3 観点を定めて映像を見る・言葉で表現する
- ――鳥の絵カードで読み札作り――
- 4 映像からひとまとまりの解釈をつくる
- ――絵本の絵を読み解こう――
- 5 タイトルの効果に気づく
- ――「読みたいな」って、開いてもらえるメールのタイトルをつけよう――
- 6 メディアの特性を比べ、理解する
- ――新聞記者に変身だ!――
- 7 映像の効果に気づき、利用する
- ――二分の一成人式で自分の成長を語るデジカメスピーチ――
- 8 宣伝作りにとりくむ
- ――「お客さんが喜んでくれるスーパーマーケット」の宣伝をしよう!――
- Ⅱ 理論編
- メディア受容能力を育てる授業設計
- 1 メディア受容能力を育てる授業にどうとりくんでいけばよいか
- 2 メディアの特性を解説した教材から出発する
- 3 調べる学習を中心にして教科書から離れる
- 4 文学や説明文の学習を生かしてメディア受容能力を育てる
- 5 文字で培った力が基礎になる
- 国語科メディア教育のための目標分析表・評価表
- あとがき
まえがき
情報化社会といわれる現代は、同時に情報氾濫社会でもある。
莫大な量の情報を鵜呑みにすることなく、主体的・批判的に取捨選択できる能力を持つことは、現代社会に生きる市民として基本的に重要なことである。また、そうした情報を伝える媒体としてのメディアそのものの正体をよく理解し活用する能力や、インターネットなどを通じて自ら情報を発信する能力も求められている。
このような時代を迎え、国語科においても従来の内容(教材も含めて)・方法の枠内にとどまらず、新たな領域や方法の開発が求められている。
私たちは、度重なる討議の末、国語科の守備範囲内で扱うべきメディア教育の核心を次のようにまとめた。
1 二一世紀の国語教育では、文字メディアで培った力を基礎としつつ、映像メディア、コンピュータなどのニューメディアにまで守備範囲を広げるべきである。特に、それぞれのメディアの複合的使用(映像+音声+文字)を重視しなければならない。そして、メディアの特性を知ることを通して、社会における表現全体に対する認識を深めることが時代の要請でもある。
2 「国語科メディア教育」は、メディアによってもたらされる情報を鵜呑みにすることなく、これを吟味検討して読み解く能力、また、メディアを積極的に活用して効果的に情報を伝えたり、価値ある情報を創り出したりする能力を身につけさせることを目標とする。
3 これらの能力(メディア・リテラシー)は、高校卒業までに身につけさせることが必要である。そのため、小学校から高校までを見通した指導目標の分析表を提案する。
右のような趣旨に基づいて、私たちは前著『メディア・リテラシーを育てる国語の授業』(明治図書、・刊)に続いて、ここに『国語科メディア教育への挑戦』全四巻の刊行を企画した。すなわち
第一巻 小学校編1(低学年~中学年) 永編
第二巻 小学校編2(中学年~高学年) 中村編
第三巻 中学校編 大内編
第四巻 中学・高校編 芳野編
の四分冊である。各巻とも「実践編」と「理論編」とから構成されているが、とくに「理論編」については、紙幅の関係もあり、左のとおり各巻に散りばめてある。全巻を合わせて参考にしていただければ幸いである。
・「国語科メディア受容能力の授業設計」 岩永正史(第一巻)
・「戦後国語科教育におけるメディア教育の歴史」 中村純子(第二巻)
・「国語科メディア表現能力を育てる授業設計」 大内善一(第三巻)
・「国語科メディア教育の教材開発」「メディア教育先進国の現状」 芳野菊子(第四巻)
本シリーズ刊行に当たり、いつものように明治図書の江部満氏には大変お世話になった。深く謝意を表する。
二〇〇三年二月
/井上 尚美(創価大学) /岩永 正史(山梨大学) /中村 敦雄(群馬大学) /大内 善一(茨城大学) /芳野 菊子(産能大学)
-
 明治図書
明治図書