- まえがき
- 1章 「発達が気になる子」と関わる担任が読んでおきたいこと
- 1 発達障害の特性をおさえる
- 2 子どもを「みる」視点を変える
- 3 「気になる子」の気づきは行動観察から
- 4 学習環境を整え、安心できる学級づくりをする
- 5 「わかる授業」に変える
- 6 個に応じた学習指導・支援でおさえておくこと
- 7 個別の指導計画を作成してみる
- 8 個と集団を往還する支援の視点をもつ
- 9 担任だけで抱え込まずにチームで支援する
- 10 関係機関を上手に活用する
- 11 保護者との教育相談
- 2章 どうすればいい?学級生活で「発達が気になる子」とその対応
- 1 一斉指示に従って集団行動をとれない
- 2 グループ活動に参加することが難しい
- 3 気持ちのコントロールがうまくできない
- 4 机をガタガタさせたり、席を離れたりと、じっと座っていることができない
- 5 授業中の課題や遊びの活動中に注意を集中し続けることが難しい
- 6 周囲のことが気になって自分のことが疎かになるなど、落ち着きがない
- 7 先生や友だちの話を最後まで聞くことができない
- 8 作業や活動をやり遂げることが難しく、途中でやめてしまう
- 9 最後までやらないと気が済まず、途中で切り上げることができない
- 10 先生や友だちからの注意や助言を素直に受け入れられない
- 11 点数や勝ち負けにこだわり、負けを認められない
- 12 カッとなりやすく、すぐに手が出てしまう
- 13 思いつくと場面に関係なく、大声で話し出す
- 14 周りの気を引こうと、目立つ行動をとる
- 15 授業中にやるべきことに集中できずに、たびたび自分の世界に入ってしまう
- 16 身近な人と会話をしているとき、嘘をついているのではと思われてしまう
- 17 自分のやり方にこだわり、教師の指示に従うことができない
- 18 学習用具の忘れ物が多く、提出物も出せないことが多い
- 19 学習や集団のルールに従って活動することが難しい
- 20 授業中、ぼーっとしていることが多い
- 21 授業中、勝手なおしゃべりを続ける
- 22 順番を待つことや守ることが難しい
- 23 相手の気持ちや状況を考えずに思ったことを言ってしまう
- 24 友だちと協力することが難しく、何でも一人でやろうとする
- 25 気持ちの切り換えができず、次の行動に移ることが難しい
- 26 一方的に話し続けたり、脈絡もなく唐突に話し始めたりする
- 27 机の中やロッカーの整理整頓が苦手で、持ち物がいつも散乱している
- 28 自分から係活動や当番活動に取り組むことが苦手
- 29 自分の意見を一方的に主張し、友だちの意見を聞こうとしない
- 30 友だちにしつこく関わり、嫌がられてしまう
- 31 急な予定変更に対応できず、混乱してしまう
- 32 興味があることには意欲的だが、興味がないことには参加しようとしない
- 33 何事に対しても不安が強く、いつも心配ばかりしている
- 34 苦手だと思うことには、はじめから取り組もうとしない
- コラム 合理的配慮とは
- 付録 発達障害について知っておきたいキーワード集
- 執筆者一覧
まえがき
学習指導と生徒指導は学校教育における車の両輪です。学校がすべての子どもたちにとって楽しく、安心して、主体的に、そして意欲的に学べる場になるためには、誰にとってもわかりやすい授業やお互いが認め合い支え合う支持的な学級づくりが求められます。
改訂版「生徒指導提要」では、特定の課題を意識することなく、すべての児童生徒を対象に、学校の教育目標の実現に向けて、教育課程内外のすべての教育活動において進められる生徒指導の基盤として、発達支持的生徒指導が位置づけられました。
支持的な学級とは、失敗や誤りを認め合い、仲間意識や連帯感がある、役割や責任が果たせる、話しやすい雰囲気がある、他者を思いやる行動が自然に見られる、話し合いによる問題解決能力があるなどが自然に見られる学級です。教師が枠にはめて厳しく指導するだけでは、こうした学級にはなっていきません。子どもたちの思いや願いを尊重しながら、子どもたち自らがこうした雰囲気を創りあげていけるような学級経営が望まれます。
学校の集団生活は様々な考え方の子どもたちで営まれていきます。物事の捉え方や考え方、受け止め方、価値観は子ども一人一人違います。全員が同じ価値観をもち、同じ方向を見て生活している集団は広がりがなく、実は学びの少ない集団になっているかもしれません。価値観が違う子ども同士が集まるところには、時としてトラブルが生じます。故意に相手を困らせようとしているわけではなく、自分が正しいと思っていること、価値観の違いがトラブルにつながる場合もあるということだと思います。物事の捉え方や考え方、受け止め方の違いは、一人一人の学び方の違いにつながっている場合もあります。自分に合った学び方により学習意欲を高め、さらに違った学び方も身につけることにより、困難な場面や状況が軽減され、学びの場としての学校生活がより安心、安定したものになっていきます。物事の捉え方や考え方、受け止め方の違い、価値観の違いを知ることは、自分の物事の捉え方や考え方、受け止め方、価値観を広げる貴重な機会になります。いろいろなトラブルを経験して子どもたちの学びは広がっていきます。また、それは教師の学びの広がりにもなっていると思います。大切なのは、教師の価値観(一般的な規範)を教え込むのではなく、子どもたち自身がどうすればよいのかを考えさせることが教育であり、教師の仕事ではないでしょうか。
そこで、ちょっとおこがましいタイトルの本をつくりました。内容を少し紹介します。1章は、「『発達が気になる子』と関わる担任が読んでおきたいこと」です。学級で気になる子どもをみる視点、安心できる学級づくりやわかる授業、個に応じた指導と集団への支援、チームによる支援などです。発達障害や特別支援教育について知っておいてほしいことというよりは、通常の学級における学級づくりやわかる授業、生徒指導などにおいて特別支援教育の視点から大切にしてほしいことをまとめました。2章は、「どうすればいい? 学級生活で『発達が気になる子』とその対応」です。通常の学級で気になる子どもたちによく見られる行動が挙げられています。その行動はどうして生じるのか、背景や要因を考えることで対応の仕方が見えてきます。たくさんの実践を積み重ねてこられている先生方に執筆をお願いし、子どもの特性を理解し、子どもの思いや願いを汲み取り、子どもと一緒に困っていることの対応を考えていく道筋をわかりやすく示していただきました。家庭でも役立つ内容になっています。
最後に、学校がすべての子どもたちにとって、楽しく、安心して、主体的に、そして意欲的に学べる場になるために、この本が少しでもお役に立てたら幸いです。
監修者 /笹森 洋樹
-
 明治図書
明治図書














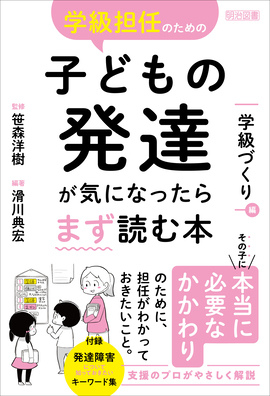
 PDF
PDF

