- まえがき
- 1章 「発達が気になる子」と関わる担任が読んでおきたいこと
- 1 発達障害の特性をおさえる
- 2 子どもを「みる」視点を変える
- 3 「気になる子」の気づきは行動観察から
- 4 学習環境を整え、安心できる学級づくりをする
- 5 「わかる授業」に変える
- 6 個に応じた学習指導・支援でおさえておくこと
- 7 個別の指導計画を作成してみる
- 8 個と集団を往還する支援の視点をもつ
- 9 担任だけで抱え込まずにチームで支援する
- 10 関係機関を上手に活用する
- 11 保護者との教育相談
- 2章 どうすればいい?授業で「発達が気になる子」とその対応
- 1 個別に言われると聞き取れるのに集団場面では難しい
- 2 言葉の指示を聞いて理解することが難しい
- 3 聞き間違いが多く見られる
- 4 単語を羅列する・単文で話すなど話が短く内容的に乏しい
- 5 思いつくままに話すなど、筋道の通った話ができない
- 6 友だちにわかりやすく伝えることが難しい
- 7 話し合いのとき、話さなかったり、話しすぎたりして参加が難しい
- 8 文章を読むとき、語句や行を抜かしたり、同じ行を繰り返したりする
- 9 文章を読むのが遅いなど、音読が苦手である
- 10 読み飛ばしや読み間違いが多い
- 11 文章の要点を正しく読み取ることが難しい
- 12 板書をノートに写すときにとても時間がかかる
- 13 長音や拗音、促音などの特殊音節をいつも書き誤る
- 14 ノートを書くといつも文字がマスからはみ出してしまう
- 15 漢字がなかなか覚えられず、覚えてもすぐに忘れてしまう
- 16 漢字の細かい部分を書き間違えることが多い
- 17 主語と述語の対応、助詞の使い方など文法的な誤りが目立つ
- 18 思いつくままに書き、筋道の通った文章を書くことができない
- 19 出来事は書けるが心情が書けない
- 20 数を数えるときに正しく数えられない
- 21 量を表す単位を理解することが難しい
- 22 簡単な計算でも暗算することができない
- 23 計算をするのにとても時間がかかる
- 24 四則の混合した式などを正しい順序で計算できない
- 25 繰り上がりや繰り下がりの計算ミスが多い
- 26 計算問題を解くときに具体物がないと理解が難しい
- 27 算数の文章問題を解くときに内容を理解して図式化できない
- 28 事物の因果関係を理解することが難しい
- 29 図形を描くことが難しい
- 30 はさみやのり、コンパスや定規などがうまく使えない
- 31 グラフや表、地図などの資料を読み取ることが難しい
- 32 観察や実験の記録をまとめることが難しい
- 33 手順に従い作業することが難しく、勝手に取り組んでしまう
- 34 教師による個別的な指導を受けることを嫌がる
- コラム 通級による指導とは
- 付録 発達障害について知っておきたいキーワード集
- 執筆者一覧
まえがき
学習指導と生徒指導は学校教育における車の両輪です。学校がすべての子どもたちにとって楽しく、安心して、主体的に、そして意欲的に学べる場になるためには、誰にとってもわかりやすい授業やお互いが認め合い支え合う支持的な学級づくりが求められます。
子どもの実態に応じて教え方や学び方は違い、授業は教師と子どもたちの関係で常に新しいものが創られていきます。子どもの学習の様子を観察するときに、どうしてもうまく学べていない子どもに注目しがちになります。思うような学習成果が上げられていない子どもには丁寧な個別的な指導により少しでも成果がでるようにと考えます。そのとき学習の評価の基準をどこに置くかがとても重要です。その時点では他の子どもたちと同じように目標達成することが難しい子どももいます。同じ目標が達成できたかどうかだけでなく、どの位できることが増えているかを評価することも大切です。できないことよりも、できたことに注目して認めてもらえることが次の学習意欲につながっていくと思います。
学校の集団生活は様々な考え方の子どもたちで営まれていきます。物事の捉え方や考え方、受け止め方、価値観は子ども一人一人違います。全員が同じ価値観をもち、同じ方向を見て生活している集団は広がりがなく、実は学びの少ない集団になっているかもしれません。価値観が違う子ども同士が集まるところには、時としてトラブルが生じます。故意に相手を困らせようとしているわけではなく、自分が正しいと思っていること、価値観の違いがトラブルにつながる場合もあるということだと思います。物事の捉え方や考え方、受け止め方の違いは、一人一人の学び方の違いにつながっている場合もあります。自分に合った学び方により学習意欲を高め、さらに違った学び方も身につけることにより、困難な場面や状況が軽減され、学びの場としての学校生活がより安心、安定したものになっていきます。物事の捉え方や考え方、受け止め方の違い、価値観の違いを知ることは、自分の物事の捉え方や考え方、受け止め方、価値観を広げる貴重な機会になります。いろいろなトラブルを経験して子どもたちの学びは広がっていきます。また、それは教師の学びの広がりにもなっていると思います。大切なのは、教師の価値観(一般的な規範)を教え込むのではなく、子どもたち自身がどうすればよいのかを考えさせることが教育であり、教師の仕事ではないでしょうか。
そこで、ちょっとおこがましいタイトルの本をつくりました。内容を少し紹介します。1章は、「『発達が気になる子』と関わる担任が読んでおきたいこと」です。学級で気になる子どもをみる視点、安心できる学級づくりやわかる授業、個に応じた指導と集団への支援、チームによる支援などです。発達障害や特別支援教育について知っておいてほしいことというよりは、通常の学級における学級づくりやわかる授業、生徒指導などにおいて特別支援教育の視点から大切にしてほしいことをまとめました。2章は、「どうすればいい? 授業で『発達が気になる子』とその対応」です。通常の学級において学習面で気になる子の様子が挙げられています。その背景や要因を考えることで支援の工夫が見えてきます。実践豊富な先生方に執筆をお願いし、子どもの特性を理解し、子どもの思いや願いを汲み取り、子どもと一緒に困っていることの対応を考えていく道筋をわかりやすく示していただきました。家庭学習でも役立つ内容になっています。
最後に、学校がすべての子どもたちにとって、楽しく、安心して、主体的に、そして意欲的に学べる場になるために、この本が少しでもお役に立てたら幸いです。
監修者 /笹森 洋樹
-
 明治図書
明治図書














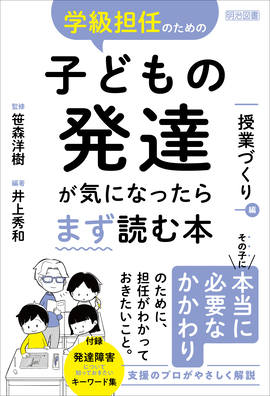
 PDF
PDF

