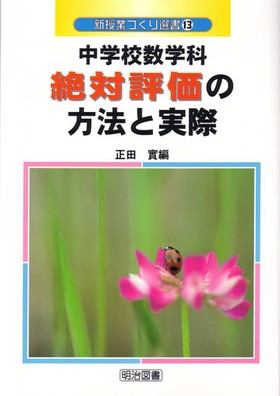- まえがき
- 1章 中学校数学科の絶対評価の方法
- §1 絶対評価への転換
- 1 評価の役割
- 2 観点別学習状況の評価
- 3 客観性と信頼性の確保
- 4 目標に準拠した評価の重視
- 5 個人内評価の重視
- 6 評価規準と評価方法の開発
- §2 多様な評価方法の工夫
- 1 形成的評価を中心とした方法
- 2 数学的活動を評価する方法
- 3 よい点や可能性を積極的に評価する方法
- 4 ペーパーテストを中心とした方法
- 5 指導の形態に応じた評価の工夫
- §3 評価の観点と方法の妥当な組み合わせ
- 1 指導計画にあわせた評価計画の作成
- 2 評価方法の特質とその選択
- 2章 中学校数学科の多様な評価方法とその実際
- §1 「小テスト」を活用した評価
- 1 「小テスト」の意義
- 2 「小テスト」による評価の規準
- 3 「小テスト」による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「小テスト」による評価の成果と課題
- §2 「ノート」を活用した評価
- 1 「ノート」を通して評価する意義
- 2 「ノート」による評価の規準
- 3 「ノート」による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「ノート」による評価の成果と課題
- §3 「ワークシート」「学習カード」を活用した評価
- 1 「ワークシート」「学習カード」を通して評価する意義
- 2 「ワークシート」「学習カード」による評価の規準
- 3 「ワークシート」「学習カード」による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「ワークシート」「学習カード」による評価の成果と課題
- §4 「観察」「机間指導」「面接」を活用した評価
- 1 「観察」「机間指導」「面接」を通して評価する意義
- 2 「観察」「机間指導」「面接」による評価の方法
- 3 「観察」「机間指導」「面接」による評価の留意点
- 4 評価の実際
- 5 「観察」「机間指導」「面接」による評価の成果と課題
- §5 「レポート」「作品」を活用した評価
- 1 「レポート」「作品」を通して評価する意義
- 2 「レポート」「作品」による評価の規準
- 3 「レポート」「作品」による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「レポート」「作品」による評価の成果と課題
- §6 「アンケート」「質問紙」を活用した評価
- 1 「アンケート」「質問紙」を通して評価する意義
- 2 「アンケート」「質問紙」による評価の規準
- 3 「アンケート」「質問紙」による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「アンケート」「質問紙」による評価の成果と課題
- §7 「自己評価」「相互評価」を活用した評価
- 1 「自己評価」「相互評価」を活用した評価の意義
- 2 「自己評価」「相互評価」を活用した評価の規準
- 3 「自己評価」「相互評価」を活用した評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「自己評価」「相互評価」を活用した評価の成果と課題
- §8 「ポートフォリオ」を活用した評価
- 1 「ポートフォリオ」を活用した評価の意義
- 2 「ポートフォリオ」を活用した評価の規準
- 3 「ポートフォリオ」を活用した評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「ポートフォリオ」を活用した評価の成果と課題
- §9 「ペーパーテスト」(客観形式)を活用した評価
- 1 「ペーパーテスト」(客観形式)の意義
- 2 「ペーパーテスト」(客観形式)の評価の規準
- 3 「ペーパーテスト」(客観形式)の評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「ペーパーテスト」(客観形式)の評価の成果と課題
- §10 「ペーパーテスト」(自由記述)を活用した評価
- 1 「ペーパーテスト」(自由記述)を通して評価する意義
- 2 「ペーパーテスト」(自由記述)による評価の規準
- 3 「ペーパーテスト」(自由記述)による評価の方法
- 4 評価の実際
- 5 「ペーパーテスト」(自由記述)による評価の成果と課題
- §11 「少人数授業」における評価
- 1 「少人数授業」の意義
- 2 少人数指導における評価
- 3 評価の実際
- 4 少人数指導による評価の成果と課題
- §12 TTにおける評価
- 1 TTによる評価の意義
- 2 TTにおける評価とその方法
- 3 TTによる評価の規準
- 4 評価の実際
- 5 TTによる評価についての成果と課題
- 3章 中学校数学科の総括的評価の実際
- §1 総括的評価,評定の実際
- 1 観点別学習状況の評価を総括し,評定を求める具体的な方法
- 2 評定の補正
- 3 指導結果としての総括的評価
- 4 評定の際の大事なこと
- §2 通知表の活用
- 1 これからの通知表に求められる工夫
- 2 新たな評価に適した通知表の作成
- §3 指導要録の実際
- 1 新指導要録での主な改善点
- 2 数学科としての指導要録
- 3 記入内容と情報開示
まえがき
学校においては,目標に準拠した評価を基本とすることになりました。教育的活動は,目標を定め,その実現をめざして行われるものですから,目標に準拠して,その実現状況を評価することは,教育評価,本来の意味からすると異論をはさむ余地はないといえましょう。
とはいえ,目標に準拠することを基本として,客観性と信頼性を確保することは,それほど容易なことではないと考えられてきました。
客観性と信頼性を確保するためには,まず,観点別に学習状況を分析的にみた上で,それらを総括的にみなおす方法がとられるようになりました。ところで「観点別学習状況」の欄が生徒指導要録に設けられたのは,1981(昭和56)年の改訂においてでありますから,すでに20年以上を経過しています。しかしながら,観点別学習状況の評価が完全に定着したとはいいにくい状態であるとお考えの方も多いことでしょう。
このような実態にもかかわらず,目標に準拠した評価を基本にすえることの意義について,あらためて考えてみましょう。
第一に,生徒一人一人のよい点や可能性を十分に伸ばすために,指導に直結する評価をすることです。観点別に学習状況を分析的にとらえることによって,補充すべきところや,さらに発展させるべきところが明らかになりますので,遅れがちの生徒に対しても十分な対応ができるようになることでしょう。7,5,3は少なくとも9,7,5に引き上げることが期待されているのです。
第二に,数学的活動の楽しさを知ることによって生涯にわたって数学を幅広く活用できる「学ぶ力」を身に付けられると考えられています。したがって,数学的活動の状況をできるだけ自然な形で評価することが求められるようになりました。条件を整えて公平性を追求するだけでは不十分と考えねばなりません。
第三に,「関心・意欲・態度」を育てることが,さらに重視されるようになりました。これは,「学ぼうとする力」が「学んだ力」「学ぶ力」とともに重要だと考えられるからです。このような数学に対する「心の構え」を育て,それをみきわめることが求められているのです。
このようにみてきますと,これまでも求められていたわけですが,一層はっきりした形で,実践に結びつけ成果を出すことを迫られているということができるでしょう。しかしながら,これまで,評価について基本的に問い直し,討議をする機会が少なかったこともあり,これらのことを実現するためには,かなりの戸惑いと具体的な方法についての疑念とが残っていることと思われます。
これらの戸惑いや疑念に応えるために,本書を企画・編集いたしました。
1章では,教育課程審議会の答申にさかのぼって,絶対評価へ転換する意義を考察し,多様な評価方法を工夫する今日的な意味をさぐりました。そして,目的に応じて,どのような評価方法を選択するかについての若干の示唆も加えました。
2章では,数学科で採用されている多様な評価方法を取り上げました。
これまでは,とかく結果としての成績に着目しがちでありましたが,これからは指導の過程において学習の状況を一人一人の伸長に注目しながら,よい点や可能性を見出し,指導に役立つ教育評価に転換する必要があります。このため,形成的な評価が中心になりましたが,総括的な評価や指導形態に応じた評価なども幅広く取り上げています。
なお,評価のための評価といわれたり,教師の負担が過重にならないよう,現場の実践例を通して,現場で役立つようにまとめました。その際に,単なる実践例としてではなく,意義,評価の規準,評価の方法,実際,成果と課題などについても深く考察するように努めました。
3章では,観点別学習状況の評価を総括する際の基本的な考え方と実際についてまとめました。これについては,各学校で独自に工夫されることが多いことでしょう。その際に参考としていただけるよう簡潔にまとめるようにしました。
絶対評価へ,改訂の趣旨を生かし,現場の実践にも役立つよう,必要なところをピックアップされ十分にご活用ください。なお,今回,ご執筆いただいた方々は,いずれも数学教育の実践を積み上げられ,なおかつ,新しい課題にたえずチャレンジされ,斬新な視点でその成果をまとめていただいています。ご参考にしていただき,実践に役立てていただければ,きっと生徒をみる力が飛躍的に向上することでしょう。
教育評価の改善は,現状に対する正しい批判と理想を実現しようとする情熱などが実践者のなかにエネルギーとして蓄積されてはじめて実現できるものと信じています。あきらめたり,きめつけたりしないで時間をかけて取り組んでいただけることを心から願っています。
最後に,お忙しいなかを,本書のためにご執筆いただいた方々,本書の企画・出版に多くの労をとってくださった明治図書編集部の安藤征宏,多賀井壽雄の両氏に心からお礼申し上げます。
平成15年4月 編者 /正田 實
-
 明治図書
明治図書