- 前書き 目標を決めて本を読んでいこう /井上 一郎(文部科学省教科調査官)
- 「ブックウォーク」の意義と展開
- 「ブックウォーク」の意義と方法 /井上 一郎(文部科学省教科調査官)
- ブックウォークの取組み方と課題 /古川 元視(佐賀県教育庁学校教育課指導主事)
- ブックウォークをサポートする司書教諭の活動アイデア /小木曽 笑子(伊丹市立天神川小学校)
- 「ブックウォーク」への挑戦
- 子どもが変わり、学校が変わる /渡邊 眞弓(京都府八幡市立美濃山小学校)
- ブックウォークで広がる本の世界 /蜂須賀 美菜(東京都渋谷区立西原小学校)
- 読書習慣を形成し、新たな読書の楽しみ方を見出す /林 理香(宝塚市立売布小学校)
- 読書記録が読書生活を創り出す /神明 照子(北九州市立あやめが丘小学校)
- 本とともに生活する子どもに /山口 京子(宝塚市立宝塚第一小学校)
- 読書目標を達成する喜びを味わう子どもたち /長谷川 榮子(芦屋市立潮見小学校)
- 多読で読書への自信を深める /藤瀬 雅胤(佐賀市立鍋島小学校)
- 読書世界が大きく広がった /小木曽 笑子(伊丹市立天神川小学校)
- 一年間のブックウォークから今年の読書目標を立てる /常田 望美(北九州市立大里東小学校)
- ブックウォークで教室に広がる読書と交流の輪 /八戸 理恵(東京都文京区立明化小学校)
- 宣言と認定で読書生活が始まった /岡崎 理真(兵庫県高砂市立伊保小学校)
- 読書の意欲と質を高めるブックウォーク /古賀 勝利(佐賀大学文化教育学部附属中学校)
- 高校生がブックウォークに挑戦 /岩瀬 弘憲(佐賀県立唐津東高等学校)
前書き
目標を決めて本を読んでいこう
―「ブックウォーク BOOK WALK」への挑戦―
不読者の嘆き
子どもたちの不読を嘆くことが日常化している。多様な調査が不読者の数値を示している。だから、読書活動に関する様々な施策が講じられている。最近の主なものを拾っても、次のような施策がある。(井上一郎編『読書力をつける』上・下巻、明治図書、二〇〇二年参照)
□一九九九年 八月 子ども読書年に関する決議
□二〇〇一年一二月 文化芸術振興基本法(平成一三年法律第一四八号)
□二〇〇一年一二月 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成一三年法律第一五四号)
□二〇〇二年 二月 新しい時代における教養教育の在り方について(中央教育審議会答申)
□二〇〇二年 八月 子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画策定(平成一四年〜一八年度にわたる施策の基本的方向)
□二〇〇三年 四月 学校図書館法改正施行(一二学級以上の学校において司書教諭必置化)
□二〇〇四年 二月 文化庁「これからの時代に求められる国語力について」(文化審議会答申)
例えば、「子どもの読書活動の推進に関する法律」には、「基本理念」として「子ども(おおむね一八歳以下の者をいう。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならないこと。」が謳われている。そのために、「子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資すること」が求められている。この法律に基づいて、地方公共団体においても、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定が求められ、既に多くの基本計画が示されている。また、法律では、四月二三日を「子ども読書の日」として制定し、全国で定着し始めている。
「ブックウォーク BOOK WALK」は封筒に入った三枚のカードから
このような国及び地方公共団体の活動や、図書館に関係する人々の様々な取組にもかかわらず、不読者の調査結果が出ているのである。だから、一層推進活動を活発にする必要があるのだが、従来とは違った新しい活動も起こさなければならないと考えられるのである。読書することが、日常生活に根付くような活動が必要だ。そのような問題意識のもとに構想したのが、「ブックウォーク BOOK WALK」であった。
本と一緒に生活し、生活と一緒に本を読んでいこう
あわてず、ゆっくり、だけど目標を決めて歩いていこう
というのがこの運動の精神である。実際には、子どもが封筒に入った三枚のカードをもらうことから始まる。自由に目標を定めて読書活動を行うために、先生や司書、保護者にこの封筒をもらいに行くことから活動が始まるのである。封筒には、「宣言書・読書カード・認定書」が入っており、一定の期間、自由な方法で読書する内容や方法を決め、読書への意欲を高め、着実に読書を行うことになる。
子どもが自由に目標を設定し、読書カードでモニタリングしながら行うことによって読書への関心・意欲・態度を高めることが最も重要である。目標の達成感や成就感によって、読書の楽しさや喜びを体験する。その結果、読書感覚を高めたり、読書習慣を形成したりしながら、豊かな読書生活を築き上げるのをサポートするのを目的とするのが「ブックウォーク BOOK WALK」である。
子どもが「ブックウォーク BOOK WALK」で変わっていく
本書には、小学校、中学校、そして高等学校とそれぞれの発達段階での実践を収録した。実践は、私が主宰する「国語教育カンファランス」の研究会員が中心となって行った。どのような工夫を行ったか、そしてどのような成果を上げたか、エピソードやデータなどの事実を記録し、考察を行った。各自が作成した「宣言書・読書カード・認定書」なども収録した。本文中には、子どもが実際に書いたものを入れ、各節の終わりに元原稿を入れた。学校全体での実践もあれば、研究会員のクラスによるものもある。
運動を構想し、趣旨や方法を定め、「ブックウォーク BOOK WALK 推進協議会」(仮称)を立ち上げられるまで頑張っていこうと決めたのが、二〇〇二年であった。本書をまとめ、実践を提唱するまでに予備実践を重ねた。本当に成果が上がるか、子どもに負担を与えないか、方法の改善は必要ないか、など再検討を繰り返した。いよいよ実践をまとめ提唱できると確信し、本書刊行の手続きを取ったのであった。
それぞれの実践が示唆するものは、子どもの次のような感想によく表れている。それは、「シリーズをこんなに読んだことはなかった」「同じ作者の作品をこんなにまとめて読んだことはなかった」といった新しい本の読み方の発見だ。さらに、読書を続けられる能力が自分にあったことへの驚きや、これなら今後も読んでいけるという自信につながっていく。「こんなに楽しいとは思わなかった」「こんなにたくさん読めるとは思わなかった」など、子どもの喜びが生き生きと伝わってくる。間違いなく「ブックウォーク」で子どもが変わっていくことを確信したのであった。個人では勿論、クラス全体でも、学校全体でも、読書生活が変容する。そして、子ども一人一人が豊かになっていくのである。
本書刊行を契機に、多くの人に、子どもの読書生活を豊かにすることをサポートしていただきたいと願うばかりである。 ブックウォークをサポートし、認定するのは、学校の担任の先生でも、司書教諭でも、学校司書(学校図書館事務職員)でも、保護者でも、地域の人でもよい。とにかく多くの大人が、少しでもこの運動に参加してくださることを期待したい。
教育への情熱と純粋な心を
最後に、本書刊行に当たっては、明治図書の石塚嘉典氏、松本幸子氏にお世話になった。ここに記し、謝意としたい。
そして、何よりも私の新しいムーブメントの提唱に応えてくれた「国語教育カンファランス」の研究会員に深く感謝したい。まだ、どのような成果が上がるか分からない時期に、情熱をもって取組んでくれた。本書での原稿執筆があるかどうかではなく、〈子どもが変わった〉という多くの研究会員による驚嘆に満ちた確信の報告がなければ、本書刊行はなかったはずだ。厳しい読書環境や多忙な教師生活の中に実践を取り込むことは、子どもへの深い愛情以外にはなし得ないことである。最大限の敬意と感謝をもって研究会員の努力を称えたいと思う。
今、教師自身が不読者になっている。教材開発のために、どれだけ日常的に読書しているだろうか。自ら教材開発する教師の主体性を失ってはいないだろうか。現実に圧倒され、多忙な日々の中で、自分を見失っていないだろうか。安易な活動や授業方法に走っていないだろうか。効率や損得ばかりを追求していないだろうか。一人一人の子どもを大切に育てたい、本当の生き方を子どもに伝えたいと思った夢を放棄していないだろうか。改めて問いたい。もう一度教育への情熱と純粋な心を再生させてもらいたい。そしてもし、私たちの「国語教育カンファランス」の研究活動に参加して下されば嬉しい限りである。大きな期待を抱き、連絡を待つものである。
二〇〇四年一二月
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 /井上 一郎














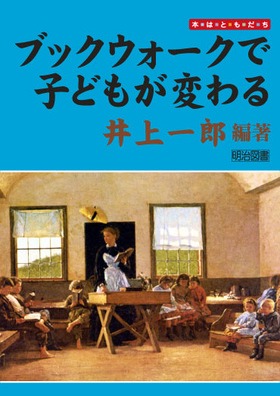


子どもの自主性、周囲が温かく認定するという趣旨は理解を得ることであろう。すぐに実践してみたくなる気持ちにさせてくれる優れた著書である。