- まえがき
- 理論編 算数授業の流れの考え方
- 1 問題解決学習の流れをつくる
- 各段階の流れの土台づくり
- 2 問題把握の段階で子どもから問いを引き出す
- 3 見通しの視点を共有する
- 4 子どもの問いからめあてをつくる
- 5 個人思考で子どもが考えをもった状態を見取る
- 6 多様な考えを練り合う
- 7 適用問題で一般化を図る
- 8 解決して分かったことをまとめる
- 9 まとめを基に練習問題に挑む
- 10 ふり返りの視点を明示する
- 11 数学的な見方・考え方を働かせる子どもの姿を明確にする
- 12 授業づくりを単元で考える
- 13 問い返しで対話を促す
- 14 板書を構造化し学びの足跡を残す
- 実践編 算数授業の流れ事典
- 帰納的な考え方を引き出す授業の流れ
- 1 共通点を見付ける
- 2 調べた結果を集める
- 類推的な考え方を引き出す授業の流れ
- 3 似たような問題はなかったか探る
- 4 結果を予想して確かめる
- 演繹的な考え方を引き出す授業の流れ
- 5 既に分かっていることを基に話し合う
- 6 何を根拠にしたのか話し合う
- よさを追究する姿を引き出す授業の流れ
- 7 見付けた考え方を試してよさを実感する
- 8 よさの視点を基に考えを比較する
- 子どもの主体性を引き出す授業の流れ
- 9 表現方法を選択し挑む
- 10 学習計画を立てて問題に挑む
- 子ども同士の協働を引き出す授業の流れ
- 11 目を付けたところを話し合う
- 12 多様な考えを関連付ける
- 生活場面に生かす授業の流れ
- 13 生活の中から算数の問題をつくる
- 14 学んだことを生活に生かす
- 多様な学習評価を取り入れる授業の流れ
- 15 なぜできなかったのかを考える
- 16 自分の学びをふり返る
- ICTを効果的に活用する授業の流れ
- 17 デジタルで試し,アナログで確かめる
- 18 友達の考えを使って自分の考えにする
- 学力差に寄り添った授業の流れ
- 19 困っていることを共有し説明する
- 20 互いの考えを確かめ再現する
- あとがき
まえがき
数ある算数の教育書の中から本書を手に取ってくださり,ありがとうございます。
日頃,先生方から算数の授業づくりについて多くのご相談を受けます。
「今度,○年生で○○の授業をしますが,流れをどうすればよいですか」
「子どもが考えたくなるような導入や教材が思いつきません」
「算数が楽しくないと言う子がいますが,改善点が分かりません」
「学級の学力差が大きいので授業がうまくいきません。対策はありますか」
「子どもがどんどん話し合うような授業づくりができません」
どれも日頃の授業で直面する課題に真剣に向き合い,よりよい授業を目指す先生方の切実な悩みです。しかし実際にお話を聞いていると,「計算ができるようにしたい」「問題が解けない」「答えに行き着かないときがある」といった声が多く,算数の授業の目指すところが「正しい答えを出すこと」に偏っている印象を受けることがあります。おそらく,子ども自身もそう感じているのではないでしょうか。このような正答主義の学習観は,子どもにとっては「わからない,できない,楽しくない」という意識につながり,教師にとっては「できるようにさせないと楽しくならない」という焦りにつながります。算数は正誤が明確な教科であるため,特にその傾向が強く現れます。
以前,ある子どもが,「先生,おれ算数苦手やけど,授業は楽しいよ」と話していました。「そうなの。なんで?」と尋ねると,「だって,わからんくてもみんなの考え聞いてたら,すごっ!ってびっくりするし,自分で考えてなるほどってなるもん」と答えました。この子のように,新しい問題場面に出合った時,あれやこれやと多様な考えを出し合い,新たな知識や価値を自ら創り出したことに感動する姿こそ,私の目指す算数の学びの姿です。
私が勤務する福岡教育大学附属小倉小学校の研究主題は「子どもが学びを愉しむ授業」です。私は,算数の愉しさは「創る」ことにあると考えています。「創る」対象は多岐にわたりますが,例えば次のようなものがあります。
・問題をつくる ・考えをつくる ・数学的活動をつくる
・きまりをつくる ・公式をつくる ・数理をつくる など
本書は,このような授業づくりを考える際に,先生方が授業の「流れ」を構築する一助となることを願って書きました。読んで終わりではなく,料理のレシピ本のように,算数の授業を考える時に何度も手に取って使っていただける本を目指しました。
理論編では,子ども達と算数の学びをつくる上で,私が日頃意識していることを「算数授業の流れの考え方」として余すことなく紹介しています。
実践編では,「論理的思考力の育成に向けて」「主体的・対話的な学びの実現に向けて」「一人一人に寄り添う授業づくりに向けて」の3つの視点から,実際に行った授業を1単位時間ごとに流れとして紹介しています。教材は各教科書会社のものに近いものを選びました。各学年での具体的な授業場面を例に説明していますが,学年を問わず活用できる要素や取り入れられるポイントも補足しています。ぜひ,ご自身の学級の子ども達に合わせて応用してください。
本書で紹介している資料データや板書記録は,右記のサイトに掲載しています。指導案や授業動画もありますので,本書と併せてご活用ください。
本書を通じて,算数を「創る」愉しさを味わい,それを子ども達と共有することで,先生方が毎日の授業にわくわくして臨めるようになることを願っています。
2025年5月 /本田 龍一朗
-
 明治図書
明治図書














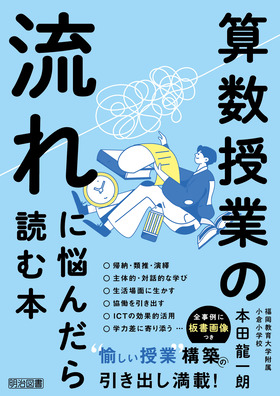
 PDF
PDF

