- はじめに
- 第1章 再考・説明文指導―逆向き設計と具体化・推測でつくる説明文の授業
- 1 説明文は何のために学ぶのか
- (1)説明文とは
- (2)説明的文章の種類
- (3)文学的文章との比較から
- (4)学習指導要領から
- (5)西郷竹彦の主張から
- (6)長崎伸仁の主張から
- (7)森田信義の主張から
- (8)まとめ
- 2 説明文学習の読みの目標「情報を読む」「論理を読む」「筆者を読む」
- (1)説明文学習の三つの目標
- (2)「情報を読む」
- ―文字面を読んで終わりにしない―
- (3)「論理を読む」
- ―つながりを見出し、書き手の意識をもって筆者による説明の工夫を見つける―
- (4)「筆者を読む」
- ―内容と論理の理解を評価につなげる―
- (5)三つの目標と学習指導要領の学習過程との関係
- (6)「系統」の考え方
- (7)国語科の螺旋構造を生かす
- 3 学習活動・発問の二本柱「具体化する」「推測する」
- (1)具体的学習活動・発問の重要性
- (2)具体化する
- (3)推測する
- (4)具体化と推測は連関する
- (5)「具体化」と「推測」の位置付け
- 4 演繹的指導・帰納的指導と国語科の螺旋構造
- (1)演繹的指導と帰納的指導
- (2)二つの指導法と国語科の螺旋構造
- (3)演繹的指導の在り方を検討する重要性
- (4)演繹的指導の段階性の提案
- (5)説明文指導と演繹的指導
- (6)「学習用語」についての私の考え
- 5 教材の特性をつかむ
- (1)説明文指導は「教材ファースト」である
- (2)長崎による説明文の五つの分類
- (3)「筆者の主張が明確に出ているか」という観点
- (4)「筆者の主張」はいつから明確に出てくるか
- (5)文章自体の特徴をつかむ
- ○題材
- ○筆者の主張について
- ○筆者の述べ方について
- ○例の挙げ方について
- ○指導事項や「国語」との適応性、関連性
- ○教師が一読して得た納得感や違和感
- ○子ども達がどのように読むか
- 6 ゴールから逆向きに指導構想する
- (1)単元のゴールを設定する
- (2)単元のゴールの表現方法を考える
- (3)ゴールから逆向きに単元全体を設計する
- (4)一時間一時間を適切に配列する
- (5)「具体化」と「推測」の具体的手立てを考える
- (6)帰納的指導と演繹的指導のバランスを考え、指導すべき学習用語等を位置付ける
- (7)子どもの様子を見て調整していく
- 第2章 定番教材で分かる説明文指導法
- 1年 どうぶつの赤ちゃん
- 2年 どうぶつ園のじゅうい
- 3年 文様/こまを楽しむ
- 4年 思いやりのデザイン/アップとルーズで伝える
- 5年 見立てる/言葉の意味が分かること
- 6年 笑うから楽しい/時計の時間と心の時間
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
私は、これまで漢字指導や音読指導の本を上梓させていただきました。ですが、実は、小学校教員になってからずっと説明文指導の魅力に取りつかれてきた一人でもあります。
そして、私が、これまで説明文指導の研究を継続してきて、心の底から思うことが、説明文指導は奥が深く、面白いということです。
説明文(指導)というと、次のようなイメージをおもちの先生方もいらっしゃると思います。
「物語と比べてかたく、面白くない文章である」
「やることが決まりきっている」
「そもそも何をどう教えたらいいか分からない。結局、指導書頼りになっている」
「子ども達もあまり意欲を示さない」
総じて、あまり「面白くない」「苦手意識がある」と思われている先生も少なくないのではないでしょうか。
そんな方々のために書いたのが本書です。私が実践を通してつかんできた説明文指導のコツや本書を通じて、先生方の説明文指導へのイメージが変わり、説明文指導を愉しめるようになれば、こんなに嬉しいことはありません。
最後に、本書の構成についてご紹介します。
本書は「理論編」である第1章と、「実践編」である第2章に分かれています。
「理論編」では、説明文指導への考え方や捉え方について述べます。文献などから引用することももちろんありますが、なるべく平易な言葉で説明文指導理論を紹介していきます。ここを読むことで、ご自分の説明文指導を見つめ直したり、自分なりの指導をつくっていったりすることができると考えています。ある程度指導経験が積み重なってきた中堅の先生方はここからお読みいただけると参考になるかと思います。
「実践編」では、「理論編」に基づいた実践を全学年一本ずつ紹介していきます。やはり具体的な実践こそ本当の意味で実践者の参考になります。特に初任者や若手の先生方は「明日の授業、どうしよう」という意識で毎日を送っておられるでしょう。ぜひ初任者や若手の先生方は実践編からお読みいただき、その後「理論編」でどのような考え方が重要なのかをお読みいただければと思います。
本書が先生方、そしてその目の前の子ども達の役に立つことを心から願っております。
/土居 正博
-
 明治図書
明治図書- 土居先生の著書には、いつも大変お世話になっています。いつもですが、文献の紹介が丁寧で、土居先生のこれまでの蓄積を肌で感じます。土居先生のおかげで私自身が国語を楽しめるようになってきました。ありがとうございます。2025/11/320代・小学校教員
- 理論的かつわかりやすく書かれていて、授業にどのような姿勢で臨めばいいのかがよくわかります。2025/10/2330代・小学校教員
- 土居先生の理論と実践がバランスよく書かれていてわかりやすい2025/8/1440代・小学校教員
- なぜ説明文を小学校で学習するのか念頭において指導したいと思いました。2025/8/330代・小学校教員














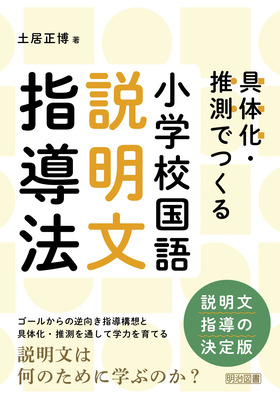
 PDF
PDF

