- はじめに
- 第1章 環境の支え
- 1 まずは「安心して学べる環境」を整える
- 2 どうほめるか、叱るかを考える前に大切にしたいことがある
- 3 「できない」ではなく、「まだできない」と捉え、少しずつ手を放していく
- 4 子どもたちを「お客様」ではなく、「参加者」にする
- 5 友達に質問できる関係、お互いを尊重する学級の雰囲気をつくる
- 6 友達の姿から学ぶ場を授業デザインしていく
- 7 友達と学ぶプラス面・マイナス面を理解して学びを展開する
- 第2章 やる気の支え
- 1 自己決定(自律性)の程度に注目して、「自律的動機づけ」を高める
- 2 子どもたちがやる気になる仕掛けづくりに、全力を注ぐ
- 3 多くの人を「熱中」させるものから学ぶ
- 4 「熱中」する5つの要素を取り入れ、子どもたちの「やる気」を高める
- 5 教師による言葉かけから始め、子ども自身の評価による「有能感(自己効力感)」へつなげていく
- 第3章 学びの支え
- 1 どう教えるかではなく、どう学ぶかを考える
- 2 子どもたちの気持ちを体感し、「学び」を促す支援や環境を考える
- 3 子どもも教師も「WHY」(目的)を意識する
- 4 教材研究でどこまで教え、どこから委ねるかをはっきりさせる
- 5 自己調整学習サイクルを意識して、循環的な学びにする
- 6 導入から終末まで、「メタ認知」を意識して授業デザインを行う
- 7 努力は大切。だけど、学習観や学習方法も指導する
- 8 多様な「学習観」への理解が「学習方法」の幅を広げる
- 9 自分で学びのコントロールができるよう、自己評価する力を高める
- 10 教師が「メタ認知」の代わりや助けをして、子どもたちの「メタ認知」を促す
- 11 「振り返り」の目的を確認することで「視点」を提供し、「メタ認知」を促す
- 第4章 そして、委ねる
- 1 子どもたちに「委ねる」前に、教師が土台を築く
- 2 「委ねた」後も、子どもを信じて見守り、理解しようとする
- 3 「やる気」にさせ、教えるべきは教えて、委ねる
- 4 子どもの実態をアセスメントして、戦略的に発達を促す
- 5 日々ほんの少しの成長を支え、発達の段階を高めていく
- 6 私たち教師も「自己調整学習」を展開する学習者となる
- Q&A
- 参考文献
はじめに
本書を手に取っていただき、ありがとうございます。
あなたの仕事を、「○○○仕事」と子どもたちに一言で紹介するとします。○○○は、17文字以内。なんと表現されますか?
私は、「未来も子どもが輝くために今を満たす仕事」です。
私は今、6年生の担任をしています。子どもたちとの日々は、本当に充実しています。担任している子どもたちが歩む「未来」、私はそばにいません。私と同じように、子どもたちを大切に思う保護者も、いつまでも子どもたちのそばにいるわけではありません。子どもたち自身が、夢や目標などに向けて、粘り強く歩み続けていきます。そのためには、子どもたちが過ごす「今」を満たし、「未来の扉」を開く「カギ」を身に付けていくことが大切になります。
「未来の扉」を開く「カギ」の1つが「自ら学びをコントロールする力」、つまり「自己調整学習能力」です。
岡田ほか(2016)によると自己調整学習についてジマーマンは、「学習者が、メタ認知、動機づけ、行動において、自分自身の学習過程に能動的に関与している」ような学習と述べ、さらにシャンクは、「自己調整学習は、予見、遂行、自己省察のサイクルを自分でまわしていくような学習の仕方」と説明しているそうです。学習者である子ども自身が、学びをコントロールすることが大切になります。
自己調整学習における予見段階では、目標を設定したり、学習方法を選択したりします。遂行段階では、選択した学習方法で難しい問題や課題に対して粘り強く取り組み続けます。自己省察段階では、学習について振り返り、次の学習につなげていきます。これらの学習過程を、学習者である子ども自身がやる気に火をつけ、メタ認知し、能動的に展開することは、とても難しいことだと思います。大人でも、難しいことではないでしょうか。
そこで、教師の役割がとても大切になります。しかし、子どもたちの自己調整学習を支え、促す教師の役割といっても、「こうすればいい」というような明確な答えはありません。なぜなら、自己調整学習を展開するのは、子どもたちであり、目の前の子どもたちは興味も得意なことも一人一人違うのです。それなのに、「こうすれば、どの子も自己調整学習ができるようになる」などという明確な方法があるとしたら、その方が怪しいです。
そもそも自己調整学習は、方法論ではありません。理論体系です。
私は、「メタ認知や動機づけ、学習方法などの要素について、こうすれば学習者自身が学びをコントロールしやすくなるのではないかと整理されているもの」と理解しています。
教師にとっては、「○○をすれば、自己調整学習といえる」などのような明確なものがある方が実践をしやすいのだと思います。しかし学びをコントロールするのは、教師ではなく子どもたちです。算数と聞くだけでやる気になる子がいる一方で、やる気を失う子もいます。また、一人一人得意とする学習方法なども異なります。では、子どもたちに任せっぱなしで、私たち教師の役割はないのかというとそうではありません。
子どもたちにとって興味を持てない学習内容でも、子どもたちが信頼するあなた(教師)が子どもたちの知的好奇心を喚起し、学びを支えるから、子どもたちはやる気になり粘り強く目標の達成に向けて学び続けます。また、学習結果などに対してもあなた(教師)が価値づけるから、その後の学びでも「やってみよう」という気持ちにつながっていきます。さらに学級が「安心して学べる環境」になっているから、学びに集中できます。この役割は、AIや他の教師には簡単に代わることができないのではないでしょうか。私は、教師の仕事は子ども・社会の未来をつくる尊い仕事だと自負しております。
学習指導要領の改訂・社会の変化などにより、「自己調整学習」への注目は日に日に高まってきているように感じます。「自己調整学習」を支える多くの理論が述べられていますが、「では、どうしたらいいの?」という現場の教師の疑問に答える書籍などは、まだ少ないように思います。「学習方法を子どもが選択すれば、自己調整学習になる」など、表層的な面が先行して広がり、教師が大切にしなければならない深層部分は、軽視されてきているのではないかと危惧しています。子どもに任せただけでは、子どもたちは育ちません。
前著『自ら学びをコントロールする力を育む 自己調整学習―子どものやる気に火をつけ、可能性を伸ばせ!』と合わせて、少しでもお役に立てば倖いです。
著者 /友田 真
-
 明治図書
明治図書- 理論的に学ぶことができる。前著と併せて内容が深まる。導入より進んで、実際にどのように続けていくのか、少し先まで考えることに役だった。2025/12/1430代・小学校教員
- 教師の仕事の1つは子供たちの学びの環境を整えることだということを改めて感じました。本書の中では「漢字の達人」の実践例がとても分かりやすかったです。2025/11/340代・小学校教員
- 第一弾に続き、子どもの姿を中心に教師がどのようなマインドで学習環境を整えていけばよいか、分かりやすく示してあります。2025/7/2040代・小学校教員
- 前作に続き、さらに方策を具体的に示していただき、大変勉強になる2025/7/930代・小学校教員














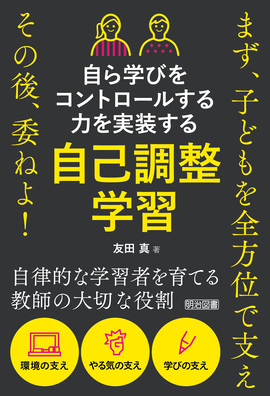
 PDF
PDF

