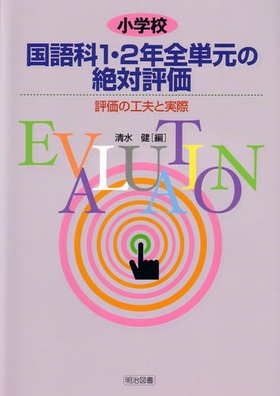- まえがき
- 1章 国語科における絶対評価の基本
- §1 観点別学習状況の絶対評価
- §2 評価・評定の絶対評価(絶対評価にした意味と進め方の課題)
- §3 評価計画と評価のポイント
- §4 授業の中の絶対評価(絶対評価の進め方と活用)
- 2章 国語科1・2年評価規準活用の全単元 絶対評価の実際
- §1 「話すこと・聞くこと」の絶対評価の実際
- 1 相手に分かるように話す 「みんなと たのしく」(教育出版1上)
- 2 大事なことを落とさないで聞く 「みんなと たのしく」(教育出版1上)
- 3 身近な事柄について話す 「わたしのたからもの」(光村図書1下)
- 4 尋ねたり応答したりする 「はる」(教育出版1上)
- 5 体験したことを話す 「夏休みの思い出を 話そう」(特設)
- 6 友だちの話を聞く 「たんけんしたよ みつけたよ」(光村図書1上)
- 7 読んだ本を紹介する 「こんな ほんを みつけたよ」(光村図書1上)
- §2「書くこと」の絶対評価の実際
- 1 相手や目的を考えて書く 「6ねんせいに おれいの てがみを かこう」(1年 特設)
- 2 必要な事柄を集める 「学校たんけん」(2年 生活科との関連)
- 3 簡単な組み立てを考える 「こんなお話を考えた」(光村図書2下)
- 4 語や文の続き方に注意して書く 「友だちに教えてあげよう」(学校図書2上)
- 5 文章を読み返し,間違いに注意する 「おもちゃの作り方」(東京書籍2上)
- 6 絵や写真に言葉を入れる 「こんなお話を考えた」(光村図書2下)
- 7 簡単な手紙を書く 「お手紙」(光村図書2下)
- 8 尋ねたことをまとめる 「インタビューをしよう」(2年 特設)
- 9 観察したことを文に表す 「むしパンを作ろう」(料理をしよう)(2年 特設)
- §3 「読むこと」の絶対評価の実際
- 1 易しい読み物を読む 「ニャーゴ」(東京書籍2上)
- 2 時間・事柄の順序,内容の大体を読む 「たんぽぽのちえ」(光村図書2上)
- 3 想像を広げて読む 「うみへの ながい たび」(教育出版1下)
- 4 声に出して読む 「おおきな かぶ」(教育出版1上)
- 5 昔話や童話の読み聞かせを聞く 「きつねのおきゃくさま」(教育出版2下)
- 6 場面の様子を想像豊かに読む 「ビーバーの大工事」(東京書籍2下)
- 7 大事なところに気を付けて,楽しく読書しよう 「サンゴの海の生きものたち」(光村図書2上)
まえがき
小学校学習指導要領が改正され,平成10年12月14日に告示となり,平成14年4月1日から施行されることになりました。教育課程の基準の改善に当たっては,完全学校週5日制の中で,ゆとりのある教育活動を展開し,児童生徒に自ら学び自ら考える力など「生きる力」を育成することを基本的な考え方としています。
国語科における改訂の基本方針の中心は,「言語の教育としての立場を重視し,国語に対する関心を高め国語を尊重する態度を育てるとともに,豊かな言語感覚を養い,互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能力を育成することを重点に置いて内容の改善を図る」としています。さらにまた,国語科の目標としての資質や能力としては,「特に,文学的な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導の在り方を改め,自分の考えをもち,論理的に意見を述べる能力,目的や場面などに応じて適切に表現する能力,目的に応じて的確に読み取る能力や読書に親しむ態度」を育てることを重視しています。そのために,これまでの2領域と[言語事項]から3領域と[言語事項]で内容を構成することにしています。
完全学校週5日制や総合的な学習の時間が第3学年以上に週3時間新設されたことにより,年間総授業時数が削減されることになりました。他の教科と同様に,国語科においても年間各学年ともにおよそ14%の削減となりました。こうしたこともあり児童の「学力が低下している」ということが言われ,話題となりました。しかし,まだ新しい学習指導要領による教育課程の実践は,一学期を経過しただけであり,現時点での学力低下が新学習指導要領の実施によるとはとうてい言えないところです。
新しい学習指導要領の下の評価について,平成12年12月の教育課程審議会の答申において,学習指導要領に示す目標に照らしてその実現の状況を見る評価(いわゆる絶対評価)を一層重視し,観点別学習状況の評価を基本として,児童生徒の学習の到達度を適切に評価することが重要であるとしています。また,従前の「集団に準拠した評価」(いわゆる相対評価)ではなく,絶対評価及び個人内評価を柱とすることを示唆しています。
絶対評価を確実に進めるためには,単元における評価の観点や評価規準を明確にしていくことが必要になります。このときの問題としては,学力の評価においては一般的な言い方で「見える学力」「見えない学力」ということがあります。「見えない学力」となれば「見えない」のであるから学力を評価することはできないことになります。ですから国語科では「見えない学力」ではなく,「見えにくい学力」としてとらえていきたいと考えます。「見えにくい学力」をいかに確かに見取って評価するか,どうしたら客観的で正確な評価ができるかを具体的に工夫していかなくてはならないと考えます。なぜなら,国語科で評価規準を設定して評価していこうとする能力や技能は,他の教科に比べて,その多くが「見えにくい学力」であると言えるからです。
絶対評価を確かに実施していくためには,単元ごとの評価の観点や評価の内容を明らかにし,単元及び毎時間の評価規準を明確にすることが必要になります。また,評価の工夫改善を進め,学習指導の過程や一人一人の児童の学習の結果を継続的に把握して,総括できるよう進めることが必要です。このことのためには各学校において,年間の評価計画を作成することやそれにそった単元における評価規準,一時間ごとの評価規準の具体が明らかに設定されていることが大切になります。
評価規準を設定する最初の段階では,設定までの過程の理解や計画の作成に多くの時間と手数がかかります。実際のところ,新しい学習指導要領による実践が始まり一学期が経過しましたが,具体的に準備ができた学校は必ずしも多いとは言えません。
本書では,1章において,評価規準の設定のための基本的な考え方や手順を示しています。国語科の目標や各学年の目標,内容の評価の観点の趣旨については,国立教育政策研究所より参考資料として示されています。それを参考にしながら,単元及び一時間における評価規準の設定及び評価の方法を明らかにしています。
2章においては,「話すこと・聞くこと」「書くこと」・「読むこと」の領域別に構成しています。新しい学習指導要領では,2学年まとめて内容を示していますが,低・中・高学年に分け,指導内容にそった主たる単元及び本時の指導における評価規準の具体を設定しています。特に,観点別評価の進め方の中でも,「十分満足できる状況と判断した児童の状況」や「単元の観点別評価表」の作成については参考にしていただけるよう工夫しています。
各学校においては,年間指導計画にそった全単元における評価規準が整えられることが求められています。作成に当たり本書を積極的に活用されることを願ってやみません。
終わりに,本書の趣旨を理解していただき執筆にご協力くださいました先生方に心よりお礼申し上げます。また,企画・出版にご尽力いただきました編集部の安藤征宏氏に深く感謝申し上げます。
平成14年10月 編者 /清水 健
-
 明治図書
明治図書