- はじめに
- 1章 個別最適な学びと国語の「学び方」
- 1 それでいいのか? 「個別最適な学び」
- 2 自由進度学習によって失われる「自由」
- 3 「令和の日本型」自己調整学習に,半分共感
- 4 「学び方」を,まず国語科で教えるわけ
- 5 授業で育む国語の「学び方」
- 6 国語の「学び方」をどう育むか
- 7 なぜ「状況設定とフィードバック」なのか
- 本書で示す国語の「学び方」一覧
- 2章 低学年で育む国語の「学び方」
- 0 低学年の子供の実態と教材 自分に引きつけて学ぶ低学年
- 1 国語の眼鏡 低学年の子供にセットしたい国語の眼鏡
- 2 基本的な言語活動/話す 聞き手を意識して話す
- 3 基本的な言語活動/聞く 話し手を見て正確に聞き取る
- 4 基本的な言語活動/書く 教材に書き込む
- 5 基本的な言語活動/読む(音読) 句読点に気を付けて音読する
- 6 基本的な言語活動/話し合う 同じものを見つめて話し合う
- 7 課題設定/課題 活動型の課題を設定する
- 8 課題設定/問い 教材(題材)内容と,既有経験とのズレから問いを生む
- 9 情報の収集/テクスト 追究に必要な情報を見つける
- 10 情報の収集/他者 他者から情報(事実的な事柄)を得る
- 11 整理・分析/ツール 観点を見いだす(XYチャート)
- 12 整理・分析/ツール 共通点や相違点を見る(ベン図)
- 13 整理・分析/話し合い 話し合って自分の考えを客観視する
- 14 まとめ・表現/まとめる 学習のまとめをする
- 15 まとめ・表現/振り返る 自分の心の動きを振り返る
- 16 まとめ・表現/ICT(蓄積) 画像や動画で記録に残す
- 3章 中学年で育む国語の「学び方」
- 0 中学年の子供の実態と教材 様々な視点で対象を見つめる中学年
- 1 国語の眼鏡 中学年の子供にセットしたい国語の眼鏡
- 2 基本的な言語活動/話す 根拠を示しながら話す
- 3 基本的な言語活動/聞く 話し手の根拠を意識して聞く
- 4 基本的な言語活動/書く 考えを文章にまとめる
- 5 基本的な言語活動/読む(音読) 文脈を捉えて音読する
- 6 基本的な言語活動/話し合う 複数の情報源を共有して話し合う
- 7 課題設定/課題 プロジェクト型の課題を設定する
- 8 課題設定/問い 設定した目的と,教材(題材)の関連から問いを生む
- 9 情報の収集/テクスト 情報のつながり,まとまりを捉える
- 10 情報の収集/国語辞典 言葉の意味を問い直す
- 11 情報の収集/他者 他者から情報(つながり,まとまり)を得る
- 12 情報の収集/web検索 キーワードを設定して情報を集める
- 13 整理・分析/ツール つながりを見いだす(関係図)
- 14 整理・分析/ツール 変化を見る(線分図)
- 15 整理・分析/話し合い 話し合って様々な視点を得る
- 16 まとめ・表現/まとめる 自他の考えを関連付けてまとめる
- 17 まとめ・表現/振り返る 自分の学習状況を評価する
- 18 まとめ・表現/ICT(蓄積) クラウド内の記録を分類する
- 4章 高学年で育む国語の「学び方」
- 0 高学年の子供の実態と教材 自分で自分を意識できる高学年
- 1 国語の眼鏡 高学年の子供にセットしたい国語の眼鏡
- 2 基本的な言語活動/話す 根拠と理由を区別して話す
- 3 基本的な言語活動/聞く 自分の考えをもちながら聞く
- 4 基本的な言語活動/書く 様々な表現で書き表す
- 5 基本的な言語活動/読む(音読) 課題解決の方法として音読する
- 6 基本的な言語活動/話し合う 自分の追究を深めるために話し合う
- 7 課題設定/課題 省察型の課題を設定する
- 8 課題設定/問い 物語の空所を見いだして問いを生む
- 9 情報の収集/テクスト テクストの特徴を捉える
- 10 情報の収集/関連図書 主教材の関連情報を収集する
- 11 情報の収集/他者 他者から情報(特徴,価値)を得る
- 12 情報の収集/生成AI 文脈に応じた情報を収集する
- 13 整理・分析/ツール 中心となる情報を見いだす(構造図)
- 14 整理・分析/ツール 2つの観点で情報を見る(二次元表)
- 15 整理・分析/話し合い 話し合って考えを一般化する
- 16 整理・分析/生成AI 自分の文章のくせを捉える
- 17 まとめ・表現/まとめる 一般化してまとめる
- 18 まとめ・表現/振り返る 自分の見方・考え方を振り返る
- 19 まとめ・表現/ICT(蓄積) ファイル名にキーワードを含ませる
- おわりに
- 参考・引用文献
はじめに
「個別最適な学び」という言葉が登場してから,いわゆる「子供に委ねる授業」がよく話題に上がります。「子供に委ねる授業」とは,明確な定義はありませんが,教師の出番を減らして,学習形態や学習方法を子供に選択させる授業を指すようです。
そのような「子供に委ねる授業」を実践すると,自らグループ学習を選択して対話したり,タブレット端末を活用しながら自分のペースで学習したりする子供の姿を見ることができます。これにより,
「一斉授業では,なかなか見られない素敵な姿だ」
「子供は,もともと学ぶ力をもっているんだ」
と,そんなふうに思えることは,大変価値があることでしょう。そうやって教師の教育観が広がれば,教師にとっても子供にとっても,授業の可能性が広がっていきます。
一方で,「子供に委ねる授業」を実践すると,安易に他者に追従して学習を進めてしまったり,深い学びとは言い難い表層的なところで学習を止めてしまったりする子供の姿も見られます。授業者としては,そんな姿に目を瞑り続けることはできません。そこで,
「慣れてくれば,子供は自分たちで学びを深められるようになっていきます」
と,そんな言説が聞かれることがあります。もちろん,そういった側面もあるのかもしれません。しかしながら,とにかくやらせれば指導上の問題が解決されるという考え方には,賛同できません。教師には,子供の難しさに向き合って,指導を改善する責任があるはずです。
「一斉授業で,教えるべきことをきちんと教えていきましょう」
と,そんな言説が聞かれることがあります。「子供に委ねた授業」で扱えなかった部分を,一斉授業で補おうという考え方です。理屈は通っているように感じますが,この考え方にも賛同できません。「教えるべきことをきちんと教える」という理念で行われる一斉授業は,教師が一方的に知識を伝達する授業を生むでしょう。その結果「教師は教えたけれど,子供は学べなかった」と,そんな状況をつくりかねません。
それでは,私たち教師は,どのように指導を改善すべきでしょうか。
本書では,一つの答えとして「子供の『学び方』を育む」ことを提案します。『学び方』とは,子供が自分自身で学習を進めたり深めたりするための方法です。
さらに,本書でこだわっているのは,「『学び方』をどう育むか」ということです。理想的な『学び方』を一覧表にして配付したり,「このようにやりなさい」と一方的に伝達したりする「教える」指導では,子供が本当に『学び方』を身に付けることは難しいと考えます。課題を追究する中で,子供の『学び方』を引き出し,それを価値あるものとして意味付ける「育む」指導が重要です。そうすることで「なるほど,こうすればうまくいくんだな」と,子供が『学び方』を実感的に理解することができるのです。
ぜひ,教室の子供たちを思い浮かべながら本書をお読みください。そして,子供たちの『学び方』を育むことについて,一緒に考えていきましょう。
2025年6月 /中野 裕己














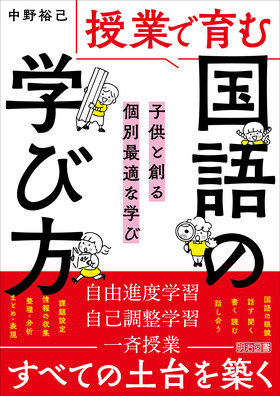
 PDF
PDF


著者の中野先生が子どもたちをどのように見とるのか、という視点から学ぶことができ、非常に深い内容でした。