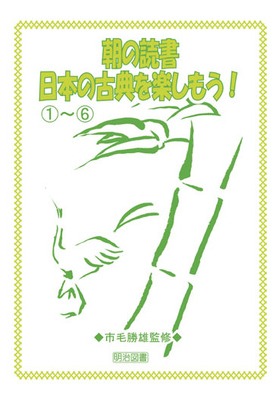- 竹取物語
- 一 かぐや姫(ひめ)
- 二 五(ご)人(にん)の貴(き)公(こう)子(し)
- 三 仏(ほとけ)の御(み)石(いし)の鉢(はち)
- 四 (ほう) (らい)の玉(たま)の枝(えだ)
- 五 玉(たま)の枝(えだ)の正(しょう)体(たい)
- 六 火(ひ)ねずみの皮(かわ)衣(ぎぬ)
- 七 龍(りゅう)の首(くび)の玉(たま)
- 八 つばめの子(こ)安(やす)貝(がい)
- 九 帝(みかど)の求(きゅう)婚(こん)
- 一〇 帝(みかど)との出(で)会(あ)い
- 一一 かぐや姫(ひめ)の悲(かな)しみ
- 一二 かぐや姫(ひめ)との別(わか)れ
- 一三 不(ふ)死(し)の薬(くすり)
- 一四 ふじの山(やま)
- 枕草子
- 一 春(はる)はあけぼのがよい(第(だい)一段(だん))
- 二 帝(みかど)のおそばに飼(か)われている猫(ねこ)は(第(だい)七段(だん))
- 三 正(しょう)月(がつ)一(つい)日(たち)、三(さん)月(がつ)三(みっ)日(か)は(第(だい)八段(だん))
- 四 将(しょう)来(らい)ののぞみもなく、きまじめに(第(だい)二一段(だん))
- 五 にくらしいもの(第(だい)二五段(だん))
- 六 木(こ)の花(はな)は(第(だい)四四段(だん))
- 七 上(じょう)品(ひん)で美(うつく)しいもの(第(だい)四九段(だん))
- 八 めったにない珍(めずら)しいもの(第(だい)七七段(だん))
- 九 いたたまれない感(かん)じのするもの(第(だい)一〇一段(だん))
- 一〇 間(ま)のわるいもの(第(だい)一三一段(だん))
- 一一 九(く)月(がつ)のころ(第(だい)一三三段(だん))
- 一二 かわいらしいもの(第(だい)一五五段(だん))
- 一三 五(ご)月(がつ)のころに(第(だい)二〇四段(だん))
- 一四 五(ご)月(がつ)五(いつ)日(か)の菖(しょう)蒲(ぶ)が(第(だい)二〇六段(だん))
- 一五 月(つき)のとても明(あか)るい夜(よる)(第(だい)二〇八段(だん))
- 一六 大(おお)蔵(くら)卿(きょう)の(第(だい)二一八段(だん))
- 一七 珍(めずら)しいというほどのことではないけれど(第(だい)二二一段(だん))
- 一八 日(ひ)は(第(だい)二二七段(だん))
- 一九 月(つき)は(第(だい)二二八段(だん))
- 二〇 星(ほし)は(第(だい)二二九段(だん))
- 二一 雪(ゆき)のたいそう高(たか)く降(ふ)り積(つ)もった日(ひ)(第(だい)二七八段(だん))
- 方丈記
- 一 河(かわ)の流(なが)れ
- 二 安(あん)元(げん)の大(たい)火(か)
- 三 (つじ)風(かぜ)
- 四 都(みやこ)遷(うつ)り
- 五 飢(き)渇(かつ)
- 六 大(おお)地(じ)震(しん)
- 七 世(よ)に従(したが)えば
- 八 わが過(か)去(こ)
- 九 方(ほう)丈(じょう)
- 一〇 境(きょう)涯(がい)
- 一一 山(やま)は見(み)はらしがよく
- 一二 閑居(かんきょ)の気味(きび)
- 一三 みずから心(こころ)に問(と)う
- 土佐日記
- 一 日(にっ)記(き)を書(か)き始(はじ)める
- 二 送(そう)別(べつ)会(かい)を開(ひら)いてもらう
- 三 亡(な)くなった娘(むすめ)のことを思(おも)い出(だ)す
- 四 見(み)送(おく)りの人(ひと)たちと別(わか)れる
- 五 羽(は)根(ね)にちなんで歌(うた)をよんだ
- 六 足(あし)止(ど)めを食(く)って旅(たび)が進(すす)まない
- 七 月(つき)を見(み)て仲(なか)麻(ま)呂(ろ)を思(おも)う
- 八 海(かい)賊(ぞく)の恐(おそ)ろしさにふるえる
- 九 浜(はま)辺(べ)で貝(かい)や石(いし)を見(み)て子(こ)どもを思(おも)い出(だ)す
- 一〇 住(すみ)吉(よし)の神(かみ)様(さま)に捧(ささ)げものをする
- 一一 淀(よど)川(がわ)をさかのぼって京(きょう)の都(みやこ)へ向(む)かう
- 一二 山(やま)崎(ざき)に到(とう)着(ちゃく)してもてなしを受(う)ける
- 一三 夜(よる)になって京(きょう)の都(みやこ)に入(はい)る
- 一四 自(じ)宅(たく)に帰(かえ)り日(にっ)記(き)をしめくくる
- 大鏡
- 一 世(よ)継(つぎ)じいさんと繁(しげ)樹(き)じいさん(序(じょ))
- 二 左(さ)大(だい)臣(じん)の野(や)望(ぼう)をくじく(藤(ふじ)原(わら)基(もと)経(つね)の伝(でん)記(き))
- 三 道(みち)真(ざね)を左(さ)遷(せん)する(藤(ふじ)原(わら)時(とき)平(ひら)の伝(でん)記(き))
- 四 きんしん処(しょ)分(ぶん)を取(と)り消(け)す(藤(ふじ)原(わら)師(もろ)輔(すけ)の伝(でん)記(き))
- 五 兄(きよう)弟(だい)の出(しゅっ)世(せ)争(あらそ)い(藤(ふじ)原(わら)兼(かね)通(みち)の伝(でん)記(き))
- 六 天(てん)皇(のう)をかえる陰(いん)謀(ぼう)(花(か)山(ざん)天(てん)皇(のう)の伝(でん)記(き))
- 七 雨(あめ)の日(ひ)のきもだめし(藤(ふじ)原(わら)道(みち)長(なが)の伝(でん)記(き))
- 八 弓(ゆみ)の腕(うで)くらべ(藤(ふじ)原(わら)道(みち)長(なが)の伝(でん)記(き))
- 九 才(さい)能(のう)ゆたかな公(きん)任(とう)(藤(ふじ)原(わら)頼(より)忠(ただ)の伝(でん)記(き)から)
- 一〇 双(すご)六(ろく)でもてなす(藤(ふじ)原(わら)道(みち)隆(たか)の伝(でん)記(き)から)
- 宇治拾遺物語
- 一 鬼(おに)にこぶとられること(第(だい)三話(わ) 巻(まき)一の三)
- 二 児(ちご)の空(そら)寝(ね)したること(第(だい)一二話(わ) 巻(まき)一の一二)
- 三 絵(え)仏(ぶっ)師(し)良(りょう)秀(しゅう)、家(いえ)が焼(や)けるのを見(み)て悦(よろこ)ぶこと(第(だい)三八話(わ) 巻(まき)三の六)
- 四 袴(はかま)垂(だれ)、保(やす)昌(まさ)に合(あ)うこと(第(だい)二八話(わ) 巻(まき)二の一〇)
- 五 きこり歌(うた)のこと(第(だい)四〇話(わ) 巻(まき)三の八)
- 六 雀(すずめ)の恩(おん)返(がえ)しのこと(第(だい)四八話(わ) 巻(まき)三の一六)
- 七 日(にち)蔵(ぞう)上(しょう)人(にん)、吉(よし)野(の)山(やま)にて鬼(おに)にであうこと(第(だい)一三三話(わ) 巻(まき)一一の一〇)
- 八 五(ご)色(しき)の鹿(しか)のこと(第(だい)九二話(わ) 巻(まき)七の一)
- 九 後(あと)の千(せん)金(きん)のこと(第(だい)一九五話(わ) 巻(まき)一五の一一)
まえがき
竹取物語(たけとりものがたり)
1 内容(ないよう)のあらまし
竹(たけ)の中(なか)からみつかったうつくしい「かぐや姫(ひめ)」に五(ご)人(にん)の貴(き)公(こう)子(し)が結婚(けっこん)を申(もう)しこむ。かぐや姫(ひめ)は五(ご)人(にん)にむずかしい問題(もんだい)をだして、あきらめさせる。さいごに帝(みかど)が結婚(けっこん)のもうしこみをする。それもことわって、十(じゅう)五(ご)夜(や)の晩(ばん)に月(つき)の世(せ)界(かい)にかえっていき、帝(みかど)も竹取(たけとり)の翁(おきな)もなげき悲(かな)しむ、という物(もの)語(がたり)です。
2 書物(しょもつ)の種類(しゅるい)
つくり物(もの)語(がたり)。いまのことばで言(い)うと「フィクション」物(もの)語(がたり)です。平安(へいあん)時(じ)代(だい)初(しょ)期(き)には「物(もの)語(がたり)」ということばは「ほんとうにあったことをつたえる話(はなし)」という意味(いみ)でした。かぐや姫(ひめ)のむずかしい問題(もんだい)にくるしむ五(ご)人(にん)の貴(き)公(こう)子(し)に「阿倍(あべ)の御主人(みうし)・大(だい)納(な)言(ごん)大(おお)伴(ともの)御(み)行(ゆき)」という『日(に)本(ほん)書(しょ)紀(き)』などに登(とう)場(じょう)する実在(じつざい)の人(ひと)の名(な)があるために、とくべつに「つくり(事(じ)実(じつ)ではない)物(もの)語(がたり)」と名(な)づけたとおもわれます。
3 長(なが)さ・構成(こうせい)
長(なが)さは「朝(あさ)の読書(どくしょ)シリーズ」の大(おお)きさに印刷(いんさつ)すると四十ページほどです。
構成(こうせい)は、①竹取(たけとり)の翁(おきな)とかぐや姫(ひめ) ②五(ご)人(にん)の貴(き)公(こう)子(し) ③石作(いしづく)りの皇子(みこ)と仏(ほとけ)の御(み)石(いし)の鉢(はち) ④~⑤倉(くら)持(もち)の皇子(みこ)と (ほうらい)の玉(たま)の枝(えだ) ⑥阿倍(あべ)の右(う)大(だい)臣(じん)と火(ひ)ねずみの皮(かわ)衣(ぎぬ) ⑦大伴(おおとも)の大(だい)納(な)言(ごん)と龍(りゅう)の首(くび)の玉(たま) ⑧石上(いそのかみ)の中(ちゅう)納(な)言(ごん)とつばめの子(こ)安(やす)貝(がい) ⑨~⑫帝(みかど)の求婚(きゅうこん)と姫(ひめ)の昇天(しょうてん) という整然(せいぜん)とした構成(こうせい)になっています。
4 成立(せいりつ)
『万(まん)葉(よう)集(しゅう)』巻(まき)十六(三七九一)の詞書(ことばがき)に「むかしおきなあり、よびなを竹取翁(たけとりのおきな)という…」という文(ぶん)があります。また有名(ゆうめい)な紫(むらさき)式(しき)部(ぶ)『源氏(げんじ)物(もの)語(がたり)』(絵合(えあわせ))の中(なか)に「物(もの)語(がたり)のいで来(き)はじめの親(おや)なる竹取(たけとり)の翁(おきな)…かぐや姫(ひめ)ののぼりけむ雲(くも)ゐは…」という文(ぶん)があります。「かぐや姫」の話(はなし)は奈良(なら)時(じ)代(だい)から有名(ゆうめい)だったことがわかります。物(もの)語(がたり)の名(な)も室町(むろまち)時(じ)代(だい)までは「竹取(たけとり)のおきなの物(もの)語(がたり)」と呼(よ)ばれていました。奈良(なら)時(じ)代(だい)にはあらすじだけの短(みじか)い話(はなし)がおおく、室町(むろまち)時(じ)代(だい)になるとくわしい話(はなし)がおおくのこっています。このことから、この物(もの)語(がたり)は一人(ひとり)の作者(さくしゃ)が書(か)きあげたのではなく、長(なが)い時(じ)代(だい)にわたって、たくさんの人(ひと)がこの物(もの)語(がたり)にかかわったことがわかります。
5 価値(かち)
①五(ご)人(にん)のりっぱな貴(き)公(こう)子(し)がみな失敗(しっぱい)して笑(わら)われるという話(はなし)で、平安(へいあん)貴(き)族(ぞく)の社会(しゃかい)を批(ひ)評(ひょう)的(てき)にえがいている。②五(ご)人(にん)の失敗(しっぱい)の場(ば)面(めん)、かぐや姫(ひめ)が天(てん)にのぼる場(ば)面(めん)など、目(め)に見(み)えるようにくわしく書(か)かれている。③貴(き)族(ぞく)の社会(しゃかい)で行(おこな)われた和歌(わか)のやりとりが、物(もの)語(がたり)の中(なか)でじょうずに正確(せいかく)におこなわれている。こういう特長(とくちょう)から、この「つくり物(もの)語(がたり)」は大人(おとな)がまじめに読(よ)む価値(かち)があるとして、むかしから尊敬(そんけい)されてきました。
6 作者(さくしや)
「4 成立(せいりつ)」でも述(の)べたように、長(なが)い間(あいだ)にしだいにりっぱな物(もの)語(がたり)に成長(せいちょう)したものですから、作者(さくしゃ)を一人(ひとり)に決(き)めることはできません。
枕草子(まくらのそうし)
1 内容(ないよう)のあらまし
宮(きゅう)中(ちゅう)で皇(こう)后(ごう)におつかえする生(せい)活(かつ)のようすを、清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)という女(じょ)性(せい)が書(か)いたものです。
2 書(しょ)物(もつ)の種(しゅ)類(るい)
感(かん)想(そう)・日(にっ)記(き)・記(き)録(ろく)などいろいろな文(ぶん)章(しょう)をふくんでいます。
3 長(なが)さ・構(こう)成(せい)
文(ぶん)章(しょう)の量(りょう)は、この「朝(あさ)の読(どく)書(しょ)シリーズ」のような本(ほん)にすると、やく三百(びゃく)ページにもなります。文(ぶん)章(しょう)の種(しゅ)類(るい)は、つぎのように三つにわける例(れい)が多(おお)いようです。(段(だん)とは文(ぶん)章(しょう)のグループのこと)
一 ものはづけ 「春(はる)はあけぼの」のように「おもしろい」と思(おも)うことをあつめた文(ぶん)章(しょう)です。全(ぜん)部(ぶ)で百(ひゃく)六十段(だん)ほどあります。
二 日(にっ)記(き)
宮(きゅう)中(ちゅう)の生(せい)活(かつ)をくわしく日(にっ)記(き)・記(き)録(ろく)のように書(か)いた文(ぶん)章(しょう)で約(やく)八十段(だん)あります。ページ数(すう)はこの文(ぶん)章(しょう)がいちばん多(おお)くなっています。
三 随(ずい)想(そう)(感(かん)想(そう))
思(おも)いつくことをあれこれと書(か)いた文(ぶん)章(しょう)で、約(やく)八十段(だん)あります。
4 成(せい)立(りつ)
清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)が宮(きゅう)中(ちゅう)につとめていた九九四年(ねん)ごろから一(いち)部(ぶ)の文(ぶん)章(しょう)が評(ひょう)判(ばん)になって、人(ひと)びとの書(か)き写(うつ)した本(ほん)が流(りゅう)通(つう)しはじめ、六年(ねん)後(ご)の一〇〇〇年(ねん)ごろにはほとんどの文(ぶん)章(しょう)ができあがったようです。一(いっ)気(き)に書(か)きあげたのではなく、すこしずつ書(か)いていったため、数(すう)種(しゅ)類(るい)の写(しゃ)本(ほん)(手(て)書(が)きのテキスト)ができました。
5 価(か)値(ち)
『枕(まくらの)草(そう)子(し)』は宮(きゅう)中(ちゅう)に生(せい)活(かつ)している女(じょ)性(せい)が、見(み)たこと、聞(き)いたこと、体(たい)験(けん)したことをくわしく書(か)いたものです。おおくの貴(き)族(ぞく)の家(か)庭(てい)では、自(じ)分(ぶん)の娘(むすめ)がよい評(ひょう)判(ばん)をえて、よい結(けっ)婚(こん)をするために必(ひつ)要(よう)な教(きょう)養(よう)、知(ち)識(しき)、こころがけなどを知(し)りたがっていました。この『枕(まくらの)草(そう)子(し)』はそういう家(か)庭(てい)の最(さい)高(こう)の参(さん)考(こう)書(しょ)になりました。父(ちち)親(おや)は先(さき)をあらそって『枕(まくらの)草(そう)子(し)』を借(か)りて筆(ひっ)写(しゃ)して、娘(むすめ)に読(よ)ませました。
6 作(さく)者(しゃ)
この本(ほん)は当(とう)時(じ)いろいろな呼(よ)び方(かた)がされました。「清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)」「清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)草(そう)子(し)」「清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)枕(まくら)」「枕(まくらの)草(そう)子(し)」などです。当(とう)時(じ)「枕(まくらの)草(そう)子(し)」という言(こと)葉(ば)はメモ帳(ちょう)という意(い)味(み)でしたが、この本(ほん)が有(ゆう)名(めい)になってからは、清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)の書(か)いた書(しょ)物(もつ)の『枕(まくらの)草(そう)子(し)』だけをさす呼(よ)び方(かた)になりました。このことから、作(さく)者(しゃ)は「清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)」と呼(よ)ばれた女(じょ)性(せい)であることは確(たし)かです。「少(しょう)納(な)言(ごん)」とは宮(きゅう)廷(てい)の官(かん)職(しょく)の名(な)です。「清」は当(とう)時(じ)の習(しゅう)慣(かん)で「せい」と音(おん)読(よ)みします。清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)は九九一年(ねん)、三十歳(さい)のとき、教(きょう)養(よう)と才(さい)能(のう)を見(み)込(こ)まれて十歳(さい)年(とし)下(した)の皇(こう)后(ごう)定(てい)子(し)に仕(つか)えました。皇(こう)后(ごう)定(てい)子(し)のライバルは中(ちゅう)宮(ぐう)彰(しょう)子(し)でしたが、その父(ちち)藤(ふじ)原(わらの)道(みち)長(なが)は清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)とは同(どう)年(ねん)齢(れい)でした。一〇〇〇年(ねん)十二月(がつ)に定(てい)子(し)が亡(な)くなってから、清(せい)少(しょう)納(な)言(ごん)は宮(きゅう)中(ちゅう)を退(たい)出(しゅつ)して、孤(こ)独(どく)な老(ろう)後(ご)を過(す)ごしたようです。
方丈記(ほうじょうき)
1 内(ない)容(よう)のあらまし
『方(ほう)丈(じょう)記(き)』は京(きょう)都(と)郊(こう)外(がい)に住(す)んでいた鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)が、京(きょう)都(と)のまちをいくつもの災(さい)害(がい)がおそうようすをくわしく記(き)録(ろく)したものです。そして、その記(き)録(ろく)のあとで、鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)は一丈(じょう)(三メートル)四(し)方(ほう)の正(せい)方(ほう)形(けい)の小(ちい)さい家(いえ)を建(た)てて住(す)み、仏(ぶつ)教(きょう)信(しん)仰(こう)の生(せい)活(かつ)をつづけたと書(か)いています。書(か)いたのは六十歳(さい)のころです。
2 書(しょ)物(もつ)の種(しゅ)類(るい)
この書(しょ)物(もつ)は、災(さい)害(がい)のくわしい記(き)録(ろく)が中(ちゅう)心(しん)です。そのあとに自(じ)分(ぶん)の人(じん)生(せい)、現(げん)在(ざい)の家(いえ)、毎(まい)日(にち)の生(せい)活(かつ)などをうつくしい文(ぶん)章(しょう)で書(か)いています。
3 長(なが)さ・構(こう)成(せい)
『方(ほう)丈(じょう)記(き)』は全(ぜん)文(ぶん)の長(なが)さが、四百字(じ)づめ原(げん)稿(こう)用(よう)紙(し)でわずか二十八枚(まい)分(ぶん)です。構(こう)成(せい)は、つぎのようにみることができます。
序(じょ)文(ぶん) 「河(かわ)の流(なが)れ」(この見(み)出(だ)しはのちの人(ひと)がつけたものです)
第(だい)一部(ぶ)は災(さい)害(がい)の記(き)録(ろく)です。「安(あん)元(げん)の大(たい)火(か)・ (つじ)風(かぜ)・都(みやこ)遷(うつ)り・飢(き)渇(かつ)・大(おお)地(じ)震(しん)」
第(だい)二部(ぶ)は自(じ)分(ぶん)の人(じん)生(せい)についての反(はん)省(せい)です。「世(よ)に従(したが)えば・わが過(か)去(こ)」
第(だい)三部(ぶ)は現(げん)在(ざい)の生(せい)活(かつ)のようすです。「方(ほう)丈(じょう)・境(きょう)涯(がい)・山(やま)は見(み)はらしがよく・閑(かん)居(きょ)の気(き)味(び)」
むすび 「みずから心(こころ)に問(と)う」
4 成(せい)立(りつ)
文(ぶん)章(しょう)の最(さい)後(ご)に書(か)かれている「建(けん)暦(りゃく)二(一二一二)年(ねん)」が、この本(ほん)の書(か)かれた年(とし)です。このように書(か)かれた年(とし)がはっきりわかるのは、めずらしい例(れい)です。
5 価(か)値(ち)
平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)末(まっ)期(き)まで、社(しゃ)会(かい)のありさまをくわしく文(ぶん)章(しょう)に書(か)いた人(ひと)はいませんでした。だから、この本(ほん)の「第(だい)一部(ぶ)」は現(げん)在(ざい)で言(い)うドキュメンタリー文(ぶん)学(がく)の初(はじ)めです。また、深(ふか)い悩(なや)みを率(そっ)直(ちょく)にくわしく書(か)いた第(だい)二部(ぶ)の文(ぶん)章(しょう)は、その後(ご)の日(に)本(ほん)の思(し)想(そう)家(か)たちに大(おお)きな影(えい)響(きょう)を与(あた)えました。
この本(ほん)でふしぎなことは、当(とう)時(じ)、日(に)本(ほん)中(じゅう)を騒(さわ)がせた平(へい)家(け)と源(げん)氏(じ)の戦(たたか)い、鎌(かま)倉(くら)幕(ばく)府(ふ)の騒(そう)動(どう)などをまったく書(か)かずに、京(きょう)都(と)の町(まち)と住(す)まいのことだけを書(か)いていることです。
6 作(さく)者(しゃ)
作(さく)者(しゃ)鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)は、賀(か)茂(もの)御(み)祖(おや)神(じん)社(じゃ)の神(しん)官(かん)の家(いえ)柄(がら)に生(う)まれ、あとつぎに決(き)まっていました。また当(とう)時(じ)、宮(きゅう)中(ちゅう)でも有(ゆう)名(めい)な歌(か)人(じん)でした。それが、家(か)庭(てい)の事(じ)情(じょう)や政(せい)治(じ)の混(こん)乱(らん)のために親(しん)戚(せき)や妻(さい)子(し)からきらわれ、ついに親(しん)戚(せき)の家(いえ)を追(お)い出(だ)されてしまいました。三十歳(さい)のころです。京(きょう)都(と)に住(す)むのがいやになった鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)は、和(わ)歌(か)の仲(なか)間(ま)とも別(わか)れて京(きょう)都(と)の郊(こう)外(がい)に住(す)み、二(に)度(ど)と京(きょう)都(と)にもどることはありませんでした。
土佐日記(とさにっき)
1 内(ない)容(よう)のあらまし
平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)の初(しょ)期(き)、紀(きの)貫(つら)之(ゆき)は九三〇年(ねん)、国(こく)司(し)土(と)佐(さの)守(かみ)として四(し)国(こく)土(と)佐(さ)の国(こく)府(ふ)(南(なん)国(ごく)市(し)比(ひ)江(え))に着(ちゃく)任(にん)し、九三四年(ねん)に京(きょう)都(と)の自(じ)宅(たく)に帰(かえ)りました。その帰(かえ)りの旅(たび)は十二月(がつ)二十一日(にち)から翌(よく)年(ねん)の二月(がつ)十六日(にち)まで五十五日(にち)かかっています。その旅(たび)のようすを記(き)録(ろく)としてくわしく書(か)いたものが『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』です。
2 書(しょ)物(もつ)の種(しゅ)類(るい)
当(とう)時(じ)(平(へい)安(あん)時(じ)代(だい))は「日(にっ)記(き)」というと、宮(きゅう)廷(てい)や官(かん)庁(ちょう)で書(か)かれた儀(ぎ)式(しき)・政(せい)治(じ)・行(ぎょう)事(じ)などの記(き)録(ろく)のことでした。そういう時(じ)代(だい)に、現(げん)代(だい)の日(にっ)記(き)とおなじように、生(せい)活(かつ)の中(なか)であじわうよろこびやかなしみをくわしく書(か)いた本(ほん)は『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』がはじめてです。
3 長(なが)さ・構(こう)成(せい)
『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』は、この「朝(あさ)の読(どく)書(しょ)シリーズ」のページ数(すう)になおすと、約(やく)四十ページくらいの長(なが)さの文(ぶん)章(しょう)です。和(わ)歌(か)が五十九首(しゅ)、船(せん)頭(どう)たちのうたった「舟(ふな)歌(うた)」が一(ひと)つあります。和(わ)歌(か)はほとんどが紀(きの)貫(つら)之(ゆき)の作(さく)品(ひん)です。
4 成(せい)立(りつ)
この日(にっ)記(き)は旅(りょ)行(こう)中(ちゅう)の記(き)録(ろく)メモを参(さん)考(こう)に、かなり時(じ)間(かん)をかけて完(かん)成(せい)させたようです。こまかい部(ぶ)分(ぶん)をよくしらべると、事(じ)件(けん)の順(じゅん)序(じょ)を変(か)えたり、フィクション(つくりごと)を交(まじ)えたりというしかけがあります。
5 価(か)値(ち)
日(にっ)記(き)をじぶんの心(こころ)の記(き)録(ろく)として書(か)いたという日(に)本(ほん)最(さい)初(しょ)の試(こころ)みが、この本(ほん)の価(か)値(ち)です。そして記(き)録(ろく)の方(ほう)法(ほう)として、会(かい)話(わ)、短(たん)歌(か)、舟(ふな)歌(うた)、景色(けしき)のくわしい描(びょう)写(しゃ)(ことばでようすを書(か)くこと)などの表(ひょう)現(げん)技(ぎ)術(じゅつ)をたくみに使(つか)い分(わ)けています。これは、当(とう)時(じ)としてはおどろくほど高(こう)級(きゅう)な文(ぶん)章(しょう)表(ひょう)現(げん)の技(ぎ)術(じゅつ)でした。この文(ぶん)章(しょう)表(ひょう)現(げん)の価(か)値(ち)を見(み)ぬいたのが大(だい)歌(か)人(じん)の藤(ふじ)原(わらの)定(てい)家(か)(一一六二~一二四一)です。鎌(かま)倉(くら)時(じ)代(だい)の一二三五年(ねん)、定(てい)家(か)は七十四歳(さい)になっていましたが、紀(きの)貫(つら)之(ゆき)自(じ)筆(ひつ)の『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』を一(いち)読(どく)してそのすばらしい文(ぶん)章(しょう)におどろき、二日(ふつか)がかりで書(しょ)写(しゃ)して、その本(ほん)を観(かん)察(さつ)した記(き)録(ろく)も残(のこ)しました(この「定(てい)家(か)本(ぼん)」は国(こく)宝(ほう))。このように紀(きの)貫(つら)之(ゆき)の『古(こ)今(きん)和(わ)歌(か)集(しゅう)』と『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』の二(に)作(さく)品(ひん)は、漢(かん)詩(し)文(ぶん)全(ぜん)盛(せい)の平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)を日(に)本(ほん)文(ぶん)優(ゆう)勢(せい)に変(へん)革(かく)した重(じゅう)要(よう)な作(さく)品(ひん)です。
6 作(さく)者(しゃ)
紀(きの)貫(つら)之(ゆき)(八七一~九四六)は平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)前(ぜん)期(き)の歌(か)人(じん)で、官(かん)職(しょく)の地(ち)位(い)は低(ひく)かったのですが、歌(か)人(じん)としては一(いち)流(りゅう)でした。日(に)本(ほん)最(さい)初(しょ)の勅(ちょく)撰(せん)集(しゅう)『古(こ)今(きん)和(わ)歌(か)集(しゅう)』(九〇五)の指(し)導(どう)的(てき)な選(せん)者(じゃ)で、漢(かん)詩(し)・漢(かん)文(ぶん)全(ぜん)盛(せい)期(き)の平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)に、日(に)本(ほん)最(さい)初(しょ)の和(わ)歌(か)の理(り)論(ろん)を純(じゅん)粋(すい)な日(に)本(ほん)語(ご)で書(か)いた「仮(か)名(な)序(じょ)」(序(じょ)「まえがき」)が有名(ゆうめい)です(『古(こ)今(きん)集(しゅう)』には別(べつ)に漢(かん)文(ぶん)の「真(ま)名(な)序(じょ)」があります)。『土(と)佐(さ)日(にっ)記(き)』の筆(ひっ)者(しゃ)は紀(きの)貫(つら)之(ゆき)の妻(つま)だと、本(ほん)文(ぶん)の最(さい)初(しょ)に書(か)いてありますが、現(げん)在(ざい)ではいろいろな証(しょう)拠(こ)から、紀(きの)貫(つら)之(ゆき)自(じ)身(しん)が筆(ひっ)者(しゃ)であることがわかっています。これは当(とう)時(じ)、日(にっ)記(き)は男(だん)子(し)が漢(かん)文(ぶん)で書(か)くものだという常(じょう)識(しき)があったためです。
大鏡(おおかがみ)
1 内(ない)容(よう)のあらまし
『大(おお)鏡(かがみ)』は藤(ふじ)原(わらの)道(みち)長(なが)を中(ちゅう)心(しん)にして政(せい)治(じ)を描(えが)いた物(もの)語(がたり)です。時(じ)代(だい)は八五二年(ねん)から一〇二五年(ねん)までの約(やく)百(ひゃく)七十年(ねん)間(かん)、人(じん)物(ぶつ)は四百(ひゃく)五十人(にん)あまりが登(とう)場(じょう)します。
2 書(しょ)物(もつ)の種(しゅ)類(るい)
人(じん)物(ぶつ)の会(かい)話(わ)や行(こう)動(どう)を中(ちゅう)心(しん)に描(えが)いた「歴(れき)史(し)物(もの)語(がたり)」です。たくさんの記(き)録(ろく)を参(さん)考(こう)にして、りっぱな行(こう)動(どう)も、わるい行(こう)動(どう)も公(こう)平(へい)にくわしく書(か)いています。
3 長(なが)さ・構(こう)成(せい)
皆(みな)さんがいま読(よ)んでいるこのページの大(おお)きさで印(いん)刷(さつ)すると、約(やく)四百(ひゃく)ページ、三十八章(しょう)からなりたつ大(だい)長(ちょう)編(へん)歴(れき)史(し)物(もの)語(がたり)です。この本(ほん)では、その中(なか)から十編(ぺん)だけとりだして題(だい)名(めい)をつけ、みじかいお話(はなし)にまとめました。
この物(もの)語(がたり)の最(さい)初(しょ)に、世(よ)継(つぎ)と繁(しげ)樹(き)というおじいさんが登(とう)場(じょう)します。年(ねん)齢(れい)は百(ひゃく)九十歳(さい)と百(ひゃく)八十歳(さい)で、この二人(ふたり)のおじいさんが昔(むかし)の政(せい)治(じ)の話(はなし)を、そこにあつまったひとたちに話(はな)して聞(き)かせるという構(こう)成(せい)になっています。そしてその内(ない)容(よう)は、たくさんの資(し)料(りょう)を活(い)かして組(く)みたててあり、正(せい)確(かく)でいきいきした歴(れき)史(し)の事(じ)実(じつ)を伝(つた)えています。
4 成(せい)立(りつ)
平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)は全(ぜん)国(こく)の生(せい)産(さん)物(ぶつ)が京(きょう)都(と)に集(しゅう)中(ちゅう)する仕(し)組(く)みができあがり、遣(けん)唐(とう)使(し)が廃(はい)止(し)され、日(に)本(ほん)独(どく)自(じ)の宮(きゅう)廷(てい)文(ぶん)化(か)がさかえました。その代(だい)表(ひょう)が『源(げん)氏(じ)物(もの)語(がたり)』と『枕(まくらの)草(そう)子(し)』です。宮(きゅう)中(ちゅう)ではたくさんの女(じょ)性(せい)が整(せい)然(ぜん)と暮(く)らすために「しきたり」が尊(そん)重(ちょう)されました。この当(とう)時(じ)書(か)かれた『栄(えい)華(が)物(もの)語(がたり)』『今(いま)鏡(かがみ)』などたくさんの歴(れき)史(し)物(もの)語(がたり)は、宮(きゅう)廷(てい)生(せい)活(かつ)の仕(し)組(く)み、宮(きゅう)中(ちゅう)のしきたり、貴(き)族(ぞく)の人(にん)間(げん)関(かん)係(けい)などをおおくのひとに知(し)らせる役(やく)目(め)をはたしました。しかし、貴(き)族(ぞく)をほめたたえる態(たい)度(ど)はみな同(おな)じでした。そういう物(もの)語(がたり)の中(なか)で、中(ちゅう)国(ごく)の司(し)馬(ば)遷(せん)の『史(し)記(き)』という歴(れき)史(し)書(しょ)にならった骨(ほね)太(ぶと)の批(ひ)評(ひょう)精(せい)神(しん)をもった歴(れき)史(し)物(もの)語(がたり)が現(あらわ)れました。それがこの『大(おお)鏡(かがみ)』です。
5 価(か)値(ち)
藤(ふじ)原(わら)氏(し)一(いち)族(ぞく)がしだいに勢(せい)力(りょく)をましていくようす、自(じ)分(ぶん)の子(こ)どもを天(てん)皇(のう)の位(くらい)につけさせるための貴(き)族(ぞく)同(どう)士(し)の陰(いん)謀(ぼう)やかけひき、藤(ふじ)原(わらの)道(みち)長(なが)の英(えい)雄(ゆう)的(てき)な姿(すがた)などがくわしく書(か)かれています。明(めい)治(じ)・大(たい)正(しょう)・昭(しょう)和(わ)前(ぜん)期(き)には政(せい)府(ふ)が天(てん)皇(のう)制(せい)を政(せい)治(じ)の手(しゅ)段(だん)として神(しん)聖(せい)化(か)するために、この『大(おお)鏡(かがみ)』という本(ほん)をしっているのは大(だい)学(がく)の一(いち)部(ぶ)の研(けん)究(きゅう)者(しゃ)だけにしました。しかし、現(げん)在(ざい)では誰(だれ)でも自(じ)由(ゆう)に読(よ)むことができます。
6 作(さく)者(しゃ)
一(いち)番(ばん)古(ふる)い写(しゃ)本(ほん)(書(か)き写(うつ)した本(ほん))にも作(さく)者(しゃ)が誰(だれ)であるか、書(か)いてありません。宮(きゅう)中(ちゅう)の政(せい)治(じ)の秘(ひ)密(みつ)のこともくわしく書(か)いてある本(ほん)なので、誰(だれ)が書(か)いたかわかると命(いのち)の危(き)険(けん)があったのでしょう。現(げん)在(ざい)でも、多(おお)くの研(けん)究(きゅう)者(しゃ)が作(さく)者(しゃ)を追(つい)求(きゅう)していて、その手(て)がかりとしては、漢(かん)文(ぶん)調(ちょう)の文(ぶん)体(たい)であること、悪(わる)いこともはっきりと断(だん)定(てい)的(てき)に書(か)いてあること、宮(きゅう)中(ちゅう)のしきたりにくわしいことなどから、男(だん)性(せい)であることだけはみとめられています。
宇治拾遺物語(うじしゅいものがたり)
1 内(ない)容(よう)のあらまし
この『宇(う)治(じ)拾(しゅう)遺(い)物(もの)語(がたり)』には農(のう)民(みん)、お寺(てら)のお稚(ち)児(ご)さん、仏(ぶつ)像(ぞう)画(が)の絵(え)師(し)、強(ごう)盗(とう)、雀(すずめ)、坊(ぼう)さん、鹿(しか)などのいろいろな人(じん)物(ぶつ)や動(どう)物(ぶつ)が登(とう)場(じょう)して、めずらしい話(はなし)、笑(わら)い話(ばなし)、おそろしい話(はなし)などを展(てん)開(かい)します。そして、賢(かしこ)く生(い)きるためにどうしたらよいかを、仏(ぶっ)教(きょう)の立(たち)場(ば)から語(かた)っています。
2 書(しょ)物(もつ)の種(しゅ)類(るい)
『宇(う)治(じ)拾(しゅう)遺(い)物(もの)語(がたり)』は説(せつ)話(わ)を集(あつ)めた本(ほん)です。「説(せつ)話(わ)」とは、お寺(てら)の坊(ぼう)さんが信(しん)者(じゃ)に仏(ほとけ)さまの教(おし)えを守(まも)るとどれほどよいことがあるか、守(まも)らないとどれほどたいへんなことになるかを、わかりやすく語(かた)ったお話(はなし)です。坊(ぼう)さんの「お説(せっ)教(きょう)」の「たね本(ほん)」です。平(へい)安(あん)時(じ)代(だい)には仏(ぶっ)教(きょう)がさかんになって、教(きょう)育(いく)制(せい)度(ど)のまったくなかった当(とう)時(じ)の日(に)本(ほん)では、お寺(てら)で坊(ぼう)さんがおもしろおかしく語(かた)る「お説(せっ)教(きょう)」が「社(しゃ)会(かい)教(きょう)育(いく)」の大(おお)きな効(こう)果(か)をあげました。そのためたくさんの「説(せつ)話(わ)集(しゅう)」がつくられました。「説(せつ)話(わ)集(しゅう)」の最(さい)古(こ)、最(さい)大(だい)のものは『今(こん)昔(じゃく)物(もの)語(がたり)集(しゅう)』三十一巻(かん)(一一二〇年(ねん)ごろ)で、千(せん)五十九話(わ)を収(おさ)めています。
3 長(なが)さ・構(こう)成(せい)
全(ぜん)部(ぶ)で百(ひゃく)九十七話(わ)の物(もの)語(がたり)が収(おさ)められています。登(とう)場(じょう)するのは天(てん)皇(のう)、貴(き)族(ぞく)、女(じょ)流(りゅう)歌(か)人(じん)、坊(ぼう)さん、武(ぶ)士(し)、きこり、農(のう)民(みん)、強(ごう)盗(とう)のほか、雀(すずめ)・蜂(はち)・鹿(しか)などの昆(こん)虫(ちゅう)・動(どう)物(ぶつ)などさまざまです。また、中(ちゅう)国(ごく)・インドの話(はなし)、「いいつたえの話(はなし)」などがあります。
4 成(せい)立(りつ)
この本(ほん)には「序(じょ)文(ぶん)」がついていて、それによると、もともと『宇(う)治(じ)大(だい)納(な)言(ごん)物(もの)語(がたり)』(いまは消(しょう)失(しつ))があって、そのつづきとして前(まえ)の本(ほん)に入らなかった話(はなし)を拾(ひろ)い集(あつ)めてつくった本(ほん)(拾(しゅう)遺(い))だということです。時(じ)期(き)は鎌(かま)倉(くら)時(じ)代(だい)初(はじ)めの一二二一年(ねん)ごろで、当(とう)時(じ)たくさんつくられた「説(せつ)話(わ)集(しゅう)」の一(ひと)つです。『今(こん)昔(じゃく)物(もの)語(がたり)』の中(なか)の話(はなし)と同(おな)じような話(はなし)がいくつか載(の)っています。
5 価(か)値(ち)
この物(もの)語(がたり)集(しゅう)は、めずらしい話(はなし)、おどろくような話(はなし)をあつめただけという他(ほか)の物(もの)語(がたり)集(しゅう)とちがって、人(にん)間(げん)の行(こう)動(どう)や心(こころ)のうごきについての観(かん)察(さつ)がわかりやすい言(こと)葉(ば)で、するどく、深(ふか)く、くわしく書(か)かれている、りっぱな文(ぶん)章(しょう)が特(とく)徴(ちょう)です。これは漢(かん)字(じ)とかたかなで漢(かん)文(ぶん)調(ちょう)で書(か)かれた『今(こん)昔(じゃく)物(もの)語(がたり)』とちがって、和(わ)歌(か)をもとにして、ひらがなで書(か)かれた日(に)本(ほん)語(ご)の文(ぶん)章(しょう)が、この時(じ)代(だい)に完(かん)成(せい)したことを示(しめ)しています。話(はなし)の語(かた)りかたも、成(せい)功(こう)した話(はなし)、失(しっ)敗(ぱい)した話(はなし)、奇(き)妙(みょう)な話(はなし)、笑(わら)い話(ばなし)、皮(ひ)肉(にく)な話(はなし)など多(た)様(よう)で、『今(こん)昔(じゃく)物(もの)語(がたり)』のように仏(ぶっ)教(きょう)のありがたさを説(せつ)明(めい)するだけの説(せつ)話(わ)とは、ちがっています。
6 作(さく)者(しゃ)
一人(ひとり)でまとめたか、何(なん)人(にん)かでまとめたかもわかっていません。ただ、作(さく)者(しゃ)は資(し)料(りょう)をたいせつにしている、仏(ぶっ)教(きょう)関(かん)係(けい)の人(じん)物(ぶつ)である、などがわかっています。
-
 明治図書
明治図書