- 序文
- 国立国語研究所長 /甲斐 睦朗
- 緒言
- 序章 語彙力の発達と国語科学習基本語彙研究
- 1 語彙力の発達研究の課題
- 1.1 言語能力と語彙力
- 1.2 従来の語彙力研究と語彙力の構造
- 1.3 語彙力研究の課題
- 2 学習基本語彙研究の歴史と構想
- 2.1 基本語彙研究から学習基本語彙選定へ
- 2.2 文献の語彙調査
- 2.3 学習者の語彙の調査
- 2.4 生活基本語彙の選定
- 2.5 教育基本語彙の選定
- 3 国語科学習基本語彙選定の意義と方法
- 3.1 国語科学習基本語彙選定の発想
- 3.2 初期の「国語科学習基本語彙」の研究
- 3.3 教師のための「国語科学習基本語彙」としての専門用語
- 3.4 国語科学習基本語彙選定のための課題
- 第1章 児童・生徒の語彙発達調査
- 1 児童作文の表現語彙の実態調査と考察
- 1.1 調査の目的と方法
- 1.1.1 調査の目的と方法
- 1.1.2 調査の対象
- 1.2 調査結果と考察
- 1.2.1 品詞的観点から見た考察
- 1.2.1.1 語彙量の学年別発達傾向
- 1.2.1.2 品詞構成比
- 1.2.1.3 使用度数分布
- 1.2.2 拡充的観点から見た考察
- 1.2.2.1 初出語
- 1.2.2.2 学年間にわたる共出現語
- 1.2.3 共出現語彙から見た考察
- 1.2.3.1 共出現語彙の量的構造
- 1.2.3.2 共出現語彙の特質
- 1.3 児童作文の表現語彙表
- 1.3.1 記事文の表現語彙表
- 1.3.1.1 体の類
- 1.3.1.2 用の類
- 1.3.1.3 相の類
- 1.3.1.4 その他の類
- 1.3.2 叙事文の表現語彙表
- 1.3.2.1 体の類
- 1.3.2.2 用の類
- 1.3.2.3 相の類
- 1.3.2.4 その他の類
- 2 語彙力の基底と習得過程
- 2.1 表現語彙考察の前提となる仮説
- 2.2 語彙力の基底
- 2.3 語彙力の習得過程
- 3 定義法と内省法による語彙力調査
- 3.1 国語科学習基本語彙試案の語彙力調査
- 3.2 調査結果の考察
- 第2章 教科書の語彙系統
- 1 物語文教材の語彙系統
- 1.1 物語文教材の語彙の研究方法
- 1.2 物語文教材の語彙の調査結果と考察
- 1.2.1 語彙量の発達
- 1.2.2 物語文教材の基幹語彙
- 1.2.3 課題の総括
- 2 説明文教材の語彙系統
- 2.1 説明文の語彙の深化と拡充
- 2.2 説明文教材の基幹語彙
- 2.3 基幹語彙の有効性
- 3 国語科学習用語の語彙系統
- 3.1 国語科学習用語の系統
- 3.2 言語知識の学習用語の系統
- 第3章 国語科学習基本語彙の選定と系統化
- 1 選定と系統化のための前提
- 1.1 選定の意義と根拠
- 1.2 選定と系統化のための参考文献
- 1.3 選定と系統化のための細則
- 2 国語科学習基本語彙一覧表
- 結章 研究の成果と課題
- 1 語彙力の発達研究と語彙指導の体系的関連
- 1.1 語彙力の発達研究と国語科学習基本語彙選定
- 1.2 国語科学習基本語彙と語彙指導の体系化
- 1.2.1 語彙指導の目的
- 1.2.2 語彙の性質から見た語彙指導の内容選定と系統化
- 1.2.3 語彙指導の実際的方法
- 1.2.4 語彙の学習場面及び教材に即した語彙指導の内容と方法
- 2 語彙力の育成を図る語彙指導の方法
- 2.1 言語事項としての語彙指導
- 2.1.1 言語事項の改革課題と語彙指導
- 2.1.2 言語事項の教材研究と語彙指導
- 2.2 文字・表記指導としての語彙指導
- 2.2.1 文字・表記指導と語彙指導
- 2.2.2 語彙指導としての漢字指導が意味するもの
- 2.3 日常の語彙指導
- 2.3.1 ボイストレーニングにおける語彙指導
- 2.3.2 言葉遊びの特質と意義
- 2.3.3 言葉遊びの内容と方法
- 2.4 取り立て単元における語彙指導
- 2.5 理解単元の語彙指導
- 2.5.1 理解単元の語彙指導の課題
- 2.5.2 語彙の構造体としての作品へのアプローチ
- 2.5.3 読書行為の成立を図る語彙指導
- 2.6 表現単元における語彙指導
- 2.6.1 調査活動の基底となる語彙指導
- 2.6.2 人物を描く基底となる語彙指導
- 2.7 総合的な単元における語彙指導
- 3 学力観の転換と語彙指導の改革
- 3.1 新学力観に即応する語彙指導の開発
- 3.2 新しい時代を切り拓く語彙力観と指導
- 3.2.1 人間形成力と語彙力
- 3.2.2 生活力と語彙力
- 3.2.3 メディアリテラシーと語彙力
- 3.2.4 コンピューターリテラシーと語彙力
- 3.2.5 言語活動力と語彙力
- 3.2.6 エディターシップと語彙力
- 3.2.7 思考力と語彙力
- 3.2.8 創造力と語彙力
- 3.2.9 コミュニケーション力と語彙力
- 3.3 人間創造としての語彙力の育成
- 初出関連文献一覧
- 跋
- 全国大学国語教育学会理事長 /浜本 純逸
- 終わりに
序文
国立国語研究所長 /甲斐 睦朗
井上一郎君が,いよいよ大著『語彙力の発達とその育成―国語科学習基本語彙選定の視座から―』を刊行する。日本語研究にとっても国語教育界にとっても,また,長年,その刊行を心待ちしてきた者にとっても喜ばしいことである。
その書名―主題及び副題―に,井上一郎君の長年にわたる国語教育研究への熱情とその道程がよく表されている。私は,「語彙力の発達」「語彙力の育成」「学習基本語彙の選定」の各調査研究及びその3調査研究の組み立てに大きな意義を見いだしている。
井上一郎君の国語教育研究について,私なりに知り得ていることを概括すると,いかにも幅広い視野と周到な方法を具備し,たゆまぬ努力に支えられている。広い視野をもつために,研究の中核が文学教育研究であると誤解する人もいるかもしれないが,彼の研究の中核には言語教育がある。それは,人間教育,国語教育,言語教育という3つの層でとらえることができる。日本人の言語生活を豊かに高めていくには,何よりも日本人の言語生活を支える言語能力の実態を言語発達の面で,幼児から成人まで調査しなければならない。そして,その言語能力の中心に語彙能力をすえている。
井上一郎君は,学部及び大学院で,国語教育に役立つ国語研究を究め,研究に専念できる大学の職に就くやすぐさま小学生の作文語彙の調査に乗り出した。その優れた成果が児童の使用語彙の調査を丹念に行った「作文の語彙」(1984年)である。児童の語彙の発達を使用語彙の面で調査するには,記事的文章に使用される語彙と叙事的文章に使用される語彙の両方の調査が必要だと考えて,同じ児童に「べんきょう」「日曜日のできごと」という2種の作文を書かせて,そこに使用されている語彙の調査に取り組んだのである。この発想は,その後,「『物語文教材』と『説明文教材』」というように教科書の語彙系統の根本にまで展開している。
この作文使用語彙の調査は,誰でも容易に思いつくような,そして誰かがすでに行っているような,まことに身近な語彙調査であるが,実際に取り組んで学界に成果を提出したのは井上一郎君が我が国では最初である。なお,前掲論文「作文の語彙」に関しては国立国語研究所報告116『日本語基本語彙―文献解題と研究』(明治書院 平成12年7月刊)が取り上げて高く評価している。
少し古い話であるが,井上一郎君は,学部時代から国語教育研究に目覚めた学生であった。私は,その年の学部の国語科教育の授業では前期に垣内松三氏の『国語の力』の講読を行い,後期は教材研究及びそれに基づく指導案作成の演習を行ったが,その授業に積極的に参加した熱心な学生の一人が井上一郎君であった。彼は,学生のころから,たとえ文学教材の読み方の授業であっても言語的な見方,乃至は論理的な見方でアプローチする姿勢を有していた。学習者の言語能力の育成を何よりも大切にしていた。その点で,私にはたいへん好ましい学生であった。
さて,井上一郎君がおよそ20年前に執筆した研究論文「学習基本語彙の構想」は,すでに国立国語研究所報告 78『日本語教育のための基本語彙調査』(秀英出版 1984年刊)の「参考文献」に掲載されている。広い視野と周到な構想をもち,学習基本語彙に正面から取り組んでいる。彼は,その後も熱心に語彙指導の調査研究に取り組み,幾編もの論文を発表してきたが,上掲の論文がその後20年間の調査研究を理論的に支えてきたのである。
私は,前掲の国立国語研究所報告116『日本語基本語彙―文献解題と研究』の中で,井上一郎君の最近執筆した論文「国語科学習基本語彙と語彙指導」を取り上げて,「この語彙表は,上に紹介した『構成』に明らかなように研究書と同様の骨太の構成になっているが,全体がわずか13ページの論文であるので意が尽くされていない。井上一郎氏には,これまでの調査研究を集大成した本格的な研究書の刊行が期待される。」云々と述べた。語彙指導は語句指導と同義ではない。語句指導をどれだけ積み重ねても語彙指導は育たない。語彙指導という構想がまずは必要である。彼は,その語彙という概念を言語発達の中に求めると同時に語彙の体系の中に求めようとしている。
井上一郎君は,そういう自らの宿題を果たすべく20数年間に及ぶ調査研究の成果を1冊の研究書にまとめ上げたのである。本書が,よく読まれて国語教育の中に語彙指導が正当に定着することを期待するものである。
2001年2月














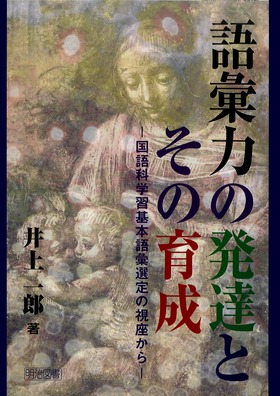


コメント一覧へ