- はじめに
- 学級経営・授業づくり
- 1 トップランナーを育てる
- 2 真面目最優先
- 3 好き嫌いで動く
- 4 挨拶ができるのは、当たり前じゃない
- 5 歌が歌えるクラスはいいクラス、掃除ができるクラスはいいクラス
- 6 食べるだけなら、せめてきれいに片づける
- 7 安全・安心をつくるのが先生の仕事、楽しくできるかは君たち次第
- 8 マイナスなことがなければ、平和
- 9 不得意な人が、有難い
- 10 宿題は、残業命令
- 11 天国がいいですか? 地獄がいいですか?
- 12 ルール設定に覚悟をもて
- 13 自分でマルつけをするからこそ生きる力が身につく
- 14 ノートに写すな、ノートをとれ
- 15 学びの主役は子ども、授業の主役は教師
- 16 「静かにして」が一番うるさい
- 17 罰もご褒美も不要
- 18 治療より予防に力を入れる
- 19 ミスする前提で心構えをする
- 20 教育には、万能な魔法など存在しない
- 生徒指導・トラブル対応
- 21 多分ないと思うけど、もしかして、万が一、しちゃった「かも」しれない?
- 22 気になる言動には「大丈夫?」
- 23 何が嫌だった? どうしたい? どうしてほしい?
- 24 好き嫌いはあっていい、誰とでも協力できる人になる
- 25 100回裏切られるつもりで「信じているよ」
- 26 親こそ最高の情報源、次は子どもの周りの友達
- 27 トラブルが起きる二大場面―休み時間と登下校時
- 28 丸くおさめるのと成長させるのとは違う
- 29 叱られるのが苦手な子どもは、愛着の問題を疑ってみる
- 30 「怒らない」「けんかしない」は難しい
- 31 いじめは「正しさ」の暴力から生まれる
- 32 いじめは「仲良し」から起きる
- 33 無責任な優しさは冷たさに似ている
- 34 悪意より善意が恐ろしい
- 35 悪口郵便屋は最悪
- 36 「正義」を疑う
- 37 けんかは同レベル同士でしか起きない、少しだけ上へ
- 38 「様子を見る」の言い訳が、いじめを悪化させる
- 39 どんな信念をもってもいい、人にそれを強いることがなければ…
- 40 両極とその間を認める
- 子ども・保護者との人間関係
- 41 大変な子どもや保護者こそが、神様
- 42 少しでも非がある点については、すぐに謝る
- 43 「ごめんなさい」と「受け入れること」は別
- 44 「ありがとう」と「ごめんなさい」は親戚
- 45 恩恵は、権利に変わる
- 46 不親切である勇気をもつ
- 47 保護者はお化けじゃない―怖さの正体を見抜く
- 48 保護者は敵ではない―ともに育てる仲間として向き合う
- 49 その行動には、未来の理由がある―目的論的に不登校を捉える
- 50 学校に行くことだけが、ゴールではない―家庭の文脈に寄り添う支援
- 51 朝を他人に任せる者は、人生を他人に委ねる―自ら目覚める力が、自立の第一歩
- 52 遅刻もまた、学びの入り口になる―「起こさない勇気」が育てる自立心
- 53 見られているのは有難い
- 54 見られているから、成長する
- 55 求めるほど、求められる
- 56 語り合っているのに、見えている世界が違う
- 57 踏み込みすぎずに、支え合う
- 58 要求は、共生への入り口に変えられる
- 59 子どもではなく、大人に疲れている
- 60 「言うべきことは言う」が優しさ
- 職場の人間関係・立ち振る舞い
- 61 異動1年目が一番大変、だからこそ来年は楽になる
- 62 スーパーティーチャーより、笑顔、ごみ捨て、電話に出る
- 63 当たり前を続ける人が、信頼をつくる
- 64 管理職は偉くて当たり前、ベテランはできて当たり前―だから、頼っていい
- 65 若手は「元気」「一生懸命」だけで百点満点
- 66 月曜の朝は「ハッピーマンデーですね!」と言い切る
- 67 「全部やる教師」ではなく、「助けを求められる教師」へ
- 68 「子どもファースト」を実現するなら、自分一人で抱え込まない
- 69 支えに気づけば、感謝はあふれ出す
- 70 有難さは、礼儀で示さねば伝わらない
- 71 理不尽が人を強くする
- 72 理不尽な人は、後で有難い
- 73 成長が止まるのは「自分はできる」と思った瞬間から
- 74 教師とは、学び続ける人
- 75 威張るが負け
- 76 「お互い様」が、最強のチームをつくる
- 77 「揃える」から「スタンダード」へ
- 78 スタンダードは、強制ではなく安心の拠り所
- 79 言うべきを言い、黙るべきを黙る
- 生き方・考え方
- 80 自分の荷物を自分で背負うことから、自立は始まる
- 81 善意ほど、厄介なものはない
- 82 自立は問いかけから始まる
- 83 期待という名の圧力
- 84 信じることが、挑戦を生む
- 85 正反対を、バランスよく
- 86 「ちょうどよさ」を探すのが教師の仕事
- 87 任せるには覚悟がいる
- 88 信じて任せて、責任を背負う
- 89 自由とは、与えられるものでなく、自ら育むもの
- 90 制限の中にこそ、真の自由が宿る
- 91 出会いは、準備した人にだけ訪れる
- 92 他に求めるより、自身を磨く
- 93 「沈黙は金」とは限らない
- 94 「いい人」より「信じて頼れる人」
- 95 口喧嘩に勝ったら、負け
- 96 先手必勝の「敗北宣言」
- 97 わかっているのに、救えない
- 98 教師の仕事は、不完全だけど素晴らしい
- 99 観を磨く
- 100 意味が見つかるまで、意味を与え続ける
- おわりに
はじめに
教育とは何か―この問いに、唯一の答えを見出すことは容易ではありません。多様な価値観や考え方が交錯する現代社会では、教育の意味や目的も、時代や地域、環境によって異なる形をとります。しかし、どんな時代においても、教師という存在が子どもたちの成長において重要な役割を果たしていることは変わりありません。そして教師自身もまた、成長を続けることが求められる職業です。
本書『正しい思考法』は、これから教師を目指す方だけではなく、現在教育現場で奮闘しているすべての教師のために書かれたものです。日々、子どもたちや保護者、同僚との関係の中で直面する多くの課題に対し、どのように思考し、行動すればよいのか―そのヒントを提供することを目的としています。
私自身、長年にわたり教師として現場で多くの子どもたちと関わってきました。その経験の中で実感したのは、教育という営みが教師自身の人間力や思考力に大きく依存しているということです。教科知識を教えるだけでは、教育は成立しません。子どもたちの多様な個性に向き合い、彼らが抱える問題に寄り添い、未来をともに考える―これが教師の本来の役割です。しかしながら、その過程で私たち教師が戸惑いや苦悩を抱える場面は少なくありません。
本書では、「教師の信念」を5つのテーマに分けて整理し、具体的なエピソードやアドバイスを交えながら解説しています。中でも重要なのは、自己反省と自己成長の姿勢です。「大変な子どもや保護者こそが、神様」という考えや、「少しでも非があれば、謝る」という基本的なスタンスは、教師だけでなく、広く人間関係を築く上でも普遍的に役立つものです。
また、「謝意」を教えることで、感謝と謝罪の共通点を子どもたちに伝える大切さや、教育現場でもつべき毅然とした態度についても触れています。教師として、どのように子どもたちと接するか、保護者とどのような関係を築くべきか、そして同僚との協力をいかに深めるか―これらすべての課題に対して、少しでも参考となる考え方を提示したいと思います。
教育現場における課題は、決して簡単ではありません。一人ひとりの教師が、自分自身の課題として受け止め、それを乗り越える努力を積み重ねることでしか解決できないものもあります。しかし、それだからこそ教師という仕事には無限の可能性が広がっています。子どもたちの成長を支えながら、同時に自分自身も成長できる―これこそが、教師という職業の最大の魅力ではないでしょうか。
本書が、教師としての新しい一歩を踏み出すきっかけとなり、日々の教育現場での実践に少しでも役立つことを願っています。そして何より、教師自身が楽しみながら成長し、子どもたちとともに素晴らしい未来を築いていく手助けとなれば幸いです。
著者 /松尾 英明














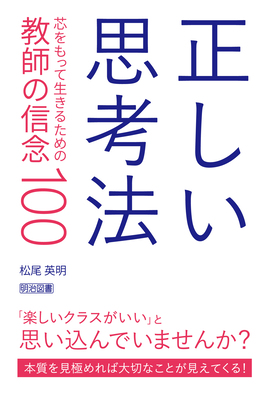
 PDF
PDF


この本には、松尾先生の「教師の信念」が全部で100個掲載され、教師が日々直面する多くの課題に対し、どのように思考し、行動すればよいのか、そのヒントを提供してくれています。
その中で印象に残るものをご紹介しますと、例えば、「好き嫌いで動く」です。先生が好き嫌いで動いていいんですか⁉と一瞬、ぎょっとしましたが、松尾先生は「好き嫌いこそが、教師が幸せに働くための行動原理なのです」と断言されています。なぜだと思いますか? 気になる方は、ぜひこの本を読んでみてくださいね。それから、「スタンダードは、強制ではなく安心の拠り所」も、「よくぞ書いてくださいました」と申し上げたい内容です。
このような感じで項目ごとに、「その通り」「なるほど」と納得したり、先生方はこんな風に考えているのかと知ったり、いろんな感情が湧いてきます。私は幸運なことに松尾先生の授業をかつて拝見したことがありますので、子供たちに語りかけるときの松尾先生の口調や表情などを思い出しながら、読ませていただきました。そして、あのときの学級のベースには、こんな考え方があったのかと、今更ながら気付くことが多かったです。ですから、「早く読もう」とは思いませんでした。さっと読んでしまうのはもったいない内容だと思ったので、一つひとつの項目を、咀嚼しながらじっくり読みました。
おそらくベテランの先生方は、「そうそう。そうなんだよ」と納得することが多いかもしれません。ところどころに学級経営のポイントがちりばめられていますので、若い先生方にはとても勉強になりそうです。
世間のイメージとして、学校の先生といえば「正義であり、常に正しい答えをもっている」と思われがちです。もしも保護者の方がこの本を手にとったら、「先生たちは日々悩みながら、ここまで考えて子供に対応しているのか」と気付くのではないでしょうか。
教育界では長い間、「出る杭は打たれる」と言われてきました。しかし、松尾先生は今や、出過ぎた杭!?になっておられるような気も……。これからも教育界の常識を突き破って進んでいく姿を拝見したいと、一人のファンとして期待している次第です。
コメント一覧へ