- はじめに 「荒れ」を生み出さない学校づくり
- 第1章 疲弊する学級担任
- 苦い記憶
- 「学級担任」から「担任外」へ
- 大暴れしたA君
- 落ち着いたら指導終了?
- 担任だけでは解決できない問題
- 私を悩ませた問題行動(3ボウ)
- 私を悩ませた問題行動(脱走)
- 私を悩ませた問題行動(不登校対応)
- 疲弊する学級担任
- 第2章 荒れをモデル化する
- 問題行動が溶けてなくなるクラスづくり
- 気づきをくれた理科の授業
- 溶ける子・溶けない子
- 「ビーカー」「水」「火」
- A君はなぜ荒れがおさまらなかったのか?
- 担任が教室を離れることの危険性
- 生徒指導主任(担任外)と協力せよ
- 子どもたちのタイプを見抜く
- 荒れを抑える授業
- 食塩を溶かす授業とは?
- 全校を見渡す
- 第3章 生徒指導主任の役割と心得を知る
- 生徒指導主任の役割
- 生徒指導主任 2つの役割
- 生徒指導主任の役割 (1)指導の方針を指し示す
- 生徒指導主任の役割 (2)場を整える
- 生徒指導主任 3つの心得
- 第4章 荒れへの基本対応を共有する
- あの子はなぜ暴れるのか?
- 暴れればヒーローになれる
- 戦略的パニック
- 「暴れればうまくいく」という誤学習
- 荒れた子の心を解きほぐすには?
- 心のバケツ大作戦
- 心のバケツを上向きにする場所
- 効果的な「クールダウンルーム(CDR)」をつくるには?
- 物を置かない
- 窓がない部屋
- 時計をはずす
- 廊下から見えないように目隠しをする
- ドアの前に線を引き、立ち入り禁止エリアをつくる
- 掲示物は高い場所へ貼る
- 目の前の子どもの姿を見ながら
- 暴れる子の「心のバケツ」を上向きにするには?
- CDRはどうして荒れた子に有効なのか?
- クールダウンルーム(CDR)での指導手順
- 「誤学習」から解き放つ
- 「成長の階段」に照らし合わせて声をかける
- 最下段「イライラしているとき」
- 危険が伴う可能性があるとき
- 2段目「立ち歩く」
- 3段目「すわる」
- 4段目「知らせる」
- 最上段「いっしょにかんがえる」
- 「いっしょにかんがえる」を終えたら
- ロールプレイで練習する
- 味方として部屋を出る
- 指導は短くなっていく
- CDRでの指導を長引かせてしまうケース
- 会話をしてしまう
- 物をさわらせてしまう
- ねむらせてしまう
- CDR指導の際のポイント
- CDRに入る教員の人数
- トイレ・水飲み・昼食の対応
- 目を合わせないで観察をする方法
- CDRで大暴れするときの対応
- CDRでの指導が長引いた場合の対応
- 行った問題行動がそこまで悪質ではない場合(妨害・逃走など)
- 行った問題行動が悪質な場合(暴力行為・傷害・いじめなど)
- CDR指導事例
- 保護者の協力が得られない場合
- 文科省の通知を熟知する
- 第5章 荒れのレベルを見極め連携する
- 担任と連携するために押さえておきたいこと
- 担任と連携を図るには?
- 〈個人の荒れレベル〉を見極める
- 段階が下がらないように
- レベルに応じた基本対応を定める
- 有言実行をする
- 「生徒指導主任を呼ぶよ」という指導は「脅し」なのか?
- 〈個人の荒れレベル3〉の基本対応
- 「最後の1回」に応じられない場合
- 対話のゴールをぶらさない
- 心が落ち着くまで待つ
- 「落ち着くまで待つよ」と伝えると落ち着かなくなる場合
- 目指すべき場所は〈担任との対話〉
- 〈個人の荒れレベル4〉の基本対応
- CDRへ連れていく際の注意点
- 〈個人の荒れレベル5〉の基本対応
- 保護者対応における連携
- 保護者対応においても連携を
- 連絡前にすり合わせをして共通認識をもつ
- 生徒指導主任が話しても伝わらない場合は
- 担任と連携する際に気をつけたいこと
- 担任を支える
- 担任の先生の状況を見極める
- 担任は「点」にとらわれる
- 担任が「想いを伝え抜く場」をつくる
- 「良い先生」って?
- 私の感じた違和感
- 人の心が病んでいく理由
- 「感情」と「理性」のバランスをとる
- おわりに
はじめに
「荒れ」を生み出さない学校づくり
近年、学校での暴力行為が右肩あがりに増加しています。特に小学校での増加傾向はすさまじく、平成25年度は1万896件だった暴力行為が、令和4年には6万1455件にまで増えています。その数はなんと10年で5倍以上です。
ここまで暴力行為が増えた背景は複雑で、いろいろな要因が絡まり合っています。
コロナ禍の影響、スマホの普及による生活習慣の乱れ、発達障害と診断される子の増加、教員不足の問題など、原因をあげればキリがありません。
しかし、原因を並べて、嘆いていても何も始まりません。私たちは、今あるリソースで、今できることを目の前の子どもたちに施していかなければならないのです。
そのために大切なことは「今、学校で奮闘している先生を疲弊させないこと」です。
教室で暴れ回る子の相手をしながら、授業を進めなければならない。
周りの保護者からは「先生、もっとしっかりと指導してください」と板挟みになる。
そんな状況で担任の先生が心身共に健康に毎日を過ごすことなどできないでしょう。
これからの時代、学校の秩序を維持し、子どもたちの成長をきちんと保証していくために「生徒指導主任」の存在が欠かせません。問題行動が起きても、その子にきちんと向き合い、対話して教室へ戻していける。そんな人材がそれぞれの学校に必要なのです。
担任の先生の指導が通らない。
そこに生徒指導主任の先生が助けに来る。
2人の先生が指導をしても、問題行動がおさまらない…。
このような状況がまかり通ってしまったならば、私たち教師の信頼は地に落ちます。
「先生が何を言ってもあの子は言うことを聞かない」「先生に相談してもしかたがない」「先生は頼りにならない」
真面目に取り組み、一生懸命学ぼうとしている子どもたちにそう思われてしまったならば、学級の荒れはますますひどくなっていくでしょう。学級の中には一生懸命にかしこくなろうと努力している子どもたちが必ずいます。そういう子どもたちに見放されてしまったときこそが、本当の終わりなのではないでしょうか。
「みんなの学びを守るために、先生が全力で支えるからね」
と子どもたちに胸をはって伝えられる存在が今の学校現場には必要なのです。
しかし、次々と起こる問題を一手に引き受けるからには、生徒指導主任の先生にもある程度の戦略が必要になります。問題行動を起こす子どもたちに押し切られてしまうような指導は避けなければなりません。引き受けるからには必ず目の前の子を成長させて教室へ戻さないといけないのです。そういう難しい役割が「生徒指導主任」の先生に求められています。
「今いる先生を疲弊させないこと」と同じぐらい大切なこと。それは「新たな荒れを生み出さない」ということです。問題行動を起こす子は初めからこんなに荒れていたのでしょうか? そんなことはありません。初めはみんなと同じように、一生懸命取り組んでいたはずです。しかし、ほんの小さな出来事から自信をなくし、次第に自暴自棄に陥っていったのでしょう。そんな毎日の中で「自分なんてどうなっても構わない」とやけになり、自分を見失っていったのです。
このような状態に陥る前に、我々、教師にできることはなかったのでしょうか?
荒れがエスカレートすることを防いでいくためには「適切な言葉かけ」「自信を育む授業の展開工夫」「対話へ導くための役割分担」などについての理解を深めていく必要があります。また、今までの学校の在り方を柔軟に変えていく姿勢も必要です。
学校は今激動の時代に入っています。この時代の舵取りをするのは「生徒指導主任」という役割を担う先生だと私は考えています。生徒指導主任がどれだけの覚悟をもって学校を支えていくのか? それが試される時代です。本書がその覚悟を支える手助けになることを願っています。
/古田 直之














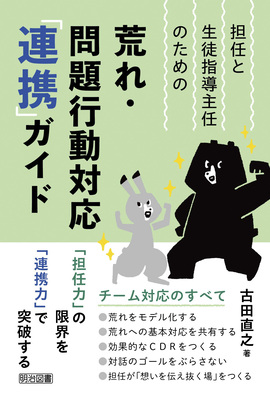
 PDF
PDF


この本には、当方の子供の通っていた小学校や教育委員会が「足りていなかったもの」が全部ありました。
古田先生の「逃がす転校」じゃなく、「向き合い続ける教育」の姿勢に、私は救われました。
書籍を出してくださりありがとうございます。