- はじめに
- 第1章 知的障害・発達障害のある子への自立活動の指導ポイント
- 01 「個別の指導計画」の作成
- 02 実態把握と指導目標,指導内容の設定
- 03 自立活動の指導の工夫
- 第2章 知的障害・発達障害のある子への自立活動の指導アイデア
- 1 健康の保持
- 01 身だしなみをチェックしよう
- 02 食べられるものを増やそう
- 03 時間内に着替えよう
- 04 自分で着替えよう
- 05 身だしなみについて考えよう
- 06 自分や友達の好きなものを知ろう
- 07 こんなときどうする? 〜苦手な音〜
- 08 踏み台運動をやってみよう
- 09 フープなわとびをやってみよう
- 10 体幹トレーニングをやってみよう
- 11 めざせ○○! 体重を記録しよう
- 2 心理的な安定
- 12 リラックスの練習
- 13 タイマーを使って待つ練習
- 14 スケジュールで活動を切り替えよう
- 15 いつもと違っても大丈夫 〜儀式的行事のスケジュール〜
- 16 外出先での見通しをもとう 〜校外学習ファイル〜
- 17 はなまるの行動はどっち?
- 18 ○回したら終わり 〜回数ボード〜
- 19 遊びのレパートリーを広げよう 〜めくり式活動スケジュール〜
- 20 自分に合ったメモの取り方を知ろう
- 21 チャレンジ日記でやる気UP
- 3 人間関係の形成
- 22 わにわにゲームで遊ぼう
- 23 よく見て一緒にボールを落とそう
- 24 動きを合わせてボールを運ぼう
- 25 相手の気持ちを考えてみよう
- 26 この顔はどんな気持ち?
- 27 自分で課題に取り組もう 〜ワークシステム〜
- 28 忘れ物を減らす工夫を考えよう
- 29 順番に遊ぼう 〜順番ボード〜
- 30 かわりばんこで遊ぼう
- 4 環境の把握
- 31 触って形を当てよう
- 32 力を調節して運ぼう
- 33 散髪練習をやってみよう
- 34 サーキット運動でボディイメージUP
- 35 粘土を使って平仮名を作ろう 〜多感覚を使った文字学習〜
- 36 棒を使って形を作ろう
- 37 ぶつからないように書いてみよう
- 38 大きさの見当をつけて切ってみよう
- 39 指示書を見て塗ってみよう 〜モザイクぬりえ〜
- 40 お話の順番を考えよう 〜お話絵カード〜
- 41 前後,左右の指示を理解しよう
- 5 身体の動き
- 42 指先を使って入れよう
- 43 ふたを回してみよう
- 44 両手を使ってペグさしをしよう
- 45 両手を使って巾着袋に入れよう
- 46 両手を使って洗濯ばさみではさもう
- 47 お箸でつまむ練習をしよう
- 48 よく見て線を消してみよう 〜なぞり消し迷路〜
- 49 端をピタッと合わせてたたもう
- 50 よく見てクリップを取り出そう
- 51 お菓子釣りゲームをしよう
- 52 手を伸ばして虫を捕ろう 〜虫捕りゲーム〜
- 53 背中のかごに入れてみよう 〜魚釣りゲーム〜
- 54 転がるボールをキャッチしよう
- 6 コミュニケーション
- 55 要求を伝えよう 〜コミュニケーションカード〜
- 56 やりとりしてボウリングをしよう
- 57 指令文を読んでやってみよう
- 58 よく聞いてやってみよう 〜ツイスターゲーム〜
- 59 要求を詳しく伝えよう 〜穴埋め式コミュニケーションカード〜
- 60 スリーヒントクイズを作ろう
- 61 タブレット端末で伝えよう
- 62 困ったときは援助を求めよう
- 資料
- おわりに
はじめに
本書の目的は,教材・指導アイデアを通して知的障害や発達障害のある子どもへの自立活動の指導について実践的な情報を届けることである。
自立活動は,障害によって生じる生活や学習上の様々な困難さを改善・克服するために,国語や算数等の教科とは別に設定される特別な指導領域である。特別支援学校のみならず,特別支援学級や通級による指導において特別の教育課程を編成する場合に,その内容を取り入れることや参考に指導することが規定されている。特別支援教育の場が広がり,対象者が増加している現状を踏まえると,自立活動を適切に指導できる教員の育成は喫緊の課題である。
知的障害を対象とする特別支援学校の教育課程では,独自に各教科の内容が設定されており,自立活動の内容と重なる部分が多い。また,知的障害の学習特性を踏まえると,各教科や領域の内容を合わせて生活場面に即して指導するのが効果的であることから,従前より「日常生活の指導」「生活単元学習」等の指導形態で自立活動を指導することが多かった。そのため,自立活動の教育課程上の位置付けやねらいが曖昧になりやすいことが指摘されている(大井ら,2020)。2018年告示の「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編(幼稚部・小学部・中学部)」(以下,学習指導要領解説)に,実態把握から指導目標,指導内容を設定するまでのプロセス(流れ図)が例示されたことを契機に,知的障害を対象とする特別支援学校においても「流れ図」を活用した研究実践や職員研修が増加してきている(石川ら,2023)。
しかし,「流れ図」の活用は,障害特性や発達段階等の幅広い知識と経験を要するため,「実態把握が難しい」「具体的な指導のイメージが湧かない」等,授業づくりの難しさを指摘する現場の声も多い。また,学習指導要領解説には具体的な教材や指導方法が記されていないため,日々の授業実践に活用するには情報が十分ではないと考える。
本書では,筆者がこれまで知的障害特別支援学校小学部を中心に実践(一部,通級指導教室での実践を含む)してきた自立活動の教材・指導アイデアを62例紹介している。教材・指導アイデアは,自立活動の6区分27項目に対応させ,どのような実態の子どもに,どのようなねらいで取り組めばよいかの目安を示している。すぐに授業に生かせるよう,教材や活動の写真とともに必要な準備物や教材の作成方法を紹介し,一部の教材はデータをダウンロードして使用できるようにしている。教材・指導アイデアを参考に目の前の子どもに合うよう調整して実践し,うまくいかなければ改善するというプロセスを大切にしてオーダーメイドの指導につなげてほしい。
さて,「困難さを改善・克服する」と聞くと「できないことをできるように」「マイナスからゼロにする」指導を思い浮かべるかもしれない。かんしゃく等の問題行動が自立活動の指導によって改善されることは望ましいが,それにとどまらず,子どもの生活を豊かにすることを目指したい。そのためには,子どもの主体的な取組の実現が鍵となる。教師側のニーズを重視した受け身的な授業ではなく,子どもの「やってみたい」「楽しそう」「もっとやりたい」を引き出す授業が求められている。例えば,目と手の協応動作が苦手な子どもが,夢中でボールを穴に入れて遊ぶことで手元を注視できるようになり,余暇が広がるような授業である。本書の教材・指導アイデアには,子どもの「やってみたい」を引き出す工夫をちりばめている。子どもたちが活動に夢中になって楽しむ中で自然と目標が達成できるよう,裏では教師が個々の目標(ねらい)をしっかりともって子どもに関わる。このような授業の実現に,教材・指導アイデアを活用していただけると幸いである。
著者 /滝澤 健
-
 明治図書
明治図書- 自立活動の事例が紹介されていて,活用しやすい。6区分27項目で分けられているため,子供の実態に応じた活用が図られる。2025/8/1850代・小学校教員
- Instagramも合わせて拝見しています。2025/8/1550代・小学校勤務
- 自立活動の項目ごとに、子どもの実態やその活動のねらいが明記されていて使いやすいです。2024/6/830代・小学校教員














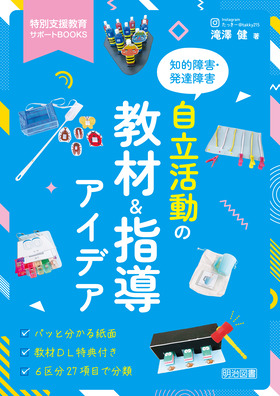
 PDF
PDF
 をクリックするとダウンロードが始まります。
をクリックするとダウンロードが始まります。
