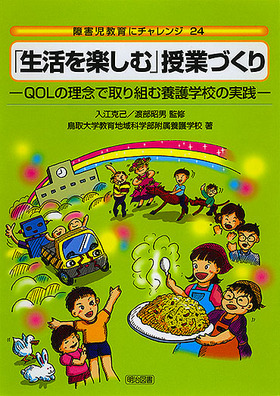- �����ɓ�������
- �w�Z�Љ�
- ��P�́@�u�������y���ށv���ĉ��H
- �P�@�u�������y���ށv�͔��z�̓]��
- �Q�@�u�����Â���v�Ɓu�ʂ̎w���v��v
- �R�@�ی�҂ƂƂ���
- ��Q�́@���w����
- �`�������Ă����ȁC�F�������Ă����ȁC���ł��`�������W�`
- [���w���̋���ɂ���]
- �P�@�u������ǁv�ł����ڂ��i���������P���w�K�j
- �����Â��J�����_�[�Ō��ʂ��o�b�`��!!
- �Q�@�U�E���ƕ��́i�N���X�����P���w�K�E��w�N�j�\�{���Ɏx���ɂȂ��Ă�́H
- ���V���肪���Â���
- �R�@�u���炾���Ă����ȁI�v�i�N���X�����P���w�K�E���w�N�j�\�������Ă����ȁC�F�������Ă�����
- ����Â���̖{�͕�
- �S�@��y�����̂ŏh���w�K������������i�N���X�����P���w�K�E���w�N�j
- ������Ȍy�g���j����ɂ̂�����
- �T�@��邼�I�@�ۂ�ۂ�z�b�P�[!!�i�����̈�j�\���ƂÂ���̕��@���Ă��낢�날����̂ł�
- ���L�����v���E�z�C�I���キ�͂�
- �U�@�����͂ǂ�ɂ��悤���ȁH�i�ʂ̉ۑ�w�K�E���w�N�j�\�v�킸�����I�@�T���łł���ۑ�O�b�Y
- �����[�I�����C�ւ�H!
- �V�@�ĂƂ����u�Ȃ܂�v�I�i�N���X�E���������P���w�K�j�\�v������C�Ă��y������
- ���킭�킭�y�����Q�[���O�b�Y��W��
- ������ɂ���H�v
- ��R�́@���w����
- �`�����悤�C�g���悤�C�[�߂悤�`
- [���w���̋���ɂ���]
- �P�@�_���X�I�@�_���X�I�i���炾�Â���j�\�g�̂��S�����Y���ɂ̂���
- �Q�@���������Ί�}�N�h�i���h�i������˃^�C���j�\�}�N�h�i���h�Ō����Ă�������
- ���u����Ă݂����v����
- �R�@�{���J�X�C�N�b�L�[�͂������i�N���X�����P���w�K�E�R�N�j�\�Ȃ�ł��`�������W�u���R�ӂꂠ���i���v
- �S�@�S�ɔn�������Ă��܂����i�����P���w�K�j�\��n�Z���s�[�ւ̓��̂�
- ���S�̈��S��n�C����܂����H
- �T�@����ɂ��́@�Ԃ����(�N���X�����P���w�K�E�P�N)�\�ڂ��̓p�p�C�킽���̓}�}
- ���u������́C�����Ȃ��́v
- �U�@�`�P�b�g�̓��b�s�[�Łi�N���X�����P���w�K�E�R�N�j�\���ꂪ���b�s�[���K�@
- �V�@���b�c�@�t�B�b�V���O�I�i�N���X�����P���w�K�E�P�N�j�\�傫�ȃT����ނ邼�@�]�ɂ��y������
- �W�@�V���J�@�V���J�@�|�R�|�R�@�g���g���g���I�i�������y�j�\�݂�Ȃʼn��̃J�[�j�o��
- �X�@�z���b�ƃX�g�[���[�����h
- �������̎�l����
- ��S�́@��������
- �`�v�����L���C��т��݂��C�����̑��ŕ�������`
- [�������̋���ɂ���]
- �P�@���������Ă��������낤�i������ʁE�P�N�j�\�v���̖����m���߂悤
- �Q�@�y�������I�u�Z���h���w�K�v�i������ʁE�P�N�j�\�K�Y�N�Ƃ��������Q����
- �R�@�����̉Ƃ̏Ă��߂����Љ�悤�i������ʁE�P�N�j�\�ƒ���������������K��
- �S�@�v���o�Ɏc�闷�����悤�`�C�w���s�`�i������ʁE�Q�N�j�\�C�w���s�̐V���Ȏ���
- �T�@�ڂ��E�킽���̏Z��ł���܂��i������ʁE�R�N�j�\�u����ȁI�@�ڂ��E�킽���̂܂��Ɂv
- �U�@�������ƂЂ��ς�C�]�Ɋ���!! �i������ʁE�R�N�j�\����������H�W�Q�I!!
- �V�@�I���G���e�[�����O�ʼnۑ蔭��!! �i������ʁE�R�N�j�\�Z������Z�O�ւ̍L������˂����
- �W�@�킠���C�ł���������@��������I�i�����I�Ȋw�K�̎��ԁE�P�N�j�\���P�_���E�Ԓd�Â���̎��g�݂���
- �X�@����ɂ��́C�����p�b�N�̉���ɗ��܂����i�����I�Ȋw�K�̎��ԁE�Q�N�j�\�L����C�ӂꂠ���̗�
- 10�@�_���@�Â����H�@������ς����H�i�E�Ɓj�\�u�����v���y���ގp�����߂�
- ��T�́@�w�Z��
- �`�i�H�E�w�Z�s���E�ی������`
- ���i�H���l����T
- �P�@�q�ǂ�����������ŁC�w�Z�s������ϐg!!�\�^����͂����Â��^���Ǝ�����ϐg�I
- �Q�@���{�i���ł������܂��H�\�ی����͋i���X
- �R�@���̎肱�̎�̔얞��\�n��A�g�Ŏ��g�ޔ얞�����
- �S�@�u���͂悤�v�͌��N�̃o�����[�^�[
- �T�@�S���ʂ������ی�ғ��m�Ɂ\���Ԃ̗ւ��L���Ă���������
- ���i�H���l����U
- ��U�́@���H���ǂ��ǂ݉�����
- �P�@�u�������y���ގq�v���͂����ފw�Z�Â���
- �Q�@�n�����E�Ȋw�������Nj�����o����`����̎���
- �R�@�p���t���Ȏq�ǂ��i�N�j���Ƃ��Ắu�������y���ގq�v
- �S�@���B�ւ̎��ȉ^���ݏo���u���ƂÂ���v
- ���Ƃ���
- ���{�����ɏo�Ă��鎙���E���k���́C���ׂĉ����ł��B
�����ɓ�������
�@���m�̂悤�ɁC�ߔN�n���ƒ�̋���͂̍Đ��ƕ��I�ȎЉ��u�J���ꂽ�w�Z�Â���v�̂��߂Ɋw�Z�]�c�����x������ȂNJw�Z���v�̓���������ł���B�������Ȃ���C�u�J���ꂽ�w�Z�v�́C�����n���ی�҂����Ɂu�Z��v���I�ɊJ�����邱�Ƃɂ���Ď��������͂����Ȃ��C�܂������������Ɋw�сC�����������ł���q�ǂ������ɂƂ��ĐS��g�̂�������������Ԃł��邱�Ƃ��C�����ł���B
�@�h���\�����Ƃ������p�^�[���������������@��u�������ށv���ƂɌŎ����������̋��t�哱�̋��炩��E���Ȃ���C�u����w�сC����l���C��̓I�ɔ��f����v�������m�͂̔��W�͖]�߂Ȃ��B�������������F������C�{�Z�ł͕���10�N�x���猤�����Ƃ��āu�������y���ގq���߂����ā`�ʂ̎w���v������Ƃɂ������ƂÂ���`�v���������C�u�������y���ށv�𒆐S�Ƃ��C�ȉ��̂S�̎��_�̂��ƂɂS�N�Ԃɂ킽�茤����i�߂��B�����āC�ʂ̎w���v��𒌂Ɏ��ƂÂ���݂̂Ȃ炸�C����ے��S�ʂɂ킽���Č�������Ƃ�i�߂Ă����B
(1)�@�q�ǂ��i�������k�j����̂ɂ����u���ƂÂ���v
�@���t�哱�̎��Ƃł͂Ȃ��C�q�ǂ������̔��B�̃v���Z�X����̓I�C�\���I�C�ӗ~�I�ȉߒ��ł���ƂƂ炦�C��Q�̂���q�ǂ�������I�ɗ������悤�Ƃ���B�����āC�x�����邽�߂̔��B�f�f�Ȃ�тɌX�̃j�[�Y��p�n�k�iQuality of Life�j�̗��O���������邽�߂Ɍʂ̎w���v���{�Z�̓Ƒn�I�Ȓi�K�ʋ�����e�\�����Ƃ������ƂÂ���𐄂��i�߂�B
(2)�@���X�̐������y����
�@�w�Z�������w�Z�Ƃ��Ăł͂Ȃ��C�w�K���݂������w�Z�Ƃ��ĂƂ炦�C�q�ǂ��������y�����w�K������W�J���C�������b�Ƃ��邽�߂ɁC�P�Ȃ���ƂƂ����g���ɂƂǂ߂�̂ł͂Ȃ��C���܂��܂ȍs�����܂߁C����܂ł̊w�Z�����ߒ����C�q�ǂ�����̂ɂ����u���������Ƃ����v�w�Z�Â���ւƉ����𐄂��i�߂�B
(3)�@�ƒ��n��E�Љ�ւ̊g���������ɂ���
�@�w�Z�̐����݂̂Ȃ炸�C�ƒ�E�n��E�Љ�ɂ���������C�q�ǂ������̐����̌�����g�[�^���ɕ��͂��C�X�̔��B�ɉ����n���Љ�Ɗւ�鑽�ʓI�ȍZ�O�w�K�v���O�����i�s���E���ށE�w�K���e�Ȃǁj��K�ɑg�D���邱�Ƃɂ���āC�s����o���̗ʂ╝�Ȃ�тɎ������߁C������L���ɂ���͂��g�債�Ă����B
(4)�@�l�i�I�����Ƃp�n�k��Nj�����
�@�����̎������߂邽�߂Ɋw�Z�����ɂ����Ă��܂��܂ȓ���̊�����I�����C�ϋɓI�ɎQ�����C���Ȍ���C�ӎv�\���̂ł���u�l�i�I�Ȏ����v���߂������Ƃɂ���Ăp�n�k�����߂悤�Ƃ���u������́v���|����B
�@�����Łg�Љ�I�����h�ł͂Ȃ��C�L�[���[�h�Ƃ�������g�l�i�I�����h�Ƃ������H���O�ɋ��߂��w�i�ɂ́C�u���܂ŎЉ�I�������߂����Đ�������͂����Ă������Ƃ��߂����Ă����v���C�u����ɁC���ʓI�Ɋy���ށC�y���݂��ʂ���͂��o�����Ƃ���q�ǂ���������ĂĂ��������v�Ƃ����{�Z�̊肢�����߂��Ă���B
�@��ʂɁu�����v�Ƃ����ꍇ�C�����ΎЉ�I�����C���������ȂǂƂ����邪�C�Ƃ����ˑ��ƑΗ�����T�O�Ƃ��ĉ��߂��ꂪ���ł���B�����������́C���������x���ł��܂��܂Ȋ����W�c�i�Ƒ��E�w�Z�E�E��E�n��E�Љ�Ȃǁj�⋕�\�̊����W�c�i�������т╶���Ȃǁj�Ƃ̌����̉ߒ��ŏ[�������ˑ��Ƌ���������I�ȊW��茋�ԂȂ��Őg�̓I�C��I�C�F�m�I�Ȕ\�͂������Ĕ\���I�ɓ��������C�̎��I�Ȕ��B�𐋂��C���n���C��̂Ƃ��Ă̎����i�A�C�f���e�B�e�B�[�j���m�����Ă������̂ƍl����B
�@�q�ǂ����������܂��܂Ȋw�K�̉ߒ��𒇗����ɋ��t�W�c�̎x���݂̂Ȃ炸�C�w���W�c��Z�O�̐����W�c�Ɛ[���ւ�荇���Ȃ���C�K�Ȉˑ��Ƌ����C�����Ď����̊W���X�p�C�����ɐD��Ȃ����Ƃɂ���Ď�̂Ƃ��Ă̐l�ԓI�Ȕ��B�𐋂��Ȃ���C����̐�����Ԃ��g�傳���C���Ă����B����́C����������Έˑ��̎��I�Ȕ��W�Ə[�����Ӗ����Ă���C�p�n�k�����߂�Ƃ�������ۑ��Љ�O�Ƃ��Ẵm�[�}���C�[�[�V�����ɔ���ؓ��ł͂Ȃ����B
�@�����������ƂÂ�����ݍ��w�Z�Â���̎��H�������i�߂�Ȃ��ŋ��t�����̊����̐l�ԊρC����ρC�w�Z�ς���ɂ͎��Ǝ��H�ɑ��邠��ӎ����v�������炷�݂̂Ȃ炸�C�q�ǂ�������ی�҂����̊w�Z�ɑ��錩���ɂ���ω��������炷��̌_�@�ɂȂ������Ƃ����͊m���ł���B
�@�{���́C�{�Z�̑n�݈ȗ��C24�N�Ƃ��������ɂ킽����H�����̒~�ς̂����Ɏ����������̂ł���C���̓x�C�������������₩�Ȏ��H�̑��Ղ𐢂ɖ₤���Ƃ��ł������Ƃ�f���Ɋ�т����Ǝv���B����ɂ͏�Q����������������ł��O�i�����邤���ň�̎��H��ɂȂ肦��K���ƍl���邪�C���̕]���́C�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����Ɏ���܂łɂ͋@��閈�ɂƂ��Ɏ��H�E�����������Ă̓���������w�Z�̐搶���C�ی�҂̋��͂̂ق��C��w�E�w���ƘA�g�������������̐��i���w�E�����Ȃ��C�����w��Q������w�����̏��搶�����玦���ɕx�ނ������������������Ƃ��ł����B�܂��{���̏o�łɉ������������������}���Ȃ�тɕҏW���̎O���R���q���ɂ͑�ς����b�ɂȂ����B
�@�����ɉ��߂Ďӂ��Ă����\���グ�����B
�@�@2002�N�Q���@�@�@�Z���@�^���]�@����
-
 �����}��
�����}��