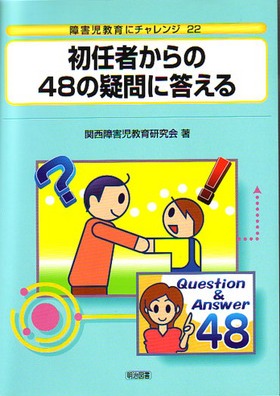- まえがき
- 1 教育課程について
- 1 合科指導についてはどう考えればよいのか?
- 2 学習課題の設定にあたって考慮しなければならないことはどんなことか?
- 3 教育課程の中へ作業学習をどのように組み入れればよいのか?
- 4 指導案はどのように書けばよいのか?
- 2 教科指導について
- 5 発達段階に応じた有効な指導法とはどのようなものか?
- 6 授業の中でドリル学習をどのように進めればよいのか?
- 7 知的障害児の学力をどのようにのばしていけばよいのか?
- 8 言葉を豊かにするには?
- 9 読み聞かせの本を選ぶ時,どのようなことに配慮すればよいのか?
- 10 文字を丁寧に書かせるためにはどのようにすればよいのか?
- 11 数の指導はどうすればよいのか?
- 12 時間とお金の指導をどうすればよいのか?
- 13 運動を少人数で行うにはどのような運動が考えられるか?
- 14 劇等でせりふへの感情の込め方の指導はどのようにすればよいのか?
- 3 日常生活の指導について
- 15 自閉的傾向をもつ子どもの持続力を伸ばすにはどのようにすればよいのか?
- 16 自傷行為のある子どもにはどのように対応するのがよいのか?
- 17 他傷行為のある子どもにはどのように対応するのがよいのか?
- 18 環境の変化に対する不適応行動のある子どもにはどのように対応するのがよいのか?
- 19 知的障害児の肥満に対する指導はどのようにすればよいのか?
- 20 指示待ちの多い子どもに対してどのように指導すればよいのか?
- 21 日常生活に必要な経験はどのようにして積ませればよいのか?
- 22 子どもの意欲を育てるにはどのような取り組みがよいのか?
- 23 教師の登下校への関わりはどのようにすればよいのか?
- 4 生活単元の指導について
- 24 養護(特殊)学級の集団をどのように指導すればよいのか?
- 25 障害の種類や状態に大きな差がある集団はどのように指導すればよいのか?
- 5 重度児の指導について
- 26 知的障害のある子どもの性教育はどのようにすればよいのか?
- 27 重度障害児のノンバーバルサインや表情はどのようにしてとらえればよいのか?
- 6 自立活動の指導について
- 28 なぐり書きをする子どもをどのように指導すればよいのか?
- 29 鉛筆を正しく持たせるにはどのようにすればよいのか?
- 30 自立活動とは?
- 31 子どもに応じた学校でできる訓練にはどのようなものがあるのか?
- 32 言葉の指導をどう考えればよいのか?
- 33 手指の巧緻性を高めるための指導はどのように行えばよいのか?
- 34 四肢の機能をどのように発達させればよいのか?
- 35 弱視の子どもの指導はどのようにすればよいのか?
- 36 寡黙な子どもの感情表現を広げるにはどのようにすればよいのか?
- 7 医師・保護者との連携について
- 37 医師とはどのように連携を取っていけばよいのか?
- 38 教科学習を中心に考える保護者にはどのように指導すればよいのか?
- 39 子どもの障害と保護者の思いをどのように理解すればよいのか?
- 40 保護者に養護(特殊)教育への理解と啓発を進めるためにはどのような事に配慮すればよいのか?
- 8 交流について
- 41 障害のある子どもの学校行事への参加ではどのようなことに配慮すればよいのか?
- 42 全校の子どもに養護(特殊)学級のことを理解させるにはどのようにすればよいのか?
- 9 進路について
- 43 将来に向けて(社会に出ていくために)どういった力をつけさせるのがよいのか?
- 44 中学校卒業後の進路についてどのように考えればよいのか?
- 10 改訂学習指導要領について
- 45 盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程改訂のポイントは何か?
- 46 盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程の編成についての具体的な変更点は何か?
- 47 「養護・訓練」についてはどのように変更されたのか?(参考資料)
- 48 授業時数等についてはどうなったのか?(参考資料)
まえがき
この本は,新しく障害児教育を担当されることになった先生方を主な読者と想定しています。もちろん,障害のある子どもの教育に興味がある方なら,どなたでも大歓迎です。棚に並んでいるたくさんの書物の中で,背表紙の『初任者からの48の疑問に答える』という文字に何らかのインスピレーションを感じ,手にとっていただいたあなたの期待に応え得る,そんな一冊をめざして,私たちはこの本をつくってきました。
はじめにおことわりしておきます。この本は,障害児教育の実践について詳しく系統的に述べたものではありません。2002年度から実施される盲学校,聾学校及び養護学校の新しい学習指導要領の内容なども盛り込んでいますが,最新情報のすべてを網羅しているわけでもありません。この本のテーマは,日々の指導実践をすすめるときに皆さんが感じておられる『わからないこと・困っていること』に焦点をあて解決のみちすじを探ることにあります。
「ひらがなの『あ』の字が書けない」。同じように見える状態像でも,その子が5歳なのか,15歳なのかによって今後の指導の見通しや用意する課題も違ってきます。障害児教育の実践には,ちょっとしたコツや工夫が大きな効果を見せることがあります。職人芸の世界もまだ少し残っています。視点をかえるだけで,『わからないこと・困っていること』の答えが見えやすくなることもあります。そのために,少しでもお役に立てたらと思います。
この本の「Q」も「A」も,実践の中から生まれました。
この本でとりあげた48項目の質問は,養護(特殊)教育をはじめて担当された先生方からの相談での『わからないこと・困っていること』が基になっています。
それぞれの質問に対する答えの最初に紹介しているのは「考えるためのポイント」です。みなさんが実際に経験される『わからないこと・困っていること』はこの本の通りとは限りませんが,これらのポイントを参考にしながら,個々の条件に応じた実践を展開していただきたいと思います。
答えの部分は,私たちの実践の積み重ねをもとにしています。個人的にうまくいった例を報告するのではなく,一つひとつの項目について各人の経験をもち寄り,成功例・失敗例をともに分析したうえで,私たちの考え方をまとめました。
この本をつくりあげる過程で,私たちは,いろいろな問題についてお互いが経験したことや持っている情報を交換・共有することができました。その議論の雰囲気を行間から感じとっていただければ幸いです。
2000年4月 著者
-
 明治図書
明治図書