- �͂��߂�
- ���@�́@�e�Ƌ��ɐi�߂鐫���灖�e�Ƌ��t�́u������̃p�[�g�i�[�v
- �P�@�e�������O�̊肢
- �Q�@�s���邱�Ƃ̂Ȃ��e�̔Y��
- �R�@��Q�̂���q�ǂ��ɑ��鐫����
- �S�@�e�Ƌ��ɐi�߂鐫����
- ��P�́@�ƒ�ɂ����鐫����
- ���u�̂̕ω��v�������ꂸ�C���т��q�ǂ�
- �P�@����V�т���n�߂��u�����v�̂���
- �e�̔Y�݇@�@�g�ӏ�������l�łł��Ȃ��č���
- �p���`�@�ƒ�ł̐��̂����́H
- �Q�@�u���킢����v������q�ǂ��̋C�������킩����
- �e�̔Y�݇A�@���킢���������̂ō���
- �p���`�@���̎w�����s���̂ɁC�u�������Ԃ̔c���v���K�v�Ȃ̂͂Ȃ����H
- �R�@�u�p���������v�Ƃ����C�������炽�Ȃ�
- �e�̔Y�݇B�@�p���������C����������Ă��Ȃ��č���
- �p���`�@�u���ȓ�������\�́v������ɂ́H
- �S�@���e�̋��͂Łu�����C�̂����v���Ȃ��Ȃ���
- �e�̕s���@�@�����n���K��邱�Ƃ��s���ł���
- �p���`�@�u�Љ�v����Ă�ɂ́H
- �T�@�R�}�[�V�����ƈႤ�u�o���v�̐F
- �e�̕s���A�@���o�̎蓖�Ă��������ł��邩�s���ł���
- �p���`�@�u���o�v�ɂ��Ă̎w���́H
- �U�@�u�����v�����˂���ƊԈႦ��
- �e�̕s���B�@�����Ȃǂ̏������������ł��邪�s���ł���
- �p���`�@�u�����v�ɂ��Ă̎w���́H
- �V�@�����́u�������v�ɐG�肽����q
- �e�̔Y�݇C�@����̑̂ɂł��G��ɂ����̂ō���
- �p���`�@�u�ِ��̑̂ɐG�ꂽ����q�ǂ��v�̎w���́H
- �W�@�ِ��ł���u���q�̐��v��������Ȃ�
- �e�̕s���C�@�C���C���₩�Ⴍ���N�����̂ł͂Ȃ����ƕs���ł���
- �p���`�@��҂̐��I�j�[�Y�́H
- �X�@�u���q�̐��v�������
- �e�̕s���D�@�}�X�^�[�x�[�V���������邱�Ƃ��S�z�ł���
- �p���`�@�u�N���̐�����v�ɂ͂ǂ̂悤�Ȕz���≇�����K�v���H
- ��Q�́@�w�Z�ɂ����鐫����
- �����I���������ʂ��đi�������Ă������̂�
- �P�@������͐e��������̂ł��傤���H
- �e�̊肢�@�@�w�Z�Ȃǂł̐�������[�����Ăق���
- �p���`�@�u���Ɋւ���w���v�Ɓu������v�̈Ⴂ�́H
- �Q�@�F������^���āu���������v���ł���
- �e�̔Y�݇D�@�g�C���̂���������č���
- �p���`�@��Q�̂���c���̐�����́H
- �R�@������̎��Ƈ@�@�u�j�̎q�C���̎q�v
- ���t�̈ӎ��@�@�����E�q���ʂŎw������������
- �p���`�@�u���Ɋւ���w���v�͂ǂ̋��ȁE���e�ŁH
- �S�@������̎��ƇA�@�u�D���ɂȂ�Ƃ������Ɓv
- ���t�̈ӎ��A�@���_�ʂŎw������������
- �p���`�@�u�w�K�w���v�́v�ɂ͐�����ɂ��Ă̋L�ڂ��Ȃ����H
- �T�@������̎��ƇB�@�u�����̐��������i�a���j�v
- ���t�̈ӎ��B�@�Љ�ʂŎw������������
- �p���`�@���w�Z��Q���w���̐�����́H
- �U�@�����狳�ނÂ���̃|�C���g
- �e�̊肢�A�@�G�{�⋳�ނ��[�����Ăق���
- �p���`�@�u���ށE����v�����p����ɂ������Ă̗��ӓ_�́H
- �V�@��q�����s���ɂ݂���u�C������ȍs���v
- �e�̕s���E�@�C������ȍs�����N�������Ƃ��s���ł���
- �p���`�@�u���I��Q�v��u���I���Q�v�ɂ��Ă̎w���́H
- �W�@�u�搶�C�L�X���āI�������āI�v
- �e�̕s���F�@�����ɂ��Ă̕s��������
- �p���`�@�u���̌����v�Ƃ́H
- �X�@������́u���t�̋��ʗ����v����
- ���t�̈ӎ��C�@���t�̊Ԃŋ��ʗ������ق�������
- �p���`�@������ɂ����鋳�t�̋��ʗ����Ƃ́H
- ��R�́@�Љ�ɂ����鐫����
- ���u�₵���v��u������߁v��������Ȃ���
- �P�@�u���ɂ��Ă̑��k�v��i�߂邽�߂�
- �e�̊肢�B�@������Ɋւ��Ă̑��k�������[�����Ăق���
- �p���`�@������̖ڕW�́H
- �Q�@�����ق𗘗p�����n��ł́u�]�Ɋ����v
- �e�̊肢�C�@�n��̊������Ăق���
- �p���`�@�W�@�ւ�n��Љ�Ƃ̘A�g�́H
- �R�@�c���Ƃ̗V�т��u�s���v�ƊԈ����
- �e�̊肢�D�@��Q���E�҂̐����C�����������ł���悤�Ɍ[�����Ăق���
- �p���`�@��Q�̂���q�ǂ��́u���̔��B�v�͒x��邩�H
- �S�@���ꂵ�������u�搶�Ƃ̏o��v
- �e�̊肢�E�@�K�v�Ȑl�I���������Ăق���
- �p���`�@�n��Љ�̒��Łu�Љ�Q�����������Đ����Ă����v�ɂ́H
- �T�@27�́u���q�̐t�v�Ƃ�������
- �e�̊肢�F�@�w���҂ւ̌��C��O�ꂵ�Ăق���
- �p���`�@�u�m�[�}���C�[�[�V�����v�̌����Ƃ́H
- �U�@�T�[�N��������ʂ��Ắu�����x���v
- �e�̕s���G�@�ِ��Ƃ̌��ۂɂ��Ă̕s��������
- �p���`�@�u�j�����ہv�ɂ��Ă̎w���́H
- �V�@�e�Ƌ��t���[���Ɏ��g�ށu������̊w�K��v
- �e�̊肢�G�@������̊w�K������Ăق���
- �p���`�@�Z�b�N�X�ƃZ�N�V�����e�B�̈Ⴂ�́H
- ������
�͂��߂�
�@1986�N��1991�N�C������1994�N�ɃC�M���X�̐����玖��ɂ��Č��C����@����M�҂́C�����Q���̐e�̉�ł̌��C��ŁC
�@�u�C�M���X�ł́w�m�[�}���C�[�[�V�����x�̌����ɂ���āC��Q�̂���l�тƂ̐����w�l�ԂƂ��Ă̓��R�̌����x�Ƃ��ĔF�m����Ă���C��Q�̂���l�тƂɎЉ�̈���Ƃ��Ă̎s������ۏႷ�邽�߁C�ʊ��Ȏ��g�݂��s���Ă��邱�ƁB�܂�, 1981�N����@�ɂ���āC��Q�̂���q�ǂ������e���w��������ҁx(parents as partners)�Ƃ��Ĉʒu�Â����C���t�͐e�Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v���d�����Ȃ��琫�����ϋɓI�ɐ��i���Ă��邱�Ɓv
�@�u�킪���ɂ����Ă��e�Ƌ��t���A�g���āC�l�ԑ��d����ՂƂ����w��Q�̂���q�ǂ��̐�����x��ϋɓI�Ɍ����E���H���邱�Ƃ��d�v�ł���C�ً}���̂���ۑ�ł��邱�Ɓv
�Ȃǂɂ��ĕ��s���܂����B
�@����ƁC�e�����̒�����u���̌����ȂǗ��z�_���v�Ƃ����w�E������C������ɂ��Ĕے�I�ŋ��ۓI�Ƃ��v����e�̔��������p���܂����B
�@�u�������e�́C�킪�q�̒j�����ۂ⌋���ɂ��Ė���������Ƃ����ł��܂���B������͐Q���q���N�����悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂ł͂���܂��v
�@�u�킪���ł̓C�M���X�̂悤�Ɂw���̌����x��ی삵�C�ۏႷ��Љ�̉����̐����Ȃ��Ȃ��ŁC�q�ǂ��̐���ڊo�߂����邱�Ƃ͎c�����Ǝv���܂��v
�@����ɁC�e�����̑i���͑����܂����B
�@�u��Q�̂���q�ǂ��́C���ɂ��ĉ�������Ύ����C������Ύ����Ă���̂�����ł��B���ɂ��Ă̋�����S�������Ȏq�ǂ��ɁC���Ă��悢���Ƃ�C�ǂ�����悢�̂����C�N��������₷�������Ă���Ă��Ȃ��̂ł��v
�@�u�q�ǂ��͎��R�ɉ߂����Ă悢���Ԃ���ɂ̂悤�ł��B���Вn��̂Ȃ��ŃX�|�[�c��N���G�[�V�����Ȃǂ��ł���N�w����l�w���ȂǁC�]�ɂ��y�����߂�����@�������Ă�肽���̂ł��v
�@�u�������邽�߂ɂ́C���������S�ʂɂ킽�鑧�̒����������k���K�v�ł��B�o�ϓI�ȕۏ���Q��z�������Z����K�v�ł��v
�@�u�O���[�v�z�[����z�[���w���p�[�Ȃǂɂ��C���퐶���ł̉������Ȃ���C��Q�҂́w�Љ�Q���x�Ȃǂ͊G�ɕ`�����݂ł��v
�ȂǁC�N�������z������Q�̂���q�ǂ��̐��ɂ�����鏔��肪��N����܂����B
�@�������ɁC���ɖڊo�߂��q�ǂ������e�́C�����̐��Ɍ˘f���C�Y�݂Ȃ��猜���ɐ����Ă���킪�q�̐������܂ƁC�^���ʂ��痧�������킴������Ȃ��Ƃ�������������������܂��B���킦�āC��Q�̂���l�тƂɑ���Љ�̌����Ό��C���ʓI�ȑԓx�Ȃǂ��C�e�̔Y�݂�����ɐ[���Ȃ��̂ɂ��Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@���ƌ�̎q�ǂ������́u���L���Ȑl���v��{�C�ɂȂ��Ċ肤�̂Ȃ�C�܂��C�u�������ϋɓI�ɐ��i���悤�v�B�����āC�u�n��ł̐��������{��̎��Ԃ�c�����悤�v�B����ɂ́C�u��̓I�Ȏ{��ɂ��Ă��C�݂�ȂŔ������Ă������v�ƁC�M�S�Ɍ�荇���Ă����e������, 1994�N�̉āC�u��Q���̐����猤���e�̉�v���������܂����B�����āC���̊����͍������ϋɓI�ɑ������Ă��܂��B
�@�{���Ɍf�ڂ��Ă��钲�������́C�w��Q�̂���q�ǂ��̐��ɂ��Ă̐e�̈ӎ��Ɋւ�����Ԓ����x(1995)���甲�����܂����B�M�҂��O�q�����e�����ƈꏏ�ɁC��Q�̂���q�ǂ��̐����߂��鐶�����Ԃ��@��N�����C�Љ�̐l�тƂɁu��Q�̂���q�ǂ��̐�����v�ɑ��邻�̏d�v���Ƌً}����i���邽�߂ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B
�@�e�⋳�t�E�w�����ȂǁC��Q�̂���q�ǂ����߂���W�҂́u�w���E���H�����v�ƂƂ��ɂ���������������K�r�ł��B
�P�@�����̖ړI
�@��Q�̂���q�ǂ��́u���v�ɂ��Ă̐e�̈ӎ������C���̂�����w���ɂ��Ă̕����T��B
�Q�@�����̍���
�@(1)�N����Q�̏�ԂȂ�
�@(2)���ɂ��Ă̔��B��
�@(3)���ɂ��č����Ă��邱��
�@(4)���ɂ��ď�������ł��낤����
�@(5)�����s����Љ�ɖ]�ނ���
�R�@�����̑Ώ�
�@���{���ݏZ�̏�Q�̂���q�ǂ������ی�ҁi��e119���C���e�P���j�v120��
�@(1)��Q�̂���q�ǂ��̔N��
�@�@�R����39�ŁC�j�q73���i60.8���j���q47���i39.2%�j,���v120��
�@(2)��Q�̏�
�@�@120����107���i89.2%�j���È�蒠�܂��͐g�̏�Q�Ҏ蒠���擾
�@(3)��Q��ʁi�����j
�@�@�u�m�I��Q�v97���i80.8%�j,�u�����Q�v66���i55%�j,�u���Q�v43���i35.8%�j�C�u�g�̏�Q�v38���i31.7%�j�C�u�w�K��Q�v30���i25%�j�C�u�d����Q�v89���i74.2%�j
�@(4)����
�@�@�A�w�O�i�ʉ��{�݂�c�t���ɒʂ��R����U�̎q�ǂ��j33���i27.5%�j
�@�@���w���i�{��w�Z���w���⏬�w�Z�ɒʂ��U����12�̎����j30���i25���j
�@�@�������i�{��w�Z���w���⍂�����ɒʂ�12����18�̐��k�j34���i28.3%�j
�@�@�N�i���Y���E��Ə���{�݂ɏ�������18����39�̐N�j23���i19.2%�j
�S�@�����̎���
�@�@1995�N�P��15���`�Q��15��
�T�@�����̕��@
�@�@�����I��@�ɂ��A���P�[�g�@
�U�@�Ґ��E�����
�@�@�������100��
�@�@�L������120��














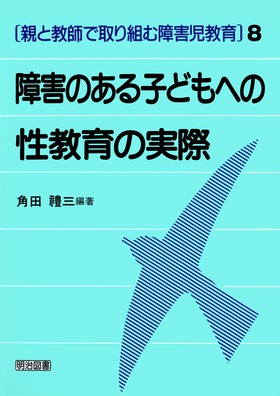


���Ⴊ���ɂ�������ڂ��Ă����̂ŁA�������Ȃ����C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
�w�Z�Ő���������ė~�����I�Ɨ���ł��A�Ȃ��Ȃ����グ�Ă���Ȃ��̂ŔY��ł������ɁA���̖{�Əo��܂����B
�C�M���X�ł̎��g�݂��Љ��Ă��āA�����ւ��������܂����B
���А搶�B�ɂ��ǂ�ł��������A�q�ǂ��B�ɐ���������ė~�����Ǝv���܂����B
�u�e�𐫋���̃p�[�g�i�[�Ƃ��āA�e�Ƌ��ɐi�߂鐫������I�v�Ƃ������҂̑i���ɓ����ł��B
�ƒ�ŁA�w�Z�ŁA�Љ�ŁA��Q���̐������i�߂��������Ƃ��āA���Ј�ǂ��Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
�܂��A�ی�҂�ΏۂƂ��Ă̒������ʂ���́A�e�̔Y�݂�s����m�邱�Ƃ��ł��A�f�[�^�������Ȃ���A�e�̋����邱�Ƃ��ł���̂ŁA���k��Ȃǂ̎��ɗ��p���Ă��܂��B
�ƒ�E�w�Z�E�Љ�̂R���ʂ���̏͗��Ă��ǂ݂₷���A���ꂩ���Q�̂���q�ǂ��̋����ۈ���߂����Ă���l��A�q��Ăɕ������̕ی�҂ɂ����Гǂ�ŗ~�����Ǝv���܂��B