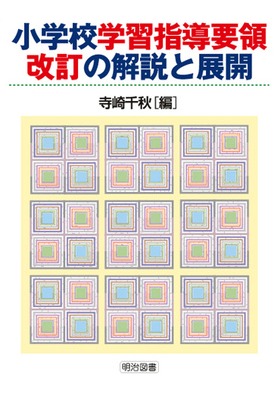- はじめに
- 1 改訂をどう受け止めるか
- 1 中央教育審議会の答申について
- 2 新学習指導要領についての基本的な考え方
- 3 子どもたちに求められている学力
- 4 学習指導要領の「基準性」の一層の明確化
- 5 「総合的な学習の時間」の一層の充実
- 6 「個に応じた指導」の充実
- 二 改訂のポイントは何か
- §1 学習指導要領の「基準性」の一層の明確化
- 1 「基準性」の趣旨と「はどめ規定」の扱い
- 2 「個に応じた指導」の創意工夫との関連
- §2 必要な指導時間の確保
- 1 標準授業時数のとらえ方
- 2 年間総授業時数のとらえ方
- 3 必要な指導時間の確保の把握と説明責任
- 4 必要な指導時間の確保の工夫
- §3 「総合的な学習の時間」の一層の充実
- 1 「総合的な学習の時間」の全体計画
- 2 「総合的な学習の時間」の目標や内容の設定
- 3 「総合的な学習の時間」と各教科等との関連
- 4 「総合的な学習の時間」の指導の充実
- 5 「総合的な学習の時間」の評価の改善
- §4 「個に応じた指導」の一層の充実
- 1 学習内容の習熟の程度に応じた指導
- 2 児童の興味・関心等に応じた課題学習
- 3 「補充的な学習」や「発展的な学習」
- 4 「個に応じた指導」を行う上での配慮事項
- §5 教育課程及び指導の充実・改善のための教育環境の整備等
- 1 国や教育委員会等による支援
- 2 保護者や地域住民等との連携・協力
- 3 学習指導要領の趣旨やねらいの周知
- 三 改訂事項を実現するプランづくり
- §1 教育効果を上げる授業時間運用のプラン
- はじめに
- 1 固定的な時間割運用のプラン
- 2 弾力的な時間割運用のプラン
- 3 モジュールによる時間割運用のプラン
- §2 「総合的な学習の時間」の充実を図るプラン
- 1 「総合的な学習の時間」の全体計画
- 2 「総合的な学習の時間」の目標や内容の設定
- 3 「総合的な学習の時間」の充実を目指したプラン例1
- 4 「総合的な学習の時間」の充実を目指したプラン例2
- 5 「総合的な学習の時間」の充実を目指したプラン例3
- §3 「個に応じた指導」の充実を図るプラン
- 1 ティーム・ティーチングのプラン(理科)
- 2 少人数授業のプラン(算数)
- 3 補充的な学習,発展的な学習のプラン(算数)
- 4 課題選択授業のプラン(社会)
- 5 興味・関心別授業のプラン(算数)
- §4 評価を生かした授業改善プラン
- 1 評価計画の実例
- 2 評価規準を活用した授業の改善プラン1(体育)
- 3 ボール運動の授業づくりと評価(体育)
- 4 評価規準を活用した授業の改善プラン2(国語)
- 5 評価規準を活用した授業の改善プラン3(算数)
- 6 算数科における評価規準活用プラン
- 四 改訂に関するキーワード解説
- 1 教育課程実施状況の自己評価と説明
- 2 長期休業日の増減や学期区分の工夫
- 3 「総合的な学習の時間」の 「目標」や「内容」
- 4 「総合的な学習の時間」の「全体計画」
- 5 「総合的な学習の時間」と各教科等との関連
- 6 「総合的な学習の時間」における各種施設や団体との連携・協力
- 7 「総合的な学習の時間」における多様な教育資源の活用
- 8 長期休業期間を活用するなどの弾力的な授業の実施
- 9 個に応じた指導
- 10 学習内容の習熟の程度に応じた指導
- 11 補充的な学習
- 12 発展的な学習
- 13 課題別学習
- 14 興味・関心別の指導
- 15 個別指導
- 16 グループ別指導
- 17 繰り返し指導
- 18 「教育課程の開発や管理に関する能力」
- 19 「時間の効率的な利用」
- 20 「子どもたちの教育のネットワーク」
- 資料 小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)新旧対照表
はじめに
学習指導要領の総則等が改訂されました。平成14年度から全面実施となってまだ2年が経っていません。平成15年の5月に中央教育審議会に「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」を諮問し,5ヵ月後の10月7日に答申を得るといったスピード審議でした。
各学校からすれば,なぜこのようにすぐに,そして早くという感が拭えないでしょう。新学習指導要領に基づく教育課程を始めたばかりです。ようやく落ちついて新教育課程を実施する体制が整ってきたという実感がもてるときでもあります。各学校・教師の一部からは,文部科学省は「学力低下問題」の指摘のなかでその姿勢が揺らいでいるのではないか,という声も聞こえてきます。しかし,各学校・教師はそのような傍観者的立場,評論家的立場で見ていてはなりません。
今回の総則等の改訂は,各学校のこの数年間の教育の取組が問われているのです。現行学習指導要領の趣旨に即した教育をしっかりと推進し展開しているかどうかということを。
現在の新教育課程に至るまでに以下のような経過があります。
平成8年7月19日 中央教育審議会「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」を答申
平成10年7月29日 教育課程審議会「幼稚園,小学校,(略),の教育課程の改善について」を答申
平成10年12月14日 新学習指導要領告示
平成11年度 新学習指導要領の趣旨の理解
平成12〜13年度 新教育課程への移行措置
平成12年12月4日 教育課程審議会「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」を答申
平成13年4月27日「小学校児童指導要録,(略)の改善等について(通知)」
平成14年4月 新教育課程全面実施
中央教育審議会の答申から8年,教育課程審議会の答申から6年,現在の学習指導要領が告示されてからでも5年ほどが経っているのです。この間,学校は何をしてきたかが問われています。その趣旨に即して教育課程の改善を準備し,教育課程を編成し,確実に全面実施しその趣旨を徹底しているかどうかが問われているのです。
今回の中央教育審議会への諮問→中間まとめ→答申,そして学習指導要領の総則等の改訂は,言わばこれら一連の教育課程,さらには各学校の教育活動の改善の仕上げ,あるいは徹底と言ってよいでしょう。各学校は,学習指導要領の総則等の改訂の趣旨をしっかりと受け止め,その具現に努めることが必要であり,保護者や地域の人々に説明していく責任があります。本書がそうした各学校の創意工夫の一助になれば幸いです。
本書の執筆者は,教育課程に関して造詣が深く,実際に各学校や各地域にてよりよい教育課程の在り方や教育活動の推進,学校経営をリードされている方々です。お忙しい中にもかかわらず玉稿をお寄せいただいたことに深く感謝します。また,本書の企画の段階からお世話になりました明治図書の安藤征宏氏に対しても特に名を記して感謝の意を表します。
2004年3月 編者 /寺崎 千秋
-
 明治図書
明治図書