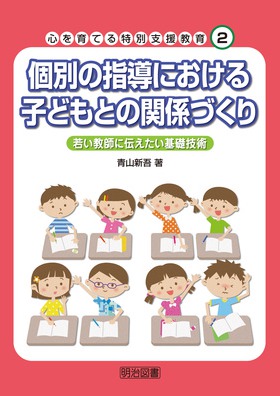- プロローグ
- 第1章 子どもとの関係づくり
- 1 子どもとの「第1段階」の関係
- 2 子どもとの「第2段階」の関係
- 第2章 子どもとの「第1段階」の関係づくり
- 1 通じ合いにくさ
- 2 通じ合うことと主導権〜桃太郎―吉備団子理論〜
- 3 意図的にやりとりをする
- (1) 歩く
- (2) まぐろさん
- (3) たいそう
- (4) 学習
- 4 環境設定が関係をつくる
- 5 わざと流す場合
- 第3章 子どもとの「第2段階」の関係づくり
- 1 子どもとの「間」に共通するモノ・ヒト・コトを考える意味
- 2 共有できるモノ・ヒト・コトを探す
- 3 同じことを考える
- 4 関わる側が内省する
- 第4章 関わりにくさを感じる子どもとの「第2段階」の関係づくり
- 1 現実に対応し,暮らし,学ぶこと〜「給食投げちゃろうか」のことばの本音を探る〜
- (1) 動作を支援する〜切り換え困難,開始困難への対応〜
- (2) 「通訳」をする
- (3) 本当の意味の「受容」
- (4) メッセージが伝わる,メッセージを伝える
- 2 気をつけたいこと〜べからず集〜
- (1) 取り締まるー取り締まられる関係になるべからず
- (2) させられていただけの関係になるべからず
- (3) 何が伝わったのかに鈍感であるべからず
- (4) 二者の関係に鈍感であるべからず
- 第5章 「第2段階」の関係で子どもに伝えたいメッセージ
- 1 君は間違っていない
- 2 あきらめないで粘るんだ
- 3 わかってくれようとする人は存在するから
- 4 話題にしていいんだよ
- 5 やりたいけれどやれないんだよね
- 6 「お兄さん」「お姉さん」になる
- 7 「可愛い」という見方
- 第6章 押さえておきたい子どもとの関係づくり基礎技術
- 1 子どもの動きを見る
- 2 子どもの視線を見る
- 3 タッチで伝える
- 4 止める
- 5 力を抜く
- 6 カウントをきる
- 7 「本人論理」を読む
- 8 さりげなく行う〜心理的な距離を意識する〜
- 9 ことばを入れる
- エピローグ
- 参考文献
プロローグ
さかのぼること20年以上前のことである。
ある小学校の1教室に,1人の男の子と未熟な教師がいた。
その男の子は,重い知的障害と自閉症のある子どもであった。表出言語はまったくなかった。自分の意思を音声言語に乗せて表現することはできなかった。
その子どもは,頻回にパニックを起こし,怒り,泣き,つかみかかり,暴れた。でも,落ち着いているときには笑顔の可愛い男の子であった。だからであろうか,どこか憎めない子どもであり,なぜか多くの人に可愛がられていた。いや,それは彼の母親があちこちで心遣いをされており,その母親の姿勢と生き方に共感した多くの人たちが,母親の姿を重ねながら,その子を見つめていたからなのかもしれない。
しかし,現実は厳しいものがあった。
当時の学級担任の先生は,時折,その子をおんぶしながら他の子どもたちに授業をされていることがあった。それでも他の保護者から大きな不満が出ていないと聞いた。
今とは時代が違ったのだろう。
しかし,その先生が,他の子どもたちに対して「おんぶ」している姿を通して「何か」を伝えていたのだろう。そして周りの子どもも育っていたのだろう。周りの子どもたちも先生に認められ安心して過ごせていたのだろう。これは,単に時代の違いとは言えないものだと思う。
その男の子は,周りから確実に愛されていた。
しかし,その子は周りから学ぶことがものすごく下手であった。それは,周りから働きかけたものを受け入れて「やろうとしてみる」ことがものすごく少なかったからである。
私は,彼とよく格闘した。
歩いてみようと促す私に,ひっくり返ろうとしたり,泣きわめこうとしたりする彼。それを許さずに一緒に歩き始めると,次第にリズムに乗ってくる。そして,いつしか2人は一緒に歩く。
一人ぼっちで,好きなことをしていたかったわけではなかったんだね。
人と一緒に何かをするって楽しいね。
彼は人から学べるようになった。
彼は人を信用する子どもになった。
彼は一人ぼっちでなくなった。
人から学べる関係が成立したのだと考える。そしてその関係をもとに彼は育っていったのだと思う。私はそれらを「第1段階」の関係,「第2段階」の関係と考えてきた。
2人で歩いている場面。
何となく歩いているようにしか見えない。でも,教師が立ち止まったときに,子どもはどうするか? 教師が話しかけたときの,子どもの一瞬のリアクションはどうか? 子どもとつないだ手に少しだけ力を入れたときの子どもの手の力の入れ具合はどうか……等々。
周囲からは単に歩いているとしか見えない何気ない場面のできごとである。しかし,ここには2人の間の「関係」が成立している。そして,目に見えない小さなやりとりがあり「物語」が紡がれていく。
「第1段階」の関係はシンプルである。しかし,その内容は非常に見えにくく繊細である。
そして,「第1段階」の関係を終えた場合には,速やかに意図的に,意識して「第2段階」の関係に移行する必要がある。
本書では,個別の指導における子どもとの関係づくりについて,「第1段階」の関係と「第2段階」の関係に分けて整理する。そして,それぞれの教育のポイントを実践場面に基づいて考察し,「技術」として伝達しようと考えている。特に,通じ合いにくさを有する子どもたちとの関係について考えることを目的としている。
目に見えない「関係」を成立させる「技術」。
これらが「気になる子ども」「支援を要する子ども」「困っている子ども」「学びにくい子ども」「暮らしにくい子ども」などと言われる多くの子どもたちを育てることにつながっていく。そして,子どもたちの表層の言動と本音の遊離を詰め,子どもたちを「孤立」させずに育てていくためのヒントになれば幸いである。
2012年5月 著者
-
 明治図書
明治図書