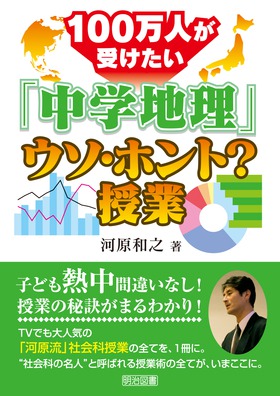- �܂�����
- ��T�́@�u�E�\�v�u�z���g�v����u�ւ��I�v�u�����������v��
- �`�u�m�邱�Ɓv�̊�т���u�킩��v��тց`
- �P�@�Ȃ��n���w�K�́C�y�����Ȃ��Ȃ����̂�
- �`�u�w�K�w���v�́v�̕ϑJ�Ɋւ���ā`
- �Q�@�u�E�\�v�u�z���g�v����u���[��v�u�Ȃ�قǁv��
- �R�@�u�t�H�g�����Q�[�W�v����Љ�̎d�g�݂�
- (1)�@�A�t���J�̃K�[�i
- (2)�@�t�B���s���̎q�ǂ�����
- ��U�́@���ԓI�n���Ɓu���p�v�u�T���v��
- �P�@�u�����I�m���v����u�T�O�I�m���v��
- �`�u�`������v�u�`�������Ă���v����u�Ȃ��C�����Ȃ̂��v�ց`
- �Q�@���E�n���g���w�K�h�Ɠ��{�n���g���j�����h
- �R�@�u���p�v�^�w�͂Ƃ��Ắu����́v�u�\���́v�u�v�l�́v�̈琬
- (1)�@�����ƃC���h�C�ǂ��炪�o�ϔ��W���邩
- (2)�@�v���[��
- �S�@�Љ�ȋ���ϊv�̃`�����X
- ��V�́@�u���E�e�n�̐l�X�̐����Ɗ��v�E�\�E�z���g�H����
- �P�@�y�~�j�l�^�z���J�����j���[�J��
- �Q�@�y�K���z�Ⴂ�̂킩�鑾���m�Ƒ吼�m�i�O��m�j
- �R�@�y�K���z�l�����ɂ܂����鋐��ȍ��i�ԓ��C���t�ύX���j
- �S�@�y�����E�K���z�_�W�����ō����i���E�̍��X�j
- �T�@�y�K���z�J�����[���̍ג����������i�����j
- �U�@�y�K���z�w�J�X�s�C�x���ĊC�Ȃ̂��H�@�Ȃ̂��H�i�̊C�j
- �V�@�y�K���z�C�X�������̃X�^�[�o�b�N�X
- ��W�́@�u���E�̏��n��v�E�\�E�z���g�H����
- �W�@�y���[�N�V���b�v�z���[�N�V���b�v�@�����i�����j
- �X�@�y���w�K�z�C���h�̐��I������Ă����I�i�A�W�A�j
- 10�@�y���w�K�z������ڎw�����[���b�p�i���[���b�p�j
- 11�@�y���w�K�z�A�t���J�̓���ƕ����i�A�t���J�j
- 12�@�y�K���E�����E�l�����z�A�����J�H�Ƃ̗��n����
- 13�@�y�T���z�A�W�A�T����IN���
- ��X�́@�u���{�̎��R���ƒn��I���F�v�E�\�E�z���g�H����
- 14�@�y�K���z���{�̍����E�̓y
- 15�@�y�K���E���p�z�����Ŕ��܂��z�e��
- 16�@�y�T���z�R���r�j����Љ���̂���
- 17�@�y���w�K�z�����̖���
- 18�@�y�~�j�l�^�z����̂��Ⴊ����
- 19�@�y�~�j�l�^�z����Ẵg�b�v�����i�[
- 20�@�y���j�����z�u�L���v�H�ꂩ��l����C�����̒������
- 21�@�y�K���zET�̎��]�Ԃ͍��H
- 22�@�y���p�z���{�͋ߋE�n���̂ǂ��ƁC��������Ί��������邩
- 23�@�y���j�����z�ޗǂւ̌ւ�Ɠ`���H�|
- 24�@�y���j�����z�H�Ɛ��Y���{��̌�
- 25�@�y���j�����z�m�H�퐶�Y�n�͍��H
- 26�@�y���j�����z��㑺�̃��^�X
- 27�@�y�K���z�ߖ��s�s�͍��H
- 28�@�y�~�j�l�^�z���{��Ⴂ�x�m�R�i���k�j
- 29�@�y�T���z�u��z�ցv�̔閧
- ���Ƃ���
�܂�����
���q�ǂ��̌�������o�����悤�I
�@2010�N10���w���̒��̒��w�Z�x�Ƃ����h���}�����f���ꂽ�B�Y�����Ɏ��Ă���Ă��钆�w�Z�𑲋Ƃ��Ă��Ȃ������҂��C�w�ђ�������ł���B���̏�ʂŁC�猴�����������镞���҂��C�u�킩��Ȃ��v���Ƃɑς���ꂸ�u������߂����Ă���B�����ς����Ȃ��B���͂����߂Ȃǂ������ƂȂ��������C���C���͂����߂����Ă���B���̂܂܁C�����ɂ�����C�ǂ�ǂ�C���Ȑl�ԂɂȂ��Ă��܂��i�v�|�j�v�Ƃ������т������C���E���悤�Ƃ����ʂ��������B���́g���сh�̏�ʂ����Ȃ���C�����̉��l���̐��k�̊炪�ڂɕ�����ł����B�{���C�u�w�ԁv�Ƃ́C�g�V���Ȕ����h�����C�g�m�I�����h�����N���C�g�������h��h���Ԃ���̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������C�u�w�͒�ʑw�v��u�w�K�ӗ~�̂Ȃ��v���k�ɂƂ��Ắw�}�����u�Ƃ��Ă̎��Ɓx�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�S���鋳�t�́C������u�w�͒�ʑw�v��u�w�K�ӗ~�̂Ȃ��v���k�����ƂɈʒu�t���悤�Ƌ������鋳�ފJ����C�O���[�v�ł̊w�K�`�ԁC�܂��́C���ی��K�����铙�̑Ή�������Y���Ă���B����e�X�g�O�ɁC10�_�ȉ��́u����ׂāI�v�Ǝv���C���ی�ɕ�K������B�قƂ�ǃe�X�g���Ɠ��l�́u���������v����n���C���������ËL������B����ł��C10�_�ȉ��̓_���������Ȃ��B���ƒ��C����ɂ͂Ƃ��ɂ͓����邪�C�����͏����Ȃ��̂Ŕ����ʂ����Ƃ��Ȃ��B�u�����I�@������I�v�ƈꉞ�͒��ӂ���B���Ƃ���̂��C���ŁC�U�����̏I��肩���ɓo�Z���鐶�k�B���̐��k�����́C���̂܂ܕ��u����C�e�X�g�͂O�_�B�܂��܂��ӗ~���Ȃ����̂ŁC�e�X�g�O�͎���Ŋw�K����B������ƒ닳�t�ł���B�w�Z�ł́C�����Ă���p��������̂͒p�����������������C�ƒ�ł͂��َq��H�ׂȂ���a�₩�Ɋw�K�ł���B�܂����ƒ��C���C�悭�������āC�Ȃ��Ȃ���D�����Ǝv���Ă�����C����̓����ɊԈ�����Ƃ���ɁC�z�z�����v�����g���ۂ߂āC�ӂĐQ�B�u�����I�@�����˂Ă�˂�I�v�Ɗ�������Ƃ܂��܂����˂Ă�B���̌�͕��u�I
�@�����Ȋw�Ȋw�͒���45�ʂ̑��{�̕��ς�肳��ɒႢ�C�����s�̂�����ƕ��i�ł���B���̂悤�Ȑ��k���������������Ɗw�K�ł���藧�Ă��l���Ȃ���C���Ƃ͕s�����ɂȂ�B
�@�܂��C����ŁC�u���́v�����݂���B������u�ł��鐶�k�v�́C�e�X�g���ɏo�肳��Ȃ��悤�ȎG�l�^�ɂ͋����������Ȃ��B�m�[�g�ɗ����������Ă��鐶�k������C���ȏ��̑��̃y�[�W��ǂ�ł���B���u����Α����Ȃ̖��W�ł���肩�˂Ȃ��B�������w�Z�̎��Ƃ́C���́u�w�͍��v�̂��鐶�k������ΏۂɎ��Ƃ�W�J���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����C�t�����������w�͂Ƃ́@�`�V�w�K�w���v�̂̎�|�`
�@����24�N�x�Łu���w�Z�Љ�ȉ����̎�|�v�ɂ����āu��b�I�E��{�I�Ȓm���C�T�O��Z�\�̏K���ɓw�߂�ƂƂ��ɁC�v�l�́E���f�́E�\���͓����m���ɂ͂����ނ��ߌ��ꊈ���̏[����}��C�Љ�Q��Ɋւ���w�K���d�����邱�Ƃ��K�v�ł���v�Ə�����Ă���B�܂��C�u���P�̊�{���j�v�ɂ́C���̂悤�ȋL�q������C���̓��e��������̎傽��˂炢�ƍl������B
�@�Љ�I���ۂɊւ����b�I�E��{�I�Ȓm���C�T�O��Z�\���m���ɏK�������C���������p����͂�ۑ��T������͂��琬����ϓ_����C�e�w�Z�i�K�̓����ɉ����āC�K�����ׂ��m���C�T�O�̖��m����}��ƂƂ��ɁC�R���s���[�^�Ȃǂ����p���Ȃ���C�n�}�ⓝ�v�ȂNJe��̎�������K�v�ȏ����W�߂ēǂݎ�邱�ƁC�Љ�I���ۂ̈Ӗ��C�Ӌ`�����߂��邱�ƁC���ۂ̓��F�⎖�ۊԂ̊֘A��������邱�ƁC�����̍l����_�q���邱�Ƃ���w�d����������ʼn��P��}��B
�@�����ŏq�ׂ��Ă���u�K���v�u���p�v�u�T���v�����āu�Q��v���C�L�[���[�h�ł���B�O�q�����n���I����ɂ����ẮC�啝�ȉ��肪�s��ꂽ�B���E�n���w�K�ɂ����ẮC�U�B�̒n����C���{�n���w�K�ɂ����Ă͂V�n���敪�ɂ��w�K���s����B�������C���̂��Ƃ��ËL�Љ�Ȃւ̉�A�ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ɁC���{�n���w�K�ɂ����ẮC�u���R���𒆊j�Ƃ����l�@�v�u���j�I�w�i�𒆊j�Ƃ����l�@�v�ȂǂV�̊�ɂ��C���j�����ɂ��u���ԓI�n���v�w�K������Ă���B��ɁC�n���I����𒆐S�ɏq�ׂĂ������C���j�I����ɂ����Ă��u�w�K�������e�����p���đ�ς��\�����銈����ʂ��āC���̎��オ�ǂ̂悤�ȓ��F�������ゾ�������𑨂���w�K�v���C�����Č����I����ɂ����Ă��u�Η��v�u���Ӂv�Ɓu�����v�u�����v�Ƃ����T�O����Љ�I���ۂ͂��邱�Ƃ��d�����Ă���B���̉����|������ɍ������藧�Ă��l���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�V�w�K�w���v�̂Łu�K���v�u���p�v�u�T���v�Ƃ����w�͂�w�K���@����������Ă��邪�C���̂R�́C�����ĐV�������̂ł͂Ȃ��B�������C�Љ�ȋ���̕ϊv�ɂƂ��āC���̂��Ƃ͏d�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�C����܂ł̊w�K�ɂ����āC���Ǝ҂́C���̂R�̊w�͂�w�K���@�����܂�ӎ������Ɏ��H���Ă�������ł���B���̂��Ƃ��ӎ����邱�ƂŁC�u�ËL�Љ�ȁv����E�炵�C�u�v�l�́v�u���f�́v�u�\���́v��g�ɕt������Ƃւƕϊv�ł���`�����X�ł���B
�@�M�҂��ł��d�����Ă���_�́C�u�w�K�ӗ~�v�Ɓu���p�v�u�T���v�Ƃ̊W�ł���B�g�ł���q�h���u���p�E�T���v�́C�g�ł��Ȃ��q�h���u�K���v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��C���ׂĂ̐��k���g�y�����킩��h�����āC�u�v�l�́v�u���f�́v�u�\���́v��t������Ƃ�W�J����K�v������B
�@�{���Ɏ��^���ꂽ���H�́C��L�Љ���C������g��������h�Ȑ��k�������C����Ȃ�Ɂg�������h�g�l���h�g�����h�������Ƃł���B�u�r��v��u�w�K�ӗ~�v�̂Ȃ����ŁC�u�K���v�����܂܂Ȃ�Ȃ����w�Z����ɂ����āC�q�ǂ����ӗ~�I�Ɏ��g�݁C�u���p�E�T���v�͂�|�����Ƃ̖���N�ł���B
�@�@2012�N�T���@�@�@�^�͌��@�a�V
-
 �����}��
�����}��- �H�v����Ă������낢2015/5/1650��E���w�Z����
- �����ɏЉ�ꂽ���X�̋��ނ́A�g���t��������ׂ����e�h�ƁA�g�q�ǂ����w�т����Ǝv�����Ɓh�̊Ԃɂ���傫�ȃ~�]�ɂ�����ꂽ�g�˂����h�ł��B���ƂɎQ�����Ȃ����k�����Ȃ��搶�����炱���J�����邱�Ƃ��ł����A���͓I�Ȕ���A���o�E���m���ށA���ƓW�J�A�l�^�ł��ӂ�Ă��܂��B�u���͂��̎�ŗ������I�v�ƁA�O�������Ȃ����Ƃ̋L�q�����ɁA�ǂ�łĂ��đS���O���邱�Ƃ�����܂���B�V���[�Y�R���̒��ōł������[���ǂ݂܂����B������K�̂��Ƃ��ɁA���E��ڎw���w���ɁA���Ƃ𐬗����������Ɗ肤�搶�ɁA�Ȃ��Љ�Ȍ����ɂȂ����낤�H�ƁA������ł��u���w�n���v���w�тȂ����Ă݂������X�ɁA���Гǂ�ł���������������ł��B2012/8/25khunyuri