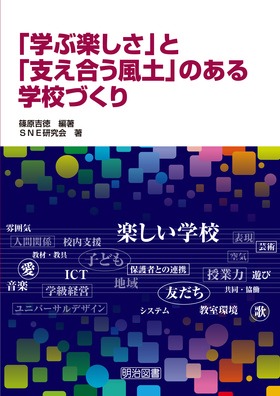- はじめに
- 1章 学校全体で取り組む「楽しい学校」づくり
- 1 「サラマンカ声明」から考えること
- 2 「ホール・スクール・アプローチ」を採って特別支援教育に取り組む
- 3 「楽しい学校」とは
- コラム Dで始まる英単語は,特別支援教育のKey Words?
- 2章 「楽しい学校」づくりのための工夫
- 1 私たちの考える「楽しい学校」
- 2 「楽しい学校」づくりのための校内支援システム
- 3 楽しい“居場所”を生み出す連携〜「苦戦」する子どもを担任と支援チームで支える〜
- 1.通級指導教室担任の支援を活用した事例
- 2.特別支援教育支援員を活用した事例
- 4 虐待を受けている児童への支援〜公立小学校の取り組み〜
- 5 高等学校における支援の進め方〜「5W1H」と3つの「co」〜
- コラム 知的障害特別支援学校ってどんなところ?
- 3章 「楽しい学校」をめざした授業づくり
- 1 国語
- お話の世界を楽しむ〜通常の学級と個別支援級共同の授業〜
- 2 国語
- 誰もが同じ「学ぶ喜び」を〜プロジェクタを活用した授業〜
- 3 書写
- 書くたびに上手くなる楽しい学習
- 4 算数
- 「頭を使う学習」を保障する〜子どもたちにとって「楽しい,おもしろい」教科とするために〜
- 5 数学
- 学習の定着に遅れが見られる子どもに対する支援
- 6 理科
- 一人ひとりを生かす個別実験〜「電流回路」を例に〜
- 7 英語
- ゲーム感覚で楽しく身につける入門期の授業
- 8 音楽
- 「耳を澄ます」「音の変化を聞き分ける」ことを大切にした授業
- コラム 「特別支援学校」になったけれど……
- おわりに
はじめに
特別支援教育が始まって,はや3年が経過しようとしています。日本の,障害のある人々への教育は,平成22年4月には,京都の盲唖院の創設から数えて,131周年を迎えることになります。日本国憲法下,教育基本法の制定以降に時代を区切っても,我が国の特殊教育は60有余年の歴史を誇っています。この間に,数知れぬほどの経験がなされ,定立された指導原理,打ち立てられた指導論,そしてまた,蓄積された知識や技法は膨大な量に上ります。
特別支援教育は,先人たちが獲得し,築き,遺してくれた,これら多大な資源を継承するとともに,充実・発展させることに努めながら,今日,その取り組みがなされています。しかし,特殊教育から特別支援教育に切り替わって間もないこともあり,特殊教育の残滓が一掃されていない(特殊教育の問題点や課題がことごとく解決されたわけではありません)ばかりか,これまでの特殊教育には欠けていた,学校が総体として,障害のある子どもたちに対しても,教育(的支援)に当たる視点が,今なお,必ずしも確立されているとは言えません。
私は,学校全体,つまり,教職員全員が一体となり,支援教育に当たることができるかどうか,がこれからの特別支援教育の帰趨を決する要因の1つに挙げられる,と考えています。本書は,こうした考えが貫かれて編集されていますので,学校挙げて取り組むことの重要性が随所で強調されるとともに,この考え方に基づく指導の仕方が具体的に示されています。
上記の特殊教育の「残滓」の1つに数え上げられる―この理由として,特殊教育がもともと,小学校や中学校で行われる教育とは「区別」される教育として始められたことも挙げなければなりません―ものとして,特殊教育が,文字どおり,「特殊」であることが強調されたことに付随して,特殊教育の「専門性」が過大視され,それが,今なお続いていることがあります。これが,小学校や中学校の先生方には,障害のある子どもの教育については,特殊教育を担当される「専門家」である先生方にすべてを委ねることこそが最善の策である,と思い込ませるような事態を招いているのではないでしょうか。私には残念なことに思えるのですが,特別支援教育の進展を妨げるような桎梏として,先の「残滓」が存在します。
特別支援教育の実施に合わせ,教育現場では,「連携」が関係者の口の端に上るようになりました。小学校教育や中学校教育と特殊教育の間に横たわる溝を覗き込んでは,関係者は一様に,「連携」の必要性を認め,受け入れざるを得なくなったのでしょう。障害のある子どもへの「支援」は,教育だけでは問題解決が図られるものではないことの認識に加え,彼らへの支援の「専門性」に関し,学校そして教員に欠落していることや不足していることを補い,埋め合わせることを意図した,ことに学校の外部にある人的・物的資源の積極的な活用という観点から,「連携」が要請されることになった,と考えられます。したがって,学校の先生が,同僚である教員と,また,学校外の医療,福祉,労働等,各分野の専門家と「連携」し,支持されながら協働することは,特別支援教育の取り組みにおいてとりわけ重要なこと,と言えます。しかし,こうしたことにとどまらず,小・中学校の先生は,自らを,教科学習を指導するエキスパートであるとの矜持を抱いて,特別支援教育に臨むことは,これからの特別支援教育にとってきわめて大切なことである,と思います。1人でも多くの先生方が,初等・中等教育のスペシャリストであることを自覚し,自分の専門性を発揮することにより,想像力を働かせ,思案を巡らし,創意工夫しながら,特別支援教育への貢献を図ってもらうことを切に願っています。
本書は,上で述べたような私たちの思いを,メッセージとして発信するために出版されました。
2010年1月 編著者 /篠原 吉徳
-
 明治図書
明治図書