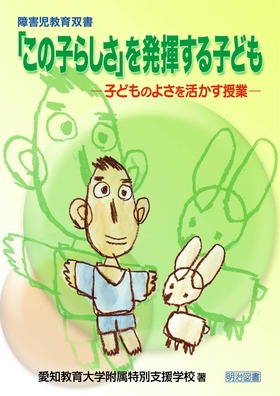- まえがき
- プロローグ
- 第1章 子どもの姿と「この子らしさ」
- 1 子どものよさを見つめる
- 2 子どもの日常の様子から「この子らしさ」をおさえる
- (1) 朋絵の日常の様子と「この子らしさ」
- (2) 朋絵にいくつもある「この子らしさ」
- 3 「この子らしさ」を授業で発揮する子どもの姿から
- (1) 何度も活動に取り組んだ栄治
- (2) いくつかの「この子らしさ」を別々に発揮した敦夫
- (3) いくつかの「この子らしさ」を関連して発揮した敦夫
- 第2章 子どもへの願い
- 1 子どもたちの日常の様子
- 2 子どもの「今の姿」,「もとめる姿」と「この子らしさ」
- 3 子どものよさを活かす授業
- 第3章 「この子らしさ」を授業に活かす
- 1 「この子らしさ」を発揮して,活動に取り組む子ども
- (1) 楽しく繰り返し活動に取り組む麻衣子
- (2) 麻衣子が「この子らしさ」を発揮できたのは
- 2 授業で「この子らしさ」を発揮するために
- (1) 麻衣子の「この子らしさ」をおさえた日常の様子にある「状態」
- (2) 日常の様子にある「状態」を授業にとりいれる
- 3 授業で「この子らしさ」を発揮する子どもたち
- ビー玉で遊ぼうとして,何度も台に上った崇士〔小学部 体育科〕
- 食べ物の名前が書かれた文字カードを読んで,欲しい食べ物をたくさん伝えた秀夫〔小学部 国語科〕
- 歌詞の一部が繰り返される曲を聞いて,木琴を鳴らし続けた久也〔小学部 音楽科〕
- いろいろな素材をいくつも貼り付けて,自分のイメージしたロボットを作った乃武〔中学部 美術科〕
- 何度もボールを投げて,たくさんの的を倒した秀光〔中学部 保健体育科〕
- 第4章 「この子らしさ」で授業をつくる
- 1 「この子らしさ」を関連して発揮する子ども
- (1) 「この子らしさ」を発揮して,「美術科におけるもとめる姿」に迫った利美
- (2) 利美が「美術科におけるもとめる姿」に迫ることができたのは
- 2 「この子らしさ」が関連して発揮される授業づくり
- (1) 利美の「今の姿」と「もとめる姿」
- (2) 利美にいくつもある「この子らしさ」のなかから,授業で利美が発揮する「この子らしさ」をとりあげる
- (3) 「この子らしさ」が関連して発揮される学習活動
- ア 「組み合わせた状態」をとりいれた学習活動
- 楽しく遊んでいる友達と一緒に電車ごっこをして遊んだ拓己〔小学部 タイム学習〕
- 輪郭線に沿って手を動かし,イルカに色をつけた良樹〔小学部 図画工作科〕
- くぼみと同じ長さのお菓子を選んだ篤史〔小学部 算数科〕
- 音や様子を表すことばを付け加えて話した凉〔中学部 国語科〕
- クラブの振り幅を変えて打った菜奈江〔中学部 保健体育科〕
- 貼る場所に沿わせてテープを引き出してから切り取った順平〔中学部 職業・家庭科〕
- 車の絵に,ドアミラーやヘッドライトをかき加えた仁志〔中学部 美術科〕
- 友達に声をかけ,レンガブロックを二人で運んだ貫二〔中学部 タイム学習〕
- 曲のさびの部分を,それまでより大きな声で歌った公太〔高等部 音楽科〕
- いろいろな色のパネルを使って,ボードを飾り付けた鴻志〔高等部 タイム学習〕
- イ 「組み合わせた状態」が変化する学習活動
- 文字を一文字ずつ見て,すべての文字を読んだ知也〔小学部 国語科〕
- 曲調に合わせて,小太鼓を強く打ったり,弱く打ったりした博文〔中学部 音楽科〕
- 三つの文を見て,異なっていることばをゆっくり読んだ茂男〔高等部 国語科〕
- ひざを一度曲げ伸ばしした後,もう一度深くひざを曲げて跳び上がった正文〔高等部 保健体育科〕
- 3 「この子らしさ」を活かした作業学習
- (1) 本校の作業学習
- ア 高等部の作業学習
- イ 中学部の作業学習
- (2) 作業学習で「この子らしさ」を関連して発揮する子どもたち
- ミシンの速度を変えて直線縫いをした友子〔高等部 縫製班〕
- 細長い粘土の両端を印に合わせて同時に置いた亜美〔高等部 窯業班〕
- 一つの作業を続けて数回行い,次の作業に移った賢司〔高等部 木工班〕
- 第5章 「この子らしさ」を関連して発揮して,「もとめる姿」に迫る子どもたち
- マレットを大きく振り上げて,大きな音で太鼓を鳴らした祐二〔小学部 音楽科〕
- 絵で表した自分の口に,ハンバーガーを重ねてかいた恵梨〔高等部 美術科〕
- 小さなウサギを見て,「ウサギがちっちゃい。」と言った夢奈〔中学部 国語科〕
- 異なる形をした図形の同じ長さの辺を合わせて,花を作った晴美〔中学部 数学科〕
- エピローグ
- あとがき
- 研究同人
- 「この子らしさ」を発揮する教具
まえがき
本校の教師は子どもをほめます。子どもを見つめ,よい姿を見逃さないように努めています。心のこもった称賛のことばは,子どもに喜びと自己肯定感情を与えます。そのことは子ども同士の関係にもよい影響を与えます。日常のなかでも,授業のなかでも,子どもたちが支え合い,励まし合う姿を見ることができます。
本校の教師は,保護者の意見に耳を傾けます。自分の授業ですら,保護者の意見を取り入れることで改善していきます。自分の子どもを中心に見ている保護者の意見を参考にするからこそ,教師は「一人一人を生かす」授業を実践することができるのです。
本校は昭和42年6月の開校以来,「一人一人を生かす」を教育理念とし,教育研究活動を継続しています。個々の子どもの特性やニーズに合わせて個別の指導計画を立て,それに基づいて支援を行っています。だからこそ,研究協議会の参加者から,「小学部さくら学級の授業では,教室に先生の机がなく,鴨居の上にラジカセが置いてあるのが印象的。遊園地のような感じ。子どもがかわいらしく,先生がタフであり,T.Tが機能している。」,「高等部の授業や作業学習では,生徒たちの真剣さとまじめさが目に付いた。適切な補助具を用いることで,正確に粘り強く作業ができていると思った。」,「小学部から高等部まで,子どもたちが確かに成長していることがわかった。」という意見を寄せていただくことができているのだと考えます。
本書は,平成18年度から,「豊かな生活につながる子どもの姿を求めて」を主題にすすめてきた研究の成果をまとめたものです。また,その研究主題には,平成18年度「この子らしさを探る」,平成19年度「この子らしさを活かす授業」,平成20年度「いくつかのこの子らしさを発揮する授業」,平成21年度「いくつかのこの子らしさを関連して発揮する授業」をそれぞれ副主題として添えてきました。すなわち,「この子らしさ」をキーワードにすることによって,子どもを見つめ,子どもから学び,子どもから出発し,子どもの自立を何よりも重視する教育本来の姿勢を厳守しているのです。しかし,そのことは教師の主体的支援を否定することを意味するわけではありません。わたしたちの姿勢は,次に示す日報(主幹教諭が教職員に向けて作成)の文章に表れています。
教育実習生に次のような話をしました。
わたしたちは,子どもの姿を大切にすると言っています。これは,子どもの姿をただ見ていればよいというわけではありません。例えば,ある子どもが,鉛筆を持って,紙の上にぐるぐると線をかいたとします。この姿を見て,絵をかけない子どもととらえがちです。しかし,その子どもは,鉛筆を持てばぐるぐると線をかけるのです。それならば,クレヨンを持つとどうだろう,紙の色や材質が変わったならばどうするだろう,点線で○や△がかいてある絵を見たとしたらどうするだろうと考え,子どもの周りにある人・もの・ことのありようを少し変えることもしてほしいのです。きっと異なる子どもの姿が見えてきます。
本書が我が国の障害児教育や特別支援教育のいっそうの発展に寄与することができれば,何よりの喜びであります。
最後になりましたが,わたしたちの研究に対して,愛情あふれる厳しいご指導ご助言をいただいた多くの先生方,ならびに,本書の刊行に際して,ご尽力いただいた明治図書の石塚嘉典様,木山麻衣子様,有海有理様をはじめ,編集部の皆様に,心からの感謝を申し上げます。
平成21年9月 愛知教育大学附属特別支援学校長 /舩尾 日出志
-
 明治図書
明治図書