- はじめに
- 第1章 中1担任のマインドセット
- 中1ギャップの正体を探る
- 生徒をみる解像度を上げる
- 「何を育てているか」を意識する
- 見取りの偏りと癖を自覚する
- 生活ノートを活用する
- 「朝の会」「帰りの会」で学級文化を醸成する
- 「学年チーム」「学校チーム」として動く
- 第2章 中1ギャップを防ぐ学級開き
- 「学級開き」の目的を捉え直す
- 初日から「できたこと」を見つける
- 「笑顔で」「目を見て」名前を呼ぶ
- 自己紹介シート+バースデーリングで生徒同士の関係を紡ぐ
- テーマに合わせたペアトークで安心感を醸成する
- 1年間を見通したシステムをつくる
- 引き継ぎ資料を生かして生徒との信頼関係を築く
- 第3章 心理的安全性を高める学級づくり
- 1学期
- すばらしい出会いを演出する
- 誕生日をみんなで祝う
- ランチバズ〜語り合う場づくり〜
- ICT技術を生徒に手渡す
- 「感謝を伝え合う」活動で6月危機を乗り越える
- 生徒が動くのを「みる」「待つ」「喜ぶ」
- プラスのフィードバックを出し続ける
- 2学期
- 一人ひとりに合った言葉で主体性を育む
- 生徒の本気に火を点ける行事マネジメント
- 生徒が変わる三者面談
- 3学期
- 成長の軌跡をビジュアルで見る
- カウントダウンカレンダーで2年生にジャンプ!
- 第4章 安心して学び合える授業づくりの勘所
- 「聴き合う」文化をつくる
- 「わからない」「みんなでわかる」に価値を置く
- 「学習内容」×「感動」で共有体験を積み重ねる
- 1時間に一度はアウトプットの場をつくる
- 友達の名前を入れた自己評価で自尊心を育む
- 部分的に授業の自由度を上げる
- 言葉がけで個の成長を促す
- 第5章 生徒の心が安定する生徒指導の勘所
- 攻めより受けの姿勢をもつ
- 一斉指導と個別指導を使い分ける
- 試し行動を見抜く目を養う
- 「ありがとう」「嬉しいよ」をフル活用して主体性を引き出す
- ヒドゥンカリキュラムを見つける
- 生徒の心を開き可能性を広げる「雑談力」
- いつでもご機嫌で一貫した自分をつくる
- 第6章 学級指導を最大化する保護者との関係づくり
- 保護者を「同志」としてみる
- 全員参加の授業参観で保護者の信頼を獲得する
- 二者面談ではエピソードを1つ用意する
- 電話連絡は「指導事項+プラス面」を伝える
- 丁寧さを意識して保護者の心をつかむ
- 批判的な保護者を強力な味方にする
- ケース別の対応を基に即応力を身につける
- 生徒を信じる思いを共有する
- おわりに
はじめに
「学級経営はね、学級の文化をつくるんだよ」
15年ほど前、附属小時代に一緒に学年を組んでいた先生の言葉です。筑波大学附属小学校の算数部のある先生から学んでいた方で、当時のわたしが憧れてやまない学級をつくっていました。校種は異なりますが、今のわたしの学級づくりの主軸はこのときにできたように思います。
文化をつくる、という言葉には様々な要素が含まれています。
安定した生活とメンバーとの関係性。
価値観やルールに対する共通理解。
集団や個で目指す方向性。
メンバーだからわかる共通言語。
集団の雰囲気を含めた、物理的な環境。
これらを問い直し、理論と実践を往還させながら生徒の姿を通してまとめたのが本書です。
英語で文化を示す「culture」は「耕す」という意味を含みます。学級文化は学級を耕すこと。学級を耕すとは、すなわち人を耕すということです。一人ひとりの心を耕す、人同士のつながりを耕す、生徒を支える家庭と一体となって耕す。鍬と鋤で田畑を掘り起こすと土壌が豊かになり作物が実るように、学級という土壌を耕すことで出会った頃は想像もできなかった生徒たちの姿や成長が見えることを実感しています。
第1章は学級をつくるうえでの「当たり前」となっている文化を見直し、学級の土壌づくりについて書きました。学校の「そもそも」を見直したい方はぜひお読みください。
第2章は学級開きに特化した具体的な実践をまとめました。年間通して実践できることや4月からの種まきについて書いてあります。一つひとつは小さな実践ですが、日々の積み重ねで大きな成果をもたらす活動を集めました。
第3章は1年間の流れに沿った具体的な実践を書きました。できるだけ活用しやすいように順序も考えて載せてあります。
第4章・第5章は学級文化を醸成する場である「授業づくり」「生徒指導」の二軸に焦点を当てて書きました。多様な生徒が同じ教室で学ぶ・さまざまな考えをもつ先生方とともに生徒を育てるという公立中学校の実態を基に、実現可能性を考慮した内容となっています。
第4章は、わたしの専門教科である理科を例に挙げながら、どのような教科でも応用できる単元デザインや活動、技術をまとめました。自由進度学習に憧れるが現実的に難しい、生徒の自由度を上げたいが学習規律が気になる、授業で生徒からの発話が少なく対話が進まない、等のお悩みをお持ちの方におすすめです。
第5章は、生徒と接するうえで特に配慮している内容をまとめました。おもしろい話ができなくても、キャラが突き抜けていなくても、教師の眼差しと働きかけ次第で生徒は心を開いてくれます。
第6章は、今多くの方々が苦労されているときく保護者対応です。わたしはありがたいことに、多くの保護者の方々と良好な関係を築かせてもらってきました。この章に関しては無自覚な部分も多かったため、周りの先生方に言語化してもらいながら書きました。すべてわかり合うことは難しいことを前提に、でも希望をもてるようにまとめています。先生方の悩みに寄り添い、心を軽くする一助となれたら幸いです。
すべて、生徒の実態に応じて合うものと合わないものがあると思いますので、網羅して実施するというよりも、生徒の実態に応じてカスタマイズすることをおすすめします。
豊かな文化の中には、網の目のような人々のつながりと対話があります。実体のないつながりの中で承認されることに居場所を求めてしまう社会だから、リアルなつながりの中で認め合い、愛され、満たされる経験を積み重ねてほしいと切に思います。経験格差という言葉が示すように、生まれた場所や環境によって人生が大きく左右される現代だからこそ、豊かなつながりの中に広がる学級という小さな社会に、大きな価値があると考えています。
本書が生徒たちと先生方のつながりと幸せをつくるきっかけとなれたら、これほど嬉しいことはありません。
2025年1月 /瀬戸山 千穂














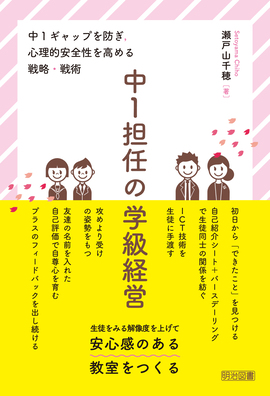
 PDF
PDF


p26の授業は素敵だな〜と感じました。
授業と行事をつなげる大切さを実感しながら
授業は授業
行事は行事と 別になってしまうことがあります。
しかし、この授業を通して行事とつなげている。
基本的なことではあるが、忘れてしまうことだと思います。子ども達の意見も4月からそのあたりを指導していたから、このような意見が出るのだと思いました。