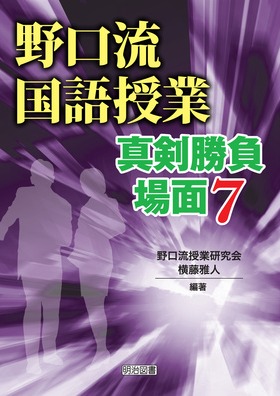- まえがき
- 1 自分の一歩を踏み出すために~見当をつける~ ○2年詩「うとてとこ」
- 1 「うとてとこ?」
- 2 「う」って何?
- 3 「うとうとうとうと」
- 4 考えには訳がある
- 5 三連はあるのか? さあ、ここが見当をつけて判断する正念場
- 6 野口先生からの宿題
- 2 「逆接」が読みを深める 詩の授業から ○3年詩「イナゴ」
- 1 授業の始まり
- 2 教材との出会い
- 3 八つの発問で読み進める
- 4 授業の終わり
- 3 学習用語で展開する作文指導 ○4年作文「前期を振り返って」
- 1 「プランくん」が足りない!
- 2 仕切り直し
- 3 「前期を振り返る」は題名か
- 4 判断と根拠
- 5 もっとハート
- 6 長所と短所
- 7 マイナス型、プラス型
- 8 題名を書く
- 9 つけた題名を検討する
- 10 具体的ということ
- 4 野口流授業は「見える授業」である ○5年物語「大造じいさんとがん」
- 1 授業前夜
- 2 すっきりと見える授業
- 3 見えるメッセージ
- 4 緊張から緩和へ
- 5 見える指示
- 6 見える学力
- 7 状況の論理による板書
- 8 見える距離感
- 9 見える発問
- 10 見える思考法
- 11 即時・即応指導
- 12 言葉の意味を教えるから国語の授業
- 13 見える授業から見えること
- 5 複合語で言葉の面白さを知る ○5年言語事項「言葉の組み立て」
- 1 授業の始まり
- 2 教材の選択
- 3 題名→単語→複合語(複合語の説明と確認)
- 4 「 」の文の読み方
- 5 ゴジック体、教科書体、明朝体
- 6 複合語→名詞、動詞
- 7 複合語の組み合わせには、色々ある
- 8 複合語を、単語に分ける
- 9 複合語で、読み方が変わる
- 10 複合語を集める
- 11 終わりに
- 6 「もっと知りたい! もっと考えたい!」 ○6年詩「船」
- 1 当たり前のことを問い直す
- 2 学びに向かう姿勢を鍛える
- 3 無意識の中にヒントが
- 4 目指せ! 百点
- 5 野口先生が残してくださった財産
- 7 「判断=根拠」が流行語に ○6年詩「船」
- 1 詩というもの
- 2 二編のうち好きなのはどっち?
- 3 最高の読みを
- 4 どこで分けるか
- 5 簡潔に話せ
- 6 さらに分かれるところは
- 7 音読で表現する
- 8 この詩のテーマは?
- あとがき
まえがき
学兄、かつ盟友の横藤雅人校長先生との御縁によって、平成二十二年の九月中旬、札幌市と北広島市にある四つの小学校で連続して四日間にわたる授業と講演をさせていただく機会に恵まれた。二十三歳で小学校の教師になって此の方、私はずっと国語科を中心に授業研究を続けてきた。ざっと五十年、半世紀もの長きにわたって子どもとの授業に明け暮れてきたと言っても過言ではない。お陰様で七十四歳になった今でも、全国各地の小学校や中学校、時には幼稚園や高校にも御縁をいただいて実際の授業を楽しんでいる。私の場合は、実際の授業と講演とがセットになって依頼されることが大半である。
授業そのものは、学校の教員ならば誰でも毎日実践していることであるが、いざそれを公開して見せてくれと頼まれると尻込みをする人が多い。教師ならば最も日常的に行っている、最も得意とする仕事である筈なのに、と思う。私は、若いころから「頼まれたら断らない」ことをモットーにしてきた。私如きが指名をされて役に立つことができるなら、身に余る光栄だと考えるからだ。授業は生きものだから、上手くいったりいかなかったりする。当然のことだ。しかし、上手くいけば小さな自信につながるし、失敗すればそこから学んで向上に努めればいいのだから、上手くいこうといくまいと、自分のためには大いに有益なのだ。そう考えれば、断る理由などなくなってくる。
講演や講話をする研究者は多いが、その人に「授業をして見せてほしい。」と頼むとほとんど断られる。「授業は勘弁してくれ。」と言う人が多い。そういう人が授業について講演をし、そういう人の話をありがたがって聞くというのも、考えてみれば妙なことだが、依然としてその事実は日本中に溢れている。私の場合は、授業と講演がセットになっているので、できもしないことは言えない。できることしか言えない。だが、それだけに実際的だし、具体的な話になるので、私の話は、「わかりやすい」とよく言われる。それもまた当然のことだろう。
たまたま明治図書出版の樋口編集長さんから、いかにも野口流だという国語の授業のダイジェスト版を作らないかとお誘いをいただいていたことを思い出した。北海道での四日間の授業は、随分熱心に参観され、記録もされていたので、よいチャンスと考え、今回の刊行に結実することになった。私の授業について私が書き下ろすのではなく、参観者が、感じとり、考えたことを自由に、率直に書いてもらう方が、読者にはよく伝わるだろうからという編集長の意向に沿って、本書では、それぞれの執筆者に自由な書き方で書き下ろしてもらうことにした。あえて形を揃えない方がバラエティーに富む報告や分析になって面白いだろう、と考えたからである。そんな訳で、本書には様々な語り口、切り口での授業の分析と報告がなされている。どのような報告のスタイルが授業の実際をよく伝えることになるか、読者諸賢の評価をぜひ聞きたいところである。
私の授業にかける思いは、次のようにまとめることができる。私が常に心がけている五か条と言ってもよい。
① 学力形成の連続的保障―授業の根本使命は「学力形成」という一点にある。「見える学力、使える技術」を具現しよう。
② 全員参加、全員当事者―一人の傍観者も作ってはいけない。常時全員当事者たる授業を作りたい。
③ 根本、本質、原点に立脚―授業は指導の一環であり、指導は教育の一環である。教育の根本、本質を踏まえることが肝要だ。
④ 向上的変容の自覚と快感―「できることより変わることが大切」なのだ。向上的に変容したという快感を重視したい。
⑤ 面白さ、楽しさの実感―授業を終えた時に、面白かった、楽しかったという知的な快感を多くの子どもらにぜひ味わわせたい。
これらを具現するために、私の常用する授業の手法には次のようなものがある。
ア 作業学習の多用。(ノートに自分の考えを端的に書かせる。作業は密室的に行われる。正直な考えが生まれる。)
イ 立場の仮定、決定。(ノートに賛否を○や×で明示させる。自分の立場が決まると人の立場が気になってくる。)
ウ 発言はずばり一言で。(長い発言は雑物を混入させる。短く、端的に、ずばりと言えるように育てる。)
エ 否定の生産性を重視。(否定されることを感謝で受けとめるよう導く。否定ほど成長を促すものはない。)
オ 価値ある強制、善意の強制。(教育に「強制」はなじまない、強制はタブーだ、という俗説に対する私の抵抗。)
実際の私の授業記録を読まれると、これらのことが「なるほどなあ。」と頷ずけることだろう。また、私は「授業の主役は子どもだ」という俗論にも反対している。授業の主役は教師であり、子どもは熱心な観客であり、受益者である。舞台で演ずる主役教師の見事な演技に夢中になり、また見に来たいと思わせるような授業こそがよい授業なのである。授業の主役が本当に子どもであるのなら、授業研究は子どもに委ねたらいい。主役こそが最も熱心にその演出や演技を研鑽すべきだからである。このような洒落た俗論が、どれほど授業の質を低下させていることか。その罪は重い。
さて、本書が形を成すにあたり、四つの小学校の執筆担当をしてくださった先生方には大変な手数をおかけすることになった。それらをすべて集約し、体裁を整えてくださったのは横藤雅人校長先生である。そうでなくても超多忙の日々を送っておいでの校長先生である。随分なお手間をとらせてしまう結果になり、申し訳なく思っている。私は、すべての文章に入念に眼を通し、私の授業観や実践がなるべくそのまま伝わるようにと若干の加除を為した。初校、二校、三校と手間をかけることになったことに恐縮しているが、読者のみなさんに対して、より確かに伝わるようにとの思いからであることに免じてお許しを願いたい。
どの小学校の子どもたちも、みんなみんないい子どもばかりだった。私は存分に授業を楽しませてもらい、若返った気分でいる。改めて四つの学校の先生方と子どもたちに心からの感謝を捧げる次第である。また、貴重な出版の機会を与えてくださった上に、適切な助言と導きをいただいた明治図書出版の編集長、樋口雅子氏に心からなる御礼を申し上げる。最後に、本書を手にされた読者の皆様にも御礼を申し上げたい。お役に立てればこれに勝る喜びはない。
(野口芳宏記す)
-
 明治図書
明治図書