- “ءڈWپ@‚ا‚¤‚·‚éپH‰p‰ïکb‚ج“±“üپEŒں“¢ƒeپ[ƒ}42
- ‘چچ‡‚إ‰p‰ïکbپ\ژ^گ¬پH”½‘خپH‚»‚ج——R
- ٹy‚µ‚ف‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·
- پ^
- ژO‚آ‚جڈًŒڈ‚آ‚«‚إژ^گ¬
- پ^
- ‰pŒêٹwڈK‚ج“±“ü‚ھ‘چچ‡“IٹwڈK‚ً”j‰َ‚·‚é
- پ^
- ڈًŒڈ‚µ‚¾‚¢
- پ^
- ژہژ{‚·‚é‚ب‚çپu‰pŒê‰بپv‚ًچى‚ê
- پ^
- ‰p‰ïکb‚ح“¹‹ï‚ئ‚µ‚ؤ•Kگ{
- پ^
- ‚ا‚ج‚و‚¤‚ب”\—ح‚ھˆç‚آ‚©‚إ”»’f‚·‚ׂ«
- پ^
- ƒOƒچپ[ƒoƒ‹‰»‚ئ“Kژگ«‚©‚ç‘هژ^گ¬
- پ^
- •غŒىژز‚ة‚àگà–¾‚إ‚«‚é——R‚ھ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©
- پ^
- ”½‘خ——R‚ب‚ا‚ا‚±‚ة‚àŒ©‚ ‚½‚ç‚ب‚¢
- پ^
- ژ^گ¬پ@چL‚¢ˆس–،‚إ‚جƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‘جŒ±‚ئ‚µ‚ؤ
- پ^
- ڈ¬’†چ‚‚جکAŒg‚ً–§‚ةپA‘–‚è‚ب‚ھ‚çچl‚¦‚و‚¤
- پ^
- ‚â‚é‚ب‚ç‚خ‹³‰ب‚ً—§‚ؤ‚ؤ
- پ^
- “ٌڈ\ˆêگ¢‹I‚ج•Kگ{ٹw—ح‚إ‚ ‚é
- پ^
- ‰p‰ïکbٹˆ“®‚ج“ئ’dڈê‚ة‚à‹^–â
- پ^
- ڈ¬ٹwچZ‚إ‰p‰ïکbپE•¶•”ڈبچ§کb‰ï•ٌچگ‚جٹT—v
- پ^
- ‚ا‚¤‚·‚éپH‰p‰ïکb‚ج“±“üپپ‚p‚`‚إ”—‚éŒں“¢‰غ‘è
- پg‘چچ‡پh‘S‘ج‚ة‚¨‚¯‚é‰p‰ïکb‚جˆت’u‚أ‚¯
- پ^
- پg‘چچ‡پh‘S‘ج‚ة‚¨‚¯‚é‰p‰ïکb‚جˆت’u‚أ‚¯
- پ^
- پgچ‘چغ—‰ًپh‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‰p‰ïکb‚جˆت’u‚أ‚¯
- پ^
- پgچ‘چغ—‰ًپh‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‰p‰ïکb‚جˆت’u‚أ‚¯
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپg‹³ژt‚جˆسژ¯•دٹv‚ئŒ¤ڈCپh‚أ‚‚è
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپg‹³ژt‚جˆسژ¯•دٹv‚ئŒ¤ڈCپh‚أ‚‚è
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپgگl“Iٹآ‹«‚أ‚‚èپh‚جƒmƒEƒnƒE
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپgگl“Iٹآ‹«‚أ‚‚èپh‚جƒmƒEƒnƒE
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپgچZ“à‘جگ§‚أ‚‚èپh‚جƒmƒEƒnƒE
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جپgچZ“à‘جگ§‚أ‚‚èپh‚جƒmƒEƒnƒE
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“üپEڈ‰”N“xڈo”‚حپg‚±‚±‚ھٹجگSپh‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- ’†ٹwچZپEچ‚چZ‚ئ‚جکAŒg‚ًچl‚¦‚é—§ڈê‚©‚ç
- پ^
- ‚ف‚ٌ‚ب‚إٹy‚µ‚پA‰pŒê‚إƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“
- پ^
- ‰pŒê‘هچD‚«‚بژq‚ا‚à‚ًˆç‚ؤ‚邱‚ئ‚ًچھٹ²‚ة
- پ^
- ˆê”N–ع‚ة’m‚ء‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢‚±‚ئ
- پ^
- چ،پA’چ–ع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپg‰pŒê‹³ˆç‚ج‰üٹvپh‚جڈذ‰î
- ‚`‚k‚s‚ج‰p‰ïکbپ\ژ„‚ھ‘جŒ±‚µ‚½‚¨ٹ©‚ك‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ”گMŒ^‚ج‰p‰ïکbپ\ژ„‚ھ‘جŒ±‚µ‚½‚¨ٹ©‚ك‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ’nˆو‚إˆç‚قڈ¬‚³‚بچ‘چغگl
- پ^
- 2001”N‰p‰ïکbژِ‹ئٹJژnپپƒEƒIپ[ƒ~ƒ“ƒOƒAƒbƒv‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- ژ„‚ھ‘E‚ك‚éپgƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚أ‚‚èپh‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ژ„‚ھگi‚ك‚éپg‚`‚k‚s‚ئ‚جٹضŒW‚أ‚‚èپh‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ژ„‚ھگi‚ك‚éپgژِ‹ئ‚أ‚‚èپh‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ژ„‚ھگi‚ك‚éپg‹³چقپE‹³‹ïٹJ”پh‚جƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ‰p‰ïکb“±“ü‚ض‚جژq‹ں‚ئ•غŒىژز‚ض‚جگà–¾ƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ژq‚ا‚à‚ح‚ا‚¤ژَ‚¯ژ~‚ك‚½پH‰p‰ïکb‘جŒ±
- گوگ¶‚àˆêڈڈ‚ة‰pŒê‚ًٹy‚µ‚ٌ‚إ
- پ^
- ‚ـ‚³‚ة‰p‰ïکb‚حژq‹ں‚ج‹»–،ٹضگS‚ة‰‚¶‚½‰غ‘è
- پ^
- ‘Sگg‚ً—h‚³‚ش‚éٹw‚ر‚جڈê‚ھƒLپ[ƒ|ƒCƒ“ƒg
- پ^
- ‰ن‚ھچZ‚ج‘چچ‡“IٹwڈK‚جژٹشƒnƒCƒ‰ƒCƒg
- پ^پEپEپE
- ƒCƒ‰ƒXƒg‚إ‘چچ‡“I‚بٹwڈK (‘و9‰ٌ)
- پuٹwڈK‚ج”ى‘ه‰»پv‚ً–h‚®
- پ^
- ‹³‰ب‚ة‘}“ü‚·‚é‘چچ‡“IٹwڈK‚ج’PŒ³‚أ‚‚èƒCƒ“ƒfƒbƒNƒX (‘و9‰ٌ)
- ژذ‰ï‰ب‚ة‘}“ü‚·‚éچ‘چغ—‰ً’PŒ³
- پ^
- ƒhƒCƒc‚ج‘چچ‡“IٹwڈKŒ»ڈꃌƒ|پ[ƒg (‘و9‰ٌ)
- گE‹ئ‘جŒ±‚ئƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA
- پ^
- ‘چچ‡“IٹwڈK‚إ‚·‚éپ\‰pŒêٹˆ“®پg‚¨‚·‚·‚كƒXƒ|ƒbƒgپh (‘و9‰ٌ)
- گi‚ٌ‚إƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ًگ}‚éٹwڈK‰ك’ِ
- پ^
- پ`ٹٍ•ŒŒ§‘هٹ_ژs—§’†گىڈ¬ٹwچZپ`
- ƒXپ[ƒpپ[چZ’·‚ھ‘n‚é‘چچ‡“I‚بٹwڈK (‘و9‰ٌ)
- ژ©Œبگf’fƒ`ƒFƒbƒNƒٹƒXƒg‚ة‚و‚éژ©Œب•]‰؟‚ج‚·‚·‚ك
- پ^
- ƒ|پ[ƒgƒtƒHƒٹƒI‚ھˆç‚ؤ‚éگV‚µ‚¢”\—حپE•]‰؟ (‘و9‰ٌ)
- ژ©Œب•]‰؟‚©‚çƒپƒ^”F’m‚ض
- پ^
- ٹآ‹«‘جŒ±ٹˆ“®‚جƒڈپ[ƒ‹ƒhƒJƒbƒv (‘و9‰ٌ)
- ƒˆپ[ƒOƒ‹ƒg‚ء‚ؤچى‚ê‚é‚جپH
- پ^
- •زڈWŒم‹L
- پ^
- ‘چچ‡“I‚بٹwڈK‚جژٹش‚إژg‚¦‚éƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒgڈî•ٌپEƒAƒ‰ƒJƒ‹ƒg
- ژذ‰ï‹³ˆçژ{گف‚جƒٹƒ\پ[ƒX‚ج—ک—p
- پ^
•زڈWŒم‹L
پ›پc•¶•”ڈب‚جپu‰pŒêژw“±•û–@“™‰ü‘P‚جگ„گi‚ةٹض‚·‚éچ§’k‰ïپv‚حپA‚±‚ج‚UŒژ30“ْپAگR‹c‚جŒo‰ك•ٌچگ‚ًŒِ•\‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@’چ–ع‚³‚ꂽ‚ج‚حپAپu“ْ–{گl‚ة‚ح‰pŒê‚ة‚و‚éƒRƒ~ƒ…ƒjƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“”\—ح‚جŒüڈم‚ھ‹‚‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ئ‚µ‚ؤپAڈ¬ٹwچZ‚إ‰p‰ïکb‚ً“±“ü‚·‚ׂ«‚¾پIپv‚ئ’ٌŒ¾‚µ‚ؤ‚¢‚é“_‚إ‚·پB
پ@‚à‚؟‚ë‚ٌپAچ§’k‰ï‚ج‚ب‚©‚إ‚àپAڈ¬ٹwچZ‚إ‰p‰ïکb‚ج“±“ü‚ة‚حژ^”غ—¼ک_‚ھچف‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ژ^گ¬ˆسŒ©‚حپA
پ@‡@“ْ–{گl‚ھ‹êژè‚ئ‚·‚é•·‚«ژو‚è‚┉¹‚ًپAژq‹ں‚جچ ‚ة‘جŒ±‚µ‚ؤ‚¨‚¯‚خŒم‚إ‹êکJ‚µ‚ب‚‚ؤ‚·‚قپB‡AŒم‚جŒêٹwٹwڈK‚ةژ©گM‚ھژ‚ؤ‚éپB
پ@”½‘خˆسŒ©‚حپA
پ@‡@‰pŒêٹwڈKٹJژn‚ج“Kگط‚ب”N—î‚âٹwڈKژٹْ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حگê–ه“I‚بŒں“¢‚ھ•K—v‚إ‚ ‚éپB‡Aڈ¬ٹwچZ’iٹK‚إ‚حپA“ْ–{Œê‚إŒ¾‚¢‚½‚¢‚±‚ئ‚ًگ®—‚µپA‘ٹژè‚ة‚ي‚©‚é‚و‚¤‚ةکb‚¹‚é”\—ح‚جˆçگ¬‚ھ‘وˆêپBŒ‹ک_‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA
پ@پuڈ¬ٹwچZ‚إ‚ج‰p‰ïکbٹwڈK‚ح‹³ژt‚ھˆê•û“I‚ة‹³‚¦چ‚ق‚و‚¤‚ب•û–@‚ً‚³‚¯پAژq‹ں‚½‚؟‚ھٹy‚µ‚ف‚ب‚ھ‚çچs‚¤‚و‚¤‚بŒ`‚إژہژ{‚·‚ׂ«پv‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚¢‚«‚ب‚è‰p‰ïکbپ\‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ًŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚àپA’N‚ھ’S“–‚µپA‚ا‚¤‚¢‚¤ƒJƒٹƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚ً‚ا‚ٌ‚بژِ‹ئ‚إ“WٹJ‚·‚é‚ج‚©پA—§‚؟‚آ‚‚µ‚ؤ‚éپc‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚±‚ë‚ج•û‚ھ‘½‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB–{چ†‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بٹwچZ‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚بگآژتگ^‚ً•`‚¯‚خ‚و‚¢‚ج‚©پA—lپX‚ب–â‘è‚ًچZ“à‚إŒں“¢‚µ‚ؤ‚¢‚ڈم‚إ‚جƒeپ[ƒ}پAچ،Œم‚جŒ¤‹†‰غ‘è‚ً‚²ڈذ‰î‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پi”َŒû‰ëژqپj
-
 –¾ژ،گ}ڈ‘
–¾ژ،گ}ڈ‘















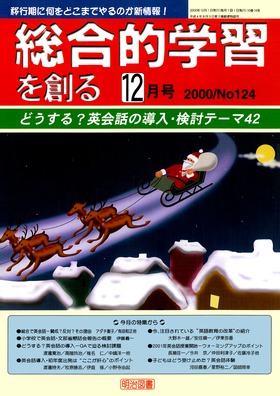
 PDF
PDF

