- 特集 ジェンダー平等教育の現在
- 国際的なジェンダー平等教育の流れと日本
- /
- SAFEプログラム―被害者を責めない安全教育に向けて
- /
- 西成高校チャレンジ学習―シングルマザーを生きる―「そんな生き方もあり、ってこと!」
- /
- 私の心も身体も自由も私のもの―囚われの愛、囚われの性からの脱皮こそ!
- /
- 協働的アプローチによるジェンダー平等教育
- /
- 参加型で気づく、変わる、生活の中のジェンダー
- /
- イギリスにおける「ジェンダーと教育」三〇年と私たち
- /
- 多文化な子どもたちの声にふれる (第17回)
- たのしい校舎
- /・
- 子どもを見る眼 (第26回)
- ひと工夫から生まれたひとさぼりが継続のコツ
- /
- おもちゃばこ (第50回)
- 教室は、誰にとってもここちよい居場所です
- /
- 映画をみる、映画でみる (第25回)
- ジャーナリストの矜持「平成ジレンマ」
- /
- 【コラム】ノリきれない国際開発仕事人のつぶやき (第14回)
- エコ(環境)とエコ(経済)
- /
- 編集部の本棚
- 『拉致―左右の垣根を越えた闘いへ』蓮池透:著/『思春期理解とこころの病―こころと心をつなぐ学習プラン』阿形恒秀、石神亙、中村敏子、森川敏子、山本深雪:編著
- 共生のトポス (第110回)
- すごく支えられているからぼくは揺れない
- /
- まいにち? マイニチ!
- 五月病
- /
- 北のおるた〜北海道からの便り〜 (第18回)
- 紋別における取組みから
- /
- 解放教育・バックナンバー
- 509号〜520号・二〇一〇年四月号〜二〇一一年三月号
- 編集後記
- /
編集後記
▼本号では、ジェンダーの観点からの特集を組んでいます。編集にあたっては、木村涼子さんに全面的に担当いただきました。日本社会における貧困化が大きな問題になり、さまざまな角度から論じられています。この数年の間に、とくに母子家庭の貧困化が注目されてきました。欧米各国と比べると、日本は所得の再分配に失敗している国だといわざるをえません。その影響が如実に表れているひとつが母子家庭だということです。ジェンダーというテーマについて、改めて論じるべき時代になったということもできます。このタイミングでこの特集が組めたことは、大きな意義を持っていると感じます。企画・編集にあたってくださった木村さん、さらに原稿をお寄せくださった皆さんに深く感謝しています。
▼現在わたしは、アジアやアフリカ、中東から来た六人の研修員とともに、識字について研修しています。まずタイに行き、都市部のスラムにおける教育活動、農村地域におけるノンフォーマル教育、高地に住む少数民族の学習活動などにふれました。それぞれが異なる識字の課題を抱えていました。その後、六人の研修員とともに日本に戻り、現場を訪問しながら研修を重ねています。たとえばタイでは、ユネスコの提唱を受けて、エキバレンシープログラムが制度化されています。これは、日本風に言えば、社会教育において学校教育の卒業資格を付与するという制度です。各国からの参加者が日本から何を持ち帰り、それぞれの現場で生かすのかを楽しみにしています。
▼この研修の時期に重なって、東北関東大震災が発生しました。研修中に地震が発生し、研修員のひとりが「これは地震だ」と指摘し、テレビなどで確かめてみたところ、大変な事態が発生していることがわかったのです。被害がどこまで広がるのか、暗澹たる思いですが、日本のわたしたちが、そして世界の人たちが思いを重ね、願いを集めて、いろいろな展開が広がることでしょう。すでに世界各地の人たちから、安否を気遣うメッセージがわたしの所にも届いています。自分自身がこれからの未来にどうかかわれるかを考えたいところです。
(森)
-
 明治図書
明治図書















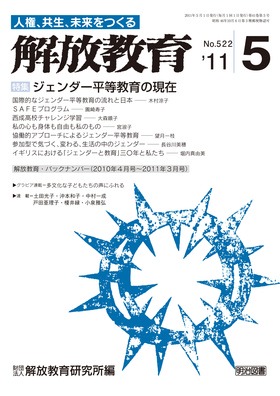
 PDF
PDF

