- 特集 勉強好きにさせる家庭学習の開発
- 提言・これまでの家庭学習どこに問題があるか
- 面白い教材を開発し「はてな?」を残す→家庭学習に
- /
- 家庭学習は授業・評価技術そのもの
- /
- 基礎学力形成が直接の目的ではない
- /
- 効率的で効果的な勉強方法を教えていないことが問題
- /
- 「百マス計算」の宿題は脳科学からみても効率の悪い学習方法である
- /
- 文科省の宿題や補習の奨励は何を意味するか
- 「適切」に行うこと
- /
- 「学びのすすめ」は「自学のすすめ」
- /
- 「授業力」への不安
- /
- 現場報告・なぜ勉強嫌いになるのか
- できないことをやらされるからである
- /
- 我流だらけの指導が勉強嫌いを生む
- /
- 教師の授業のイメージが乏しいと生徒は意欲を失う
- /
- 勉強好きにさせる家庭学習のポイント
- 勉強好きにさせる家庭学習のポイント
- /
- 日記指導を効果的に行うワザ
- /
- 基準を示す ほめる 求めすぎない
- /
- 勉強の面白さをこう教えたい
- 楽しく驚きのある授業をしよう!
- /
- 15分間の基礎学力タイムで、地図帳に慣れさせる
- /
- 学校に来るのはなぜか?を確認する
- /
- 勉強すればできることを実感させる
- /
- 勉強好きにさせる家庭学習の開発
- 国語の場合
- 学校でやったことを家庭でもう一度行う
- /
- 個別評定の基準を入れ、例示し、ほめ続けるだけでどんどんやる気になる宿題
- /
- ノート学習を定着させる
- /
- 社会の場合
- 内部情報の蓄積と確実な知識の習得をめざす!
- /
- 家庭学習は選択制の「自学」である
- /
- 《対策プリント》が生徒の学習意欲を喚起する
- /
- 算数の場合
- ポイントは、「やっていて楽しい、おもしろい」
- /
- 家庭学習を「やる気」にさせる教師の指導
- /
- 数学の場合
- 家庭学習も「向山型数学」でさせるのがよい
- /
- 理科の場合
- 「なぜ、どうして」を連発するコドモ、それを許容できる親が理科好きを育てる
- /
- 勉強好きの子供を育てるには「楽しい宿題」で
- /
- 日常生活と関連付けのある家庭学習
- /
- 楽しいクラスをみんなで創る (第5回)
- 「明るい掲示で楽しいクラス」を創る
- /
- 心を育てる言葉かけ
- 「良い結果」を生む言葉かけを
- /
- 8月の仕事
- 夏休み中の生活指導―重点をどこに置くか
- ラジオ体操に必ず出るべし
- /
- リズムのある夏休みの生活は「生活表」から
- /
- ゲームの時間はルールを決めて
- /
- 夏休みには「おもしろ発見」をお手紙で
- /
- 直接会って変化を見逃さない
- /
- 学級経営力を高める研修―テーマのしぼり方
- 授業改善に結びつく研修会へ出よ
- /
- 子どもの示す事実と数値からテーマをしぼる
- /
- 校内研修をフル活用する
- /
- TOSS講座で最高の授業のイメージと段取り力を学ぶ
- /
- 教室掃除は、ほうき何本を割り当てているか
- /
- 学級の教育力を生かす学習集団の再構築 (第5回)
- メッセージを「聞き分けあう」学級づくり
- /
- 子どもは仲間集団によって育つ (第5回)
- 女子集団を理解しよう―佐世保の事件を繰り返さないために―
- /
- 「学級経営力」を高める私の修業 (第5回)
- 学級づくりの出発として向山氏の学級経営案の骨格・構想を追試、そして私家版経営案を作成する
- /
- 酒井式で子どもの絵が変わる (第5回)
- おすすめ、夏休み前後にやる題材「虫と遊んだぼく、わたし」
- /
- 効果的な勉強法のすすめ (第5回)
- 小学校低学年/おすすめの雑誌、研究会、脳の本
- /
- 小学校中学年/最先端の脳科学からみた教材の良し悪し
- /
- 小学校高学年/夏休みの効果的な勉強法
- /
- 学級担任の責任を問う (第5回)
- 不審者侵入事件の「責任」はどこにあるのか
- /
- 編集後記
- /
編集後記
〇…文科省が「学びのすすめ」で宿題や補習の奨励をしたことから、現場では改めて家庭学習の在り方をめぐって話題になっています。学びの機会を充実させるとして「適切な宿題や課題など家庭における学習の充実を図ることにより、子どもたちが学ぶ習慣を身に付ける」と文科省は言います。
〇…家庭学習と宿題は必ずしも同じではないという説がありますが、今日ではほとんどの家庭で、家庭における学習の独自性を失い、学校の教師の課した宿題が家庭での学習となっているようです。今では宿題がなければ家庭学習の成立はないとまで言われています。
〇…しかし多くの教師の間では、宿題の是非をめぐってなかなか意見の一致が見られないという説もあります。今回の「学びのすすめ」は宿題や補習を奨励していることから家庭学習としての「宿題」の在り方が注目されているわけです。つまり宿題によって学習内容に習熟し、子どもの学力を鍛えることが出来るというわけです。
〇…ただし家庭学習の教材開発を進めるだけでは、勉強意欲は高まらないという指摘も出ています。勉強意欲を阻害したままでは家庭学習の成果は期待出来ないというわけです。そのためには、(1)目的を知らせないで勉強を強制したり、(2)目標を決めないで勉強をさせたり、(3)勉強の結果がどうであったか、進歩の程度を分からせなかったり、(4)適切な勉強のやり方を教えなかったり、(5)子どもの自発性や自主性を認めなかったり等々、していては「勉強好き」になることは期待できないかもしれません。
〇…本号は、子どもが「勉強好き」になる家庭学習の開発を改めて考えてみたいとする特集です。
(江部 満)
-
 明治図書
明治図書















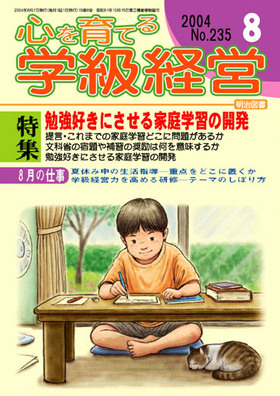
 PDF
PDF

