- 特集 今、中学校の生活指導を考える
- 今、中学校の生活指導を考える
- /
- 実践記録 今、中学校の生活指導を考える
- 学び・グループからの学校づくり
- /
- 自治と共同の世界をめざして
- /
- 学びと出番をつくり、市民を育てる学校づくりを
- /
- 分析
- 今、中学校実践の困難さの中で
- /
- 今こそ、中学生の生きるちからを育てる学校を
- /・
- 第2特集 学校の中のもう一つの居場所
- 実践記録 学校の中のもう一つの居場所
- 個を集団へ、そして学級・学校・社会へ
- /
- ツッパリ学習会とは
- /
- 学校における「もう一つの居場所」―複数の共同(世界)を考える―
- /
- 関係図書紹介
- 「もう一つの居場所」から学校を問い直すために
- /
- 今月のメッセージ
- 肯定と共感のメッセージを
- /
- 風の声―この人に聞く
- 「『非行』と向き合う親たちの会」ってどんな会?
- /
- 21世紀の生活指導を探る (第5回)
- 子どもの世界を生きる―障害児学級の中の教師と子ども―
- /
- 案内板 集会・学習会のお知らせ
- 書評
- 『不登校になった時、先生とどう向き合う?』
- /
- 読者の声
- 6月号を読んで
- 全生研第44回全国大会基調提案
- 新自由主義的な学校解体に抗して、新しい学校づくりと子ども集団づくりを構想しよう
- /
- 基調提案を読んで
- /
- 〜基調提案から見えてくること〜
- 基調提案を学習して
- /
- 〜集団づくりを豊かに広げる〜
- 基調提案を読んで
- /
- 〜学級・学年にこだわる集団づくりを〜
- 基調提案の学習に期待すること
- /
- 全生研第44回全国大会参加要項
- 編集後記
- /
今月のメッセージ
肯定と共感のメッセージを
常任委員 柏 木 修
「私、みんなから嫌われているのかな」と質問されたとき、あなたならどう答えますか?
皆さんの答えは、<A>「そんなことないと思うよ。私はあなたのことが好きだよ」でしょうか。それとも<B>「どうしてそう思うの」でしょうか。共感的に対応しなければと考えて、<C>「みんなから嫌われていると思うんだね」でしょうか。
いずれも答えとしてはよくない、と言うのは袰岩奈々さんです【「感じない子どもこころを扱えない大人」(集英社新書)】。
<A>だと、嫌われていると感じる子どもを教師が否定していることになる(自分のもやもやした感じを分かってもらえない、こんなことをまわりに言っても無駄なのかな、と感じてしまうかもしれない)し、<B>だと、「なんとなく」としか答えられないと対話がそこで終わってしまうし(聞き方によっては「どうして」というのは責めているようにも聞こえる)、<C>に至っては、「そこまで自分は決めつけていない」と反発したくなるというのです。なるほどと思います。
ではどうしたらよいのでしょうか。子どもが「気持ち」を訴えているときには、気持ちで答えるべきだと袰岩さんは主張します。例えば、「嫌われているのかなと思うと不安な感じがするよね」と感情を表す言葉で答えると、自分の気持ちを受け止めてもらえたと感じて、さらに気持ちを言いやすくなるというのです。「不安というかすごくつらくて夜も眠れなくて」というように。
私は、教員に一番多い答えは、「どうしてそう思うの」だと思います。教員というのは、知的というか理詰めで何とかして解決しようと思いがちだからです。そしてもし「なんか、私に話しかけてくれないの」という返事が返ってくれば、「そういうときは自分から話しかけなくちゃ」などと本人の努力を促すようなことにもなりかねません。本人は解決を求めて言ったのでなく、ただ気持ちを聞いてほしかったのかもしれないのに。
「嫌われているかも」といったネガティブな気持ちは、気持ちそのものが扱われることなく、こうして居場所を失ってしまいます。むしろこんな気持ちを持つことがいけないかのような印象を子どもは持ってしまうかもしれません。「嫌われているのかな」という気持ちを持つことは自分にもあったし、なんとなくそう思ってしまうこともあるのだ、あなたのように感じていいんだよ、という肯定と共感のメッセージを送りたいものです。
こうしたメッセージを最も必要としているのは、もしかしたら、いじめっ子かもしれません。私たちは、「いじめ」は許せない、という強い「正義感」を持つゆえに、時として、「いじめたくなる気持ち」というネガティブな気持ちまで否定して抑えつけてはいないでしょうか。子どもとの対話に際して、「いじめたくなる気持ち」は誰でも持つものだという前提に立たなければならないと思います。そしてどんな時にいじめたくなってしまうのか、その気持ちを実際のいじめという行動に結び付けないために、自分の気持ちをどうなだめたらいいのか、といった対話をしていく必要があるのではないでしょうか。
「キレ」る人は我慢ができない人ではなく、我慢しすぎている人だという主張がかつてされましたが、そのとおりだと思います。ネガティブな気持ちを封じ込めすぎて、それらが大爆発を起こすのだろうと思うからです。
世の中全体が、知的なこと、スッキリしたこと、きれいなこと、効率のよさ、などなどを重視しているように思います。こんなときこそ、逆に「もやもやすること」「スッキリしないこと」「悩むこと」「葛藤すること」などの一見否定的に思えることに対して肯定の目をむけることが大切だと思います。
ネガがあるからこそポジがあります。ネガティブな気持ちやことがらをむやみに抑えこまずに、それらに居場所を!
-
 明治図書
明治図書















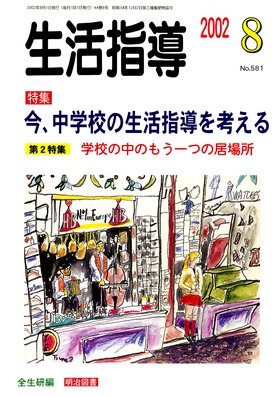
 PDF
PDF

