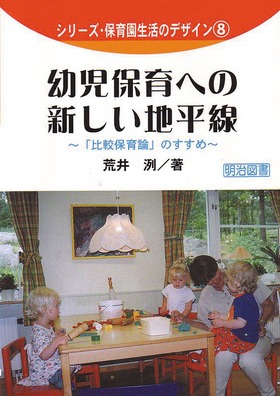- �܂�����
- �v�����[�O�c�V�����L����n����
- �T�@�ۈ�𖾂邭������
- �\�L�����E�����킽���Ȃ���\
- �P�@�w�����̐��I�x��U��Ԃ��ā`�gThe Century of the Child�h
- �Q�@���퐫�ւ̃N�G�X�`������}�[�N�`Why�H & Why not�H
- �R�@�䂽���ɃG�R���W�J���ȉ���ց`Kindergarten�ւ̉�A
- �S�@�����C�q��ăT�����ց`Open-system�ւ̒��
- �T�@���퐶���͢��b�����`�L�[����[�h�� dialogue
- �U�@�ۈ�҂́g���h�����`personality�̎����
- �V�@�������������䂽���Ɂ`�ۈ���e�Ƃ��Ă� living culture
- �W�@�W���̖��͂ƃv���b�V���[�` grouping ���H�v����
- �X�@�l�G�̍s����S�䂽���Ɂ`�q�ǂ������ festival
- 10�@�g���h��ۈ�̃e�[�}�Ɂ`sense of beauty
- 11�@�g�H���h���������̒��S�Ɂ`�Ȃ��₩�� lunch time
- 12�@�������̐������Ƃ��ā` humanism ���e�[�}��
- �U�@���邢������Ԃ��f�U�C������
- �\���������Ƃ��Ă̋��Z��Ԃց\
- �P�@�I�A�V�X(oasis)�Ƃ��Ẳ����
- �Q�@���փz�[���ƃN���[�N����[��(cloak-room)
- �R�@�L����(wide window)����̎،i
- �S�@�e���X(terrace)�̌��p
- �T�@�ǖʂ̃Z���X(wall decoration)
- �U�@�Ɨ������H���̕���(dining room)
- �V�@�Ɩ�(lighting)���y����
- �W�@�R�[�i�[(corner)�̍H�v
- �X�@�����I�ȐԂ����̕���(baby room)
- 10�@�X�^�b�t����[��(staff room)�̏[��
- �V�@�X�J���f�B�i���B�A�̕ۈ畗�y����
- �\�m���f�B�b�N��f���N���V�[�Ɋw�Ԃ��́\
- �P�@�k���̗̂Ȃ��̎q�ǂ�����
- �Q�@�P���I�O�̖k��
- �R�@�q���͖����̐�������^����
- �S�@�m���E�F�[�̎q��Ăƕۈ琭��
- �T�@�X�E�F�[�f���̕ۈ琭��Ɖۑ�
- �U�@�k���̗c���ۈ�ɂ����钍�ړ_�`�t�B�������h�ƃm���E�F�[�̏ꍇ
- �W�@�q��Ă̎v���o��
- �\�A�����J��C�M���X��X�E�F�[�f���\
- �P�@�A�����J�E�Ԃ����Ƃ́g��b�h
- �Q�@�A�����J�E�q�ǂ��̂�����
- �R�@�C�M���X�E�v������y���ރo�[�X�f�C��p�[�e�B�[
- �S�@�X�E�F�[�f���E�Ȃ������N���X�}�X�̂ɂ���
- �G�s���[�O�c�u��r�ۈ�_�v�̂�����
�܂�����
�@���I�����܂낤�Ƃ���Ƃ��C�������͉�������̔������҂��C�܂��C�ǂ̂悤�Ȕ����̂������ɕ`�����Ƃ��܂��B�����āC���܂ł̂�������C���E���傫���L���鍂�݂ւ̏㏸���肢�܂��B
�@�������C���̂��Ƃ͎��͂̏̂悢�����ւ̕ω��ƁC����̓w�͂ɂ��Z���X�ƒm���̌���������Ƃ��܂��B
�@���́C������܂߂����Ƃ����傢�Ȃ�ۑ�ɗ����������Ƃ��C�������͍L�����E�ɖڂ��������C��r�����_�I�Ȃ��̂̌����̗L�͂ł��邱�ƂɋC�����܂��B�Đ��I�Ȏ��o����̒E�o�ɁC�L�����ƌ���C���X�s���[�V������^���Ă���邩��ł��B
�@���I�̓]���̎����ɍۂ��āC�{�V���[�Y�̂W���߂̃^�C�g���̒��ɁC�g�V�����n�����h�Ɓg��r�ۈ�_�h�Ƃ��������t������̂́C���̂悤�ȍl��������ł��B
�@�ۈ�̐��E�ɐ�����҂Ƃ��āC���E���傫���L����C���͓I�ȃe�[�}���ǂ�ǂ�킫�o���Ă��邱�Ƃ����҂���̂ł��B
�@���E���L�����n���Ȃ���C���邭�������ۈ�̂���悤���C����₩�ɁC�����炩�Ƀf�U�C�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�@�^�r��@��
-
 �����}��
�����}��