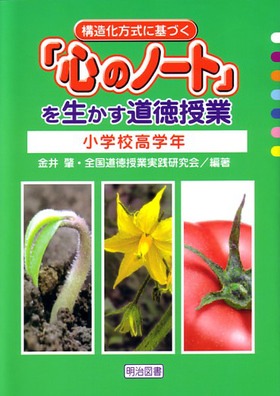- はじめに
- Ⅰ章 構造化方式による『心のノート』を生かした授業の基本
- 1 構造化方式の勧め
- 2 構造化方式での『心のノート』の生かし方
- 3 構造化方式における評価
- 4 高学年『心のノート』を生かす着眼点
- Ⅱ章 構造化方式による『心のノート』を活用した授業実践
- 1 視点1のとらえ方と生かし方
- 自分を育てる
- (1) 「自分の一日は自分でつくる」
- ・資料『食べ残されたえびになみだ』
- (2) 「夢に届くまでのステップがある」
- ・資料『もう一つの五輪・パラリンピック』
- (3) 「自由ってなんだろう」
- ・資料『うばわれた自由』
- (4) 「まじめであることはわたしのほこり」
- ・資料『のりづけされた詩』
- (5) 「好奇心が出発点」
- ・資料『セロハンテープの発達』
- (6) 「自分を見つけみがきをかけよう」
- ・資料『天女,再び宇宙へ』
- 2 視点2のとらえ方と生かし方
- ともに生きる
- (1) 「心と心をつなぐネットワーク」
- ・資料『朝のほほえみ』
- (2) 「あなたの心にあるそのあたたかさ」
- ・資料『最後のおくり物』
- (3) 「友だちっていいよね」
- ・資料『言葉のおくりもの』
- (4) 「よりそうこと,わかり合うことから」
- ・資料『すれちがい』
- (5) 「『ありがとう』って言えますか?」
- ・資料『電車の中でのできごと』
- 3 視点3のとらえ方と生かし方
- 生命を愛おしむ
- (1) 「生きているんだね自然とともに」
- ・資料『一ふみ十年』
- (2) 「いま生きているわたしを感じよう」
- ・資料『わたしの思い』
- (3) 「大いなるものの息づかいをきこう」
- ・資料『百一歳の富士』
- 4 視点4のとらえ方と生かし方
- 社会をつくる
- (1) 「いきいきしている自分 かがやいている仲間」
- ・資料『できなかったリレーの練習』
- (2) 「ぐるりとまわりを見渡せば…」
- ・資料『ふくらんだリュックサック』
- (3) 「どうしてゆがめてしまうのか?」
- ・資料『愛の日記』
- (4) 「働くってどういうこと?」
- ・資料『マザー・テレサ』
- (5) 「わたしの原点はここにある」
- ・資料『鈴虫が鳴いた』
- (6) 「学び合う中で」
- ・資料『さざんかの花』
- (7) 「見つめようわたしのふるさと そしてこの国」
- ・資料『日本の美しさと俳句の心』
- (8) 「心は世界を結ぶ」
- ・資料『もうひとつのふるさと』
- 5 『心にひびく言葉』『わたしのページ』
- 『わたしの主張』『さあ中学生 そして未来へ』
- 『道はつづく』構造化方式での活用
はじめに
高学年になると,中学年までよりも一段と道徳授業に困難を感ずるようになる。
高学年では,自分の将来に関心が向いてくる。そこにかかわる悩みも感ずるようになる。その悩みが行動に表れることもある。教師の目に自分勝手と映る行動も多くなる。
その児童の置かれた状況をどう受け止めるか,児童の気持ちを理解しようとするかどうかで,道徳授業の組み立て方が変わってくる。
行動面に目を止めれば,直接に道徳的実践を目指す指導になりがちで,児童の行いを矯め直そうとしがちである。児童の置かれた状況とその気持ちに目を向ければ,児童に役立つように道徳性を育てる指導になる。この違いが生き生きと児童に受け入れられる道徳授業になるか重苦しい授業になるかを分ける。なぜそうなるかは,本書を子細に吟味していただければはっきりする。
道徳授業を抜本的に改善することが急務で,学習指導要領ではありとあらゆる創意工夫を求めているのだが,現状は工夫が行われても枝葉末節にとどまって根本の発想の転換までいっていない場合が多い。その発想を転換し,抜本的に授業を改革するのが構造化方式である。構造化方式は道徳授業の困難点をすべて解決して明るく楽しい授業にする原理でもあるのである。
構造化方式は,中国の道徳教育にも取り入れられ始めた。中国では「思想品徳」という教科で道徳教育が行われているが,改革・解放路線と一人っ子政策によって社会の自由化と家庭の子どもの甘やかしが進み,「思想品徳」の指導を子どもが受け付けず,指導にならなくなり,自由で勝手気ままに育った子どもにも通用する指導の原理を求めた結果,構造化方式に活路を見いだしたとのことである。
文部科学省から『心のノート』が配布された。『心のノート』は,児童がありのままの自分からよりよい自分への願いに即して考えを深めるようになっている。この発想は構造化方式に極めて近い。だから,構造化方式の授業では『心のノート』を生かしやすい。また,構造化方式や『心のノート』の考え方で指導することが,前述の道徳授業の抜本的な改善になるのである。
『心のノート』をどう生かすか。これまで授業を技術的に組み立ててきた場合は,形骸化していても本人が気づかないでいる場合が多い。そのままで『心のノート』を授業に利用しようとしても試行錯誤となる。『心のノート』を生かす授業には児童中心の授業の組み立て方が大切で,構造化方式によって指導をすすめることが最善である。
本書は,Ⅰ章「構造化方式による『心のノート』を生かした授業の基本」と,Ⅱ章「構造化方式による『心のノート』を活用した授業実践」からなる。Ⅰ章は構造化方式の要点を分かりやすく述べたものである。Ⅱ章は,構造化方式の考え方によって,各事例を分担した教師の持ち味を生かして授業を実践した事例である。Ⅰ章で『心のノート』と構造化方式の要点をとらえ,Ⅱ章を参考にして,本書を優れた道徳授業の創出に役立てていただければ,これに過ぎる喜びはない。
本書は,明治図書出版の,仁井田康義氏のご支援と叱咤激励によって誕生することができた。紙上を借りて厚く感謝の意を表したい。
平成15年1月 /金井 肇 /斎藤 宥雄
-
 明治図書
明治図書