- はしがき
- 第1章英語科の到達度評価にはどんな工夫が必要か
- §1 目標に準拠した評価(到達度評価)の重要性
- 1 外国語の目標
- 2 外国語の学習の評価
- 3 「集団に準拠した評価」から「目標に準拠した評価」へ
- §2 指導計画の作成と指導・評価の工夫
- 1 観点別到達度評価に必要な手順
- 2 評価規準設定上の留意点と評価規準の例
- 3 評価問題の作成とその学習法
- 4 通知表や指導要録の「学習の記録」への表記について
- 第2章「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」の指導と評価事例
- 1 (1)未習語を気にせず,話されている場面・状況や内容をつかもうとする
- (2)既習語を用い,積極的に話し,コミュニケーションを続けようとする1年・1学期
- 2 (1)未習語を気にせず,対話のトピック(話題)をつかもうとする
- (2)細かい間違いを気にせず,伝えたいことを書こうとする1年・2〜3学期
- 3 (1)未習語を気にせず,大切な部分を聞き取ろうとする
- (2)書き手の意向を理解し,適切に応答しようとする2年・1学期
- 4 (1)未習語を気にせず,話されている場面・状況や内容をつかもうとする
- (2)スピーチを聞いて,質問に答える2年・2〜3学期
- 5 友達から送られたEメールを読んで,返事を出す3年・1学期
- 6 まとまりのある文章を読んで,その内容に関する質問に答えるとともに,自分の感想や意見を書く3年・2〜3学期
- 7 「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」の総合的評価全学年・随時
- 第3章「表現の能力」の指導と評価問題例
- 【話すこと】
- 8 初歩的な英語を使って自己紹介ができる1年・1学期
- 9 身近な話題について正しい英語で話す1年・2学期
- 10 場面や相手に応じて適切に話す1年・3学期
- 11 相手の意向や内容を理解し,聞かれたことに適切に応じる2年・1学期
- 12 読んだことについて,問答したり意見を述べる2年・2学期
- 13 伝えたい内容,場面や相手によって適切な語句や表現を選択する2年・3学期
- 14 いろいろな工夫をして話を続ける3年・1〜2学期
- 【書くこと】
- 15 簡単な英語で自己紹介(スピーチ)の原稿を書こう1年・1学期
- 16 絵を見て,一日の行動を簡単な英語で書こう1年・2学期
- 17 絵を見て,いま行っていることを書こう1年・3学期
- 18 先生,読んで!−先生に最近のことの日記を書こう2年・1学期
- 19 友達と交換日記をしよう!2年・2学期
- 20 外国人講師の先生に手紙を書こう!2年・3学期
- 21 外国人講師の先生の話を聞いてメモを取ったり,感想を書いたりしよう3年・1〜2学期
- 第4章「理解の能力」の指導と評価問題例
- 【聞くこと】
- 22 語句や文の意味を正しく聞き取る1年・1学期
- 23 質問の内容を正しく聞き取り,答える1年・2学期
- 24 まとまりのある英語の内容を正しく聞き取る1年・3学期
- 25 いろいろな場面で聞かれる英語を適切に聞き取る2年・1学期
- 26 まとまった文の情報を正しく聞き取る2年・2学期
- 27 聞いたことに対し,聞き返しや,意思表示などをする2年・3学期
- 28 意見を聞いて,話し手の意向を理解する3年・全学期
- 【読むこと】
- 29 語句や文の強勢,音調に注意して,内容を正しく伝えるように読む1年・1学期
- 30 登場人物の意向を汲み取りながら,内容を正しく理解する1年・2学期
- 31 質問の内容を理解し,正しく答える1年・3学期
- 32 紀行文を読んであらすじをつかむ2年・1学期
- 33 説明文のあらすじや大切な部分を読み取る2年・2学期
- 34 物語文の内容を味わいながら黙読し,その内容が表現されるように音読する2年・3学期
- 35 対話文の内容が表現されるように,気持ちを込めて音読する3年・1〜2学期
- 36 スキャニング読みから表現読みへ総合
- 第5章「聞くこと話すこと」の指導と評価問題例
- 【聞くこと話すこと】
- 37 ALTを巻き込んだSKITをしよう1年・2学期
- 38 ALTとおしゃべりをしよう!1年・3学期
- 39 ALTの話を聞いて質問しよう!2年・1学期
- 40 Show & Tell3年・2学期
- 第6章「言語や文化についての知識・理解」の指導と評価問題例
- 【言語に関すること】
- 41 (1)アルファベットや,符号などを正しく書こう
- (2)季節,月,曜日などの基本語をマスターしよう
- (3)現在形,現在進行形,助動詞などを含む文などの肯定文・否定文・疑問文のしくみをマスターしよう1年・3学期
- 42 (1)文におけるイントネーション・区切りをマスターしよう
- (2)疑問詞をマスターしよう
- (3)不規則動詞過去形の文・受動態の肯定文・疑問文・助動詞のある文のしくみをマスターしよう2年・3学期
- 43 (1)考えを深めたり,伝えたりする表現をマスターしよう
- (2)現在完了形の肯定文・否定文・疑問文をマスターしよう
- (3)関係代名詞のある文に慣れよう3年・3学期
- 【文化に関すること】
- 44 国際電話をかけて,東京とニューヨークの情報を交換する1年・2学期
- 45 日本語と英語の表現の発想の違いに気付き,正しく使う1年・3学期
- 46 アメリカの旅先からALTのJones先生にはがきを書く2年・2学期
- 47 外国の文化などについて理解する3年
- 48 各国の国旗と文化・歴史について関心を持つ3年
- 49 あいさつやジェスチャーなどによるコミュニケーションについて理解する総合
- 50 やさしい英語のことわざに親しむ総合
- 付録1 音声教材
- 付録2 問題の全解答
はしがき
平成元年度に告示され,これまで使われてきた現行の学習指導要領も,いよいよ本年で使用済となる。ここに示されていた中学校外国語科の目標は,「外国語で理解し,外国語で表現する基礎的な能力を養い,外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てるとともに,言語や文化に対する関心を深め国際理解の基礎を培う。」ことであった。これに対応して平成3年度には,生徒指導要録の様式,取扱い等も改善がなされた。即ち,「各教科の学習の記録」には,この目標を受けた内容としての「言語活動」及び「言語材料」等の指導が行われ,その結果を,「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」,「表現の能力」,「理解の能力」及び「言語や文化についての知識・理解」の4つの観点から,生徒一人一人の学習の達成の状況として評価すべきことが示された訳である。いわゆる「新しい学力観」に基づく中学校外国語科の指導については,こうした学習指導要領と生徒指導要録の両者の合体によって,文字通り「指導」と「評価」一体化の枠組が示され,全国の教室現場での実践が期待されたのである。
その後今日まで,各学校,各地区において,外国語科の目指す新しい学力はこの「指導」と「評価」の一体化を図りながら,どのように取り組まれてきたであろうか。残念ながら,今日に至ってもなお,従来の中間・期末等のペーパーテスト,時々の実技テストや小テスト等の総合から割り出したいわゆる5段階相対評価を主軸とし,日常の授業観察やワークシート等からA,B,C等の絶対評価的な見方による観点別評価をある程度“加味”していくといった方法が依然として採られているのではないだろうか。
さて,教育課程審議会は平成12年10月に「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」の中間まとめを発表し,児童生徒指導要録の「各教科の学習の記録」について,「観点別学習状況欄」は従来の考え方を更に発展させて「目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)」によるものとし,「評定欄」の評価についても従来の「集団に準拠した評価(いわゆる相対評価)」から「目標に準拠した評価」に改めるという評価方法の大変革を提言した。これに対して,特に中学校現場や教育関係者からは,高等学校入学者選抜の調査書においては全都道府県が相対評価を採用している現状を考えると,「内申書が変わらなければ,成績による序列化の状況は変わらない。」との声が多く出されていた。そこで同最終答申では,高等学校入学者選抜の実務を担当する各都道府県において「絶対評価に改める努力が行われることを期待したい。」との踏み込んだ要請がなされたのである。
その理由は,第1に,基礎的な学力の習得状況をみるには絶対評価が適していること。第2に,少子化でクラスや学年の規模が小さくなり,相対評価の客観性が確保できなくなりつつあること,などを挙げている。このことは,学校の評価方法を全面的に絶対評価に転換することにより,成績によって子どもを序列化しがちな体質から学校が脱却すべきことを強くめざしたものである。
更に,この度文部科学省が策定した「義務教育第七次教職員定数改善計画」の施行に伴い,子どもたちの基礎学力の向上ときめ細かな指導を目指し,英語や理数科等の教科における少人数による指導が全国的に広まろうとする中で,児童生徒の学習の習熟の程度に応じた少人数学習集団のため,指導に生きる評価を行っていくためには,「目標に準拠した評価」を常に行っていく必要が強まっているのである。
こうした状況から今後,全国の都道府県も答申に沿って指導要録や内申書の見直しを図る動きに出てくることが十分予想される。その際は,答申にもあるように,「児童生徒の学習の到達度を客観的に評価するための評価規準,評価方法等を関係機関において研究開発し,各学校における評価規準の作成に活用できるようにする」ことが期待されている。
本書は,先に刊行し好評を得てきた『中学校英語科の観点別評価問題』(1995.7 明治図書)を土台とし,これを今次の新学習指導要領並びに新生徒指導要録の「各教科の学習の記録」の改善の趣旨に沿って全面的に書き改めたものである。
「指導と評価の一体化」とは即ち「目標に準拠した観点別の到達度評価」を行うことである。しかし,日常の授業における教師の観察や生徒の自己評価,相互評価等によるといった方法だけでは必ずしも妥当性,信頼性と客観性のある評価結果が得られるとは限らない。生徒にとって最も関心の高い学習評価の場面である中間テストや期末テストの場においてこそ,観点別の到達度評価問題を用意して与えることが必要なのである。そこで,このたびも前刊の作成に協力戴いた先生方に,上述したような新たな視点からのご検討をいただき,各学年,各学期の定期テストにも利用できるよう英語科の4観点から考えた評価問題例を作成したものである。本書が,生徒の基礎学力の向上を目指す木目細かな指導と評価に有効であるばかりでなく,個に応じた選択学習や学習の習熟度に応じた少人数学習集団のための編成にも役立つものとなれば幸いである。
終わりに,本書の刊行に当たって,終始ご助力を賜った明治図書の安藤征宏氏に心より御礼を申し上げたい。
平成13年11月 編者 /荒木 秀二














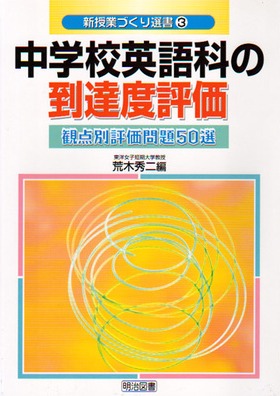


特に、評価の観点における「言語や文化に対する知識・理解」については、今後記述力(書く力)がますます要求されるため、今まで以上に入念にテスト問題を作成していく必要がある。
この本では具体的にテスト問題や授業での練習問題を取り上げ、それぞれが学習指導要領のどの指導事項と関連があるのか、また、指導時期や評価方法及び評価基準についても細かく整理され、とてもわかりやすくまとめられている。
さらに、それぞれの右ページ(問題部分)はコピーOKなので教材作りの時間がない方にはお勧めである。
今大切なことは、「できることから始める!」ということであると強く感じている。
無理なく、ほどよく活用できる、英語教師必携の良書である。