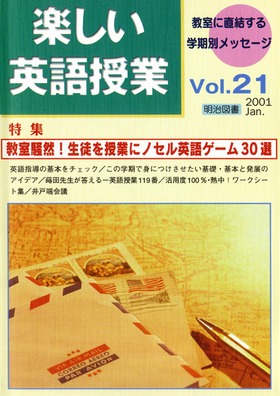- ���W�@�������R�I���k�����ƂɃm�Z���p��Q�[��30�I
- �T�@�����_���u�p��ƃQ�[���v
- �p����Ƃ̖@�����ƃQ�[���@�^����@�q�F
- �o�b�V���O����Ă��C����ς�Q�[���@�^�k���@���W
- �U�@�u�p��Q�[���͐��k���������C���ƂɃm�Z���I�v
- �Q�[�������̔錍�@�^����@�돟
- �Q�[���̑�햡�R�v�f�@�^��k�@�C��
- �V�@�������R�I �ʔ��Q�[���A�C�f�A�W
- �y�A�ŔR����I���X�j���O�Q�[���@�^���ʁ@�a�}
- �s�J�C�`�{�L���u���E�����h�@�^�쑺�@����
- �ʏ�̎��Ƃɂ�����Q�[���I�v�f�@�^����@�R����
- ��Z���uI think�`�v�Q�[���ƔO�͂𑗂��āuI feel�`�v�Q�[���@�^�r�c�@�_�K
- diversity��creativity���y���ރQ�[���@�^�c�K�@��Y
- �������R�I�P����Why-Because�Q�[���@�^�C�@�K�o
- �Q�[���̘A���\���Ŋy�������Ƃ��@�^�P��@��
- �Q�[���ƃe�X�g�����т��悤�I�@�^����@���W
- �y���݂Ȃ���͂����Ă����Q�[���@�^�叼�@�T�V
- �Q�[���̉��l�gFruit Basket�h�@�^���c�@����
- ���ʂȏ����Ȃ��I�ł����k���̂���Ɓ@�^��@�O
- ���ꂩ��͂c�u�c�ƃC���^�[�l�b�g�@�^�����@�N�v
- ���k�̒P��A�z�͂�b����Imagination Game50��@�^���c�@���F
- �E�H�[�~���O�A�b�v�Ŏg����Tail Letter Game�@�^�H�J�@�G�T
- �W�@���W�̂܂Ƃ�
- Don't forget �p��w�K�Q�[���@�^���@�L�l
- �~�j���W�T�@�w�y�����p����Ɓx�����Ɏg����������X�g
- �~�j���W�U�@�p�ꋳ�t�̂��߂̂������߃z�[���y�[�W�@�^��k�@�C��
- ��D�]�A��
- �`�@�p��w���̊�{���`�F�b�N�m�U�n
- �@�@�Q�[�������̊�{�@�^�O�Y�@�K�q
- �A�@���ꊈ���̊�{�@�^�R�{�@���Y
- �B�@�X�s�[�`�w���̊�{�@�^�V�ȁ@�a�V
- �C�@���K���̈������̊�{�@�^���Ɓ@����
- �D�@�O���l�u�t�Ƃ̂s�s�̊�{�@�^��v�ہ@�m�q
- �a�@���̊w���Őg�ɂ�����������b�E��{�Ɣ��W�̃A�C�f�A�m�R�n
- ���w�Z�p��@�p�ꊈ���̊�b�E��{�@�^���R�@�ؖȎq
- ���P�F�R�w���@�������ƁE�b�����Ƃ̊�b�E��{�@�^�����@�m��
- ���P�F�R�w���@�ǂނ��ƁE�������Ƃ̊�b�E��{�@�^�v�ۓc�@���G
- ���Q�F�R�w���@�������ƁE�b�����Ƃ̊�b�E��{�@�^���c�@�m
- ���Q�F�R�w���@�ǂނ��ƁE�������Ƃ̊�b�E��{�@�^�r��@��
- ���R�F�R�w���@�������ƁE�b�����Ƃ̊�b�E��{�@�^�a�c�@���I�q
- ���R�F�R�w���@�ǂނ��ƁE�������Ƃ̊�b�E��{�@�^�����@��q
- ���Z�I�[�����F�R�w���@�n�b�̊�b�E��{�@�^����@�G��
- ���Z�p��T�F�R�w���@�p��T�̊�b�E��{�@�^�J���@�K�v
- �b�@�\���c�搶��������\�p�����119�ԁm�U�n�@�^���c�@��
- �����ɎQ�����Ȃ����k�́C�����Ă����Ă悢�̂��H�^�@�R�N�Ԃ����ʂ����w���v��Â���̋�̓I���@�́H
- �c�@���p�x100���E�M���I���[�N�V�[�g�W�m�R�n
- �@�@�M���I���@�p�Y���@�^�씨�@����
- �A�@�M���I���[�h�E�p�Y���@�^�g�c�@���T
- �B�@�M���I�N���G�C�e�B�u�E���C�e�B���O�@�^�{�c�@�q�V
- �C�@�M���I�J���`���[�E�p�Y���@�^�R�{�@���q
- ��˒[��c�\�V���I�p�ꋳ��ւ̃��b�Z�[�W
- �^�ΐ�@�j�E��k�@�C��E��_�@���P�E����@������E�{�c�@�q�V�E�|���@�����E�J���@�K�v�E�z���@�a���E�����@�m��
- �O���r�A�\�_�ˑ�w���B�Ȋw�������Z�g���w�Z�@�^���ԁ@��q
- ���\���\�F�{��w����w���������w�Z�@�^���c�@���F
���ƃC���t�H���[�V����
�@�Q�[���c�c����̓X�|�[�c�̐��E�ł͓�����O�̌��t�Ƃ��Ďg���Ă���B�����āC���̃X�|�[�c�ɂ�����Q�[�������Ă���ƁC�K�������̋��ʓ_�������������B����́u���_�v�u��������v�u�y�����v�u���Ԑ����v�u�ْ����v�Ƃ��������ʓ_�ł���B�p����Ƃɂ����鐔�X�̃A�N�e�B�r�e�B�[�ɁC�����̊ϓ_���ӎ����ē���Ă݂�B����ƁC��R�Q�[�����ʔ����Ȃ�B
�@�C�O�̉p��Q�[������{�̋����ł���Ă݂�B�Ⴆ�C�n���O�}�����ǂ��̃Q�[���Ɏ��̂悤�ȃQ�[��������B�ԈႦ��ƉE�̐}�̂悤�ɐl�Ԃ��P���P���K�i���~��Ă����Q�[���ł���B�����S�̂̑O�ł���Ă��ʔ����Ȃ��B�����ŁC�K�i���Q�`���C�j�q�Ώ��q�ɂ���B�����ɉ������̕������P���܂�ƂP�_�Ƃ��C���_���^����悤�ɂ���B�����ǑR�ł���Ă��悢�B�|�C���g�́u��������v����邱�ƂƁC�u���_�v�����邱�Ƃł���B
�i�}�ȗ��j
�@�܂��C���t���ǂ�ǂ��Ă����Q�[��������B�������ɍs���Č������́B�P�l�̐l���CI went to the zoo and I saw a lion. �ƌ�������C���̐l���CI went to the zoo and I saw a lion and a tiger. �ƌ����B����Ɏ��̐l���CI went �E�E�E a lion, a tiger and a rabbit.�Ɠ������ǂ�ǂ₵�Ă����B���̃Q�[�������Ƃł��ƂȂ�Ƃ�����Ƃ����H�v���K�v�ł���B�Ⴆ�ΑS���������C���k�Ɏ������������B���������k�͍���B�܂�C���������Ɍ������������Ȃ悤�Ɏd�|����̂ł���B
�@�C�O�ɂ͑����̐�s�Q�[�����H������B������������̂܂ܓ��{�̋����ł͎g���Ȃ��̂ŁC��肩����K�v������B
-
 �����}��
�����}��