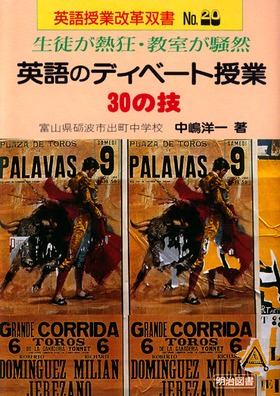- �܂�����
- ������
- �T�@�Ȃ��f�B�x�[�g������̂�
- §�P�@�Ȃ��f�B�x�[�g���p��w�K�ŕK�v�Ȃ̂�
- �\�\�̌��^�w�K�̂����߁\�\
- �P�@�����Ɓu�Ӗ��̂���J��Ԃ��v��
- �Q�@�Ⴂ������Ĉӌ���h�R������
- §�Q�@�I�����_�Ō��������ׂ��f�B�x�[�g�̎���
- �\�\�S�Ă͂�������n�܂����\�\
- �P�@���ꂪ�f�B�x�[�g�Ȃ̂��I�H
- �Q�@�f�B�x�[�g�͎d�|�������̂�����
- �R�@���̃f�B�x�[�g�𐬌�����������
- §�R�@�R�~���j�P�[�V�����\�͂����߂�f�B�x�[�g
- �\�\����Ȃ�b����悤�ɂȂ�\�\
- �P�@���ꂩ��͕K���f�B�x�[�g�w�K���K�v�ɂȂ�I
- �Q�@�p��Ńf�B�x�[�g������̂͂Ȃ���
- §�S�@�f�B�x�[�g�͋����ʼn�����Ă邩
- �\�\���k���M������ɂ͂킯������\�\
- �P�@�f�B�x�[�g������
- �Q�@�f�B�x�[�g�̖ʔ����i����
- �U�@�u�p��Ńf�B�x�[�g�v�̉��n�����
- §�P�@�R�~���j�P�[�V�������}���W�c�����
- �\�\comfortable�Ȓ��ԂÂ�����y�A�w�K�Ł\�\
- �P�@�͂��߂�
- �Q�@�y�A�̍����ɔz������
- �R�@�y�A�����
- �S�@�Z��y�A�C���C�o���E�y�A�����
- �T�@�y�A�E���[�_�[�����
- �U�@�y�A�w�K�̗L�����𗝉�������
- �V�@�S�Ă͎��Ԕc������
- �W�@�}���l������E�炳����A�C�f�A
- �X�@���k�������y�A�w�K���x�����闝�R
- §�Q�@�u���M�^�v�p��ւ̓�
- [�P]�@�p����y����������銈�����d�g�ށ@�\�\�R�~���j�P�[�V�����̓L���b�`�{�[���\�\
- �P�@����̌����Ă��邱�Ƃ���������ƕ���
- �Q�@�����Ƃ��悤�ɂȂ邽�߂̌��ʓI�ȕ��@
- �R�@���ǂ������q�A�����O�\�͂����߂�
- �S�@�q�A�����O�Ń������ǂ��c����
- [�Q]�@���������Ȃ�C�b�������Ȃ�C���������Ȃ銈�����d�g�ށ@�\�\�܂������S����Ă悤�\�\
- �P�@���������Ȃ�C�b�������Ȃ�C���������Ȃ� Show and Tell
- �Q�@�����Ƃ��̎w�����ǂ����邩
- �R�@�b���Ƃ��̎w�����ǂ����邩
- �S�@Show and Tell �̋��t�̉��o
- �T�@Show and Tell �̃X�s�[�`���ăR�����g������
- �U�@�V����ǂ�ŃX�s�[�`�iMy Opinion�j������
- [�R]�@�p��Ŕ��M���銈�����d�g�ށ@�\�\�X�L�b�g��h���}����ʂ��ā\�\
- �P�@�p��Ŕ��M����Ƃ�
- �Q�@�\���͂����邽�߂̗��K
- �R�@authentic �ȏ�ʂ����o��
- �S�@���������ۂɎ����Ă��ĉ��Z������
- §�R�@�\���͂Ƙ_���������߂�
- [�P]�@�����̈ӌ����q�ׂ����Ȃ銈�����d�g�ށ@�\�\�g�߂Șb��œ������炩������\�\
- �P�@�����\���`�e�����g���i�Ώۂ͂Q�N�C�R�N�j
- �Q�@�ǂ�ł킩��ɂ���������₤�i�Ώۂ͂Q�N�C�R�N�j
- �R�@�D�������������ӎ�������i�Ώۂ͂Q�N�C�R�N�j
- [�Q]�@�����Ȃ��Ęb��W������@�\�\�R���e�N�X�g���ӂ���܂���\�\
- �P�@���^����̒E�o
- �Q�@���̗���ŕt�������C�܂��͗��R������
- [�R]�@����ɂ��₭��������@�\�\�����S�����g���Ċy�����\�\
- [�S]�@�ԈႢ�T���ƓY��ʼnp��̗͂�����@�\�\�N�ł��C�y�ɎQ���ł��銈�����\�\
- [�T]�@��̓I�ȏ�ʂ�z�����ďq�ׂ�@�\�\lt's interesting�D�ł͂킩��Ȃ��\�\
- �P�@����z��ł͂Ȃ���`���邱�ƣ�ɖړI��ς���
- �Q�@�ǂݎ�i������j���ӎ����ď����i�b���j
- �R�@��̓I�ȕ`�ʂɋC�Â�
- [�U]�@�����Ř_����b����@�\�\�N�ł����_����̂͊y�����\�\
- [�V]�@�ӌ���_���I�ɏq�ׂ���悤�ɂ���@�\�\���ʂ���l����\�\
- [�W]�@Four Corners�Ŏ����̈ӌ������@�\�\�ǂ̎q�ɂ� Because�`�D�ňӌ������܂��\�\
- �P�@�����̈ӌ������悤�ɂȂ� Four Corners
- �Q�@�ЂƖ������ Four Corners
- §�S�@�w�т̎��E�i�܂Ƃ܂������e�̂��́j������
- �\�\�p���C�n�쓶�b�C�G�b�Z�C���y����ō��\�\
- �P�@���ȕ\���̂��������l����
- �Q�@�w�т̎��E�����
- �R�@�g���Ȃ���p����w��
- �V�@�f�B�x�[�g��̌�����
- §�P�@���s����w����
- �\�\�킩��������ƌ��蔭�Ԃ����s���������\�\
- §�Q�@��f�B�x�[�g�͊y�����I��Ƃ����C���[�W����낤
- �\�\�܂����{��ł���Ă݂āC�Ή��̎w��������\�\
- �P�@�ӌ��̋j�R�͊w�K�ւ̃G�l���M�[�ɂȂ�
- �Q�@�f�B�x�[�g�Ő��k���ς�����I
- §�R�@�b�������Ȃ�悤�Ș_���ݒ肷��
- �\�\�g�߂ȑ�ނňӌ������������̂��\�\
- §�S�@�W���b�W����Ă�
- �\�\�_���������ɂ߂邱�Ƃ̑����������\�\
- �P�@�_���I�v�l�����
- �Q�@���t���W���b�W�̌��ʂ������Đ�������
- §�T�@���ۂɃf�B�x�[�g��̌�����i���{��ҁj
- [�P]�@�R�l�O���[�v�̃}�C�N���E�f�B�x�[�g���y���ށ@�\�\�W���b�W��̌����Ę_�������w�ԁ\�\
- �P�@�Ȃ��}�C�N���E�f�B�x�[�g�����ʓI�Ȃ̂�
- �Q�@�}�C�N���E�f�B�x�[�g�̎��ۂ̎w�����ǂ����������
- [�Q]�@�S�l�O���[�v�R�̃f�B�x�[�g���y���ށ@�\�\�i���o�����O�C�O���[�s���O�C���x�����O���w�ԁ\�\
- �P�@�i���o�����O�C�O���[�s���O�C���x�����O�Ƃ́H
- �Q�@���ۂ̃f�B�x�[�g��̌�����
- �R�@�����������K�v�ɂȂ�悤�Ș_���ݒ肷��i��P���j
- �S�@���ʂ�����������i��P���j
- �T�@�l��������i�i���o�����O�C�O���[�s���O�C���x�����O�j�i��Q���j
- �U�@�����l����i��R���j
- �V�@�t���[�V�[�g�̏��������w��
- [�R]�@�N���X�R�̃f�B�x�[�g�����y���ށ@�\�\��萷��オ��悤�ɋ��t���d�|����\�\
- �P�@���C�o���ӎ��𗘗p����
- §�U�@�p��Ńf�B�x�[�g������
- [�P]�@�y�A�Ŏ���f�B�x�[�g���y���ށ@�\�\���Ԃ��C�ɂ����莆�̂��Ƃ�̊��o�Ŏ��R�Ɂ\�\
- [�Q]�@�N���X�R�̎���f�B�x�[�g������y���ށ@�\�\�^�������ӌ����`�F�b�N�������f�B�x�[�g�ց\�\
- �P�@���ȒʐM�̏�Ŏ���f�B�x�[�g������d�g��
- �Q�@�y�A�̎���f�B�x�[�g��
- [�R]�@�R���s���[�^�Ńf�B�x�[�g������y���ށ@�\�\�k�`�m�Ƣ�L�[�{�[�h���L��̋@�\���g���ā\�\
- §�V�@�P���Ԃő̌��ł���p��̃f�B�x�[�g
- �\�\���{��i�y�A�j���p��@�i�S�́j���p��i�y�A�j�\�\
- §�W�@�p���V�����g���ĉp��̃f�B�x�[�g������
- �\�\�ǂ�Ȏ����ƃt���[�V�[�g��^���邩�\�\
- �P�@�m���ƕ��@�����ł̓R�~���j�P�[�V�����͐}��Ȃ�
- �Q�@�p���V���𗘗p����
- §�X�@���t�����ۂɃf�B�x�[�g��̌����悤
- �\�\���t���y�������������悤�\�\
- �P�@�`�k�s�Ɩ͋[�f�B�x�[�g��̌����Ă݂�
- ���Ƃ���
�܂�����
�@���w�Z�ł��p��̃f�B�x�[�g�͂ł���B
�@���ۂɂR�N�ԃf�B�x�[�g�����H���Ă݂Ď��͂����m�M�����B
�@�����Ŏ��̂Q�̖ړI�ł��̖{���������B
�@[1]�@�f�B�x�[�g���ł���悤�ɂȂ鐶�k���琬���邽�߂̃V���o�X�ɂ��ċ�̓I�ɏЉ��i�U�́j
�@[2]�@�p��̃f�B�x�[�g�����ۂɎw���������ƍl���Ă�����搶���Ƀf�B�x�[�g�̂����̂��낢��ȕ��@���Љ��i�V�́j
�@������C�ł��邾�����ƂŎg����A�C�f�A����@�������悤�ɂ����B
�@���k�����͎��̎��Ƃ̂������u�����}�W�b�N�v�ƌĂ�ł���B����Ȕނ炪�C���̖{�̓ǎ҂Ɍ����ă��b�Z�[�W���l���Ă��ꂽ�B
�@�@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@��
�E�����搶�̓}�W�V�������B�搶������ӂ�B�������������Ȃ��Ƃł��Ȃ���ƌ����Ă��S�R����Ă���Ȃ��B���傤���Ȃ��̂Ńu�c�u�c�����Ȃ�����g�ށB���̂����ɖ����ɂȂ��Ă��鎩���ɋC�Â��B�I��������͂Ȃ����������Ă���B���ɂ͊������Ă��܂����Ƃ�������B�搶�͂��ꂪ�킩���Ă������̂悤�Ɍ��Č��ʂӂ�����Ă���B�i����6�N�x���@���䋽�q�j
�E�����搶�́C���k���ǂ��������p�ꂪ�g�ɂ��̂���S���Ă��āC�����ȃA�C�f�A�ł��܂�B�f�B�x�[�g�C�y�A�w�K�C�p��̉́C�ЂƖ�������������ȂǁC���܂��܂��B�����玟�ɂǂ�Ȃ������o�Ă���̂��킭�킭����B���̒����}�W�b�N�����̖{�ŏЉ��邻�����B����͐�̂��E�߂���i�R�N�@��������j
�E�����搶�̎��Ƃ́C���̐搶���ƂȂ������ɓ���Ȃ��̂ɁC���̎��Ԃ̂����Ɋo���Ă����Ă��܂��B�ƂĂ��s�v�c���B�������ƂĂ��y�����B�i�R�N�@���������q�j
�E���Ƃ̏��߂ɁC�悭�R���ԂŊȒP�ȉp��̓��_���s���B�搶�����鎿����o���Ď��������W�����P���ōm��C�ے�ɕ�����đΌ�����̂ł���B���ꂪ���M����B�������C����̂��Ƃ�^���ɕ����悤�ɂȂ�ƁC����̋C�������킩��悤�ɂȂ��Ă���̂ł���B�i�R�N�@���|�@���j
�E�����搶���f�B�x�[�g�̖{���o���Ƃ����B�������Ƃ��B�f�B�x�[�g�͎��ɂ킭�킭����B���肪�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��邩�킩��Ȃ����炾�B����̈ӌ��ɑf�����������Ĕ��_����Ƃ����̂͑�ς��B�f�B�x�[�g�ɂ͋؏������Ȃ��B������ʔ����̂��B�܂��p��Ńf�B�x�[�g������ƁC�{���ɉp����g���Ęb���Ă���Ƃ����C�����ɂȂ��B�K���ɑ���̈ӌ����C�����̈ӌ����p��œ`���悤�ƕK���ɍl����B�����Ԃ��Ȃ����悤�ȋC������B�i�R�N�@���ꌩ�R��j
�E�f�B�x�[�g�Ŏ����̈ӌ������낢��l������C����̌������Ƃ�\�z�����肷��̂͊m���ɓ���B�ł��C�����搶�̕��@���ƕs�v�c�Ȃ��Ƃɂ�肽���Ƃ����C�ɂȂ�B�f�B�x�[�g�œ����g���̂���ɂł͂Ȃ��Ȃ�C�p����g���̂��y�����Ȃ��Ă���B�i�R�N�@�ēc�ɓs�q�j
�E�f�B�x�[�g�͊y�����B����ƈӌ������������̂łƂĂ���肪��������B���������Ęb���̂�������C���̏�ő����ɉp��������ă��b�Z�[�W��K���ɓ`���悤�Ƃ���͔̂��z�͂����߂邱�Ƃ��ł��ĂƂĂ������B���ЁC�N���X�ʼnp��Ńf�B�x�[�g������邱�Ƃ����E�߂���B�i�R�N�@�쌴�厑�j
�E�f�B�x�[�g�́C���̉�]�𑁂�����ƂĂ��������@�ł���B�Ȃɂ��������̂��C���������^���ɂȂ��Ƃ������Ƃ��B���������̈ӌ����킹�Ă���Ƃ��C�p�ꂪ��i�ł��邱�ƂɋC�Â��B����ƁC�ƂĂ��C���y�ɂȂ��ĉp����g�����Ƃ��y�����Ȃ��Ă���B�܂��C�f�B�x�[�g���o������ƕ�����[���l���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B���̖{�ŁC��������̕��Ƀf�B�x�[�g�̗ǂ������Ă��炦��̂ł͂Ȃ����ƁC���͖����Ɋ��҂��Ă���B�i�R�N�@���t�T�q�j
�@������Ƒ傰�����ȂƎv����悤�Ȃ��̂����邪�C�ނ�̊��҂ɉ�������悤�ȏo���f���ɂȂ��Ă��邩�ǂ����͓ǎ҂̔��f�ɂ��C���������B
�@�Ƃ���ŁC�{�������ǂ݂ɂȂ�O�ɏq�ׂĂ����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B���̎��Ƃ��x�����{���O�ɂ��Ăł���B���̖{�͂���Ɋ�Â��ď�����Ă��邱�Ƃ��܂��������������������B����3�_�ł���B
�@�P�@�������Ƃ��d�v�����Ă���
�@�_���I�ɘb�����߂ɂ́C�܂������̍l�����܂Ƃ߂��邱�Ƃ���ł���B�b�����Ƃ����𑱂��Ă��C�����Ă܂Ƃ߂���悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����Ȏ��C�����Ƃ����s�ׂ���������̂ɂƂĂ����ɗ��B�Ȃ��Ȃ�C�����̏��������e�̘_�|���ɓǂ�Ŋm�F�ł��邩�炾�B������Ɠǂݎ�Ƃ���������ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��C���̢�m���߂飂Ƃ�����Ƃ��\�ɂ���B�����玄�̎��Ƃł͏������Ƃ��ƂĂ���ɂ��Ă���B��{�I�ɂ͢��������̗ʂ�������Ƃ������Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�C�蒅������ɂ͗ʁi����j�����Ȃ����Ƃ��������ł���B�����Ă��̓��e�ƕ��@�͎��̂悤�ɂȂ�B
�@�F�l�̈ӌ���X�s�[�`��r�f�I�i�f���̂̃r�f�I�N���b�v�j���C����Ƃ��������̌�ŕK���ӌ��������B
�@���������Ƃ����K�v���ݏo�����߂ł���B
�A���C�G�b�Z�C�C���b��I�s���Ȃǂ̂悤�ɂ܂Ƃ܂������������B
�@�����܂ł��Ȃ����C�܂Ƃ܂�̂��镶���������ƂŘ_�����ӎ��ł���悤�ɂȂ邩�炾�B
�B�p�앶�i�a���p��j������B
�@���{��Ɖp���Δ䂳���邱�ƂŁC���{�l�̈�Ԃ܂����₷���ꏇ���ӎ��ł���悤�ɂȂ邩��ł���B
�@�������ƂȂ�N�ł��ł���B���l�̍l���ɍ��E����Ȃ������̈ӌ������Ă�B�����Ă��̌��ʁC�b�������ɂ���̓I�ɎQ���ł���悤�ɂȂ�B
�@�Q�@���ȒʐM���𗘗p���u���l�ϕ��i�ӌ���l���̈Ⴂ�j�v�ݏo��
�@�����̍l���Ɠ����Ȃ��͎̂�������߂Ă���Ȃ��B�ނ��뎩���̍l���Ƃَ͈��Ȃ��̂͋������킫�������C�V���������������Ă����B�����ŁC���ȒʐM�𗘗p���āC�����Ȑ��k�̍l�����i�����B��w�͕���ł͂Ȃ�����l�ϕ���Ɋ�Â����Ƃ�����o���̂ł���B�F�����̍l����ӌ��C��i�͔ނ�ɂƂ��Ă܂��ɐ��������ނȂ̂��B����ɂ��ẮC��ŋ�̓I�ɏq�ׂ����B���ȒʐM�����̂͂Ȃ��Ȃ���ς�������C�H������悤�ɓǂސ��k�����̐^���Ȋ炪����Ȕ��Ȃǐ�������Ă����B
�@�R�@�w���̓��e���ł��邾���P��������B�������C�ʔ����Ɛ[�������˔��������e�i�R���Z�v�g���������Ɓj�ɂȂ�悤�H�v����B
�@���k���������C�ɂ�����R�c�́C�����ɋ�������e��P�������邩�ł���B�ނ����������Ƃ��₳����������B���ꂪ����B���͈ꎞ�Ԃ̎��Ƃʼn�������|�C���g���Q�C�����Ă��R�Ƃ��Ă���B�Ȃ��Ȃ碂킩������Ƃ������������傫���Ǝ��̊����ɂȂ��邩�炾�B
�@�����āC�ӗ~�I�ɂ���ɂ͂��������������B���e�𖣗͓I�Ȃ��̂ɂ���Ƃ������Ƃ��B������Ɠw�͂����ꂻ�����Ƃ��C���܂ł̌o�������Ăł��������Ƃ������ʂ������Ă�悤�ȉۑ�ɂ����Ƃ���ɐ��k�͈ӗ~��������悤�ɂȂ�B
�@�C���������̂́C���e�͂����ɒP���ł킩��₷���Ă��C�ʔ����Đ[����������̂ɂ���Ƃ������Ƃ������Ă��������ɂǂ�ǂ��̍l�����[���Ȃ�C�ʔ����Ȃ��Ă���Ƃ�����ނ�w�K�ߒ��ɂ��������̂��B
�@���Ă��̖{�́C�T�͂��u���_�ҁv�C�U�͂��u�\���͂�_������g�ɂ���A�C�f�A�ҁv�C�V�͂��u�f�B�x�[�g�̎��H�ҁv�Ƃ����R���\���ɂȂ��Ă���B
�@�ړI�ɉ����Ăǂ�����ł��ǂݐi�߂Ă������������B
�@��Ȃ����w�Z�Ńf�B�x�[�g�Ȃ̂��H��Ƃ�����̎��Ƃ�ς�������Ƃ��l���̕��͇T�͂���ǂ܂��Ƃ悢�B�f�B�x�[�g����ȗ��R���킩���Ă���������Ǝv���B
�@�����f�B�x�[�g�����Ă݂������C�܂����k�ɒi�K�I�ɕ\���͂�_������g�ɂ����������Ƃ��l���̕��͇U�͂���ǂ܂��Ƃ悢���낤�B
�@�����ɂł����w�Z�Ńf�B�x�[�g�����H�����̓I�ȕ��@�����m��ɂȂ肽�����́C���̂܂܇V�͂���ǂ܂��Ƃ悢���낤�B
�@��������C���܂ōu����[�N�V���b�v��S�����̔��\�Ȃǂł��Љ�D�]���������̂����グ���̂ŁC�����Ƃ����ɓ��X�̎��Ƃɖ𗧂̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�Ō�ɁC�ǎ҂݂̂Ȃ���Ɏ��̍D���Ȃ��Ƃ��v���[���g����B
�@�{�C�ł��Α��̂��Ƃ��ł���B
�@�{�C�ł��Ή��������y�����B
�@�{�C�ł��ΒN���������Ă����B
�@���͂���́C�{�Z�̍Z�����C�������C�E�����C���̎���ɂ������Ă��邱�Ƃł���B���̖{��ǂ܂ꂽ�ǎ҂݂̂Ȃ��C�{�C�Ńf�B�x�[�g�����H���Ă���������C����ȂɊ��������Ƃ͂Ȃ��B
�@�@�@�^�����@�m��
-
 �����}��
�����}��- �����g���S�x����ƍ��ɊS������A���̖{���ǂ����Ă���ɓ��ꂽ���Ǝv���Ă��܂��B�����搶�̏��͖{���ɑf���炵���A�������w�ԑ��ɂ͐�ɒm���Ă����ׂ������̂��̂�����͂��ł��B���Е��������肢�������ł��B2018/1/28