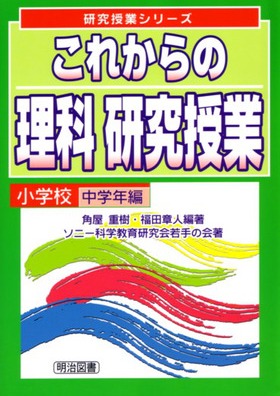- まえがき
- 第1章 子どもが「知」を創る小学校理科授業づくり
- 1.子どもに力を付けるために
- 1 子どもが知を創ること
- 2 子どもが創る知
- 3 子どもが科学的な知を創る学習指導の構想
- 4 子どもが科学的な知を創る学習指導の構成要件
- 2.子どもに力を付けさせるための学習指導の構成
- 1 子どもの実態のとらえ方
- 2 単元の構成の仕方
- 3 本時の構成の仕方
- 4 授業の実際
- 5 授業の評価の仕方
- 第2章 子どもが「知」を創る研究授業の実践例
- 1 「昆虫」の研究授業 3A(1)ア,ウ
- 2 「植物」の研究授業 3A(1)イ
- 3 「光の性質」「日なたと日陰」の研究授業 3B(1),C(1)
- 4 「豆電球と乾電池」の研究授業 3B(2)
- 5 「磁石の性質」の研究授業 3B(3)
- 6 「日なたと日陰」の研究授業 3C(1)
- 7 「季節と生き物」の研究授業 4A(1)
- 8 「空気や水の性質」の研究授業 4B(1)
- 9 「温度と物のかさ」の研究授業 4B(2)ア
- 10 「物の温まり方」の研究授業 4B(2)イ
- 11 「電気の働き」の研究授業 4B(3)
- 12 「月と星」の研究授業 4C(1)
- 13 「水の変化」の研究授業 4C(2)
まえがき
現在の小学校学習指導要領と児童指導要録は,子どもに「生きる力」をはぐくむことを目指している。
この生きる力は,具体的には,以下の3点でとらえることのできるものである。
(1) 自分で課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する能力
(2) 自らを律しつつ,他人と協調し,他人を思いやる心や感動する心など
(3) 豊かな人間性とたくましく生きるための健康や体力
これら(1)〜(3)は次のように整理できる。生きる力とは,豊かな人間性やたくましく生きるための健康や体力をもとに,主体的に問題解決を行っていく力であるといえる。このため,問題解決能力の育成が生きる力の基底になっているといえる。
生きる力の基底となっている問題解決能力の育成は,知の創造の育成である。知の創造である問題解決活動には,創られた知と知の創り方,及び他者とのかかわりによる知,のそれぞれの獲得がある。このため,問題解決能力の育成が基底となっている生きる力は,創られた知と知の創り方,及びかかわりによる知,のそれぞれの獲得であるといえる。
ところで,子どもは対象に対して働きかけ,自ら知を創る存在である。つまり,子どもは自ら自然の事物や現象に対して働きかけ,予想などを設定し,設定した予想に対して,見通しを発想し,それを検討するとともに,自らあるいは他者とかかわり,見通しを確認したり修正したりする過程を通して,自然事象に関する知を創っていく。このような知は,学問的な見地から見ると,妥当でない場合が多い。そこで,これからの学習指導では,一人一人の子どもが主体的に問題解決活動を行い,科学的に妥当な知を構築していくことが大切になる。
したがって,これからの学習指導は,子どもが科学的に妥当な知を構築することを目指すことが大切になる。このためには,子どもに付けるべき力,手順としては,単元や本時の目標,評価規準,評価方法などを明確にし,明確にしたこれらを確実に子どもが獲得できるようにすることが求められており,そのような研究授業が必要となる。
そこで,ソニー科学教育研究会の若手の先生方が前述の考え方をもとに,本書を分担で執筆し,これからの理科の研究授業のあり方を示した。
本書は,前述の状況をもとに,子どもに真の意味での科学的に妥当な知を付ける学習指導を,すべての教師が展開できる研究授業を想定し,その学習指導の仕方を明確にしたものである。具体的には,子どもの実態のとらえ方や教材の意味についての吟味,単元の構成の仕方,評価計画を含む指導計画の立案の仕方などをもとに,単元の構成の方法や本時の構成の方法を分かりやすく解説した。解説した手順をもとに,教師が単元や本時を構成していけば,必ず,子どもが科学的に妥当な知を創ることができると考える。
本書で述べられている指導計画や本時の計画案の立案の考え方をもとに,それぞれの地域の子どもの実態を考慮して学習指導を展開していただくことを,執筆者一同願っている。
平成15年5月 広島大学大学院教育学研究科教授 /角屋 重樹
-
 明治図書
明治図書