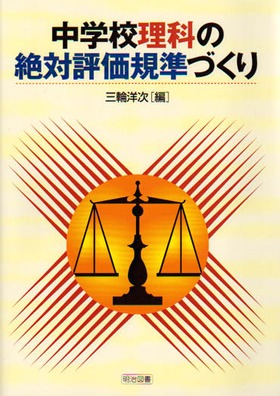- まえがき
- 1章 評価の新しい動向と理科教育の課題
- §1 評価の新しい動向
- 1 教育の新しい動向
- 2 新しい評価の在り方
- (1) 評価の二つの機能
- (2) 新しい評価の在り方,二つのポイント
- (3) 観点別評価と評定の関係
- 3 新しい評価における評価方法
- 4 開かれた学校と説明責任
- 5 海外及び世界における評価の取り組み
- §2 理科教育の課題と新しい評価
- 1 理科教育の新しい方向
- 2 理科における評価の観点及びその趣旨
- 3 理科における絶対評価規準づくりの基礎・基本
- 2章 理科での絶対評価規準づくりの方法
- §1 学習指導要領の構造分析と読み取り
- 1 理科の目標
- 2 第1分野の目標
- 3 第1分野の内容
- 4 第2分野の目標
- 5 第2分野の内容
- §2 参考資料・国研モデルの見方・考え方
- §3 自校規準づくりのポイント
- §4 絶対評価規準作成の手順と工夫
- 3章 中学校理科の観点別絶対評価規準
- §1 理科の観点別評価規準作成にあたって
- 1 評価規準とは
- 2 観点別評価規準作成の原則
- §2 第1分野の観点別絶対評価規準
- (1) 身近な物理現象
- ア 光と音
- (ア) 光の反射と屈折/ (イ) 凸レンズの働き/ (ウ) 音の性質
- イ 力と圧力
- (ア) 力の働き/ (イ) 圧力
- (2) 身の回りの物質
- ア 物質のすがた
- (ア) 物質の性質とその調べ方/ (イ) 物質の状態変化/ (ウ) 気体の発生と性質
- イ 水溶液
- (ア) 水溶液と再結晶/ (イ) 酸,アルカリ,中和
- (3) 電流とその利用
- ア 電 流
- (ア) 静電気と電流の関係/ (イ) 回路と電流・電圧/ (ウ) 電流・電圧と抵抗
- イ 電流の利用
- (ア) 磁界と電流/ (イ) 磁界中の電流/ (ウ) 電流と熱や光
- (4) 化学変化と原子,分子
- ア 物質の成り立ち
- (ア) 物質の成分/ (イ) 物質と原子・分子
- イ 化学変化と物質の質量
- (ア) 化学式と化学反応式/ (イ) 化学変化に関係する物質の質量
- (5) 運動の規則性
- ア 運動の規則性
- (ア) 物体の運動/ (イ) 力と運動/ (ウ) いろいろなエネルギー
- (6) 物質と化学反応の利用
- ア 酸化と還元
- (ア) 酸化と還元/ (イ) 化学変化とエネルギー
- (7) 科学技術と人間
- ア エネルギー資源
- (ア) エネルギー資源の有効利用
- イ 科学技術と人間
- (ア) 科学技術の進歩と人間生活
- §2 第2分野の観点別絶対評価規準
- (1) 植物の生活と種類
- ア 生物の観察
- (ア) 生物の観察
- イ 植物の体のつくりと働き
- (ア) 花のつくりと働き/ (イ) 葉・茎・根のつくりと働き
- ウ 植物の仲間
- (ア) 種子植物の仲間
- (2) 大地の変化
- ア 地層と過去の様子
- (ア) 野外観察と地層
- イ 火山と地震
- (ア) 火山活動と火成岩/ (イ) 地震
- (3) 動物の生活と種類
- ア 動物の体のつくりと働き
- (ア) 動物の体のつくりと働き/ (イ) 刺激と反応/ (ウ) 生命維持
- イ 動物の仲間
- (ア) 脊椎動物の仲間
- (4) 天気とその変化
- ア 気象観測
- (ア) 気象観測
- イ 天気の変化
- (ア) 霧や雲の発生/ (イ) 前線の通過と天気変化
- (5) 生物の細胞と生殖
- ア 生物と細胞
- (ア) 細胞のつくり/ (イ) 細胞分裂と生物の成長
- イ 生物の殖え方
- (ア) 有性生殖と無性生殖
- (6) 地球と宇宙
- ア 天体の動きと地球の自転・公転
- (ア) 天体の動きと地球の自転/ (イ) 天体の動きと地球の公転や地軸の傾き
- イ 太陽系と惑星
- (ア) 太陽系と惑星
- (7) 自然と人間
- ア 自然と環境
- (ア) 自然界のつりあい/ (イ) 自然環境の保全
- イ 自然と人間
- (ア) 自然と人間のかかわり方
- 4章 評価規準に基づく評価例
- §1 第1分野の評価例
- 1 小単元の評価規準
- 2 指導・評価計画
- (1) 評価方法
- (2) 指導・評価計画
- 3 観点別評価の進め方
- (1) 関心・意欲・態度
- (2) 科学的な思考
- (3) 技能・表現
- (4) 知識・理解
- §2 第2分野の評価例
- 1 小単元の評価規準
- 2 指導・評価計画
- 3 観点別評価の進め方
- (1) 関心・意欲・態度
- (2) 科学的な思考
- (3) 技能・表現
- (4) 知識・理解
- 5章 観点別評価から評定へ
- §1 第1分野・観点別評価から評定へ
- 1 基本的な考え方
- 2 学期ごとの観点別評価から評定への総括
- 3 学年の評定への総括
- §2 第2分野・観点別評価から評定へ
- 1 年間の指導・評価計画の作成
- 2 単元の観点別評価の総括
- 3 学期ごと及び学年の観点別評価の総括
- 4 学期ごと及び学年の観点別評価から評定への総括
まえがき
平成14年4月より,完全学校週5日制による教育課程が実施の運びとなった。そして同時に,小・中学校では,新しい学習指導要領が実施されている。このことに伴い,平成12年12月,教育課程審議会から新しい評価の在り方が示された。これまでも,学習指導要領の改訂に伴い評価の在り方に変更が加えられてきたが,今回の評価の在り方は,趣旨から言えばこれまでの路線を強めただけと言えよう。しかし,それらを実際に実現するとなると,結果として大きな変更が必要となることから,国立教育政策研究所の教育課程研究センターにおいて,評価規準・評価方法等の研究開発を進め,各学校の参考となる資料を平成14年2月末に発表した。
従前の学習指導要領の下においても,基礎・基本を重視し,自ら学ぶ意欲や思考力,判断力,表現力などの資質や能力の育成とともに,生徒のよさや進歩の状況などを積極的に評価し,生徒の可能性を伸ばすことを重視した「新しい学力観」に立つ評価を行うよう求められていた。この考え方は各学校にも浸透してきているが,実際には,従来どおりの知識・理解に偏りがちな評価が依然として行われている面も見られる。そこで,「これからの児童生徒の学習状況の評価の在り方としては,学習指導要領に示す目標に照らしてその実現の状況を見る評価(いわゆる絶対評価)を基本に据えることが適当である」と,教育課程審議会の答申で示された。そして,目標に準拠した評価を適切に行うためには,生徒の学習の到達度を客観的に評価するための評価規準等を作る必要があるとされた。つまり,学習指導要領の目標に照らした評価規準をつくり,それに基づいて評価活動を行い,生徒には学習の改善に,教師にとっては指導の改善に生かすことが求められたわけである。
これらの経緯で,教育課程研究センターから参考資料が出されたわけだが,ここには各教科とも内容のまとまりごとの評価規準の例が示されている。すなわち,理科においては,学習指導要領の内容の大項目に相当する評価規準の例が示されている。しかし,実際に授業を行い評価活動を行うには,授業の計画に沿った各単元,小単元ごとの評価規準が必要となる。そこで,それぞれの学校の授業計画に沿って評価規準を作る際に,参考となるよう本書を構成した。評価は,指導と一体化されて意味をもつ。計画(Plan)に沿って指導を行い(Do),評価(See)してそれを指導に生かすというサイクルがうまく回ることによって,生きた指導ができるのである。そのためにも,各学校の指導計画に即した絶対評価規準づくりが求められている。本書が各学校の絶対評価規準づくりに役立ち,より良い教育活動につながれば幸甚である。
平成14年4月 編 者
-
 明治図書
明治図書